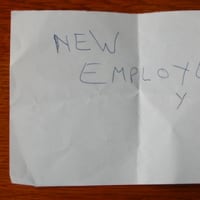「スパルタ式」がちょっと話題になっている。
もちろん最近公開された映画「300(スリーハンドレッド)」の影響であります。
スパルタ。。スパルタ式。。。
戸塚ヨットスクール事件なんかも思い出しちゃいますけど、要するに上からの絶対的な命令で有無を言わせず、勝ち抜く為にいろいろな試練を与え鍛えあげる方法です。
私は老人ホームで働いていますが、私の職場、福祉の世界も非常にスパルタチックです。
措置制度から介護保険という契約の制度に変わり、利用者に選んでもらう上で他施設との競争に勝たねばなりません。地味で辛くて身体を壊すハードなお仕事ですから、介護士にそれをもっともっとたくさんやらせようとするなら、スパルタ式になるのは当然です。
弱音を吐かずお年寄りの為に歯をくいしばり「働け」「働け」です。
スパルタ式は、競争社会で戦う為には適したやり方なのかもしれませんが、私は性にあいません。
あまりにスパルタ式だと、究極に価値があるのは強さであって(相手や自分の)弱さを押しつぶすことが正当化されてしまい、本当に苦しんでいる人や弱っている人に対して鈍感になってしまう恐れがあるのではないかと思います。
ところで、スパルタといえばすぐ頭に浮かぶのはアテネ。
「母親と教師がなおす登校拒否」という本はアテネ式(受容式)にのっとって書かれていますが、スパルタ式の功罪について述べている箇所があります。
その中の挿話をここに紹介します。
親鸞の弟子が二人争っていた。
事の起こりは、一人の弟子が蚊を殺したのを見て、そこに居合わせたもう一人の弟子が、殺傷戒を犯したと責めたのである。
蚊を殺した方の弟子は、なるほど自分は殺傷戒を犯したが、一匹の蚊を殺すことにより、多くの人や生き物を伝染病から救った。これも広い意味で仏の心に背いたことにはならないと、反論したのである。
二人の論争は、決着がつかなかったので、お師匠さんのところへ行って、判断してもらおうということになった。
親鸞は二人の言うことにじっと耳を傾け、二人の主張を黙って尽きるまで聞いていた。二人が自分の主張を言い切ったその後で、蚊を殺した弟子に向かって、
「お前は涙して蚊を殺したか」と問うたそうである。
二人の弟子は、おのが主張の浅薄なことを恥じて、ますます、修行の道を深めたという。
この「涙したか」という部分が、重要な鍵にあたる部分だそうです。
つまりスパルタ式をしている人の人格に関わる部分です。
スパルタ式をしようとする人物は、人の心、自然の摂理に涙する心を持っているか、常に自分に問いかける必要がある。
涙する心がないままスパルタ式を遂行していると、例えスーパーマンのように有能であり傍目に立派な行いをしていたとしても、真実の苦痛の声、心の痛みを汲み取りにくくなる。理想や思い(理念)がいくら素晴らしく華々しくても、本当の人の心というものを素通りし、気がつかぬまま平気で踏みにじってしまいがち。。
この本では涙する心が、弱さからくる単なる逃げの声と、命にかかわる苦痛の声を聞き分けられる道ではないのかと述べています。
私はこの著者の書く本が大好きです。
たぶんこの著者は、人の心をきちんと汲み、涙する心を持っている人なんだろうと思います。小難しいことを書く人は多いのですが、どれだけきちんと人やものの心を奥深く正確に感じ取り思いやれるか...頭のいいというのはこういう人のことなんだろうと思います。
母親、教師、登校拒否児以外でも為になり考えさせられる本ではないかと思います。
ここに書かれている内容に、人と人とのつながりのもつれ全てにおいての共通の鍵が納められているような気がします。
私のお勧めの一冊です。
| 母親と教師がなおす 登校拒否―母親ノート法のすすめ創元社このアイテムの詳細を見る |
余談ですが、
お年寄りの為に身を粉にして働くのはプロとして介護士の務め。「できない」という言葉はその人がラクする為の逃げ口上だなどと決めつけず(まそういう場合もありますが)、いかに耐え、頑張っているか少しでも感じとっていただければなあ、スパルタ式で福祉にすごーく思い入れのお持ちの方々。
涙する心(直情的に泣いたり感動したりとは別)があれば、無理なことをガムシャラに押し付けないだろうし、同じことを言ったとしても相手に理解させ耐えさせる何かが伝わるもんです。(あなた達は自分達が「できる」からこそ「やれ」とおっしゃるのでしょうが)
体力的にあなた達ほどすぐれていない人も普通にいます。(お年寄りなどなお更でしょう)「介護士のプロとして」いろんなことを疑問に思わず当然のごとく強要するあなた達に、逆に強者の驕りを見てしまうのです。口で「お年寄りの為にたくさんのことをしてあげよう」と言うのとは裏腹に、弱者に対しての痛みがわかってないような気がします。言うなとは言わない。痛みをわかって言って欲しいのです。そうすれば、どこまで言うべきか線引きが自ずとわかってくるでしょう。