
名古屋裁判所(高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所)見学に参加しました。(豊田市社会科自主研主催による。)
裁判所へ入るのは初めての体験でした。
◆刑事裁判の傍聴
法廷は、傍聴席が40席。思ったよりも小さな部屋でした。私は最前列に座りました。裁判官、書記官は黒服(法衣)をまとってみえました。緊張。
1件目は、覚せい剤所持に対する判決の言い渡しでした。
被告人は、警察官(のような人)に両方から付き添われ、胴は紐で縛られ、手首には手錠がかけらけていました。これが、本物の裁判であることを感じました。この裁判は短く、裁判官が判決を読み上げ、5分ほどで終了しました。
2件目は、暴力団組員とその共犯者(女性)による恐喝事件の裁判でした。この裁判は、検察官、被告人、弁護士の間でいくつかやり取りがありました。検察官が起訴状を読み上げると、被告人が「お金は取ったが、脅すようなことは言っていない」と異議を申し立てました。また、弁護士が共犯者の妹を証人(参考人)として、共犯者が人格障害であることを立証しようとしました。
検察官による膨大な調書に驚きました。しかし、あれだけ煩雑な事件を真実どおりに再現することが可能だろうか?検察官の推論による部分があるのではないか?と感じました。また、共犯者が人格障害であると立証された場合、判決にどのような影響がでるのだろう?などと様々な疑問が浮かんできました。
約1時間の裁判の後、次回の予定を決めて閉廷となりました。
始めから「犯人が悪い」と決めてかかりそうなことに対して、弁護人がついて裁判が行われることに、人権尊重の精神を感じました。
◆裁判員制度スタートについて
平成21年度から裁判員制度がスタートするそうです。これは、無作為に選ばれた一般市民が裁判員として裁判に参加するものです。しかも、裁判員の意見は裁判官と同じ扱いで。今回の傍聴で一番印象に残ったことは、起訴状、検察官と弁護人が示す証拠などにより、同じ事件でありながら、事件の様相は変わるということです。(もちろん従来の判例活用など、様々な方策なされると思いますが。)そうした中で選ばれた市民は、責任を持って自らの判断を示していかなければならいと感じました。そして、この仕組みを形骸化させないためには、自らの判断をはっきりと口にすることも重要だろうと感じました。裁判員制度が始まると、裁判官、裁判員の間で話しあって意見が分かれることが増えるだろう、と感じました。ちなみに、裁判員候補者に選ばれる可能性は、一年間に310人~620人に1人とのことです。
説明の後、許可を得て法廷の写真を撮りました。(写真参照。)みんな、ここぞ!とばかりに写真をバシバシ撮りました。この法廷は裁判員制度に既に対応して、裁判官の場所に、裁判員も座れるようにイスが9つ設置してありました。
また、裁判官、弁護人、被告、検察官のイスに座らせていただきました。感激!
すばらしい機会を設定していただいた、市自主研の事務局のみなさんありがとうございました。夏休み開けの子どもたちへの土産話ができました。
次回の自主研は、"足助地区"が担当します。
私も含め地元・足助の社会科部員の総力を挙げて(?)取り組みます。
歴史、グルメと企画満載です。お楽しみに!
また、今回何人か、新しく豊田に先生方とお話をさせていただきました。少しずつ仲間、同士が増えていくことが何よりの喜びです。ありがとうございました。
裁判所へ入るのは初めての体験でした。
◆刑事裁判の傍聴
法廷は、傍聴席が40席。思ったよりも小さな部屋でした。私は最前列に座りました。裁判官、書記官は黒服(法衣)をまとってみえました。緊張。
1件目は、覚せい剤所持に対する判決の言い渡しでした。
被告人は、警察官(のような人)に両方から付き添われ、胴は紐で縛られ、手首には手錠がかけらけていました。これが、本物の裁判であることを感じました。この裁判は短く、裁判官が判決を読み上げ、5分ほどで終了しました。
2件目は、暴力団組員とその共犯者(女性)による恐喝事件の裁判でした。この裁判は、検察官、被告人、弁護士の間でいくつかやり取りがありました。検察官が起訴状を読み上げると、被告人が「お金は取ったが、脅すようなことは言っていない」と異議を申し立てました。また、弁護士が共犯者の妹を証人(参考人)として、共犯者が人格障害であることを立証しようとしました。
検察官による膨大な調書に驚きました。しかし、あれだけ煩雑な事件を真実どおりに再現することが可能だろうか?検察官の推論による部分があるのではないか?と感じました。また、共犯者が人格障害であると立証された場合、判決にどのような影響がでるのだろう?などと様々な疑問が浮かんできました。
約1時間の裁判の後、次回の予定を決めて閉廷となりました。
始めから「犯人が悪い」と決めてかかりそうなことに対して、弁護人がついて裁判が行われることに、人権尊重の精神を感じました。
◆裁判員制度スタートについて
平成21年度から裁判員制度がスタートするそうです。これは、無作為に選ばれた一般市民が裁判員として裁判に参加するものです。しかも、裁判員の意見は裁判官と同じ扱いで。今回の傍聴で一番印象に残ったことは、起訴状、検察官と弁護人が示す証拠などにより、同じ事件でありながら、事件の様相は変わるということです。(もちろん従来の判例活用など、様々な方策なされると思いますが。)そうした中で選ばれた市民は、責任を持って自らの判断を示していかなければならいと感じました。そして、この仕組みを形骸化させないためには、自らの判断をはっきりと口にすることも重要だろうと感じました。裁判員制度が始まると、裁判官、裁判員の間で話しあって意見が分かれることが増えるだろう、と感じました。ちなみに、裁判員候補者に選ばれる可能性は、一年間に310人~620人に1人とのことです。
説明の後、許可を得て法廷の写真を撮りました。(写真参照。)みんな、ここぞ!とばかりに写真をバシバシ撮りました。この法廷は裁判員制度に既に対応して、裁判官の場所に、裁判員も座れるようにイスが9つ設置してありました。
また、裁判官、弁護人、被告、検察官のイスに座らせていただきました。感激!
すばらしい機会を設定していただいた、市自主研の事務局のみなさんありがとうございました。夏休み開けの子どもたちへの土産話ができました。
次回の自主研は、"足助地区"が担当します。
私も含め地元・足助の社会科部員の総力を挙げて(?)取り組みます。
歴史、グルメと企画満載です。お楽しみに!
また、今回何人か、新しく豊田に先生方とお話をさせていただきました。少しずつ仲間、同士が増えていくことが何よりの喜びです。ありがとうございました。










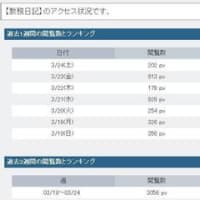









コメントありがとうございます。
裁判が一日にいくつも開かれること、被告は法廷に来るまで縄で腕を縛られていることなど、いくつも、実際に見て「あっ」と思ったことがありました。
また、この見学以来、テレビで裁判の場面が映ると、イメージが浮かんできます。
体験することの大切さを私も知りました。
豊田市社会科自主研をしています。
また、ご参加ください。