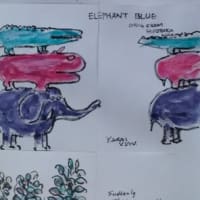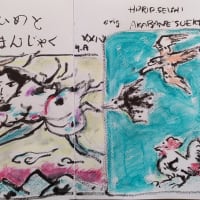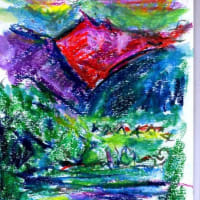朝日記150308 今日の絵と 「再帰哲学」~フォン・ノイマンが語る数学と哲学の界面におもう
3・8おはようございます。
すこしながいので トピックとしました。
絵は Henri Matisse Hommage in tapestry
朝は雨空でしたのでいったん用意したのですが
家で体操しました。
2月はゲーデルに取り組んで いました。そういえば三年前のいまごろも 一生懸命放送大学のテキスト「数学基礎論」をよみながら呻吟しいたことを覚えています。今回はAmazonのブックレビューで出色のものがあり、そのコメントを掲載していますが、あらためて「徒然こと」としてメモします。」数学と哲学との境界に興味があったからです。
いました。そういえば三年前のいまごろも 一生懸命放送大学のテキスト「数学基礎論」をよみながら呻吟しいたことを覚えています。今回はAmazonのブックレビューで出色のものがあり、そのコメントを掲載していますが、あらためて「徒然こと」としてメモします。」数学と哲学との境界に興味があったからです。
徒然こと 「再帰哲学」~フォン・ノイマンが語る数学と哲学の界面におもう
荒井康全 2015/3/8
*フォン・ノイマンが『数学者』とう題名で精神的なはたらきとしての数学とはなにかという講演の中からの特に哲学と数学の境界ともいうべき部分に触れた部分を抽出してみました。ご承知のように彼は二十世紀を代表する大数学者のひとりで、いまのコンピュータの発明者としても知られています。 この講演は第二次大戦が終了した直後の1945年~1946年にシカゴ大学で行われた連続講演の第1回からの引用であります。因みにこの講演会は、画家のマーク・シャガール、彫刻家のフランク・ロイド・ライト、作曲家のアーノルド・シェーンベルクなど現代芸術や現代科学を代表するさまざまな人物が、おなじ「精神のはたらき」という題名で自分の仕事について講演しています。目くるめくような輝かしいアメリカ文化の始まりの時代を思い起こします。
*この講演のことを知ることができたのは、 筆者はいま岩波文庫 ゲーデル「不完全性定理」に読み取り組んでいますが、偶然に、書籍のネット通販Amazonに投稿されたブックレビューを開いたことによります。 このレビューア[1]は、講演集[2]を 東京大学の物理学教室図書室所蔵から探し出されたそうです。 ノイマンの講演を多分自ら翻訳なされ、これを彼のレビューとして紹介されたのです。[3]ノイマンと比肩する後進の巨星クルト・ゲーデルの数学的な定理がもたらす、人間理性への歴史的な意味づけとして掲載されました。
筆者は、この現代の数学に疎いことは認めるとして、この数学が人類の知的営為として完全ではないことが 人類社会にどのような影響を及ぼすか、特に人間の認識という営為において、たとえば哲学と数学の境界状況に焦点を当あてることに個人的興味があったのでノイマンの言を取り上げてみました:
(以下は、彼が、数学の現代的状況をいくつかの例を述べた後、数学と哲学におよびます):
「[前略]「絶対的な」数学的厳格性の概念は、不変ではないということを示しているのだ。[中略] 2つのことが、しかしながら、明らかである。第一に、何か非数学的なものが、なんらかのやり方で経験科学または哲学、あるいはその両方と結びついていて、どうしても入ってくるのだ。そしてその非経験主義的な性格は、哲学(あるいはより具体的にいうと認識論)は、経験から独立して存在できるということを前提にしないことには、成り立たない。[4](そして、この前提は、必要条件でしかなく、それ自体は十分条件ではないのだ。)」
数学の集合論では、 集合とそこにふくまれる要素つまり部分集合の関係を扱います。ところが、「カントールの矛盾」というのが早い段階でわかっていていました。これは、考えている自分を含む全体集合を考えると数学論理上の矛盾が起こるというものです。有限を無限に拡張するときに陥る矛盾であるといわれます。 これが、ノイマンのいう数学理論が「不変ではない」というところの主旨です。ゲーデルはこれを最終的に数学の「不完全性定理」として、数学の不完全性として証明します。このような背景のもとで、ノイマンは続けます:
「集合論だけに限らず、ほとんどの現代数学において、「一般的な有効性」や「存在」という概念の使われ方が、哲学的にみていかがわしいということが示された。これらの望ましくない特徴から免れる数学システムとして「直観主義」*がブラウワーによって生み出された。(*訳注:直観主義 intuitionism とは、五官に入ってくる刺激それ自体は正しく、それに正しいか正しくないかの判断基準をおく経験主義的な考え方であると考えられる。言葉以前の数学を目指しているところは禅に近いともいえるだろうか。)」
このレビューアは親切にも訳注で 「直観主義」の説明をしてくれます。この哲学は紛うことなくカントの認識哲学そのものです。かれの哲学の経験知による認識の典型方式を説明していると筆者は理解します。 ブラウアーも論争相手のヒルベルトも ともに哲学をカントによっていたことから窺がい知り得て印象的でさえあります。
(徒然におもうこと)
話は、飛躍しかつ独断的ですが、筆者は、ゲーデルの不完全性定理の結果が起こしたことのひとつは、哲学へ、とくにカント哲学への「再帰的」であったとおもいます。彼は基本的な4つの二律背反(アンチノミー)を純粋理性批判で延べます。その結果、人 間の自由意志と経験知(現象知)からなる知的営為を提案します。これが科学主義を生みます。 時空間を主観側に取り込み、結果的には記述(記号)構成となりますから、その思考はシステム・モデリングそのものであることになります。 現代的なシステム論理に置けば「目的関数」と「制約条件」という定型形式に落ち着きます。
さて、「再帰的」に哲学に帰ってきた問題は よくよく吟味することが要求されます。
目下の筆者の関心は、「目的関数」の部分です。 これを決定するのは「価値」です。
それは、単なる論理的あるいは機械的な次元ではないことを意味します。カントの認識(批判)哲学はその目的関数を価値命題として構成する問いをわれわれに投げかけます。 それを駆動するのは何か? カントなら理性となります。では、その理性の根拠は何か?と問うと 証明のしようがない。それで超越的存在からの賦与される「直観」ということで主観として置き換わります。 もちろん理性は完全ではなく、間違いはおこしますが、間違いをおこすということの上に立って知る活動をすることになります。 理性への信頼性の根拠に人間自由をおきます。これも超越的な前提です。
さて、気になるのは理性の信頼性を説くに、彼は典型として幾何や代数という数学をおいていることです。ところが、これを使っていくと「不完全」な結果に至るということになります。 カント先生はいかに見ていたかですが、もしかしたら見通し済みであったかもしれません。これをいま「哲学再帰とよびますと、これからのは現代文明へインパクトは、大きいはずです。 なぜなら、すべて人間自由意志の旗印のもとに人類はみずからへの責任が課せられているからです。
[1] Amazon ブックレビュー 岩波文庫 ゲーデル 林・杉浦訳不完全性定理 http://www.amazon.co.jp/review/R1OX7GGIM5PGRK?_encoding=UTF8&ASIN=4003394410&cdMSG=addedToThread&cdPage=&newContentID=Mx1ZGIZIIU5FHDN&newContentNum=1&ref_=cm_cr_pr_cmt#CustomerDiscussionsNRPB
[2] 出典:Collected works / John von Neumann ; general editor, A.H. Taub, vol.1 "Logic, theory of sets, and quantum mechanics" (New York ; Oxford : Pergamon Press, 1961 2011年7月に東京大学・理学部物理学科図書館にてレビューアが複写した)
[3] 2013年9月 投稿者名 tokuちゃん
[4] 下線は 筆者が挿入。