
肖像 わずか1年余で平氏を滅ぼした若き天才武将・源義経
本編に登場する若き革命児……源頼朝 木曾義仲 源義経 佐藤兄弟
聖徳太子が日本の礎を築いてから500余年の年月が流れ、日本の歴史は、新たな転機を迎えようとしていた。
それまで日本を支配してきた貴族の体制が衰え、代わって、武士の台頭が著しかった。平氏と源氏が2大勢力として対立し、情勢は混沌として予断を許さない。今再び、日本を築き直すために、乱世を駆ける若者が必要とされていた。
源氏の御曹司である源義経は、そんな時代に生を受けた。幼名は、牛若丸。牛若がわずか1歳のとき、父・義朝は平時の乱に敗れ、殺された。母の常盤に連れられて、平清盛の元に自首し、命だけは助けられたが、母の元から離され、平氏の監視の元に、鞍馬山に預けられる。7歳のときだった。
このとき、牛若は、自分が源氏の御曹司であることを知らなかったという。それがいつ真相を知り、源氏の再興を誓ったのかは、定かではない。
一説には、武芸を教わった山伏から真相を聞かされたと伝えられる。この山伏の素性は明らかではないが、源氏に所縁のある人間であったことは、間違いないだろう。
牛若は、この山伏の手引きで、強力(荷担ぎ)に変装し、監視の目を盗んで、鞍馬山を脱け出したという。15歳のときだった。
京を離れた牛若が向かったのは、みちのく平泉だった。当時、みちのくでは、奥州藤原氏が巨大な勢力を誇り、さすがの平氏も力が及ばなかった。奥州藤原氏も、源氏が将来、力を持った場合に備えて、「源氏の御曹司をかくまった」という借りを作っておきたかった。
牛若は、平泉の地で武芸に励み、来たるべき時に備えた。当時の戦は、一騎討ちが作法だったので、大将に武芸のたしなみは必須だった。
それから1年後、牛若は、密かに京に向かっている。京では平氏が幅をきかせ、かむろという赤い服を着た少年たちに、平氏の悪口を言った者を取り締まらせていた。公家でさえ、平氏のやることに口出しできなかった。
ところが、平氏の侍たちでもかなわない、怪力の僧兵がいた。この僧兵の名は、武蔵坊弁慶。夜ごとに京の街に出没し、通りかかる侍を襲っては、刀を奪うという。
牛若は、清水観音の境内(五条大橋というのは伝説)で単身弁慶に挑み、軽業で翻弄して、降参させたという。当時の僧侶は、寺院の防衛を名目に、武芸に励んでいた。特に、興福寺や延暦寺の武力は、平氏さえ恐れさせていた。その中でも、随一のつわものだったという弁慶が、16歳の牛若丸に負けたとはにわかに信じがたいが、ともかく、弁慶は相手が源氏の御曹司と知ると、その場で家臣となった。
こうして、生涯の側近を得た牛若は、平泉に戻って元服し、源九郎義経を名乗った。
その後も、平氏はますます力をつけ、ついに清盛は、実の孫を天皇に即位させる(安徳天皇)。武士として初めて皇族となり、独裁的な権力を振るう清盛は、反発を招き、あちこちで、打倒平氏の旗が掲げられることになる。義経の兄である33歳の頼朝も、立ち上がった若武者の1人だった。
21歳になっていた義経は、兄の挙兵を知るや、参戦を決意。奥州一の武将として名高い、佐藤継信・忠信兄弟を従え、頼朝軍に合流する。このとき、継信は22歳、忠信は18歳という若さだったが、「この2人がいなければ、平氏は討てなかった」といわれるほどの働きをすることになる。
義経、継信、忠信。平氏追討は、実質的に、この3人の若武者によって成し遂げられることになるのだった。
しかし、鎌倉の開発が優先されたこともあって、頼朝は当初、義経を出陣させようとしなかった。それどころか、鶴岡八幡宮の上棟式で、頼朝は、義経に大工に贈る馬を引かせている。
馬を引くのは、臣従の意を示す行為で、本来、武将のすることではない。しかし頼朝は、実の弟だろうと、他の家来と区別しないことを示したかったと見える。
いかに腕が立っても、チャンスが与えられなければ、実力をアピールすることはできない。いたずらに、月日だけが流れていった。
義経が鎌倉でくすぶっている間、もう1人の若武者が、時代を大きく動かしていた。同族の木曾義仲だった。
義仲は、信州木曾谷で育てられた。26歳にして平氏を討つべく挙兵し、翌年には、北陸道を制圧する。若き武将はますます勢いを増し、倶利伽羅峠の戦いでは、牛の角に松明を結びつけて突進させるという奇抜な作戦で、平氏の大軍を打ち破った。
義仲は、比叡山の僧兵も味方につけ、ついに、絶大な権力を誇った平氏を、京から追い落とすことに成功した。このとき、義仲はまだ29歳。誰もが願いながらできなかったことを、20歳代の若き天才武将が成し遂げたのだった。平氏の都落ちにより、歴史の歯車は大きく回転し始める。
しかし、京に入った義仲は、打ち続く戦と飢饉で荒れ果てた都の様子に、唖然とする。もともと義仲は、京に入りさえすれば、家来に恩賞を取らせ、兵糧を補給できると考えていただけに、これは全くの計算外だった。
しかも、法皇は続けて、義仲に、「西国に逃げた平氏に追い討ちをかけ、安徳天皇と三種の神器を取り戻すよう」命ずる。義仲は渋々これに応じるが、命懸けで戦いながら、恩賞どころか兵糧さえ満足に補給されなかった家来たちの志気が上がるはずもなく、逆に、返り討ちにあってしまう。
ますます苦境に陥り、その日の食事にも事欠く義仲軍の末端では、京で庶民の財産や食料を略奪する者まで出始めた。もはや、義仲の力では、そのような家来たちを抑えることができなくなっていた。朝廷では、義仲への不満が高まり、義仲は孤立してしまった。
頼朝の元に、法皇から義仲追討が命じられたのは、そんなときだった。まず、義仲を利用して平氏を追い落とし、その後は源氏同士で争わせようというシナリオが、法皇の狙い通りに進んだと見える。
頼朝は奥州藤原氏を警戒していて、自身が鎌倉を空けるのは、避けたかった。そこでとうとう、義経に義仲追討の司令が下る。源氏同士で争うことは本意ではないが、こうなったら、源氏の汚名を濯ぐためにも、義仲を討たねばならない。こうして、待ちに待った初陣が決まった。時に、義経25歳、継信26歳、忠信22歳だった。
しかし、百戦錬磨の義仲に対して、義経には、実戦の経験が1度もない。義経の苦戦は、十分に予想された。が、蓋を開ければ、結果は義経の圧勝だった。その陰には、奥州1の武将として名高い佐藤兄弟の働きがあったことは、言うまでもない。こうして、義仲は京に入ってから、わずか半年で戦死する。まだ30歳だった。
義仲は、世間で言われているほど、ひどい武将ではない。それどころか、あれほどの強権を誇った平氏を怒濤の進撃で破り、都落ちさせた実績は、特筆に値する。が、都に入ればなんとかなるという読みの甘さが、命取りになった。
ともあれ、義仲はわずか5年ほどの間に己の天命を全うし、平氏打倒のバトンを義経に託して、歴史の舞台から去っていった。
義仲に代わって京に入った義経の評判は、すこぶる良かった。義仲の二の徹を踏まぬよう、十分に食料を持参し、兵士たちの略奪を禁じたからだった。法皇も、義経を重用した。だがそこには、いずれ頼朝が朝廷に口出ししてきたとき、義経を朝廷につけて源氏同士で争わせ、自滅させようという、したたかな計算が隠されていた。
頼朝は続けて、義経に、一ノ谷(神戸)に陣を張る平氏の追討を命じる。こうして、平泉で6年、鎌倉で4年、足掛け10年間、待ちに待った打倒平氏を、ついに実現できるときがやってきた!
義仲戦の疲れを癒す間もなく京を出た義経軍は、まず、丹波で夜営している平氏軍に夜討ちをかけて蹴散らした。その翌日、義経は、一ノ谷を背後から急襲する作戦を立てる。
一ノ谷は、前後を断崖と海に挟まれた、天然の要塞。義経は、この断崖を駆け降りて、平氏を攻めようというのだった。さっそく、地元の猟師である鷲尾三郎に鎧を取らせ、鹿の通る獣道を案内させる。
一度決断するや、義経の行動は稲妻のように早かった。翌朝、まだ暗いうちから、義経はわずか70騎を率い、一ノ谷を見下ろす鵯越に向かった。その、あまりの嶮しさに尻ごむ兵士たちを差し置き、義経は、自ら先頭に立って、絶壁を駆け下った。
その姿を見た兵士たちは奮い立ち、義経に続く。驚いたのは平氏軍だった。全く予想していなかった早朝からの奇襲に、槍をとる暇もなく、多くの武将を討ち取られ、海に敗走するしかなかった。
一ノ谷の合戦では、少数精鋭主義、家柄にこだわらない現地住民の活用、率先垂範、しきたりにとらわれない奇襲攻撃、短期決戦など、義経本来の戦い方が、遺憾なく発揮されている。
特に、夜討ち朝駆けや背後からの急襲などは、当時の武士の感覚からは、卑怯この上ないやり方になろうが、もともと大軍を擁していない義経にとって、最低限の犠牲で最大限の効果を挙げるには、これしかなかった。
日本で、このような奇襲が一般的な戦法として認められるのは、戦国時代からである。義経は、300年も時代を先取っていた。斬新な発想と、思い切った決断が、義経の最大の武器だった。
しかし、このあまりにも見事な勝利が、かえって頼朝に警戒心を抱かせることになった。頼朝は、今回の功績に対して、3人の源氏を国司に推薦したが、その中に、義経は含まれていなかった。
事態は、法皇の狙い通りに展開していった。法皇は、さらに頼朝と義経の関係を悪化させようと企て、義経に検非違使尉(警察の長官)の位を授ける。案の定、頼朝は自分に許可なく官位を得た義経に激怒し、次の平氏追討から、義経を外してしまった。
さらに、その年の10月、義経が昇殿を許されたことで、頼朝は再び激怒。もはや、義経は、このまま干され続けるかに見えた。
だが、もともと平氏のホームグラウンドである瀬戸内海では、義経を欠いた源氏は、なかなか攻めることができなかった。関東の山野を駆け巡ってきた源氏は、騎馬戦は得意でも、海戦は未経験。一方、平氏は、代々海運を生業として発展してきたくらいで、海戦は十八番中の十八番。ましてや、奥深い瀬戸内海では補給路も分断され、逃亡する兵士も出る始末。頼朝も、ここに至っては、戦の天才・義経を用いるしかなかった。

こうして翌年、義経はやっと参戦を認められる。しかし、頼朝が送ってきた戦奉行(司令官)の梶原景時は、あくまで、平氏の水軍と正面から激突するつもりだった。
それは、確かに武士らしい戦い方かもしれないが、多くの犠牲を出すことは、目に見えている。それに、鎌倉の武将たちは、海戦が陸とは全く勝手が違うことを、理解していなかった。このままでは、ほとんど勝ち目はない。
一方、京にとどまって戦況をつぶさに分析し続けていた義経は、平氏の、海戦での強さを知り抜いていた。そこで、相手の土俵である海ではなく、陸での戦いに持ち込むことを考えた。
平氏は、四国の屋島に陣を構えている。そこで義経は、わずかな兵を率いて、嵐の吹きすさぶ深夜の瀬戸内海を渡り、密かに四国に上陸。背後から屋島を急襲する。
平氏もまさか、嵐の海を渡ってくるとは予想外で、一時は海に逃げ出すが、義経が小勢と見るや、引き返して反撃に移る。この戦で、惜しくも、片腕と頼る佐藤継信が討たれる。まだ27歳だった。
義経は、継信の供養をした僧に、名馬・大夫黒を取らせたという。家臣を大切にする義経の姿は、兵士たちを奮い立たせた。
京でもそうだったが、義経は、人心を得るのが極めて上手かった。アレキサンダー大王のように、敵地の民衆をも味方につける、不思議な魅力があった。それも、私欲がなく、高潔な義経の人格によるものだろう。
ここ四国でも、義経は、現地の河野水軍や熊野水軍を味方につけ、もともと兵力で圧倒的に勝っていたはずの平氏軍を追いやってしまった。嵐が収まって、景時率いる本隊が駆けつけたときには、すでに戦は終わっていた。
こうして水軍を得た源氏軍は、いよいよ、壇之浦で最後の合戦に臨む。前回遅れを取った景時は、先陣を希望するが、義経はここでも、先陣をかって出て譲らない。もともと反りの合わなかった2人だが、ここに来て、対立は決定的になった。
総大将自らが、最も危険な先頭に立つのは、常識として考えられないことだが、それが義経のやり方だった。義経の兵は、「戦わされている」という感覚ではなく、「義経と共に戦っている」という感覚を持つことができた。だからこそ、兵士たちの志気が高まり、数に勝る相手を撃退することができたのだろう。
これも、アレキサンダー大王と同様である。天才には、やはり多くの共通点がある。
義経が初めての海戦で用いたのは、まず、船の漕ぎ手を狙い討つという戦法だった。当時、武士同士は戦っても、漕ぎ手はお互い攻めないのが、合戦の作法だった。
しかし、直接攻撃はしなくても、漕ぎ手も戦闘に積極的に加担しているのは、間違いない。義経は、この大切な決戦を確実に勝利に導くために、この戦法を選んだのだった。
予想もしていなかった義経の奇抜な作戦に、平氏の旗色はどんどん悪くなっていく。その上、阿波水軍が平氏から源氏へ寝返ったことで、平氏の敗北は決定的なものになる。阿波水軍から平氏軍の機密が源氏に伝えられ、小さな兵舟に隠れていた平氏の武将たちは、次々に討ち取られていく。
この時、平教経に一騎討ちを挑まれた義経が、舟から舟へと飛び移って翻弄したエピソードは有名。鎧兜に身を固め、不安定な舟の上でそれほどの身軽さを見せるとは、よほど強い足腰を持っていたらしい。教経はとても追いつけず、観念して海に沈んだ。
こうして、平氏は壇之浦で滅亡する。義経が平氏追討に立ってから、わずか1年余の電撃決着だった。まだ26歳の若武者だった義経だが、もはや、義経以上の戦上手は、天下に見当たらなかった。
しかし、獅子を滅ぼすのは、常に内側からの裏切りである。戦奉行の景時は、手柄を立てられなかった腹いせからか、頼朝に対して、「義経が、手柄を自分1人で立てたかのように吹聴している」との手紙を送る。
もともと、あまりにも人気があり、戦に強過ぎる義経を脅威と見ていた頼朝は、平氏の滅亡を機に、義経を潰す決断をする。
武士たちには義経に従うことを禁じ、さらに「兄弟の縁を切る」と義経に告げる。義経は、話し合いを求めて鎌倉に向かうが、頼朝は鎌倉入りを許さない。それどころか、義経の所領を取り上げる。さらに、京に戻った義経の屋敷に、頼朝の刺客が乱入するという事件まで起こった。
最大の功労者である義経に対して、あまりにもむご過ぎる裏切り。ここに至っては、義経も、鎌倉を敵に回す覚悟を固めざるを得なかった。しかし、鎌倉を攻めるには、あまりにも兵力がない。義経は、わずかな側近と共に、西国へ逃れた。朝廷までも、鎌倉を恐れて、最大の恩人である義経を見捨てた。
厳しい追手の目を逃れて、2年。山伏に化けた義経は、ようやく平泉の地に辿り着く。奥州の武士を率いて、鎌倉を討つ心積もりだった。しかし、奥州藤原氏も、結局は鎌倉からの圧力に屈し、義経を攻める。
もはや、この世のどこにも、義経の味方はいなかった。観念した義経は自決。享年、わずか30歳だった。
頼朝が、大軍を率いて奥州藤原氏を滅ぼしたのは、義経の死から、わずか5カ月後のことだった。歴史に「もし」は無いというけれども、仮に、奥州藤原氏が、戦の天才・義経を大将に立てて鎌倉と戦っていたなら、日本の歴史は、全く違う展開を見せていたかも知れない。小説の題材としては、興味深いテーマであろう。
後世の人々は、この不遇な若者が平泉で命を絶ったという悲惨な結末に、納得できなかった。そして、義経は平泉を脱け出し、日本など比べものにならない広大なユーラシア大陸に渡り、ジンギスカンと名乗って、アジアを駆け巡ったという伝説が生まれた。
一方、頼朝は、挙兵からわずか10年ほどで実質的に天下を平定し、史上初の幕府を開いた。以後は、数世紀に渡って武家政権が続くことになる。なお、一度は逆賊として義経を追った頼朝だが、後に悔い改めて永福寺を建て、義経を供養している。
没後900年を経た今もなお、義経は日本史上最大のヒーローとして、最も愛されている人物である。それは、彼の悲劇の生涯が、若者の純粋さと無限の可能性、そして、それを利用して生き残る狡猾な権力者という、いまだに変わらない社会の構図を象徴しているからなのかも知れない。
続きを読む
最初から読む
本編に登場する若き革命児……源頼朝 木曾義仲 源義経 佐藤兄弟
聖徳太子が日本の礎を築いてから500余年の年月が流れ、日本の歴史は、新たな転機を迎えようとしていた。
それまで日本を支配してきた貴族の体制が衰え、代わって、武士の台頭が著しかった。平氏と源氏が2大勢力として対立し、情勢は混沌として予断を許さない。今再び、日本を築き直すために、乱世を駆ける若者が必要とされていた。
源氏の御曹司である源義経は、そんな時代に生を受けた。幼名は、牛若丸。牛若がわずか1歳のとき、父・義朝は平時の乱に敗れ、殺された。母の常盤に連れられて、平清盛の元に自首し、命だけは助けられたが、母の元から離され、平氏の監視の元に、鞍馬山に預けられる。7歳のときだった。
このとき、牛若は、自分が源氏の御曹司であることを知らなかったという。それがいつ真相を知り、源氏の再興を誓ったのかは、定かではない。
一説には、武芸を教わった山伏から真相を聞かされたと伝えられる。この山伏の素性は明らかではないが、源氏に所縁のある人間であったことは、間違いないだろう。
牛若は、この山伏の手引きで、強力(荷担ぎ)に変装し、監視の目を盗んで、鞍馬山を脱け出したという。15歳のときだった。
京を離れた牛若が向かったのは、みちのく平泉だった。当時、みちのくでは、奥州藤原氏が巨大な勢力を誇り、さすがの平氏も力が及ばなかった。奥州藤原氏も、源氏が将来、力を持った場合に備えて、「源氏の御曹司をかくまった」という借りを作っておきたかった。
牛若は、平泉の地で武芸に励み、来たるべき時に備えた。当時の戦は、一騎討ちが作法だったので、大将に武芸のたしなみは必須だった。
それから1年後、牛若は、密かに京に向かっている。京では平氏が幅をきかせ、かむろという赤い服を着た少年たちに、平氏の悪口を言った者を取り締まらせていた。公家でさえ、平氏のやることに口出しできなかった。
ところが、平氏の侍たちでもかなわない、怪力の僧兵がいた。この僧兵の名は、武蔵坊弁慶。夜ごとに京の街に出没し、通りかかる侍を襲っては、刀を奪うという。
牛若は、清水観音の境内(五条大橋というのは伝説)で単身弁慶に挑み、軽業で翻弄して、降参させたという。当時の僧侶は、寺院の防衛を名目に、武芸に励んでいた。特に、興福寺や延暦寺の武力は、平氏さえ恐れさせていた。その中でも、随一のつわものだったという弁慶が、16歳の牛若丸に負けたとはにわかに信じがたいが、ともかく、弁慶は相手が源氏の御曹司と知ると、その場で家臣となった。
こうして、生涯の側近を得た牛若は、平泉に戻って元服し、源九郎義経を名乗った。
その後も、平氏はますます力をつけ、ついに清盛は、実の孫を天皇に即位させる(安徳天皇)。武士として初めて皇族となり、独裁的な権力を振るう清盛は、反発を招き、あちこちで、打倒平氏の旗が掲げられることになる。義経の兄である33歳の頼朝も、立ち上がった若武者の1人だった。
21歳になっていた義経は、兄の挙兵を知るや、参戦を決意。奥州一の武将として名高い、佐藤継信・忠信兄弟を従え、頼朝軍に合流する。このとき、継信は22歳、忠信は18歳という若さだったが、「この2人がいなければ、平氏は討てなかった」といわれるほどの働きをすることになる。
義経、継信、忠信。平氏追討は、実質的に、この3人の若武者によって成し遂げられることになるのだった。
しかし、鎌倉の開発が優先されたこともあって、頼朝は当初、義経を出陣させようとしなかった。それどころか、鶴岡八幡宮の上棟式で、頼朝は、義経に大工に贈る馬を引かせている。
馬を引くのは、臣従の意を示す行為で、本来、武将のすることではない。しかし頼朝は、実の弟だろうと、他の家来と区別しないことを示したかったと見える。
いかに腕が立っても、チャンスが与えられなければ、実力をアピールすることはできない。いたずらに、月日だけが流れていった。
義経が鎌倉でくすぶっている間、もう1人の若武者が、時代を大きく動かしていた。同族の木曾義仲だった。
義仲は、信州木曾谷で育てられた。26歳にして平氏を討つべく挙兵し、翌年には、北陸道を制圧する。若き武将はますます勢いを増し、倶利伽羅峠の戦いでは、牛の角に松明を結びつけて突進させるという奇抜な作戦で、平氏の大軍を打ち破った。
義仲は、比叡山の僧兵も味方につけ、ついに、絶大な権力を誇った平氏を、京から追い落とすことに成功した。このとき、義仲はまだ29歳。誰もが願いながらできなかったことを、20歳代の若き天才武将が成し遂げたのだった。平氏の都落ちにより、歴史の歯車は大きく回転し始める。
しかし、京に入った義仲は、打ち続く戦と飢饉で荒れ果てた都の様子に、唖然とする。もともと義仲は、京に入りさえすれば、家来に恩賞を取らせ、兵糧を補給できると考えていただけに、これは全くの計算外だった。
しかも、法皇は続けて、義仲に、「西国に逃げた平氏に追い討ちをかけ、安徳天皇と三種の神器を取り戻すよう」命ずる。義仲は渋々これに応じるが、命懸けで戦いながら、恩賞どころか兵糧さえ満足に補給されなかった家来たちの志気が上がるはずもなく、逆に、返り討ちにあってしまう。
ますます苦境に陥り、その日の食事にも事欠く義仲軍の末端では、京で庶民の財産や食料を略奪する者まで出始めた。もはや、義仲の力では、そのような家来たちを抑えることができなくなっていた。朝廷では、義仲への不満が高まり、義仲は孤立してしまった。
頼朝の元に、法皇から義仲追討が命じられたのは、そんなときだった。まず、義仲を利用して平氏を追い落とし、その後は源氏同士で争わせようというシナリオが、法皇の狙い通りに進んだと見える。
頼朝は奥州藤原氏を警戒していて、自身が鎌倉を空けるのは、避けたかった。そこでとうとう、義経に義仲追討の司令が下る。源氏同士で争うことは本意ではないが、こうなったら、源氏の汚名を濯ぐためにも、義仲を討たねばならない。こうして、待ちに待った初陣が決まった。時に、義経25歳、継信26歳、忠信22歳だった。
しかし、百戦錬磨の義仲に対して、義経には、実戦の経験が1度もない。義経の苦戦は、十分に予想された。が、蓋を開ければ、結果は義経の圧勝だった。その陰には、奥州1の武将として名高い佐藤兄弟の働きがあったことは、言うまでもない。こうして、義仲は京に入ってから、わずか半年で戦死する。まだ30歳だった。
義仲は、世間で言われているほど、ひどい武将ではない。それどころか、あれほどの強権を誇った平氏を怒濤の進撃で破り、都落ちさせた実績は、特筆に値する。が、都に入ればなんとかなるという読みの甘さが、命取りになった。
ともあれ、義仲はわずか5年ほどの間に己の天命を全うし、平氏打倒のバトンを義経に託して、歴史の舞台から去っていった。
義仲に代わって京に入った義経の評判は、すこぶる良かった。義仲の二の徹を踏まぬよう、十分に食料を持参し、兵士たちの略奪を禁じたからだった。法皇も、義経を重用した。だがそこには、いずれ頼朝が朝廷に口出ししてきたとき、義経を朝廷につけて源氏同士で争わせ、自滅させようという、したたかな計算が隠されていた。
頼朝は続けて、義経に、一ノ谷(神戸)に陣を張る平氏の追討を命じる。こうして、平泉で6年、鎌倉で4年、足掛け10年間、待ちに待った打倒平氏を、ついに実現できるときがやってきた!
義仲戦の疲れを癒す間もなく京を出た義経軍は、まず、丹波で夜営している平氏軍に夜討ちをかけて蹴散らした。その翌日、義経は、一ノ谷を背後から急襲する作戦を立てる。
一ノ谷は、前後を断崖と海に挟まれた、天然の要塞。義経は、この断崖を駆け降りて、平氏を攻めようというのだった。さっそく、地元の猟師である鷲尾三郎に鎧を取らせ、鹿の通る獣道を案内させる。
一度決断するや、義経の行動は稲妻のように早かった。翌朝、まだ暗いうちから、義経はわずか70騎を率い、一ノ谷を見下ろす鵯越に向かった。その、あまりの嶮しさに尻ごむ兵士たちを差し置き、義経は、自ら先頭に立って、絶壁を駆け下った。
その姿を見た兵士たちは奮い立ち、義経に続く。驚いたのは平氏軍だった。全く予想していなかった早朝からの奇襲に、槍をとる暇もなく、多くの武将を討ち取られ、海に敗走するしかなかった。
一ノ谷の合戦では、少数精鋭主義、家柄にこだわらない現地住民の活用、率先垂範、しきたりにとらわれない奇襲攻撃、短期決戦など、義経本来の戦い方が、遺憾なく発揮されている。
特に、夜討ち朝駆けや背後からの急襲などは、当時の武士の感覚からは、卑怯この上ないやり方になろうが、もともと大軍を擁していない義経にとって、最低限の犠牲で最大限の効果を挙げるには、これしかなかった。
日本で、このような奇襲が一般的な戦法として認められるのは、戦国時代からである。義経は、300年も時代を先取っていた。斬新な発想と、思い切った決断が、義経の最大の武器だった。
しかし、このあまりにも見事な勝利が、かえって頼朝に警戒心を抱かせることになった。頼朝は、今回の功績に対して、3人の源氏を国司に推薦したが、その中に、義経は含まれていなかった。
事態は、法皇の狙い通りに展開していった。法皇は、さらに頼朝と義経の関係を悪化させようと企て、義経に検非違使尉(警察の長官)の位を授ける。案の定、頼朝は自分に許可なく官位を得た義経に激怒し、次の平氏追討から、義経を外してしまった。
さらに、その年の10月、義経が昇殿を許されたことで、頼朝は再び激怒。もはや、義経は、このまま干され続けるかに見えた。
だが、もともと平氏のホームグラウンドである瀬戸内海では、義経を欠いた源氏は、なかなか攻めることができなかった。関東の山野を駆け巡ってきた源氏は、騎馬戦は得意でも、海戦は未経験。一方、平氏は、代々海運を生業として発展してきたくらいで、海戦は十八番中の十八番。ましてや、奥深い瀬戸内海では補給路も分断され、逃亡する兵士も出る始末。頼朝も、ここに至っては、戦の天才・義経を用いるしかなかった。

こうして翌年、義経はやっと参戦を認められる。しかし、頼朝が送ってきた戦奉行(司令官)の梶原景時は、あくまで、平氏の水軍と正面から激突するつもりだった。
それは、確かに武士らしい戦い方かもしれないが、多くの犠牲を出すことは、目に見えている。それに、鎌倉の武将たちは、海戦が陸とは全く勝手が違うことを、理解していなかった。このままでは、ほとんど勝ち目はない。
一方、京にとどまって戦況をつぶさに分析し続けていた義経は、平氏の、海戦での強さを知り抜いていた。そこで、相手の土俵である海ではなく、陸での戦いに持ち込むことを考えた。
平氏は、四国の屋島に陣を構えている。そこで義経は、わずかな兵を率いて、嵐の吹きすさぶ深夜の瀬戸内海を渡り、密かに四国に上陸。背後から屋島を急襲する。
平氏もまさか、嵐の海を渡ってくるとは予想外で、一時は海に逃げ出すが、義経が小勢と見るや、引き返して反撃に移る。この戦で、惜しくも、片腕と頼る佐藤継信が討たれる。まだ27歳だった。
義経は、継信の供養をした僧に、名馬・大夫黒を取らせたという。家臣を大切にする義経の姿は、兵士たちを奮い立たせた。
京でもそうだったが、義経は、人心を得るのが極めて上手かった。アレキサンダー大王のように、敵地の民衆をも味方につける、不思議な魅力があった。それも、私欲がなく、高潔な義経の人格によるものだろう。
ここ四国でも、義経は、現地の河野水軍や熊野水軍を味方につけ、もともと兵力で圧倒的に勝っていたはずの平氏軍を追いやってしまった。嵐が収まって、景時率いる本隊が駆けつけたときには、すでに戦は終わっていた。
こうして水軍を得た源氏軍は、いよいよ、壇之浦で最後の合戦に臨む。前回遅れを取った景時は、先陣を希望するが、義経はここでも、先陣をかって出て譲らない。もともと反りの合わなかった2人だが、ここに来て、対立は決定的になった。
総大将自らが、最も危険な先頭に立つのは、常識として考えられないことだが、それが義経のやり方だった。義経の兵は、「戦わされている」という感覚ではなく、「義経と共に戦っている」という感覚を持つことができた。だからこそ、兵士たちの志気が高まり、数に勝る相手を撃退することができたのだろう。
これも、アレキサンダー大王と同様である。天才には、やはり多くの共通点がある。
義経が初めての海戦で用いたのは、まず、船の漕ぎ手を狙い討つという戦法だった。当時、武士同士は戦っても、漕ぎ手はお互い攻めないのが、合戦の作法だった。
しかし、直接攻撃はしなくても、漕ぎ手も戦闘に積極的に加担しているのは、間違いない。義経は、この大切な決戦を確実に勝利に導くために、この戦法を選んだのだった。
予想もしていなかった義経の奇抜な作戦に、平氏の旗色はどんどん悪くなっていく。その上、阿波水軍が平氏から源氏へ寝返ったことで、平氏の敗北は決定的なものになる。阿波水軍から平氏軍の機密が源氏に伝えられ、小さな兵舟に隠れていた平氏の武将たちは、次々に討ち取られていく。
この時、平教経に一騎討ちを挑まれた義経が、舟から舟へと飛び移って翻弄したエピソードは有名。鎧兜に身を固め、不安定な舟の上でそれほどの身軽さを見せるとは、よほど強い足腰を持っていたらしい。教経はとても追いつけず、観念して海に沈んだ。
こうして、平氏は壇之浦で滅亡する。義経が平氏追討に立ってから、わずか1年余の電撃決着だった。まだ26歳の若武者だった義経だが、もはや、義経以上の戦上手は、天下に見当たらなかった。
しかし、獅子を滅ぼすのは、常に内側からの裏切りである。戦奉行の景時は、手柄を立てられなかった腹いせからか、頼朝に対して、「義経が、手柄を自分1人で立てたかのように吹聴している」との手紙を送る。
もともと、あまりにも人気があり、戦に強過ぎる義経を脅威と見ていた頼朝は、平氏の滅亡を機に、義経を潰す決断をする。
武士たちには義経に従うことを禁じ、さらに「兄弟の縁を切る」と義経に告げる。義経は、話し合いを求めて鎌倉に向かうが、頼朝は鎌倉入りを許さない。それどころか、義経の所領を取り上げる。さらに、京に戻った義経の屋敷に、頼朝の刺客が乱入するという事件まで起こった。
最大の功労者である義経に対して、あまりにもむご過ぎる裏切り。ここに至っては、義経も、鎌倉を敵に回す覚悟を固めざるを得なかった。しかし、鎌倉を攻めるには、あまりにも兵力がない。義経は、わずかな側近と共に、西国へ逃れた。朝廷までも、鎌倉を恐れて、最大の恩人である義経を見捨てた。
厳しい追手の目を逃れて、2年。山伏に化けた義経は、ようやく平泉の地に辿り着く。奥州の武士を率いて、鎌倉を討つ心積もりだった。しかし、奥州藤原氏も、結局は鎌倉からの圧力に屈し、義経を攻める。
もはや、この世のどこにも、義経の味方はいなかった。観念した義経は自決。享年、わずか30歳だった。
頼朝が、大軍を率いて奥州藤原氏を滅ぼしたのは、義経の死から、わずか5カ月後のことだった。歴史に「もし」は無いというけれども、仮に、奥州藤原氏が、戦の天才・義経を大将に立てて鎌倉と戦っていたなら、日本の歴史は、全く違う展開を見せていたかも知れない。小説の題材としては、興味深いテーマであろう。
後世の人々は、この不遇な若者が平泉で命を絶ったという悲惨な結末に、納得できなかった。そして、義経は平泉を脱け出し、日本など比べものにならない広大なユーラシア大陸に渡り、ジンギスカンと名乗って、アジアを駆け巡ったという伝説が生まれた。
一方、頼朝は、挙兵からわずか10年ほどで実質的に天下を平定し、史上初の幕府を開いた。以後は、数世紀に渡って武家政権が続くことになる。なお、一度は逆賊として義経を追った頼朝だが、後に悔い改めて永福寺を建て、義経を供養している。
没後900年を経た今もなお、義経は日本史上最大のヒーローとして、最も愛されている人物である。それは、彼の悲劇の生涯が、若者の純粋さと無限の可能性、そして、それを利用して生き残る狡猾な権力者という、いまだに変わらない社会の構図を象徴しているからなのかも知れない。
続きを読む
最初から読む




















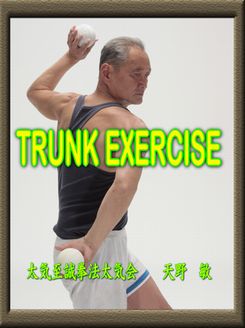

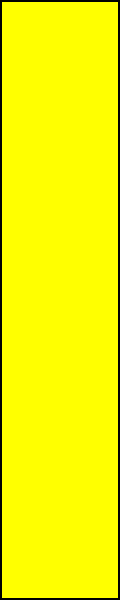





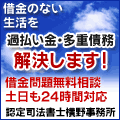
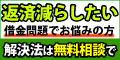






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます