安倍晋三首相が26日に財界幹部を集めて官邸で開く「官民対話」で、省エネ対策の一環として表明する。今月末にパリで始まる国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)に向けて、日本の温室効果ガス削減への取り組みを具体化する狙いもあるとみられる。
政府はLEDと蛍光灯それぞれについて、品目ごとに省エネ性能が最も優れた製品の基準を満たさないと製造や輸入をできなくする「トップランナー制度」で規制してきた。来夏をめどにつくる省エネ行動計画に、照明についての品目を一つにまとめることを盛り込む。LED並みの省エネを達成するのが困難な白熱灯と蛍光灯は、事実上、製造や輸入ができなくなる見通しだ。来年度にも省エネ法の政令を改める方針。
-----------
電球で比べると、LED電球の消費電力は、60ワット形相当で白熱電球の約8分の1で、電球型の蛍光ランプよりも約3割低い。政府は、30年度の温室効果ガス排出量を「13年度比26%減」とする削減目標の前提として、家庭などで使われている照明のほぼ100%を、30年度までにLEDにする目標を掲げるが、割高な価格がネックとなってLEDの比率は12年度で9%にとどまった。
白熱灯と蛍光灯の製造と輸入ができなくなれば、国内市場で在庫がなくなった時点で、LEDへの置き換えが急速に進み、量産効果でコストが下がることも期待される。ただ、割安な電灯を買う選択肢がなくなることになり、LEDの価格が下がらなければ、家計や企業の重荷になる可能性もある。
電球型のLEDが登場したのは09年前後。11年の東日本大震災後に省エネ意識が高まって一気に普及した。日本の大手電機メーカーでは、東芝ライテック、パナソニック、日立アプライアンスが一般的な白熱電球の生産をすでに終えている。電球型の蛍光ランプも、東芝ライテックが今年3月に生産をやめるなど、LED電球への切り替えが進んでいる。東芝ライテックによると、一般的なLED電球の希望小売価格は、09年の発売時に約1万円だったが、いまは2千~3千円台まで下がり、「店頭の販売価格はもっと安いだろう」(広報担当者)という。
蛍光灯が中心だった天井用照明でも、10年ごろからLEDが売り出されている。ただ、照明器具そのものをLED対応に切り替える必要があることから、電球ほどはLED化が進んでいない。LEDへの移行を後押しする支援策を求める声が出る可能性もある。(高木真也、南日慶子)
※11/28 朝日新聞 記事追記 http://digital.asahi.com/articles/ASHCT5JHKHCTULFA021.html?rm=416 (2015年11月26日05時00分) より
(管理人より) ”テクノクラート社会”がいよいよ本格化してきました。こういうのが実に迷惑なんです。目に悪いことが明らかになっているLED照明を、ついに市民に国策で強制してきましたね。
こういうことされると市民に選択肢がなくなってしまいます。デジタルテレビの時と同じ。メーカーと国が結託して、蛍光灯などを製造中止にしてしまえば、無理やりLEDを買わせることができるのですから実にいやらしい。
法律も改正して根拠を作り、ゴリ押ししてきます。一般家庭だけではなく学校の教室などもどんどんLEDに変えられていくでしょうね。まあ、恐ろしいことです。
大義名分が「温室効果ガス削減」。CO2温暖化説は誤りなのに。
LEDのノーベル賞も利権と強く結びついています。判断能力のない市民に対して、国や企業にとって都合のいい理論を、ノーベル賞の権威で刷り込んでいきます。
ノーベル賞受賞時のメディアの持ち上げ方は異常でした。これは環境問題を新たな商売の種にしているに過ぎないということです。再エネ政策と全く同じ構造。
目が悪くなるなどの悪影響が大学の研究者から報告されているのにLEDがノーベル賞を受賞するなんてどう考えてもおかしいです。
ノーベル賞自体がプロパガンダに使われています。
賞で権威付けし、市民が逆らえないような空気を醸成する。権威に弱く、情報弱者の市民がノーベル賞連発で喜んでいる様に、本当に恐怖を感じました。
NHKでも2014/7/23 に以下のような報道をしているのに・・・↓
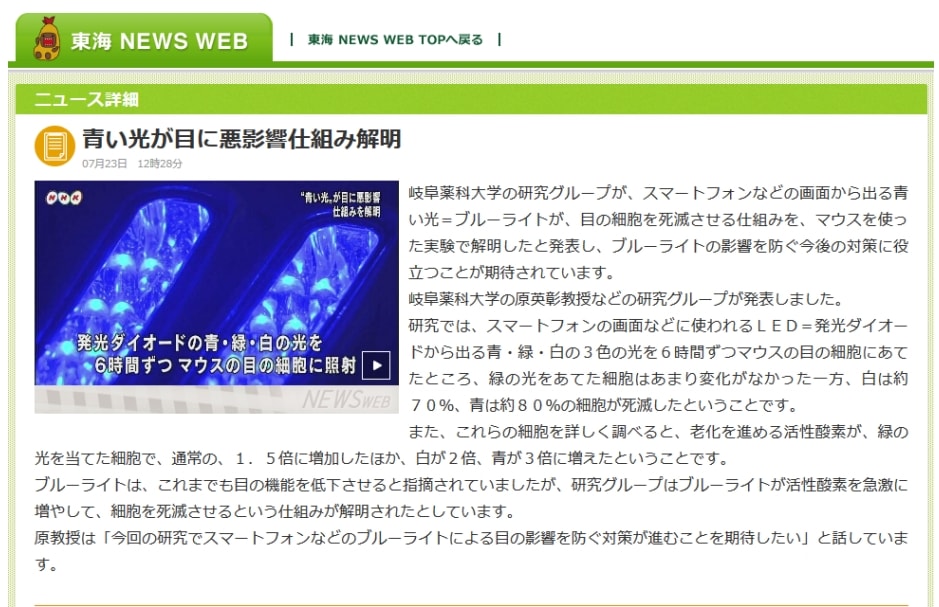
MEDIA KOKUSYO のLEDに関する記事です↓
青色LEDによる人体影響を示唆する体験談はネット上に複数ある、環境問題で優先されるのは被害の事実
実際に札幌市役所でLED照明により体調不良者が出ていることが日経新聞でも記事になっています。↓
法の“空白地帯”でLEDトラブル、札幌市
日本経済新聞 2010/8/26 23:00
急速に普及し始めたLED(発光ダイオード)照明。ところが、性能を定めた規格や基準の法整備が追い付いていない。庁舎内の蛍光灯をLED照明に交換した札幌市役所で今春、象徴的なトラブルが起こった。
札幌市が市役所の執務室や廊下にある約9000本の蛍光灯を直管型LED照明に取り換えたのは2010年3月のこと。その直後、一部の職員が「目が疲れる」「気分が悪い」といった体調不良を訴えた。市がアンケート調査した結果、「業務に支障がある」と答えた職員が7.4%に及んだ。

体調不良を訴えた職員がいる執務室のLED照明は、細かく点滅していた。「目の前で指を左右に動かすと、こま送りのように見えた」。同市庁舎管理課係長の池田政幸氏はこう話す。
「フリッカー」と呼ぶこうしたちらつきが生じる原因は、LED照明に内蔵する整流器にあった。LEDは直流で光るので、交流の電源を直流に変換する回路が必要となる。この役割を整流器が担う。
問題となったLED照明の整流器は、交流の電圧を凹凸のある直流の波形に変換していた。札幌市の場合、交流の周波数は50Hz。整流器を介した電圧は1秒間に100回の頻度でオンとオフを繰り返していた。 電圧の変化による明るさの変化は、蛍光灯でも起こる。ただし、LED照明は蛍光灯のように残光時間がなく、明るさが瞬時に変わる。その結果、ちらつきを感じやすくなる。
札幌市がLED照明の調達を4つの契約に分けて一般競争入札したのは09年12月。3つの契約をウチダシステムソリューション(札幌市)が、残りの1つをクリアス(東京都中央区)がそれぞれ落札した。 ちらつきが問題となったのは、クリアスが約1681万円で落札して納入したジェネライツ(東京都千代田区)製のLED照明2550本だ。
「数字で規制するのは難しい」
クリアス社長の竹之内崇氏は以下のように話す。「同タイプの整流器を内蔵するLED照明は世の中に何万本も出回っているが、特に問題は起こっていない」。同市役所では、LED照明が職員の目に入りやすい位置にあったり、新しい照明に対する個人の順応性が違ったりしたことで、体調不良を招いた可能性がある。
クリアスが納入したジェネライツ製のLED照明は、市の仕様に適合していた。市が入札の際、明るさや電圧の変動幅を制限するなど、ちらつきを抑えるための仕様を盛り込んでいなかったのだ。「仕様は蛍光灯の規格に準じてつくった。ちらつきが問題になるとは思ってもいなかった」(池田氏)
それでもクリアスは健康被害が出たことを重視。2550本すべてについて今後、電圧がゼロに落ちず、変化も少ない回路を備えた別のLED照明を納入し直す。詳細は決まっていないが、同社は追加費用を市に求めない方針だ。
こうしたトラブルの根本的な原因は、LED照明の規格や基準の法整備が進んでいないことにある。例えば、大半のLED照明は電気用品安全(PSE)法の規制対象外で、安全性が法的に担保されていない。
経済産業省は同法の政令改正の方針をようやく掲げた。11年3月までに電球形のほか、光源と灯具が一体のLED照明を規制対象に加える。
ただし、ちらつき防止の規定は「安定的に点灯動作するための装置を設ける」といった記述にとどめる見込み。「明るさや電圧の変動幅がいくらまでなら健康被害が生じないのか、客観的な数字で規制するのは難しい」(同省製品安全課)からだ。
日進月歩の技術に規制をかけるのは好ましくないという見方はある。しかし、規制がないばかりに玉石混交の製品が市場にあふれ、トラブルに巻き込まれた消費者が不信感を募らせるという不幸な状況も生まれている。時には変化を先取りした「攻め」の規格や基準の整備も必要だ。
- LED照明を国策で強制するな!(8)LEDメーカーのウシオ電機会長と安倍首相は姻戚関係という事実
- LED照明を国策で強制するな!(7)青色LEDで卵、幼虫、蛹、 成虫みんな死ぬ。可視光の生物に対する毒性
- LED照明を国策で強制するな!(6)グリーンエネルギークリスマスの電飾は再エネとLED利権=原子力ムラ
- LED照明を国策で強制するな!(5)省エネ政策のトップランナー制度は、原子力ムラ我田引水のシナリオ
- LED照明を国策で強制するな!(4)未来投資に向けた官民対話の出席者に経済三団体、日立、積水ハウスなど
- LED照明を国策で強制するな!(3)LEDにはインジウムやヒ素といった毒物が使われている
- LED照明を国策で強制するな!(2)有害物質を含むLED照明、落下の危険も?
- LED照明を国策で強制するな!(1)「目に悪影響」と大学が発表し、実際に健康被害も出ているのに!




























