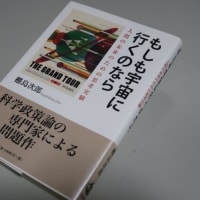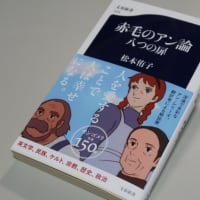☆『天災と国防』(寺田寅彦・著、講談社学術文庫)、『天災と日本人』(寺田寅彦・著、山折哲雄・編、角川ソフィア文庫)☆
東日本大震災、そしてそれに連なる原発事故のあと、災害や原発に警鐘を鳴らしてきた人たち、あるいは人間と自然との関係を問い直してきた人たちに、あらためて注目が集まった。一般には「天災は忘れた頃にやってくる」の言葉で知られる物理学者の寺田寅彦もその一人である。標記の2冊は今回の災害を受けて編まれた寺田寅彦のアンソロジーである。基本的な主旨は同じであるから、選ばれた文章は同じものもあるが、かなりのちがいも見られて興味深い。列挙してみると、
『天災と国防』 『天災と日本人』
・天災と国防 ・天災と国防
・火事教育 ・津浪と人間
・災難雑考 ・流言蜚語
・地震雑感 ・政治と科学
・静岡地震被害見学記 ・何故泣くか
・小爆発二件 ・震災日記より
・震災日記より ・颱風雑俎
・函館の大火について ・日本人の自然観
・流言蜚語
・神話と地球物理学
・津浪と人間
・厄年とetc
あらためて見てみると、編集の主旨は同じであると思われるのに、両方に重なる文章はたった4編しかない。(ちなみに「震災日記より」は大正12年の関東大震災の体験記であり、「津浪と人間」は昭和8年に起きた昭和三陸地震についての考察である) 岩波文庫版の『寺田寅彦随筆集』には若いころから親しんできたが、災害に関連した文章を寺田がいかに多く発表していたか、あらためて驚かされる。一方でちがいに注目すると、編集部あるいは編者の選択眼が反映されているようにも見える。
『天災と国防』では、編者にはなっていないが、かなりのページ数を割いた解説を畑村洋太郎さんが書いている。畑村さんは「失敗学」を提唱した工学者として知られ、今回の原発事故の事故調査・検証委員会委員長を務めている。畑村さんの解説の視点は、科学者としての寺田寅彦に向けられている。とはいえ、科学技術のハード面を論じているわけではなく、むしろヒューマン・ファクターを含むリスクやエラーについての考察を進めている。
しかし、その視点はあくまで工学者のものである。たとえば、寺田の「文明が進むに従って人間は次第に自然を征服しようとする野心を生じた」(「天災と国防」)の言葉を文明批評として受け取るのではなく、防災論(技術論)として捉えようとしている。それはそれで一つの見識である。また、東京電力の過ちを、東電が内部基準を持たず、外部基準(国が示している基準)のみに頼ってきた姿勢にあるともしている。これも一つの見方ではあるが、畑村さんの真意はわからないものの「ここで東京電力のことをことさら責める気はない」という言葉に違和感を持つ人がいるかもしれない。「技術論でいうと、原子力はかなり安全なものになってはいるが、基本的な視点が欠けているように見える」の「かなり安全なもの」にも同様なものを感じる。
『天災と日本人』の方は宗教学者の山折哲雄さんが編者となっている。山折さんは東北大学で学び、宗教や日本文化などに関する著作を多数著している。こちらは最後に「日本人の自然観」が収められており、そこがもっとも特徴的である。山折さんの解説も主に「日本人の自然観」を受けた内容になっている。また、災害とは一見無関係のように見える「何故泣くか」が入っているのも、おもしろい選択である。
山折さんは、寺田が自然を「慈母」であると同時に「厳父」でもあるといっていることに注目する。さらに「仏教の根底にある無常観が日本人のおのずからな自然観と相調和する」との言葉(視線)に注意を促し、寺田のいわば感性的な側面について論じている。山折さんの視点は畑村さんの視点とは明らかに異なっており、感性的な面も寺田を理解するうえで忘れてはならないように思う。
寺田寅彦は地球物理学を専門とし、地震などの研究をした一方で、身近な現象をユニークな視点から研究したことでも知られている。さらに、夏目漱石を師として仰ぎ、俳句をものにした人物でもある。このような興味関心の幅広さや感性豊かな人間性が彼の随筆に凝縮されており、その随筆が理科系の人間のみならず多くの人たちによっていまだに読み継がれている所以は、そこにあるのだろう。
寺田の随筆からは、科学技術的な視点からであれ、感性的な視点からであれ、多くのことが学び得るように思う。しかしながら、科学技術的な理解に偏ったり、あるいは感性的な側面に安住することを、たぶん寺田はよしとはしないだろう。期せずして、この2冊のアンソロジー(とくに、その解説)を読み比べることで、複眼的に見ることの重要性が浮かび上がってくるように思われる。

東日本大震災、そしてそれに連なる原発事故のあと、災害や原発に警鐘を鳴らしてきた人たち、あるいは人間と自然との関係を問い直してきた人たちに、あらためて注目が集まった。一般には「天災は忘れた頃にやってくる」の言葉で知られる物理学者の寺田寅彦もその一人である。標記の2冊は今回の災害を受けて編まれた寺田寅彦のアンソロジーである。基本的な主旨は同じであるから、選ばれた文章は同じものもあるが、かなりのちがいも見られて興味深い。列挙してみると、
『天災と国防』 『天災と日本人』
・天災と国防 ・天災と国防
・火事教育 ・津浪と人間
・災難雑考 ・流言蜚語
・地震雑感 ・政治と科学
・静岡地震被害見学記 ・何故泣くか
・小爆発二件 ・震災日記より
・震災日記より ・颱風雑俎
・函館の大火について ・日本人の自然観
・流言蜚語
・神話と地球物理学
・津浪と人間
・厄年とetc
あらためて見てみると、編集の主旨は同じであると思われるのに、両方に重なる文章はたった4編しかない。(ちなみに「震災日記より」は大正12年の関東大震災の体験記であり、「津浪と人間」は昭和8年に起きた昭和三陸地震についての考察である) 岩波文庫版の『寺田寅彦随筆集』には若いころから親しんできたが、災害に関連した文章を寺田がいかに多く発表していたか、あらためて驚かされる。一方でちがいに注目すると、編集部あるいは編者の選択眼が反映されているようにも見える。
『天災と国防』では、編者にはなっていないが、かなりのページ数を割いた解説を畑村洋太郎さんが書いている。畑村さんは「失敗学」を提唱した工学者として知られ、今回の原発事故の事故調査・検証委員会委員長を務めている。畑村さんの解説の視点は、科学者としての寺田寅彦に向けられている。とはいえ、科学技術のハード面を論じているわけではなく、むしろヒューマン・ファクターを含むリスクやエラーについての考察を進めている。
しかし、その視点はあくまで工学者のものである。たとえば、寺田の「文明が進むに従って人間は次第に自然を征服しようとする野心を生じた」(「天災と国防」)の言葉を文明批評として受け取るのではなく、防災論(技術論)として捉えようとしている。それはそれで一つの見識である。また、東京電力の過ちを、東電が内部基準を持たず、外部基準(国が示している基準)のみに頼ってきた姿勢にあるともしている。これも一つの見方ではあるが、畑村さんの真意はわからないものの「ここで東京電力のことをことさら責める気はない」という言葉に違和感を持つ人がいるかもしれない。「技術論でいうと、原子力はかなり安全なものになってはいるが、基本的な視点が欠けているように見える」の「かなり安全なもの」にも同様なものを感じる。
『天災と日本人』の方は宗教学者の山折哲雄さんが編者となっている。山折さんは東北大学で学び、宗教や日本文化などに関する著作を多数著している。こちらは最後に「日本人の自然観」が収められており、そこがもっとも特徴的である。山折さんの解説も主に「日本人の自然観」を受けた内容になっている。また、災害とは一見無関係のように見える「何故泣くか」が入っているのも、おもしろい選択である。
山折さんは、寺田が自然を「慈母」であると同時に「厳父」でもあるといっていることに注目する。さらに「仏教の根底にある無常観が日本人のおのずからな自然観と相調和する」との言葉(視線)に注意を促し、寺田のいわば感性的な側面について論じている。山折さんの視点は畑村さんの視点とは明らかに異なっており、感性的な面も寺田を理解するうえで忘れてはならないように思う。
寺田寅彦は地球物理学を専門とし、地震などの研究をした一方で、身近な現象をユニークな視点から研究したことでも知られている。さらに、夏目漱石を師として仰ぎ、俳句をものにした人物でもある。このような興味関心の幅広さや感性豊かな人間性が彼の随筆に凝縮されており、その随筆が理科系の人間のみならず多くの人たちによっていまだに読み継がれている所以は、そこにあるのだろう。
寺田の随筆からは、科学技術的な視点からであれ、感性的な視点からであれ、多くのことが学び得るように思う。しかしながら、科学技術的な理解に偏ったり、あるいは感性的な側面に安住することを、たぶん寺田はよしとはしないだろう。期せずして、この2冊のアンソロジー(とくに、その解説)を読み比べることで、複眼的に見ることの重要性が浮かび上がってくるように思われる。