第二章 柳田國男の保守主義
柳田國男の創始した日本民俗学は、究極に於て何を目指すものであろうか。この問いを自らに課した柳田学の高弟折口信夫は、自身の得た結論を次のように語る。
「先生のあゝした学問は、どういう動機ではじめられ、先生の学問の目的はどこにすゑられてあったか、そう言う事の探究は、後来の人の研究に任すより、我々の方が確かなものを得ていると言へませう。一口に言へば、先生の学問は‘神’を目的としてゐる。日本の神の研究は、先生の学問の着手された最初の目的であり、其が又、今日において最明らかな対象として浮き上って見えるのです。」(「先生の学問」昭21・9)
このころ柳田は『新国学談』全三冊を刊行しているが、その作業は、「新国学談を世に出す為には、自分は文字通り寝食を忘れていた」と述べられるような性質のものであった。「どうして又其様にまで、急いで此本を書いて置こうとしたのか。心有る人ならばすぐにその下心を看破ることが出来るが、看破られるよりも自分で語った方がよい。神社はどうなるのだろうかといふことは、如何にも今日は萬人の疑問となって居る。そうして稀には大胆にその疑問に、答えようとする人もないとは限らぬが、正直にいふと誰にもそんな資格は無い。日本人の予言力は既に試験せられ、全部が落第といふことにもう決定したのである。是からは蝸牛(かたつむり)の匐ふほどな速力を以って、まず其予言力を育てて行かねばならぬのだが、私などはただ学問より以外には、人を賢こくする途はないと思って居る」(『新国学談』)
このような感慨はまた、『先祖の話』(昭・20)の序文で述べられた「今度といふ今度は十分に確実な、又しても反動の犠牲となってしまはぬような、民族の自然と最もよく調和した、新たな社会組織が考え出されなければならぬ」という決意とも通ずるようなものを含んでいた。この序に於てもやはり「国民をそれぞれに賢明ならしめる道は、学問よりも他に無い」と断定されている。
「山に死者の霊魂が先づ入って行き、次第に高く清らかなる處に登っては行くが、久しい約束があって、春秋の初の満月の夜頃に故郷の家に還って来るものと、我々の祖先たちは考え又は想像した」。
『新国学談』で示されたこのような見解は、『田社考大要』(昭・25)では次のように拡張されている。
「人の霊魂がもしも死と共に消えてしまはぬものならば、必ず生きてゐる間の最も痛切な意思、即ち子孫後裔の安全の為に、何か役に立とうという念慮くらゐは、いつ乞も持ち続けられるだろうと、昔は生きてゐるうちから、そう思ってゐた者が多かったのである。我が邦固有の神の信仰には、こういう推理の基礎があり、無言の約束への期待があり、これに対する無限の感謝があって、各人思ひ思ひの祈願は無く、且つ又何でもかでも有るだけの欲望をすべて叶へて下さるものとも、始めから信じてはゐなかった。近代の解釈は無論改定せられてゐるだろうが、ともかくこれは日本の常民の持ち伝へた信仰の特徴であり、同時に又大小諸種の客神の、外から次々と入って来る余地でもあった」。
柳田は、氏神信仰の歴史的な変遷過程の解明と、日本人の信仰形態の復原とを、同時におこなった。柳田は、「私は折口氏などとちがって、盆に来る精霊も正月の年神も、共に家々の祖神だろうと思って居るのである」と、折口との差異を強調するような発言もしている。その折口信夫は、「柳田先生のやうな優れた、何百年に一人か二人しかないやうなお方だと、人間生活のもつ複雑性をうまく見抜れますが、普通の人には、なかなかそれが出来ないのです」(「山の生活」)とも言っているが、しかし彼もやはり熱烈に神を求めた人である。『民族史観における他界観念』はその豊かな成果であった。折口の求めた神は、柳田のそれとはどこか異なっている。一口に言えば、柳田の求めた神は、折口のもとめた神より大きかった。柳田の神の「探究」は、次の歌に示されるような、ある意味でグロテスクな文学的支えを必要としなかった。
神ここに 敗れたまひぬ
すさのをも おほくにぬしも
青垣の内つ御庭(ミニハ)の
宮出でゝ さすらひたまふ
(折口信夫『近代悲傷集』「神 やぶれたまふ」)
むろんこの二人の考えは根本的に同質でありいわば伴信友と平田篤胤が同じである程度に同じだった。柳田は『神道私見』(大・10)で既に次のように語っている。
「所謂平田派の神道と云ふものは、ごく危ない二つの仮定を基礎として立っている。その二つの仮定と申しますのは、一つは喜式時代までの千五百年間には日本の神道には何等の変遷が無かったと云ふこと、第二にはその後の八、九百年間には非常に激しい混乱があったと云ふこと、此二つの仮定を立脚地として居るのであります。(中略)……玄に於てか自分が衷心より景慕の情を表せざるのを得ぬのは伴信友であります。伴翁は平田翁と同じ時分に世に出て、同じ様な学風に浸って居られながら、而も其研究の態度は別であった。どうしても解釈のつかないことは斯う云う事実があるが理由は分からぬ。又はこの點は斯うかもしれぬが確かには言へないと云う風で、断定を避けて専ら材料の蒐集に心を用ゐられた」。
ここで柳田は、国学の方法について語ると同時に、民俗学の方法についても語ろうとしているのは明白である。国学と目的・志向を同じゅうするがゆえに新国学と名づけられた柳田の学問と、宣長の学問の違いも実はこの方法的差異が主なものである。宣長の国学が中心に置いたのは文献資料であり、それは『古事記』その他であった。いっぽう、柳田は「現実に残って居るものならば、至って幽かな切れ切れの記憶と言ひ伝へ、寧ろ忘れそこなひと謂ってもよい隅々の無意識伝承を、少しも粗末にせず湛念に拾い合せて、今まで心づかづに居たことを問題にして行く」(「鼠(ねずみ)の浄土」)という方法を採った。
宣長も柳田も、共に日本の固有信仰の原形を求めて過去へと遡る。しかし、宣長の文献学的な遡行には、決定的な限界があった。書かれたものだけを方法的に問題としたという点で宣長は、自分が批判した儒教の学者と同じ近世的偏見を免れてはいない。両者の争いは、学問の正当性がどの書物によって保証されるか、という本末転倒の議論に堕する危険性を常にはらんでいた。両者は共に、文献資料で確定される限りの過去しか問題にしえなかったのである。しかも、神典の解読が学の中心に置かれ続ける限り、その仕事は、たとえ上首尾にやりおおせたとしても、文芸批評家の仕事以上に出ることはできない。事実、国学は歌学への関心から出発している。儒学もまた、儒書の注釈がその本来の仕事(ワーク)である。
「都鄙遠近のこまごまとした差等が、各地の生活相の新旧を段階づけて居る。その多くの事実の観測と比較とによって、もし伝わってさえ居てくれるならば、大体に変化の道程を跡付けられるものである」(『先祖の話』)
つまり、柳田は民衆生活の「残留資料(フォークロア)」の空間的分布の比較分析によって、段階的に何処までも時間を遡って行く方法を編み出した。柳田は編み出したその方法によって、いわば学を「言語空間」の枠から開放し、国学的古代研究のレベルから、決定的に飛躍したのである。
「実は自分は現代生活の横断面、すなわち毎日われわれの眼前に出ては消える事実のみに拠って、立派に歴史は書けるものだと思って居る」(『明治大正史世相篇』)とは、その方法に対する特異な自信の程をのぞかせる発言である。(ただしその試みは「失敗した」とこの書に関しては述べている。おそらく日本民俗学の方法論を典型的に示した成功例は古語の退縮過程を検証した『蝸牛考』であると思われる。)
宣長も柳田も、一国の固有の伝統を総体として問題にしたという点で、共通の志向に貫かれていた。しかし、以上のべたように、後者(新国学)は前者(国学)の批判の契機を本質的に内包していたのである。
柳田は、最晩年に、固有信仰の研究から日本民族の起源を巡る問題へと、研究対象の重心を移動している。南島研究の諸論考をとりまとめた『海上の道』こそは、その豊かな成果である。ところで、柳田の民俗学の初期の最大関心事は「山人」の問題にあった。しかし、たとえば「山」と「海」のようなかけ離れたものが、柳田学の内部ではどのように結びつくのか?
「その中でも私等が一番興味を有って見て居るのは、紀州の熊野の海岸の文化、是が大きな仕事をして居ることである。熊野の御山は大変な高い山に祭られている。中世に始めて現われた神様である。……記録が焼けたり失われたりして居るが、熊野の権現様などは、陸地は何處を通って来たといふ言ひ伝へがなくて、船から渡られたらしい痕跡が残っている。船で渡って来るといふと、人は海岸に祭ってなければならぬやうに思ふが、是が熊野といふ信仰の一つの特徴であった。即ち熊野人は山の民であって同時に船に乗る民であった。現在でも山の人間と海の人間とはカテゴリーが違ふやうに考えて居る人もあるが、木をくぼめて舟を造る人間は山の人間であり、又海の人間でなければならぬ」(「海上文化」)。
すなわち、ここでは、山の信仰と海上生活との関係が、紀州の伝統文化に即して考察されている。柳田の探求した諸領域は、内部で網の目のように縦横に連結されている。このことが、柳田を探検するおもしろさを生む理由であり、また柳田学の全貌が容易に見極め難い原因にもなっている。
《参考までに、「山と海」の問題は、折口の場合にはどう考えられたか。
「譬へば、我々が旅行をして、海岸近い山を遠くから見ると、海からずっと浮び出てゐる山の様に見えます。(中略)普通、山の信仰は、山の根元でなく或距離があって、山を始終目にしてゐる土地から起ります。其處から山へ精進しに登って行くのです。海岸地方ならば、海の中から生えてゐる、と思はれる山が信仰の対象になる事が多いのです。そんな現象が起るのは、何故かと申しますと、海から神が出現して来る、といふ信仰があって、其神は、山の方へ登ってゆく、と信じてゐたからなのです」。(「春来る鬼」)
海から出現した神が山へ登って行く光景を、舟に揺られながら見ているような臨場感がある。ここでの折口の推理などは天才的であり、めくるめくまでに美しい。ただし、その仮設が検証できる性質のものか、という問題が残る。いづれにせよ、柳田との差は歴然としている。》
柳田は、真の保守主義を打ち立てるべく、次の如く主張している。
「真の保守主義はやはり亦、歴史の正しい研究から起って、我々の生活の中で維持しなければならぬ現状は何々であるかを考え、若しくは同じ昔風と言っても、過去に於ける不当不必要な改革に由って、中頃以来新たに設けられたものを、再び排除するのもやはり一つの保守事業である。」(『日本農民史』)
柳田の保守主義は、このような問題関心に支えられたものであった。

















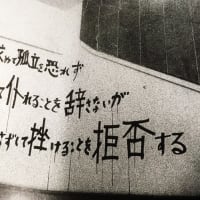


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます