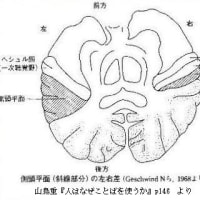私は自分の祖父母を知らない。どんな人だったかは伝え聞いている。どんな風貌の人だったかはセピア色の写真で見た事がある。私の家族は選択肢なしに核家族だったと言える。
そんな私だから義理の祖母が90歳を超えるまで長生きをした彼女を愛おしくさえ思った。昔は「可愛いお婆ちゃん」が街のあちこちに見られた。自分も高齢者予備軍に席を置いているが、あと10年もしたらそんな風に思われたい。無理かな?! メルボルンで会った90歳近いお婆ちゃんが「私の結婚前の名前はLoveだったけど結婚して Darlingという姓に変わったのよ。でも主人が先に亡くなって、私はまたMiss Loveって呼んで貰うのが嬉しいわ」と言った時、冗談かと思った。本当にMiss Loveから Mrs Darlingになったんですって。でもそのお婆ちゃん、名前を聞かなくても充分にLady Loveだった!
最近、日本では祖父母が孫の手で殺人事件に巻き込まれる事が多いのに目を見張る。お婆ちゃんお爺ちゃんが、自分の分野からはみ出してとやかく所謂「親風」を負荷しすぎなのだろうか。年寄りが「学」が有り過ぎて「親の姿勢がじれったくなる」とか「孫に過大な期待を持って采配を揮い過ぎる」のか? 年寄りが自由に使うお金が有り過ぎるのか、そんな時間も有り過ぎるのか。とにかく過剰が犯罪のきっかけを作るような気がしてならないのは私だけだろうか。人間が持つべきハングリー精神がないのが老若男女、現代の日本人だと言ったら、それこそ言い過ぎだろうか。
かつて自分の子供達が幼い頃、子供番組で「ダメダメダメママ!」というような歌が始終流れていたのが記憶にある。あの歌が私に対しては「ダメ!」を禁語にして「煩くないママ」の道をまっしぐらに進ませたと苦笑いしながら思い出す。小学校高学年になってくると、子供も色々な事に対して「ウザイ!(煩い!)」という表示を出し始める。
人間は「止めろ!」と言われるとやりたくなるし、「やりなさい!」と命令されると止めたくなるものである。子といっても、また孫といっても、所詮独りの個人である。人の事ばかりに神経を磨り減らさず、自分に神経を使う年寄りって、何か素敵なような気がする。
かつて私は「老後」という言葉を取り上げた事がある。私には老後はないと言い切ってしまおう。何故なら、老いの後に来るのは「死」だけだからである。そして今、私は「老人」という言葉に封印をして「年寄り」という言葉を大切にしたい、と本気で思っている。そもそも「年寄り」という言葉は歴史に残る職名で、武家時代、政務に参与した重臣、また室町幕府の評定衆・引付衆、江戸幕府の老中、大名家の家老などがある、若年寄などもよく聞く。更に、江戸幕府の大奥の取り締まりを司った女中の重職も年寄りといい、江戸時代、町村の行政にあたった指導的立場の人をいうと覚えていたらいいという訳である。今、イザコザが起きている大相撲の世界では、関取以上の力士が引退して年寄名跡を襲名した者や継承した者を年寄といって日本相撲協会の運営や各部屋の力士養成に当たるのである。
「年寄り」イコール「指導的立場の人」という事を年寄りも若者もしっかり把握すれば悲劇は避けられるのではないかと思う私はやっぱりプラス人間だと思う。「年寄りに新湯は毒」と言っては強い刺激は避け、「年寄りの冷や水」も避ける事を念頭に若者に接する事が出来るようなお婆ちゃんを目指して生きていきたいな、と思う。
そんな私だから義理の祖母が90歳を超えるまで長生きをした彼女を愛おしくさえ思った。昔は「可愛いお婆ちゃん」が街のあちこちに見られた。自分も高齢者予備軍に席を置いているが、あと10年もしたらそんな風に思われたい。無理かな?! メルボルンで会った90歳近いお婆ちゃんが「私の結婚前の名前はLoveだったけど結婚して Darlingという姓に変わったのよ。でも主人が先に亡くなって、私はまたMiss Loveって呼んで貰うのが嬉しいわ」と言った時、冗談かと思った。本当にMiss Loveから Mrs Darlingになったんですって。でもそのお婆ちゃん、名前を聞かなくても充分にLady Loveだった!
最近、日本では祖父母が孫の手で殺人事件に巻き込まれる事が多いのに目を見張る。お婆ちゃんお爺ちゃんが、自分の分野からはみ出してとやかく所謂「親風」を負荷しすぎなのだろうか。年寄りが「学」が有り過ぎて「親の姿勢がじれったくなる」とか「孫に過大な期待を持って采配を揮い過ぎる」のか? 年寄りが自由に使うお金が有り過ぎるのか、そんな時間も有り過ぎるのか。とにかく過剰が犯罪のきっかけを作るような気がしてならないのは私だけだろうか。人間が持つべきハングリー精神がないのが老若男女、現代の日本人だと言ったら、それこそ言い過ぎだろうか。
かつて自分の子供達が幼い頃、子供番組で「ダメダメダメママ!」というような歌が始終流れていたのが記憶にある。あの歌が私に対しては「ダメ!」を禁語にして「煩くないママ」の道をまっしぐらに進ませたと苦笑いしながら思い出す。小学校高学年になってくると、子供も色々な事に対して「ウザイ!(煩い!)」という表示を出し始める。
人間は「止めろ!」と言われるとやりたくなるし、「やりなさい!」と命令されると止めたくなるものである。子といっても、また孫といっても、所詮独りの個人である。人の事ばかりに神経を磨り減らさず、自分に神経を使う年寄りって、何か素敵なような気がする。
かつて私は「老後」という言葉を取り上げた事がある。私には老後はないと言い切ってしまおう。何故なら、老いの後に来るのは「死」だけだからである。そして今、私は「老人」という言葉に封印をして「年寄り」という言葉を大切にしたい、と本気で思っている。そもそも「年寄り」という言葉は歴史に残る職名で、武家時代、政務に参与した重臣、また室町幕府の評定衆・引付衆、江戸幕府の老中、大名家の家老などがある、若年寄などもよく聞く。更に、江戸幕府の大奥の取り締まりを司った女中の重職も年寄りといい、江戸時代、町村の行政にあたった指導的立場の人をいうと覚えていたらいいという訳である。今、イザコザが起きている大相撲の世界では、関取以上の力士が引退して年寄名跡を襲名した者や継承した者を年寄といって日本相撲協会の運営や各部屋の力士養成に当たるのである。
「年寄り」イコール「指導的立場の人」という事を年寄りも若者もしっかり把握すれば悲劇は避けられるのではないかと思う私はやっぱりプラス人間だと思う。「年寄りに新湯は毒」と言っては強い刺激は避け、「年寄りの冷や水」も避ける事を念頭に若者に接する事が出来るようなお婆ちゃんを目指して生きていきたいな、と思う。