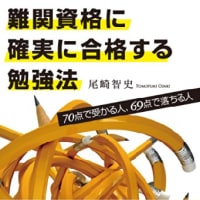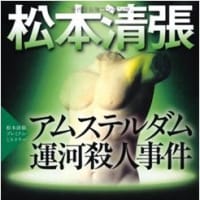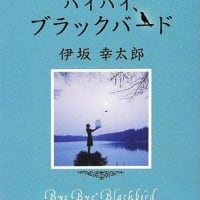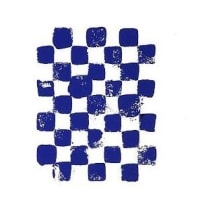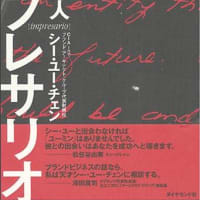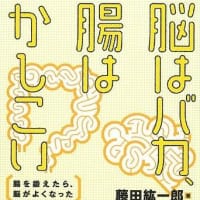本作の重要な脇役に井伊直弼がいます。「篤姫」では、松平慶永と井伊直弼が将軍家定と篤姫の御前でトップ面接を受けます。慶永がドイツ式の雄藩による合議体を主張したのに対し、直弼は徳川家を中心にした強い幕府の存続を主張します。尚、本作では、「安政五年四月二十三日六つ半(午前七時)すぎ、直弼が登城すると、将軍家定から御座の間で上意があり、大老職を命じられ」ましたが、再三辞退したい旨を告げたとあります。

いずれにしても、直弼が徳川家を中心にした強い幕府を主張したことは史実のようですが、彼がこうした意見を持つに至った経緯を本作では次のような場面で描いています。藩主になった直弼は五回にわたる領内巡視に赴きますが、道中の宿にした、北海道の開拓に活躍した近江商人、藤野四郎兵衛の屋敷で「そなた、商いにとってなにより大事なものは、どんなものだと思われる?」と聞き、四郎兵衛は次のように答えます。
「はい。それは、ご先祖さまと世間さま。そのふたつでございましょうか。・・・店は、ご先祖さまからの預かりもの。店が栄えるのは、すべてご先祖さまのお蔭でございますゆえ。・・・商いはもとより世間さまを抜きには語れますまい」
「領外に出て商いを営む近江の商人は、おそらく皆一様に肝に銘じておることでございましょうが、他国に赴いて、商いをいたしますときは、その国を他国と思わず、その地の民すべてを大事にすることが肝要でございます。売り手が存するにも、買い手があってのこそのこと。そして、両者の商いが成就しますのも、すべては神仏のお恵みがあってのこと」「世間さまのことを忘れて、私利私欲を貪っては、所詮は先が見えてしまいます。商いは牛の涎(よだれ)とも申しますゆえ。・・・細く、長くが肝要と・・・」
こうした四郎兵衛の発言が、直弼に井伊家の存続の重要性、ひいては徳川家の存続への強い主張に繋がったのだろうと考えられます。
さて、この小説が「藍色のベンチャー」として連載されたのは、京都新聞で2002年7月3日~2003年7月22日、中部経済新聞で2002年7月16日~2003年10月11日。時は、小泉首相の在任期間(2001年4月26日-2006年9月26日)にあたります。一方、本書では水野忠邦(1794-1851)の「天保の改革」(1841-1843)が行われた時期を描き、主人公の半兵衛とその妻・留津に次のようなダイアローグを語らせています。
「やれ改革やなんやとか言うてはるけど、うちらにばっかり痛みを押しつけて、お役人ら本人がわが身大事では、なんのための改革かわからへん、先のことをちゃんと考えて、大きな目で世の中全体の将来を見て役人が、どれだけいることか」
「そうやな。留津、三方領地替えみたいなもんも、誰が見てもおかしい。お上が、なんとかひいきの大名にええ思いをさせようというのが見え見えや。世の中の実情やら、そこに住んでいる庶民の心情を全然知らん役人連中が、ただ屋敷のなかだけで考えて物事を決めて、それで世の中を変えようと目論んでも、的外れのええとこや」
三方領地(領知)替えとは、「江戸時代に徳川幕府が行った大名に対する転封処分の手法のひとつ。大名3家の領地(知行地)を互いに交換させることを言う。例えば、領地aを持っている大名家Aを領地bへ、領地bを持っている大名家Bを領地cへ、領地cを持っている大名家Cを領地aへ同時に転封すること」。
「三方」といえば、小泉首相の在任当時の「三方一両損」のキャッチフレーズがありました。これは、大岡越前守のお裁きのお噺ですが、近江商人の心得として「三方よし」があります。
三方よし(さんぽうよし)
「近江商人の行商は、他国で商売をし、やがて開店することが本務であり、旅先の人々の信頼を得ることが何より大切であった。そのための心得として説かれたのが、売り手よし、買い手よし、世間よしの「三方よし」である。取引は、当事者だけでなく、世間の為にもなるものでなければならないことを強調した「三方よし」の原典は、宝暦四(1754)年の中村治兵衛宗岸の書置である」。
本書では、この近江商人の経営術や経営理念としての「乗合商い」や「飢饉普請」が描かれています。
更に、本作では近江商人特有の経営手法として次の二つのポイントが描かれています。
乗合商い(のりあいあきない)
「多店舗展開のための資金調達の方法として創出されたのが、乗合商い(組合商い)と呼ばれる一種の合資形態をとった共同企業の形成である。酒造業を中心とする矢尾喜兵衛家の出店網は、地元の酒造業者から施設店舗を居抜きで借り受け、奉公人を支配人として送り込むやり方で作られた。その動機には、資本の有効活用・危険分散・人材の活用という、経営合理主義が貫いていた」。
飢饉普請(ききんぶしん)
「天保7~8(1836~7)年の飢饉のとき、藤野四郎兵衛は郷里の窮民救助の一策として、住宅を改築し、寺院仏堂を修築した。最初、領主の彦根藩は譴責しようとしたが、すぐに四郎兵衛の真意を了解し、嘆賞したといわれる。この慈善事業が、飢饉普請と呼ばれて後世に伝えられたものである。明治19(1886)年の関東地方の飢饉においても、埼玉の騎西の出店で小森久左衛門が同様の美挙を行った」。
<「三方よし」ミニ情報-用語解説-近江商人関係>
http://www.shigaplaza.or.jp/sanpou/mini_info/ohmi_businessman.html#
また、近江商人の経営手法には女性がしっかり組み込まれてもいました。
「汐踏みというのは、若いころの留津のように、上(かみ)女中として行儀見習いに奉公に上がる若い娘のことを言う。『辛い目を見る』という意味の『塩を踏む』から来ている呼び名だ。豪商の家には、文人や茶道華道の大家などさまざまな文化人が長逗留することも多く、貴重な蔵書も揃っている。だから良家の子女でも汐踏みとして大店(おおだな)に奉公に上がり、単に労働力となるためではなく、むしろ商家の娘なりの実地教育として、商いのあうんの呼吸や、気働きなどを教わったのである」。
「そうして商家に稼ぐための教育を受けた、すぐれた娘たちが、妻として内助の功を発揮し、近江商人たちのめざましい成長の一翼を担ったことは言うまでもない。女性の地位が低かった時代にありながらも、大店のなかでの、とくに人事管理や雇い人の教育において、妻は大きな実権を握り、その存在は家そのものにも多大な影響を与えていた」。
「大店の妻は、汐踏みの上女中のなかから適任者を選び、奉公人の結婚の世話もする。その結果奉公人が祝言をあげると、その妻は郷里に戻って亭主の留守を守るのだが、その若い妻と、大店の主の妻との関係も、主従のつながりに準ずるようになるのである」。
そんな近江商人は「近江泥棒に、伊勢乞食」といわれていたようです。
「泥棒というのは、はいってきて持ち帰るから近江商人。それに対して、乞食というのは、座っていて通るか人から取るから伊勢の商人」
半兵衛が築いた窯を藩窯として召し上げた彦根藩は、職人の就業規則をかなり適正に決め、運用したようです。
「夜勤もしっかりあるし、まあ、夏のほうが長う働くことになるけど、給金も出来高払いから日払いになったそうや、その代わり、作ったもんは帳面に書けということやな。喜平がうちに来てくれる休みの日も、毎月一日と十五日、それから五節句と決められている。年末は二十五日が仕事仕舞いで、正月は十一日が仕事始めというのまで、きちんと決めて身持ちのよい暮らしをするようにという藩の役人らの気遣いなのやろ。だらだら働かされることもないし、まあ、職人にとっては、幸せなことやないか」
幸田真音さんはあとがきで次のように記しています。
「こうした素晴しい日本の宝物(湖東焼)は、近江や京だけではなく、この国のいたるところにまだたくさん埋もれているはずだ。そうした宝物探しは、病んだ現代のわれわれに、深い示唆を与えてくれるだろうし、この国が持っている大きな底力を思い出させてくれるに違いない」
彦根にとっての幸運は、こうした埋もれた歴史を掘り返した幸田真音さんがいたことであるでしょう。

井伊 直弼(いい なおすけ;文化12年10月29日(1815年11月29日)- 安政7年3月3日(1860年3月24日))は、「近江彦根藩の第15代藩主。江戸幕府の大老である。幼名は鉄之介・鉄三郎。字は応卿。号は埋木舎・柳王舎・宗観。第13代藩主・井伊直中の十四男。本来ならば他家に養子に行く身であったが、兄で14代藩主・井伊直亮の養子となる。その後、第15代藩主となり、安政の大獄を行なって反対派を処罰するなどして、事実上の幕府最高権力者となるが、大獄に対する反発から桜田門外で水戸浪士らに暗殺された」。

松平 春嶽 / 慶永(まつだいら しゅんがく / よしなが;文政11年9月2日(1828年10月10日)-明治23年(1890年)6月2日)は、「江戸時代後期の大名、第16代越前福井藩主。[1]明治の政治家である。諱は慶永、号は春嶽(なお嶽は岳の旧字体であるが、春嶽の場合はなぜか現在でも旧字で表記されることの方が多い)。田安徳川家第3代当主・徳川斉匡の八男。松平斉善の養子。将軍徳川家慶の従兄弟。英邁な藩主で後に幕末の四賢侯に数えられた。明治維新後の初期にも重要な役割を果たした」。(ウィキペディア)

いずれにしても、直弼が徳川家を中心にした強い幕府を主張したことは史実のようですが、彼がこうした意見を持つに至った経緯を本作では次のような場面で描いています。藩主になった直弼は五回にわたる領内巡視に赴きますが、道中の宿にした、北海道の開拓に活躍した近江商人、藤野四郎兵衛の屋敷で「そなた、商いにとってなにより大事なものは、どんなものだと思われる?」と聞き、四郎兵衛は次のように答えます。
「はい。それは、ご先祖さまと世間さま。そのふたつでございましょうか。・・・店は、ご先祖さまからの預かりもの。店が栄えるのは、すべてご先祖さまのお蔭でございますゆえ。・・・商いはもとより世間さまを抜きには語れますまい」
「領外に出て商いを営む近江の商人は、おそらく皆一様に肝に銘じておることでございましょうが、他国に赴いて、商いをいたしますときは、その国を他国と思わず、その地の民すべてを大事にすることが肝要でございます。売り手が存するにも、買い手があってのこそのこと。そして、両者の商いが成就しますのも、すべては神仏のお恵みがあってのこと」「世間さまのことを忘れて、私利私欲を貪っては、所詮は先が見えてしまいます。商いは牛の涎(よだれ)とも申しますゆえ。・・・細く、長くが肝要と・・・」
こうした四郎兵衛の発言が、直弼に井伊家の存続の重要性、ひいては徳川家の存続への強い主張に繋がったのだろうと考えられます。
さて、この小説が「藍色のベンチャー」として連載されたのは、京都新聞で2002年7月3日~2003年7月22日、中部経済新聞で2002年7月16日~2003年10月11日。時は、小泉首相の在任期間(2001年4月26日-2006年9月26日)にあたります。一方、本書では水野忠邦(1794-1851)の「天保の改革」(1841-1843)が行われた時期を描き、主人公の半兵衛とその妻・留津に次のようなダイアローグを語らせています。
「やれ改革やなんやとか言うてはるけど、うちらにばっかり痛みを押しつけて、お役人ら本人がわが身大事では、なんのための改革かわからへん、先のことをちゃんと考えて、大きな目で世の中全体の将来を見て役人が、どれだけいることか」
「そうやな。留津、三方領地替えみたいなもんも、誰が見てもおかしい。お上が、なんとかひいきの大名にええ思いをさせようというのが見え見えや。世の中の実情やら、そこに住んでいる庶民の心情を全然知らん役人連中が、ただ屋敷のなかだけで考えて物事を決めて、それで世の中を変えようと目論んでも、的外れのええとこや」
三方領地(領知)替えとは、「江戸時代に徳川幕府が行った大名に対する転封処分の手法のひとつ。大名3家の領地(知行地)を互いに交換させることを言う。例えば、領地aを持っている大名家Aを領地bへ、領地bを持っている大名家Bを領地cへ、領地cを持っている大名家Cを領地aへ同時に転封すること」。
「三方」といえば、小泉首相の在任当時の「三方一両損」のキャッチフレーズがありました。これは、大岡越前守のお裁きのお噺ですが、近江商人の心得として「三方よし」があります。
三方よし(さんぽうよし)
「近江商人の行商は、他国で商売をし、やがて開店することが本務であり、旅先の人々の信頼を得ることが何より大切であった。そのための心得として説かれたのが、売り手よし、買い手よし、世間よしの「三方よし」である。取引は、当事者だけでなく、世間の為にもなるものでなければならないことを強調した「三方よし」の原典は、宝暦四(1754)年の中村治兵衛宗岸の書置である」。
本書では、この近江商人の経営術や経営理念としての「乗合商い」や「飢饉普請」が描かれています。
更に、本作では近江商人特有の経営手法として次の二つのポイントが描かれています。
乗合商い(のりあいあきない)
「多店舗展開のための資金調達の方法として創出されたのが、乗合商い(組合商い)と呼ばれる一種の合資形態をとった共同企業の形成である。酒造業を中心とする矢尾喜兵衛家の出店網は、地元の酒造業者から施設店舗を居抜きで借り受け、奉公人を支配人として送り込むやり方で作られた。その動機には、資本の有効活用・危険分散・人材の活用という、経営合理主義が貫いていた」。
飢饉普請(ききんぶしん)
「天保7~8(1836~7)年の飢饉のとき、藤野四郎兵衛は郷里の窮民救助の一策として、住宅を改築し、寺院仏堂を修築した。最初、領主の彦根藩は譴責しようとしたが、すぐに四郎兵衛の真意を了解し、嘆賞したといわれる。この慈善事業が、飢饉普請と呼ばれて後世に伝えられたものである。明治19(1886)年の関東地方の飢饉においても、埼玉の騎西の出店で小森久左衛門が同様の美挙を行った」。
<「三方よし」ミニ情報-用語解説-近江商人関係>
http://www.shigaplaza.or.jp/sanpou/mini_info/ohmi_businessman.html#
また、近江商人の経営手法には女性がしっかり組み込まれてもいました。
「汐踏みというのは、若いころの留津のように、上(かみ)女中として行儀見習いに奉公に上がる若い娘のことを言う。『辛い目を見る』という意味の『塩を踏む』から来ている呼び名だ。豪商の家には、文人や茶道華道の大家などさまざまな文化人が長逗留することも多く、貴重な蔵書も揃っている。だから良家の子女でも汐踏みとして大店(おおだな)に奉公に上がり、単に労働力となるためではなく、むしろ商家の娘なりの実地教育として、商いのあうんの呼吸や、気働きなどを教わったのである」。
「そうして商家に稼ぐための教育を受けた、すぐれた娘たちが、妻として内助の功を発揮し、近江商人たちのめざましい成長の一翼を担ったことは言うまでもない。女性の地位が低かった時代にありながらも、大店のなかでの、とくに人事管理や雇い人の教育において、妻は大きな実権を握り、その存在は家そのものにも多大な影響を与えていた」。
「大店の妻は、汐踏みの上女中のなかから適任者を選び、奉公人の結婚の世話もする。その結果奉公人が祝言をあげると、その妻は郷里に戻って亭主の留守を守るのだが、その若い妻と、大店の主の妻との関係も、主従のつながりに準ずるようになるのである」。
そんな近江商人は「近江泥棒に、伊勢乞食」といわれていたようです。
「泥棒というのは、はいってきて持ち帰るから近江商人。それに対して、乞食というのは、座っていて通るか人から取るから伊勢の商人」
半兵衛が築いた窯を藩窯として召し上げた彦根藩は、職人の就業規則をかなり適正に決め、運用したようです。
「夜勤もしっかりあるし、まあ、夏のほうが長う働くことになるけど、給金も出来高払いから日払いになったそうや、その代わり、作ったもんは帳面に書けということやな。喜平がうちに来てくれる休みの日も、毎月一日と十五日、それから五節句と決められている。年末は二十五日が仕事仕舞いで、正月は十一日が仕事始めというのまで、きちんと決めて身持ちのよい暮らしをするようにという藩の役人らの気遣いなのやろ。だらだら働かされることもないし、まあ、職人にとっては、幸せなことやないか」
幸田真音さんはあとがきで次のように記しています。
「こうした素晴しい日本の宝物(湖東焼)は、近江や京だけではなく、この国のいたるところにまだたくさん埋もれているはずだ。そうした宝物探しは、病んだ現代のわれわれに、深い示唆を与えてくれるだろうし、この国が持っている大きな底力を思い出させてくれるに違いない」
彦根にとっての幸運は、こうした埋もれた歴史を掘り返した幸田真音さんがいたことであるでしょう。

井伊 直弼(いい なおすけ;文化12年10月29日(1815年11月29日)- 安政7年3月3日(1860年3月24日))は、「近江彦根藩の第15代藩主。江戸幕府の大老である。幼名は鉄之介・鉄三郎。字は応卿。号は埋木舎・柳王舎・宗観。第13代藩主・井伊直中の十四男。本来ならば他家に養子に行く身であったが、兄で14代藩主・井伊直亮の養子となる。その後、第15代藩主となり、安政の大獄を行なって反対派を処罰するなどして、事実上の幕府最高権力者となるが、大獄に対する反発から桜田門外で水戸浪士らに暗殺された」。

松平 春嶽 / 慶永(まつだいら しゅんがく / よしなが;文政11年9月2日(1828年10月10日)-明治23年(1890年)6月2日)は、「江戸時代後期の大名、第16代越前福井藩主。[1]明治の政治家である。諱は慶永、号は春嶽(なお嶽は岳の旧字体であるが、春嶽の場合はなぜか現在でも旧字で表記されることの方が多い)。田安徳川家第3代当主・徳川斉匡の八男。松平斉善の養子。将軍徳川家慶の従兄弟。英邁な藩主で後に幕末の四賢侯に数えられた。明治維新後の初期にも重要な役割を果たした」。(ウィキペディア)