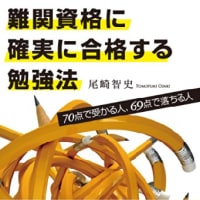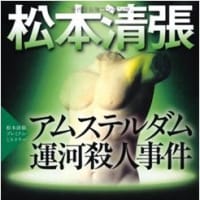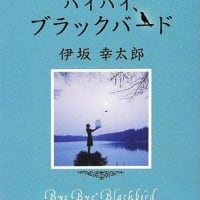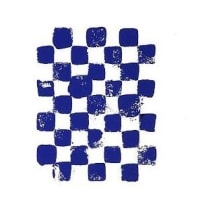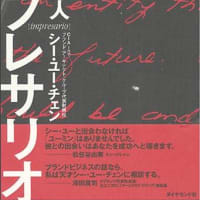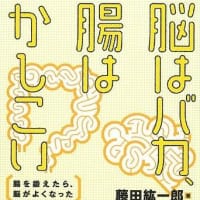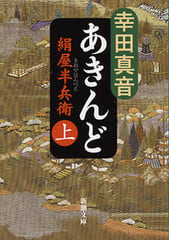
本書は、実在した呉服、古着商を営む彦根(滋賀県)の商人絹屋半兵衛等によって1829年に伊万里から陶工をスカウトして窯を築いて始められた湖東焼の物語であり、幕末に「安政の大獄」(1858)による粛清を行い、「桜田門外の変」(1860)で暗殺された近江彦根藩の第15代藩主で江戸幕府の大老、井伊直弼の物語でもあります。更に、事実には登場しない絹屋半兵衛の16歳年下の後妻・留津との夫婦愛の物語でもあります。まず、史実は次のようになっています。
~幕末文政(1818-1829/11代将軍徳川家斉)の頃、彦根の商人絹屋半兵衛が当時先端技術の華であった磁器の焼成導入を考えて伊万里の職人を招き、佐和山山麓に築いた窯で成功させたのがそもそものはじめである。国産奨励は諸藩の風潮彦根藩は特に強力に援助し、十年にして彦根焼・湖東焼の名は確立された。~
~天保年間(1830-1843/家斉~12代将軍徳川家慶)、井伊直亮(なおあき)のとき、召上げて藩直営に移した。藩窯は直亮の代八年、直弼の代十年が盛期、直憲の代二年は終末期で、通算二十年の短い歴史にすぎないが、焼成技術は景徳鎮・伊万里に劣らない世界最高の水準、絵付けにいたっては緻密豪華高尚湖東焼独特の味を完成した。~

~磁器の原料石は天草産に少量の彦根物生山の石を混ぜ、呉須染付の品はすべて藩の茶碗山の窯で焼き、赤絵金欄手の類は、素地すべて藩の窯で焼いたのち、藩の絵付窯で絵付けすることも多かったが、城下町や近在の民家に据えられた錦窯と呼ぶ小さい絵付け窯でも焼かれた。民家赤絵湖東焼と呼ばれるものである。~
(NPO法人湖東焼を育てる会http://www.kotoyaki.com/history.html)
*1)磁器(じき);高温で焼成されて吸水性がなく、叩いた時に金属音を発する陶磁器。
*2)焼成(しょうせい);原料を高熱で焼いて性質に変化を生じさせること。粘土を窯(かま)で加熱して石質にするなど。
*3)金襴手(きんらんで);器に金箔や金粉で表した文様のことで、あたかも金襴を散りばめたようにみえることから名づけられたものです。色絵の上に金彩色を施した磁器。中国、明代に流行し日本に輸入された。器物は碗が最も多い

近江商人といえば、大阪商人、伊勢商人(三重県)と並ぶ日本三大商人のひとつですが、これまで近江、彦根がどこのことを指しているのか自覚することがありませんでしたが、本作を通じて印象づきました。滋賀県を指して「湖国」、彦根市は、滋賀県の北東部に位置する都市であることから、「湖東焼」の由来となるんですね。
本作は上述したような歴史小説ですが、「三貨制度」(P370)、「借銀」(P364)、「彦根藩からの融資の実情」(P452)など、当時の経済状況が詳細に記述されているなど、そこはやはり幸田さんの真骨頂です。
~幕末文政(1818-1829/11代将軍徳川家斉)の頃、彦根の商人絹屋半兵衛が当時先端技術の華であった磁器の焼成導入を考えて伊万里の職人を招き、佐和山山麓に築いた窯で成功させたのがそもそものはじめである。国産奨励は諸藩の風潮彦根藩は特に強力に援助し、十年にして彦根焼・湖東焼の名は確立された。~
~天保年間(1830-1843/家斉~12代将軍徳川家慶)、井伊直亮(なおあき)のとき、召上げて藩直営に移した。藩窯は直亮の代八年、直弼の代十年が盛期、直憲の代二年は終末期で、通算二十年の短い歴史にすぎないが、焼成技術は景徳鎮・伊万里に劣らない世界最高の水準、絵付けにいたっては緻密豪華高尚湖東焼独特の味を完成した。~

~磁器の原料石は天草産に少量の彦根物生山の石を混ぜ、呉須染付の品はすべて藩の茶碗山の窯で焼き、赤絵金欄手の類は、素地すべて藩の窯で焼いたのち、藩の絵付窯で絵付けすることも多かったが、城下町や近在の民家に据えられた錦窯と呼ぶ小さい絵付け窯でも焼かれた。民家赤絵湖東焼と呼ばれるものである。~
(NPO法人湖東焼を育てる会http://www.kotoyaki.com/history.html)
*1)磁器(じき);高温で焼成されて吸水性がなく、叩いた時に金属音を発する陶磁器。
*2)焼成(しょうせい);原料を高熱で焼いて性質に変化を生じさせること。粘土を窯(かま)で加熱して石質にするなど。
*3)金襴手(きんらんで);器に金箔や金粉で表した文様のことで、あたかも金襴を散りばめたようにみえることから名づけられたものです。色絵の上に金彩色を施した磁器。中国、明代に流行し日本に輸入された。器物は碗が最も多い

近江商人といえば、大阪商人、伊勢商人(三重県)と並ぶ日本三大商人のひとつですが、これまで近江、彦根がどこのことを指しているのか自覚することがありませんでしたが、本作を通じて印象づきました。滋賀県を指して「湖国」、彦根市は、滋賀県の北東部に位置する都市であることから、「湖東焼」の由来となるんですね。
本作は上述したような歴史小説ですが、「三貨制度」(P370)、「借銀」(P364)、「彦根藩からの融資の実情」(P452)など、当時の経済状況が詳細に記述されているなど、そこはやはり幸田さんの真骨頂です。