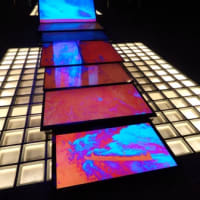ずっと楽しみにしていたワシントンDCのフリーア&サックラー・ギャラリーでの俵屋宗達展に、終了日前日、ようやく行くことができた。
フリーア・ギャラリーとサックラー・ギャラリーは共にスミソニアン博物館群に属するアジア美術の美術館で、隣接して建ち、内部は通路でつながっている。フリーア・ギャラリーはデトロイトの鉄道王チャールズ・ラング・フリーアが蒐集し寄贈した美術品を所蔵している。本展出品作品は、フリーア・ギャラリー所蔵の作品に、アメリカ、ヨーロッパ、日本所在の作品を加えて総数63点(展示替えあり)。フリーアが寄贈した作品は、外部での展示、貸出をしないことが条件になっているため、ここでしか見られない宗達作品がまとめて見られる貴重な機会だ。日本からは屏風などの大きな作品は来ていないが、今回のお目当ては何と言ってもフリーア・ギャラリーの<松島図屏風>と<雲龍図屏風>である。

サックラー・ギャラリー。先週末のブリザードで一面の雪。
展示会場の入り口正面に早くも<松島図屏風>が姿を現す。六曲一双の屏風で、右隻には島、左隻には松の木が描かれ、それらの周囲を荒々しく渦巻く波が覆っている。松の緑や波涛の白など絵具の色も鮮やかで、波が墨と金で交互にひかれた線で表わされているのも端正だ。左隻の松が生えている州浜のラインは右隻にそのままつながっているので、左右の光景は同じ距離から見たものかと思わせるが、左隻の松と右隻の島に生える松とは大きさが全然違う。右隻の金雲は州浜の続きではなく、たなびく霞なのかもしれない。右隻の島のかたちもおかしくて、キュビズムに似てどの方向から見たものなのか定かでなく、波の表現とも相まって、真横から見ているようにも、俯瞰しているようにも見える。そんなふうに視点と視線で翻弄されていたら、私自身が渦巻く波に取り巻かれ、波の上で揺られているような気分になった。この不思議な絵の狙いは、そんな身体感覚をもたらすことにあるのだろうか。
2つの展示室を過ぎて地下1階から2階に下りると、そこに<雲龍図屏風>があった。<雲龍図屏風>も六曲一双の屏風で、一度には視野におさめきれない規模の作品である。右隻と左隻に一匹ずつ龍がいる。足やしっぽのほうまで描かれているのが面白いなあと思いながら見ていた時、それぞれの龍の格好が<風神雷神図屏風>の風神・雷神のそれによく似ていることに気が付いた。左隻の龍の前足のかたちは、雷神の腕の大きな動きにそっくりだ。そう思って見ると、右隻の龍の胴体は右下から左上へと弧を描いていて、風神の白い風袋のかたちと似ている。二つの屏風がどういう関係にあるのかはわからない。この発見はちょっと嬉しかったけれど、この屏風にも不思議な点が残る。龍のかたちに不自然なところが多いのだ。特に右隻の龍の、首のかたちがおかしくて、顔の上下に胴体が見えるけれど、顔・首からはどう考えてもうまくつながらない。
宗達の絵が、こんなふうに、見る者に身体的な効果を与えたり、落ち着かなくさせたりするような仕掛けをもったものだとは、今まで知らなかった。人の身体と対峙し、空間を作り出す、屏風だからこその仕掛けではあろう。日本にある屏風作品もできるだけ見て、宗達が何を目指していたのか、もっと考えてみたくなった。
その他、本阿弥光悦とのコラボレーション作品を集めた部屋では、美しい色紙や和歌巻が並ぶ中で、活字印刷による「嵯峨本」のうち<光悦謡本>に出会えたのも、最近、辻邦生の『嵯峨野明月記』を読んだことから嬉しいことだった。
日本とアメリカ各地から集められた<伊勢物語色紙>は計10点、展示替えがあって見られたのは5点だが、いずれも古さを感じさせないほどに保存状態がよく、絵具が色鮮やかで驚いた。
同じ部屋にあった<西行物語絵巻>は文化庁所蔵の渡辺家本。ちょうどギャラリーツアーをしていた担当学芸員さんによると、この絵巻が海外で展示されるのは1939年のベルリンでの日本古美術展以来のことだという。
さらに同じ部屋にあった<扇面貼付屏風>もフリーア・ギャラリーの所蔵作品。扇にさまざまな絵が描かれているので目を凝らすと、なんと馬に乗った武士二人が互いに相手の首を搔こうとしているものがある。隣には鳥の図柄ののどかな扇。解説によると、開いている30の扇のうち、保元物語を描いたものが13、平治物語が3、北野天神縁起が2、伊勢物語が2、花木図が7、花鳥図が2、亀の図が1なのだという。こんなふうに、いろいろな物語の場面を取り合わせるものだとは知らなかったので、へえ、と思うけれど、組み合わせがちょっとシュール。
Sotatsu: Making Waves
(1/30/2016, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution)
フリーア・ギャラリーとサックラー・ギャラリーは共にスミソニアン博物館群に属するアジア美術の美術館で、隣接して建ち、内部は通路でつながっている。フリーア・ギャラリーはデトロイトの鉄道王チャールズ・ラング・フリーアが蒐集し寄贈した美術品を所蔵している。本展出品作品は、フリーア・ギャラリー所蔵の作品に、アメリカ、ヨーロッパ、日本所在の作品を加えて総数63点(展示替えあり)。フリーアが寄贈した作品は、外部での展示、貸出をしないことが条件になっているため、ここでしか見られない宗達作品がまとめて見られる貴重な機会だ。日本からは屏風などの大きな作品は来ていないが、今回のお目当ては何と言ってもフリーア・ギャラリーの<松島図屏風>と<雲龍図屏風>である。

サックラー・ギャラリー。先週末のブリザードで一面の雪。
展示会場の入り口正面に早くも<松島図屏風>が姿を現す。六曲一双の屏風で、右隻には島、左隻には松の木が描かれ、それらの周囲を荒々しく渦巻く波が覆っている。松の緑や波涛の白など絵具の色も鮮やかで、波が墨と金で交互にひかれた線で表わされているのも端正だ。左隻の松が生えている州浜のラインは右隻にそのままつながっているので、左右の光景は同じ距離から見たものかと思わせるが、左隻の松と右隻の島に生える松とは大きさが全然違う。右隻の金雲は州浜の続きではなく、たなびく霞なのかもしれない。右隻の島のかたちもおかしくて、キュビズムに似てどの方向から見たものなのか定かでなく、波の表現とも相まって、真横から見ているようにも、俯瞰しているようにも見える。そんなふうに視点と視線で翻弄されていたら、私自身が渦巻く波に取り巻かれ、波の上で揺られているような気分になった。この不思議な絵の狙いは、そんな身体感覚をもたらすことにあるのだろうか。
2つの展示室を過ぎて地下1階から2階に下りると、そこに<雲龍図屏風>があった。<雲龍図屏風>も六曲一双の屏風で、一度には視野におさめきれない規模の作品である。右隻と左隻に一匹ずつ龍がいる。足やしっぽのほうまで描かれているのが面白いなあと思いながら見ていた時、それぞれの龍の格好が<風神雷神図屏風>の風神・雷神のそれによく似ていることに気が付いた。左隻の龍の前足のかたちは、雷神の腕の大きな動きにそっくりだ。そう思って見ると、右隻の龍の胴体は右下から左上へと弧を描いていて、風神の白い風袋のかたちと似ている。二つの屏風がどういう関係にあるのかはわからない。この発見はちょっと嬉しかったけれど、この屏風にも不思議な点が残る。龍のかたちに不自然なところが多いのだ。特に右隻の龍の、首のかたちがおかしくて、顔の上下に胴体が見えるけれど、顔・首からはどう考えてもうまくつながらない。
宗達の絵が、こんなふうに、見る者に身体的な効果を与えたり、落ち着かなくさせたりするような仕掛けをもったものだとは、今まで知らなかった。人の身体と対峙し、空間を作り出す、屏風だからこその仕掛けではあろう。日本にある屏風作品もできるだけ見て、宗達が何を目指していたのか、もっと考えてみたくなった。
その他、本阿弥光悦とのコラボレーション作品を集めた部屋では、美しい色紙や和歌巻が並ぶ中で、活字印刷による「嵯峨本」のうち<光悦謡本>に出会えたのも、最近、辻邦生の『嵯峨野明月記』を読んだことから嬉しいことだった。
日本とアメリカ各地から集められた<伊勢物語色紙>は計10点、展示替えがあって見られたのは5点だが、いずれも古さを感じさせないほどに保存状態がよく、絵具が色鮮やかで驚いた。
同じ部屋にあった<西行物語絵巻>は文化庁所蔵の渡辺家本。ちょうどギャラリーツアーをしていた担当学芸員さんによると、この絵巻が海外で展示されるのは1939年のベルリンでの日本古美術展以来のことだという。
さらに同じ部屋にあった<扇面貼付屏風>もフリーア・ギャラリーの所蔵作品。扇にさまざまな絵が描かれているので目を凝らすと、なんと馬に乗った武士二人が互いに相手の首を搔こうとしているものがある。隣には鳥の図柄ののどかな扇。解説によると、開いている30の扇のうち、保元物語を描いたものが13、平治物語が3、北野天神縁起が2、伊勢物語が2、花木図が7、花鳥図が2、亀の図が1なのだという。こんなふうに、いろいろな物語の場面を取り合わせるものだとは知らなかったので、へえ、と思うけれど、組み合わせがちょっとシュール。
Sotatsu: Making Waves
(1/30/2016, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution)