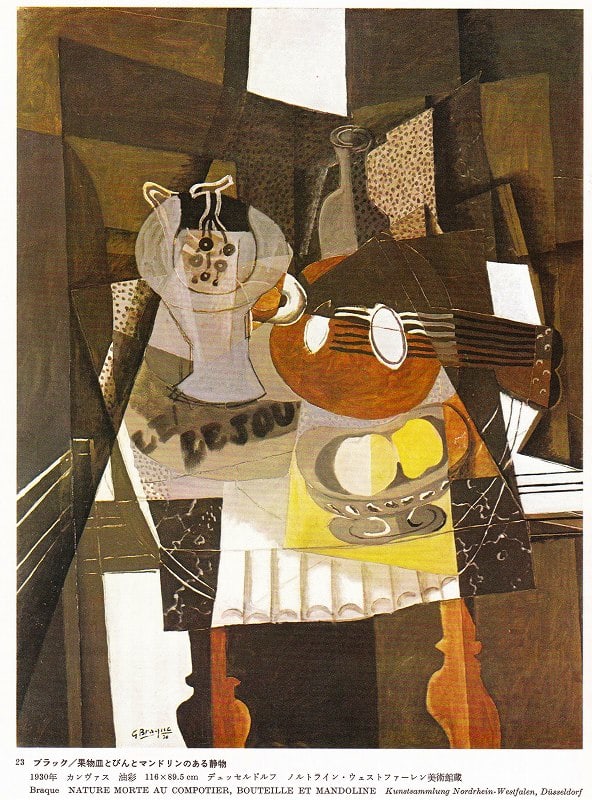(西の品川神社に対する東の荏原神社)
これまで言われてきた日本的企業風土である終身雇用制、年功序列、学歴偏重などとともに、具体的な経営方法としては、職務権限の不明確からくる稟議制度などに象徴される責任の曖昧さなどの諸点が、最近では、かなり崩れてきて、途中採用に見られる雇用の流動性の増加や学歴無視、具体的な実績に基づく勤務評価による報酬体系の確立など、かなり欧米諸国並の企業風土に変貌しつつあることは、否定できない現実であろう。
しかし、そうは言ってもまだまだ伝統的な日本的企業風土は、根強く残存していることも確かであろう。企業風土に限らず、どういう分野の風土でも、およそ風土といえる以上は、すべて一朝一夕にそう簡単に変わるものではあるまい。
ここでは、そういう一般的な問題ではなく、やはり日本的企業風土の象徴の一つと思われるいわゆる総会屋の問題を簡単に取り上げてみよう(欧米には、総会屋はおらず、なんでそんな者に、会社の金を出すのかと言って、欧米人には、いくら説明しても理解してもらえない)。
昭和25年の商法改正において、政府原案にあった「会社荒らし等に関する贈収賄罪」の規定がそのままでは、安易に総会屋への利益供与に適用されることを危惧して財界が要求した修正、すなわち、「不正の請託」を伴う利益供与がなされた場合に限り適用し、「不正の請託」を伴わない総会屋に対する単純な利益供与には、この規定は適用できないようにした修正を原案に加えて、現行規定(商法494条)が成立したため、爾来、一般に、総会屋に対する利益供与に対してこの規定が実際に発動されて、総会屋も会社側も処罰されることは、事実上まず起こることはないであろうとされてきた。
そこで、従来からの根強い日本的企業風土の一つであるこの総会屋に対する会社からの利益供与は、半ば公然とますますエスカレートして行ったのであったが、その後たまたま有名な東洋電機カラーテレビ事件で、最高裁が、「不正の請託」を伴う利益供与がなされたとみて、この規定を発動して関係者を処罰した判決を下し、広く会社関係者に強い衝撃を与えたものの、これもこの根強い企業風土に少しも警鐘を与えたことにはならず、一過性の軽い風邪を引いた程度に終わり、その後も引き続きこの慣行はさらに一層エスカレートして行き、再び総会屋への利益供与に対して、この規定が発動されることはなかった。
しかし、周知のとおり、昭和56年の株主総会の活性化を含む商法大改正の際、今度こそは、本腰を入れてこの慣行を撲滅する姿勢から、前記の適用しにくい規定は、そのままとして、それとは別に、簡単に、直接、会社の総会屋に対する利益供与を処罰することができる新規定を制定したのであった(商法497条)。
この改正規定は、目算どおり絶大の威力を発揮し、今日まで沢山の違反事件が摘発され、実際の処罰もかなりの件数に登っており、会社も、昭和56年以来、一転、今度は、積極的に真剣に利益供与の自粛を図ってきているが、しかしこの総会屋に対する利益供与は、株の買い占め、会社乗っ取りと同様、現在の取締役の地位の保身にかかる問題であるうえ、長い伝統的風土に根ざした慣行であることから、確かに以前の最盛期に較べると、総会屋も大幅に減少し、利益供与もうんと少なくなってきているように見受けられるが、水面下のことはよく分からないが、まだまだ容易に撲滅するところまでは来ていないのではあるまいか。
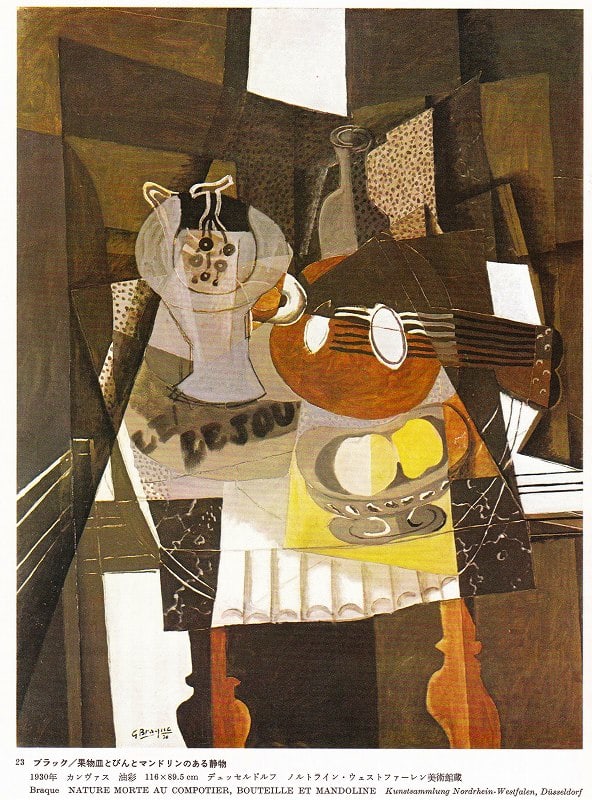
これまで言われてきた日本的企業風土である終身雇用制、年功序列、学歴偏重などとともに、具体的な経営方法としては、職務権限の不明確からくる稟議制度などに象徴される責任の曖昧さなどの諸点が、最近では、かなり崩れてきて、途中採用に見られる雇用の流動性の増加や学歴無視、具体的な実績に基づく勤務評価による報酬体系の確立など、かなり欧米諸国並の企業風土に変貌しつつあることは、否定できない現実であろう。
しかし、そうは言ってもまだまだ伝統的な日本的企業風土は、根強く残存していることも確かであろう。企業風土に限らず、どういう分野の風土でも、およそ風土といえる以上は、すべて一朝一夕にそう簡単に変わるものではあるまい。
ここでは、そういう一般的な問題ではなく、やはり日本的企業風土の象徴の一つと思われるいわゆる総会屋の問題を簡単に取り上げてみよう(欧米には、総会屋はおらず、なんでそんな者に、会社の金を出すのかと言って、欧米人には、いくら説明しても理解してもらえない)。
昭和25年の商法改正において、政府原案にあった「会社荒らし等に関する贈収賄罪」の規定がそのままでは、安易に総会屋への利益供与に適用されることを危惧して財界が要求した修正、すなわち、「不正の請託」を伴う利益供与がなされた場合に限り適用し、「不正の請託」を伴わない総会屋に対する単純な利益供与には、この規定は適用できないようにした修正を原案に加えて、現行規定(商法494条)が成立したため、爾来、一般に、総会屋に対する利益供与に対してこの規定が実際に発動されて、総会屋も会社側も処罰されることは、事実上まず起こることはないであろうとされてきた。
そこで、従来からの根強い日本的企業風土の一つであるこの総会屋に対する会社からの利益供与は、半ば公然とますますエスカレートして行ったのであったが、その後たまたま有名な東洋電機カラーテレビ事件で、最高裁が、「不正の請託」を伴う利益供与がなされたとみて、この規定を発動して関係者を処罰した判決を下し、広く会社関係者に強い衝撃を与えたものの、これもこの根強い企業風土に少しも警鐘を与えたことにはならず、一過性の軽い風邪を引いた程度に終わり、その後も引き続きこの慣行はさらに一層エスカレートして行き、再び総会屋への利益供与に対して、この規定が発動されることはなかった。
しかし、周知のとおり、昭和56年の株主総会の活性化を含む商法大改正の際、今度こそは、本腰を入れてこの慣行を撲滅する姿勢から、前記の適用しにくい規定は、そのままとして、それとは別に、簡単に、直接、会社の総会屋に対する利益供与を処罰することができる新規定を制定したのであった(商法497条)。
この改正規定は、目算どおり絶大の威力を発揮し、今日まで沢山の違反事件が摘発され、実際の処罰もかなりの件数に登っており、会社も、昭和56年以来、一転、今度は、積極的に真剣に利益供与の自粛を図ってきているが、しかしこの総会屋に対する利益供与は、株の買い占め、会社乗っ取りと同様、現在の取締役の地位の保身にかかる問題であるうえ、長い伝統的風土に根ざした慣行であることから、確かに以前の最盛期に較べると、総会屋も大幅に減少し、利益供与もうんと少なくなってきているように見受けられるが、水面下のことはよく分からないが、まだまだ容易に撲滅するところまでは来ていないのではあるまいか。