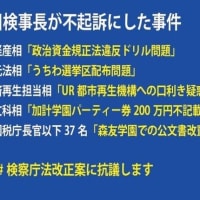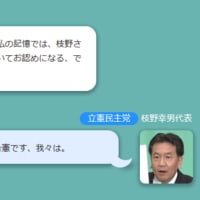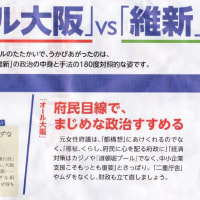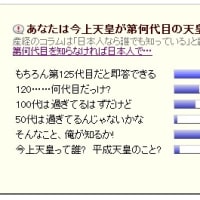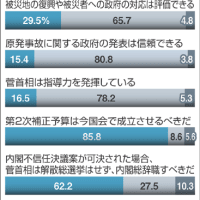ポツダム宣言の発表に接したわが国政府は、これを「黙殺」すると表明した。この「黙殺」という言葉を、わが国としては「無視する」「問題にしない」という程度の意味で用いたのに、連合国側には「拒否する」と受け取られ、それが原爆投下、さらにはソ連参戦を招いたといった話はしばしば耳にする。
例えば、鳥飼玖美子・立教大教授の『歴史を変えた誤訳』(新潮文庫、2004)では、「第一章 歴史を変えた言葉」の冒頭でこの「黙殺」が取り上げられており、
《外交上の誤訳とされるもの、コミュニケーションの失敗例とされるものはいくつかあるが、その中で最たるものは、ポツダム宣言に対する日本側の回答で「黙殺」とあるのをignoreと英訳したことであろう。》
《鈴木貫太郎首相および日本政府は「黙殺」という肝心な言葉がどういう結果をもたらすかまで考えいたらなかったのだろうか。》
との記述がある。
読売新聞社が国民による戦争責任認識の材料を提供するものとして刊行した、読売新聞戦争責任検証委員会編『検証 戦争責任』の2巻(中央公論新社、2006)では、
《鈴木はポツダム宣言の対応でも、大きな過ちをおかした。閣議では、東郷が宣言は拒絶せず、少なくともソ連から返事が来るまで回答を延ばすよう提案した。梅津、豊田は反発したが、結局、政府は宣言への意思表示はしないと決めた。
だが、鈴木は、大西軍令部次長らの圧力もあって、記者会見でポツダム宣言は「黙殺するのみである」と述べてしまう。この発言が原爆投下、ソ連参戦の口実に使われた。》
と鈴木の責任を問うている。
私も当然、鈴木首相は「黙殺」と発言したのだと思っていた。
ところが、先般、前回の記事を書く過程でいろいろ調べていると、どうもそう単純な話ではないことがわかってきた。
前回の記事で挙げたように、朝日新聞が「政府は黙殺」との見出しを掲げたのは、7月28日の紙面である。これは、ポツダム宣言の発表とその内容を報じる記事に続けて掲載されている。再度記事を引用する。
《政府は黙殺
帝国政府としては米、英、重慶三国の共同声明に関しては何ら重大な価値あるものに非ずしてこれを黙殺すると共に、断乎戦争完遂に邁進するのみとの決意を更に固めている》
この記事は、先の私の記事で引用した迫水久常の回想のうちの、
《新聞側の観測として、政府はこの宣言は無視する意向らしいということを付加することは差支えないということにする》
という箇所に当たるのだろう。
この朝日記事の「黙殺」は、鈴木首相の発言を受けてのものではない。何故なら、鈴木首相がポツダム宣言について触れた記者会見は、宣言についての報道があったにもかかわらず、政府がこの宣言に対して何ら明確な意思表示をしていないことを批判する軍部の圧力によって、この28日に行われたものだからだ。
高見順の『敗戦日記』(文春文庫、1991)の同日付の記述を見ると、
《米英蒋の対日降伏条件の放送について、読売も毎日も「笑止」という形容詞をつけている。》
とあり、さらに読売の記事が引用されている。
《 戦争完遂に邁進
帝国政府問題とせず
敵米英並に重慶は不逞にも世界に向って日本抹殺の対日共同宣言を発表、我に向って謀略的屈服案を宣明したが、帝国政府としてはかかる敵の謀略については全く問題外として笑殺、断乎自存自衛たる大東亜戦争完遂に挙国邁進、以て敵の企図を粉砕する方針である。》
《笑止、対日降伏条件
トルーマン、チャーチル、蒋連名
ポツダムより放送す
〔チューリッヒ特電廿五日発〕トルーマン、チャーチルおよび蒋介石は廿五日ポツダムより連名で日本に課すべき降伏の最後的条件なるものを放送した、右条件要旨次の如し》
(以下引用省略)
読売の記事には「問題とせず」「全く問題外」「笑殺」「笑止」との表現はあるが、「黙殺」はない。
ポツダム宣言に対して最初に「黙殺」の語を用いたのは、鈴木首相ではなく、朝日新聞ではないのか?
そして、その語が鈴木首相の記者会見での回答に転用されたということではないのだろうか?
という疑問が生じた。
それと、先の記事で引用した鈴木の回想では、
《そこで余は心ならずも、七月二十八日の内閣記者団との会見において「この宣言は重視する要なきものと思う」との意味を答弁したのである。
この一言は後々に至るまで、余の誠に遺憾と思う点であり、この一言を余に無理強いに答弁させたところに、当時の軍部の極端なところの抗戦意識が、いかに冷静なる判断を欠いていたかが判るのである。》(太字は引用者による。以下同じ)
となっており、ここに「黙殺」の文字がないのも気になった。
鈴木首相は、本当に「黙殺」との言葉を用いたのだろうか?
迫水書記官長は『機関銃下の首相官邸』で、記者会見で予定された首相の回答を陸海軍の軍務局長と協議しているうちに、強い表現になっていったとして、
《結局、記者側から「ポツダム宣言に対する首相の考えはどうか」と質問させ、それに対して首相が「ポツダム宣言は、カイロ宣言(昭和十八年一月)の焼き直しであり、政府としては重要視しない、黙殺するだけである」という要領で答えることとなった。この「重要視しない」という前に「あまり」という言葉をつけるか、「黙殺する」という言葉の前に「さしあたり」という言葉をつけるかが最後の論争の要点であったが、ついに私の負けになって、つけないことにきまった。》
と述べている。しかしここでも「という要領で答えることとなった」という表現になっている。「黙殺」という言葉が鈴木首相の口から発せられたのかどうかは明確でない。
蔵書を漁っていると、小堀桂一郎が『宰相 鈴木貫太郎』(文春文庫、1987、単行本は文藝春秋、1982)の第6章「黙殺?」で、これらの点について、多数の資料に当たり、詳細な検討を加えていることがわかった。
大変興味深い内容なので、興味のある方は是非参照されたい。
小堀の記述の要旨は、次のようになる(小堀の文章は旧仮名遣いを用いているのが特徴だが、変換の便宜上、引用文においても新仮名遣いを用いる)。
・軍部からの突き上げの結果、28日午後4時から予定されていた鈴木首相の記者会見において、一問一答という形でポツダム宣言に対する首相の所信を明らかにすることとなった。
・下村海南情報局総裁は既に28日早朝に一問一答の原案を起草し、秘書官に口授していた(下村『終戦記』)。
・鈴木首相は《下村総裁の書いたシナリオを演じただけのことである。記者団との一問一答は実は下村総裁の作文した原稿を型の如く棒読みに読み上げただけのことだったのであろう》。
・記者会見の結果は30日の新聞に掲載された。朝日の記事を見ると、
《問 最近敵側は戦争の終結につき各種の宣伝を行っているが、これに対する所信はどうか。
答 私は三国共同声明はカイロ会談の焼直しと思う。政府としては何ら重大な価値あるものとは思わない。ただ黙殺するのみである。われわれは断乎戦争完遂に邁進するのみである。》
となっている。これは28日の朝日の記事とあまりによく似ている。偶然の一致とは思われない。
・28日の朝日記事を書いた柴田敏夫は、東京12チャンネル報道部編『私の昭和史5 終戦前夜』によると、「黙殺」という言葉の出所を問う質問に対して、
《総理との会見ってのはね、〔中略〕前からその日に予定していたわけです。それで、たまたまポツダム宣言の問題が出たんで、総理との会見の中でも一部は出ましたけどね。私の印象はむしろ迫水書記官長とクラブとの会見の席上で、まあ、あのころ朝一〇時と正午と午後四時と三回(今もそれやってるわけですけれども)一〇時の会見から話は出たと思うんです。それで正午の会見の時かなんかにですね、いったい政府はどうするんだという話が出た時に、まあ迫水さんとしてはですね、これは今、日本としてはこれを受諾するとかそういう態度はとれないんだと。だから結局まあ重要視しないっていうか、ネグレクトするという方向へいくことになるだろうと。じゃあ黙殺かっていう話が出たんですね。「黙殺? ネグレクトってのは黙殺とも言えるかなあ」というようなやりとりがあったのを記憶しています。》
と述べている。
・仮に下村の回想の「28日早朝」という時期が記憶違いであれば、下村か、迫水の記者会見の席上のどちらかが、「黙殺」の出所だということでつじつまが合う。ここで自分(小堀)は下村が朝日新聞社の元副社長であったことを想起するが、これが邪推であるならむしろ幸いである。
・また、下村、柴田の証言にかかわらず、「黙殺」は「内閣にみなぎる一種の空気の如きもの」に根ざしているのではないかという推測も成り立つ。
小堀はここで、
《私はここで〔中略〕結局誰の責任に於て生じたのか、といった問題の究明に紙数を費やすつもりはない。》
として、話を、鈴木は閣議で「黙殺」と明言したと断定するロバート・ビュートウへの批判に転じる。
続いて、日本側の要人が、戦後、鈴木の「黙殺」発言を強く批判していることを挙げる。
しかし、米国での受け止められ方は、実際のところどうだったのか。
小堀は、7月28日付の『ニューヨーク・タイムズ』が、ポツダム宣言に対する同盟通信社の論評(日本の政府見解ではない)に既に ignore 、reject の語句が用いられていることに注目する。
《鈴木首相の〈黙殺〉が ignore と訳され、それが海外に送られると、APもロイター通信社もこれを reject 即ち拒絶と解し、かくて日本の姿勢に就ての極めて不利な見解が一般に成立した、というのがこれまでの定説である。それは大筋に於てはその通りである。だが、日本がこの宣言を ignore し、 reject するであろうという筋書は27日の閣議の空気を報ずるこの段階ですでに出ていたことである。〔中略〕同盟通信がこの様な通信を海外に向けて流した根拠は、朝日新聞が〈政府は黙殺〉という見出しを使うに至った状況と全く同じものであるはずである。》
さらに、28日の鈴木首相の記者会見を報じる30日付の『ニューヨーク・タイムズ』『ワシントン・ポスト』の両紙が、鈴木発言を「日本帝国政府としてはこの宣言に関心を払わない(take no notice)」と訳していることにも注意を促す。
この両紙の記事は、30日付のわが国の新聞に掲載された「黙殺」発言を翻訳したものではない。日本時間28日午後7時のラジオ放送に基づいた記事だという。とすれば、仮にこの放送で「黙殺」の語が用いられていたのなら、米国はもっと刺激的な表現に翻訳することができたのではないか。しかし「黙殺」が歴史的効果を振るい始めたのは、30日付の日本の新聞にこの語が印刷されてより後のことである。
小堀は「黙殺」について、次のように結論づけている。
《現在の如くに録音機械のよく発達普及した時代であったら、総理のこの記者会見での発言を肉声を以て言葉通りに記録しておくのは何でもないことであったろうし、また必ずやその手続がとられていたことであろう。ところが総理の言葉は文字通り虚空に消えて残らなかった。消えてしまった言葉の近似値を再現するために、こうした私はあまり決定的なものは出て来そうにない傍証集めを試みたわけであるが、しかし鈴木首相が記者会見の席上で〈ただ黙殺するのみである〉とほんとうに言ったのか、それとも言わなかったのか、という問題は畢竟それほど重大な意味のあることではない。
重要なのは、総理の記者会見での応答の不備が日本のポツダム宣言拒否を初めてアメリカに印象づけたわけではない、ということである。あれはアメリカ側に於て既に成立していた解釈であり、鈴木首相の表明した政府の態度というのもアメリカ側の予想していた通りであった。この宣言を受諾の用意がある、受諾すべく検討中である、とでも言わない限り、アメリカ側の解釈があのような形で出てくることは決まっていた。そして当時の日本には、受諾を示唆する様な一言半句すらも首相の口に上すわけにはゆかない空気があったことはあらためていうまでもない。》
《「黙殺」に対して応答したというのは口実である。それに「黙殺」の語そのものが敵を刺激したわけではない。「黙殺」の二字が原爆投下につながったとみるのは所謂短絡推理である。》
私もそのように思う。
《そして繰り返しておくが、もし人が「黙殺」の語に従来信ぜられて来た如き致命的効果があったと考えるのならば、その人は、それが果たして現実に鈴木首相の責任に於てその口に上ったものかどうかを確認してみなくてはならない。私の見るところでは、それは朝日新聞の記事に発し、下村情報局総裁のペンに引取られ、そしておそらくは鈴木首相の口には上らぬままに、インタヴュー記事の原稿に再現し、それが放送協会の電波に乗り、また七月三十日の新聞に首相談話として確定的に活字化されてしまったものだったのである。》
小堀によると、下村海南は『終戦秘史』で次のように述べているという。
《閣議では進んで意思表示しないことになっていたが、軍部は強く反駁しないと士気にひびくという。記者団との一問一答で、首相は重要視しないといわざるを得ない。新聞では黙殺するという語を用いたのであった。》
小堀はこの箇所に「或るひっかかりを感ずる」とし、
《鈴木首相は記者団との会見の際、ほんとうに〈ただ黙殺するのみである〉と答えたのであろうか。下村氏のこの文章が、もし注意深く、事実に即して綴られたものであり、後世の者がそう扱ってもよいものだとするならば、下村氏はここで、鈴木首相はただ「重要視しない」と言っただけだ、「黙殺する」とは言っていない、書いているのである。そして、新聞だけが「黙殺する」という語を談話として印刷したのだ、と述べていることになる。》
としている。
私も同様の感想を持つ。
下村のこの『終戦秘史』や『終戦記』は読んでいない。だから、小堀が持論に都合のいい引用をしている可能性も否定できないが、少なくとも、『終戦秘史』のこの箇所だけ読めば、何も示唆されずとも、私も同様の感想を持つだろう。
そして、鈴木の自伝の文章といい、小堀が引用した柴田の証言といい、「黙殺」発言の責任を一人鈴木に押し付けて済むような話ではないことは確かだろう。
例えば、鳥飼玖美子・立教大教授の『歴史を変えた誤訳』(新潮文庫、2004)では、「第一章 歴史を変えた言葉」の冒頭でこの「黙殺」が取り上げられており、
《外交上の誤訳とされるもの、コミュニケーションの失敗例とされるものはいくつかあるが、その中で最たるものは、ポツダム宣言に対する日本側の回答で「黙殺」とあるのをignoreと英訳したことであろう。》
《鈴木貫太郎首相および日本政府は「黙殺」という肝心な言葉がどういう結果をもたらすかまで考えいたらなかったのだろうか。》
との記述がある。
読売新聞社が国民による戦争責任認識の材料を提供するものとして刊行した、読売新聞戦争責任検証委員会編『検証 戦争責任』の2巻(中央公論新社、2006)では、
《鈴木はポツダム宣言の対応でも、大きな過ちをおかした。閣議では、東郷が宣言は拒絶せず、少なくともソ連から返事が来るまで回答を延ばすよう提案した。梅津、豊田は反発したが、結局、政府は宣言への意思表示はしないと決めた。
だが、鈴木は、大西軍令部次長らの圧力もあって、記者会見でポツダム宣言は「黙殺するのみである」と述べてしまう。この発言が原爆投下、ソ連参戦の口実に使われた。》
と鈴木の責任を問うている。
私も当然、鈴木首相は「黙殺」と発言したのだと思っていた。
ところが、先般、前回の記事を書く過程でいろいろ調べていると、どうもそう単純な話ではないことがわかってきた。
前回の記事で挙げたように、朝日新聞が「政府は黙殺」との見出しを掲げたのは、7月28日の紙面である。これは、ポツダム宣言の発表とその内容を報じる記事に続けて掲載されている。再度記事を引用する。
《政府は黙殺
帝国政府としては米、英、重慶三国の共同声明に関しては何ら重大な価値あるものに非ずしてこれを黙殺すると共に、断乎戦争完遂に邁進するのみとの決意を更に固めている》
この記事は、先の私の記事で引用した迫水久常の回想のうちの、
《新聞側の観測として、政府はこの宣言は無視する意向らしいということを付加することは差支えないということにする》
という箇所に当たるのだろう。
この朝日記事の「黙殺」は、鈴木首相の発言を受けてのものではない。何故なら、鈴木首相がポツダム宣言について触れた記者会見は、宣言についての報道があったにもかかわらず、政府がこの宣言に対して何ら明確な意思表示をしていないことを批判する軍部の圧力によって、この28日に行われたものだからだ。
高見順の『敗戦日記』(文春文庫、1991)の同日付の記述を見ると、
《米英蒋の対日降伏条件の放送について、読売も毎日も「笑止」という形容詞をつけている。》
とあり、さらに読売の記事が引用されている。
《 戦争完遂に邁進
帝国政府問題とせず
敵米英並に重慶は不逞にも世界に向って日本抹殺の対日共同宣言を発表、我に向って謀略的屈服案を宣明したが、帝国政府としてはかかる敵の謀略については全く問題外として笑殺、断乎自存自衛たる大東亜戦争完遂に挙国邁進、以て敵の企図を粉砕する方針である。》
《笑止、対日降伏条件
トルーマン、チャーチル、蒋連名
ポツダムより放送す
〔チューリッヒ特電廿五日発〕トルーマン、チャーチルおよび蒋介石は廿五日ポツダムより連名で日本に課すべき降伏の最後的条件なるものを放送した、右条件要旨次の如し》
(以下引用省略)
読売の記事には「問題とせず」「全く問題外」「笑殺」「笑止」との表現はあるが、「黙殺」はない。
ポツダム宣言に対して最初に「黙殺」の語を用いたのは、鈴木首相ではなく、朝日新聞ではないのか?
そして、その語が鈴木首相の記者会見での回答に転用されたということではないのだろうか?
という疑問が生じた。
それと、先の記事で引用した鈴木の回想では、
《そこで余は心ならずも、七月二十八日の内閣記者団との会見において「この宣言は重視する要なきものと思う」との意味を答弁したのである。
この一言は後々に至るまで、余の誠に遺憾と思う点であり、この一言を余に無理強いに答弁させたところに、当時の軍部の極端なところの抗戦意識が、いかに冷静なる判断を欠いていたかが判るのである。》(太字は引用者による。以下同じ)
となっており、ここに「黙殺」の文字がないのも気になった。
鈴木首相は、本当に「黙殺」との言葉を用いたのだろうか?
迫水書記官長は『機関銃下の首相官邸』で、記者会見で予定された首相の回答を陸海軍の軍務局長と協議しているうちに、強い表現になっていったとして、
《結局、記者側から「ポツダム宣言に対する首相の考えはどうか」と質問させ、それに対して首相が「ポツダム宣言は、カイロ宣言(昭和十八年一月)の焼き直しであり、政府としては重要視しない、黙殺するだけである」という要領で答えることとなった。この「重要視しない」という前に「あまり」という言葉をつけるか、「黙殺する」という言葉の前に「さしあたり」という言葉をつけるかが最後の論争の要点であったが、ついに私の負けになって、つけないことにきまった。》
と述べている。しかしここでも「という要領で答えることとなった」という表現になっている。「黙殺」という言葉が鈴木首相の口から発せられたのかどうかは明確でない。
蔵書を漁っていると、小堀桂一郎が『宰相 鈴木貫太郎』(文春文庫、1987、単行本は文藝春秋、1982)の第6章「黙殺?」で、これらの点について、多数の資料に当たり、詳細な検討を加えていることがわかった。
大変興味深い内容なので、興味のある方は是非参照されたい。
小堀の記述の要旨は、次のようになる(小堀の文章は旧仮名遣いを用いているのが特徴だが、変換の便宜上、引用文においても新仮名遣いを用いる)。
・軍部からの突き上げの結果、28日午後4時から予定されていた鈴木首相の記者会見において、一問一答という形でポツダム宣言に対する首相の所信を明らかにすることとなった。
・下村海南情報局総裁は既に28日早朝に一問一答の原案を起草し、秘書官に口授していた(下村『終戦記』)。
・鈴木首相は《下村総裁の書いたシナリオを演じただけのことである。記者団との一問一答は実は下村総裁の作文した原稿を型の如く棒読みに読み上げただけのことだったのであろう》。
・記者会見の結果は30日の新聞に掲載された。朝日の記事を見ると、
《問 最近敵側は戦争の終結につき各種の宣伝を行っているが、これに対する所信はどうか。
答 私は三国共同声明はカイロ会談の焼直しと思う。政府としては何ら重大な価値あるものとは思わない。ただ黙殺するのみである。われわれは断乎戦争完遂に邁進するのみである。》
となっている。これは28日の朝日の記事とあまりによく似ている。偶然の一致とは思われない。
・28日の朝日記事を書いた柴田敏夫は、東京12チャンネル報道部編『私の昭和史5 終戦前夜』によると、「黙殺」という言葉の出所を問う質問に対して、
《総理との会見ってのはね、〔中略〕前からその日に予定していたわけです。それで、たまたまポツダム宣言の問題が出たんで、総理との会見の中でも一部は出ましたけどね。私の印象はむしろ迫水書記官長とクラブとの会見の席上で、まあ、あのころ朝一〇時と正午と午後四時と三回(今もそれやってるわけですけれども)一〇時の会見から話は出たと思うんです。それで正午の会見の時かなんかにですね、いったい政府はどうするんだという話が出た時に、まあ迫水さんとしてはですね、これは今、日本としてはこれを受諾するとかそういう態度はとれないんだと。だから結局まあ重要視しないっていうか、ネグレクトするという方向へいくことになるだろうと。じゃあ黙殺かっていう話が出たんですね。「黙殺? ネグレクトってのは黙殺とも言えるかなあ」というようなやりとりがあったのを記憶しています。》
と述べている。
・仮に下村の回想の「28日早朝」という時期が記憶違いであれば、下村か、迫水の記者会見の席上のどちらかが、「黙殺」の出所だということでつじつまが合う。ここで自分(小堀)は下村が朝日新聞社の元副社長であったことを想起するが、これが邪推であるならむしろ幸いである。
・また、下村、柴田の証言にかかわらず、「黙殺」は「内閣にみなぎる一種の空気の如きもの」に根ざしているのではないかという推測も成り立つ。
小堀はここで、
《私はここで〔中略〕結局誰の責任に於て生じたのか、といった問題の究明に紙数を費やすつもりはない。》
として、話を、鈴木は閣議で「黙殺」と明言したと断定するロバート・ビュートウへの批判に転じる。
続いて、日本側の要人が、戦後、鈴木の「黙殺」発言を強く批判していることを挙げる。
しかし、米国での受け止められ方は、実際のところどうだったのか。
小堀は、7月28日付の『ニューヨーク・タイムズ』が、ポツダム宣言に対する同盟通信社の論評(日本の政府見解ではない)に既に ignore 、reject の語句が用いられていることに注目する。
《鈴木首相の〈黙殺〉が ignore と訳され、それが海外に送られると、APもロイター通信社もこれを reject 即ち拒絶と解し、かくて日本の姿勢に就ての極めて不利な見解が一般に成立した、というのがこれまでの定説である。それは大筋に於てはその通りである。だが、日本がこの宣言を ignore し、 reject するであろうという筋書は27日の閣議の空気を報ずるこの段階ですでに出ていたことである。〔中略〕同盟通信がこの様な通信を海外に向けて流した根拠は、朝日新聞が〈政府は黙殺〉という見出しを使うに至った状況と全く同じものであるはずである。》
さらに、28日の鈴木首相の記者会見を報じる30日付の『ニューヨーク・タイムズ』『ワシントン・ポスト』の両紙が、鈴木発言を「日本帝国政府としてはこの宣言に関心を払わない(take no notice)」と訳していることにも注意を促す。
この両紙の記事は、30日付のわが国の新聞に掲載された「黙殺」発言を翻訳したものではない。日本時間28日午後7時のラジオ放送に基づいた記事だという。とすれば、仮にこの放送で「黙殺」の語が用いられていたのなら、米国はもっと刺激的な表現に翻訳することができたのではないか。しかし「黙殺」が歴史的効果を振るい始めたのは、30日付の日本の新聞にこの語が印刷されてより後のことである。
小堀は「黙殺」について、次のように結論づけている。
《現在の如くに録音機械のよく発達普及した時代であったら、総理のこの記者会見での発言を肉声を以て言葉通りに記録しておくのは何でもないことであったろうし、また必ずやその手続がとられていたことであろう。ところが総理の言葉は文字通り虚空に消えて残らなかった。消えてしまった言葉の近似値を再現するために、こうした私はあまり決定的なものは出て来そうにない傍証集めを試みたわけであるが、しかし鈴木首相が記者会見の席上で〈ただ黙殺するのみである〉とほんとうに言ったのか、それとも言わなかったのか、という問題は畢竟それほど重大な意味のあることではない。
重要なのは、総理の記者会見での応答の不備が日本のポツダム宣言拒否を初めてアメリカに印象づけたわけではない、ということである。あれはアメリカ側に於て既に成立していた解釈であり、鈴木首相の表明した政府の態度というのもアメリカ側の予想していた通りであった。この宣言を受諾の用意がある、受諾すべく検討中である、とでも言わない限り、アメリカ側の解釈があのような形で出てくることは決まっていた。そして当時の日本には、受諾を示唆する様な一言半句すらも首相の口に上すわけにはゆかない空気があったことはあらためていうまでもない。》
《「黙殺」に対して応答したというのは口実である。それに「黙殺」の語そのものが敵を刺激したわけではない。「黙殺」の二字が原爆投下につながったとみるのは所謂短絡推理である。》
私もそのように思う。
《そして繰り返しておくが、もし人が「黙殺」の語に従来信ぜられて来た如き致命的効果があったと考えるのならば、その人は、それが果たして現実に鈴木首相の責任に於てその口に上ったものかどうかを確認してみなくてはならない。私の見るところでは、それは朝日新聞の記事に発し、下村情報局総裁のペンに引取られ、そしておそらくは鈴木首相の口には上らぬままに、インタヴュー記事の原稿に再現し、それが放送協会の電波に乗り、また七月三十日の新聞に首相談話として確定的に活字化されてしまったものだったのである。》
小堀によると、下村海南は『終戦秘史』で次のように述べているという。
《閣議では進んで意思表示しないことになっていたが、軍部は強く反駁しないと士気にひびくという。記者団との一問一答で、首相は重要視しないといわざるを得ない。新聞では黙殺するという語を用いたのであった。》
小堀はこの箇所に「或るひっかかりを感ずる」とし、
《鈴木首相は記者団との会見の際、ほんとうに〈ただ黙殺するのみである〉と答えたのであろうか。下村氏のこの文章が、もし注意深く、事実に即して綴られたものであり、後世の者がそう扱ってもよいものだとするならば、下村氏はここで、鈴木首相はただ「重要視しない」と言っただけだ、「黙殺する」とは言っていない、書いているのである。そして、新聞だけが「黙殺する」という語を談話として印刷したのだ、と述べていることになる。》
としている。
私も同様の感想を持つ。
下村のこの『終戦秘史』や『終戦記』は読んでいない。だから、小堀が持論に都合のいい引用をしている可能性も否定できないが、少なくとも、『終戦秘史』のこの箇所だけ読めば、何も示唆されずとも、私も同様の感想を持つだろう。
そして、鈴木の自伝の文章といい、小堀が引用した柴田の証言といい、「黙殺」発言の責任を一人鈴木に押し付けて済むような話ではないことは確かだろう。