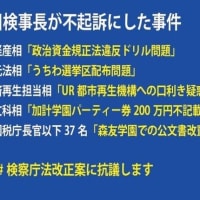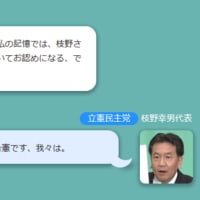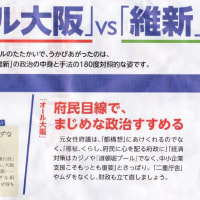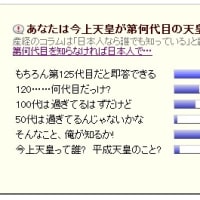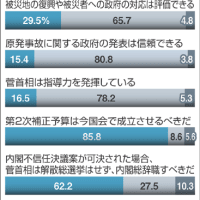昔読んだ本だが、ふと思うところがあって、読み返してみた。
著者は1922年生まれのドイツ文学者。60~80年代に保守系言論人として活動したらしい。近年の動静は不明(ネットで検索してもよくわからない。同姓同名のマンガ家が現在活躍中らしく多数ヒットする)。同じくドイツ文学者の保守系言論人としては竹山道雄や西尾幹二が著名だが、両者の中間の世代に当たる。
本書は雑誌に発表した文章を全面改稿したもの。
《第一章 われらが天皇を愛すべし ―津田左右吉の戦後
第二章 変ったのは誰なのか! ―天皇論をめぐる戦後思想界
第三章 文化外圧と日本人 ―文化大革命への反応》
の3章で構成。1章と2章は津田左右吉の天皇論をめぐる戦後知識人の動向を、3章はタイトルどおり文化大革命をめぐる戦後知識人の動向を論評したもの。
津田左右吉(1873-1961)は歴史学者。戦前、古事記や日本書紀の内容についても、通常の歴史学と同様の史料批判を行うこと(記紀批判)を主張したことで知られる。そのため、国粋主義者から攻撃を受け、一部の著作は発禁とされ、さらに出版法違反で執行猶予付きの有罪判決を受けた。逆に戦後は、進歩派陣営からヒーローとして迎えられた。
しかし津田は、皇室を崇拝する保守主義者であり、天皇制と民主主義は両立すると説いたため、天皇制廃止を志向する進歩派の期待は裏切られた。この津田論文を掲載した雑誌『世界』の吉野源三郎編集長は、巻末に、自身が津田に書き直しを懇請し、快諾を得たと明らかにしたという。書き直させたことを何故公表する必要があるのか。それは、編集部として修正を求めたけれども出来上がったのはこの程度のものだった、その内容に編集部としては必ずしも同意しているわけではないという表明ではなかったか。
著者はのちに発表された吉野の回想を用いて、当時の津田論文をめぐる吉野の対応を批判している(1章)。
《氏は津田の天皇論が「学者としての権威に裏付けられている」ことを、一応承認する。吉野氏はこの方面の専門家ではないが、それでも津田が正しいのではないか、少なくとも説得的ではあるまいかということを予感しているらしいのである。だからといって津田に賛成するかと言うとそうではない。逆である。説得力があると感ずれば感ずるほど、敵に利用されるのではないかと恐れているかのごとくである。
戦後史においてかなり長い間、このような論理が影響力をもっていたような気が私にはする。かなり長い間というのは、私がドイツの難民について関心を抱いたころにも―つまり六〇年安保の近くでも―ときどき耳にしたからである。
「それは真実かも知れぬ、しかし、いまそれを言うと敵を利するだけである!」。この論理によって、日本の戦後は、社会主義国家の欠陥を指摘することをタブー視してこなかったか? スターリン批判もこの国では、いつのまにか曖昧とならなかっただろうか? ハンガリー動乱も、東ドイツ、ポーランドの内乱も、東ドイツからの難民流出も、この論理の前にいくどかほかへそらされてしまわなかっただろうか?》(p.53~54)
やがて津田は変節漢、転向者と非難され、家永三郎からは「蓑田胸喜の亡霊が乗り移ったという印象」「権力のイデオローグ化した思想家」とまで評される。著者はこれに対し、津田は断じて変わらなかった、変わったのは周囲の現実であると述べている(2章)。
3章は、文革を支持し擁護した日本の一部知識人の言行を論評したもの。
この種のものは他にもあるが、あまり指摘されることがないであろう点が2つ、目についたので、書き留めておく。
一つは、文革中に投獄された日本人がいたということ。1967年12月、柿崎進さんとその次女久美子さんは、天津革命委員会にスパイとして逮捕され、紅衛兵たちの法廷で裁かれ、天津の監獄に延べ1532日間投獄され、72年に国外追放されたという。当時14人の邦人が同様に検挙されたが、この父子以外の人々は災難と諦めて口を閉ざしてきたが、柿崎さんだけは無実を訴え続けたところ、中国側もそれを認めて謝罪し、父子を招待したというニュースが、78年の『朝日新聞』で報じられたという。
父子の無実の訴えに対して、日中友好運動の関係者の対応は、全く冷たかったそうだ。父子の支援者はこう語ったという。
「異国の、非公開裁判の裏情報をうのみにして、絶望の日々を送る家族の不安、願いに耳をかそうともしない。これでも日本人なのか」
「長いものには巻かれろ、という日本人の卑屈さ、トラの威をかるキツネみたいに、中国の御用聞きをしてのさばっている中国屋たちの、軽率さ、いやらしさ。こんどの出来事は、中国人の問題である以上に、私たち日本人の心の貧しさを浮彫りにした面があった」
近年の北朝鮮による日本人拉致問題への親朝派の対応を思い起こした。
このころに比べれば、日本人も少しはマシになったと言えるだろうか。
もう一つは、「ふたたび茶番を演じないために」という一節で、次のように述べられている点。
《とくに中国に対しては、私たちはややもすれば、自分の感情を投入しすぎるきらいがある。(中略)二子山親方は、帰ってからすっかり中国びいきになったそうだ。会う人ごとに、一時は中国を讃歎してやまなかったらしいが、その言葉はいつも次の一句で終っていたという。
「中国はいいですよ。若いものがきびきびと規律正しくて、まるで日本の戦時中のようじゃった」
自民党のあるタカ派議員が中国を訪問して、やはり同じような感慨を洩らしたことが、新聞をにぎわせたことがあった。
(中略)
たしか中国訪問して、日本には自由が多すぎると発言したのは石川達三だったようだ。共通しているのは、自己への嫌悪、自己の住む自由世界(資本主義社会)への反発、自由放恣に見える若い世代への不満、贅沢と過剰への後ろめたさ、逆に言えば、純真、規律、醇乎、献身、簡素への憧憬、それらは発言者の思想方向の左右を問わず共通のものとして存在するようである。
重要なのは、それらを新しい中国のなかに見たように思うことだろう。いかにも革命に湧き立っている新生・中国のことだから、理想への献身、厳正なる規律などが支配していることはたしかであるが、それは日本のような自由主義社会においてもないわけではない。日本の社会が退廃一色でないと同様、中国の社会も純真と規律で塗りつぶされているのではない。常識をもってすれば、それらは当たり前すぎることであるが、社会主義国家においては、自由主義国家には不足乃至欠如する、それらの徳目を見たと思うのであろう。
思えば―中国に限って言えば―戦前・戦中のいわゆるシナ浪人といわれた人たちにも、その自己の心情の過剰なる投影があったように思う。今日の中国観にも彼らと、しばしば似たところがあるように思われる。
(中略)
中国の文化大革命と日本の知識人との関係は、ひろく言って外国との文化接触の問題を考える歴史的な事件となるだろう。しかし私たちが、この経験をこれからもくりかえすか、くりかえさないかは、だれも言うことはできない。私たちは、これまでも何度も、性こりもなくこの経験をくりかえしているからである。
(中略)
日本人が―いや、人類が―歴史に学ぶことができるかどうか、疑わしいところもあるが、にも拘わらず、私たちは何度でも歴史をふりかえってみようと呼びかけねばならないだろう。》(p.201~205)
以上のほかにも、興味深い記述が散見される。
《いずれにせよ、叱責されるたびに彼らは「恐懼おく處を知らずして退出」するのだが、本当に恐懼したのかどうか、面従腹背というべきか、あとはケロリとして天皇の叱責もヌカに釘、つねに無視してしまうのである。さきの原田日記の一節「これは又瞞すのかと思召されたらしく」は痛烈である。ひょっとすれば、天皇は事変のはじめから、自分がていよくダマされていることを自覚されていたかも知れないと想像したくさえなる。(中略)天皇と国民(の一部)との関係は、「宸襟を安んじたてまつる」などの美辞麗句とはまったく縁もゆかりもないどすぐろい不信の関係だったようにも考えられる。(中略)
ひょっとすれば美濃部達吉や津田左右吉の天皇観は、この不信の関係をいかにもありそうな忠君愛国で飾ろうとする偽善への怒りから発していたかも知れない。東京裁判で被告たちが、天皇を戦争責任から遠ざけようとしたとき、はじめて彼らはその生涯において「忠義」を示したのかも知れない。》(1章、p.38~39)
《戦後、日本には俄かづくりの「民主主義者」「戦争反対者」が満ちあふれた。平和と文化国家が突然、この国の合い言葉となった。こんなに沢山の民主主義者がいたのに、どうして結核の私が軍隊に引っぱられ、やがて乞食同然の外地引揚家族と、馬小屋を改造した、その名も「平和寮」という板張りのバラックに住まなければならなかったのか?
戦中派たるもの、いささか憮然たる思いであったことは書いておいてもいいであろう。》(あとがき、p.207)
著者の名は、近年まるで聞かない。私は本書ともう1冊しかこの著者の本を読んだことはないのだが、今日においても十分読み返すだけの価値はある文章だと思う。
(引用文中、旧かな、旧漢字は新かな、新漢字に修正した。また傍点は省略した)
(以下2011.2.11付記)
著者は2008.10.9に86歳で逝去されたと2009年1月に公表された。
著者は1922年生まれのドイツ文学者。60~80年代に保守系言論人として活動したらしい。近年の動静は不明(ネットで検索してもよくわからない。同姓同名のマンガ家が現在活躍中らしく多数ヒットする)。同じくドイツ文学者の保守系言論人としては竹山道雄や西尾幹二が著名だが、両者の中間の世代に当たる。
本書は雑誌に発表した文章を全面改稿したもの。
《第一章 われらが天皇を愛すべし ―津田左右吉の戦後
第二章 変ったのは誰なのか! ―天皇論をめぐる戦後思想界
第三章 文化外圧と日本人 ―文化大革命への反応》
の3章で構成。1章と2章は津田左右吉の天皇論をめぐる戦後知識人の動向を、3章はタイトルどおり文化大革命をめぐる戦後知識人の動向を論評したもの。
津田左右吉(1873-1961)は歴史学者。戦前、古事記や日本書紀の内容についても、通常の歴史学と同様の史料批判を行うこと(記紀批判)を主張したことで知られる。そのため、国粋主義者から攻撃を受け、一部の著作は発禁とされ、さらに出版法違反で執行猶予付きの有罪判決を受けた。逆に戦後は、進歩派陣営からヒーローとして迎えられた。
しかし津田は、皇室を崇拝する保守主義者であり、天皇制と民主主義は両立すると説いたため、天皇制廃止を志向する進歩派の期待は裏切られた。この津田論文を掲載した雑誌『世界』の吉野源三郎編集長は、巻末に、自身が津田に書き直しを懇請し、快諾を得たと明らかにしたという。書き直させたことを何故公表する必要があるのか。それは、編集部として修正を求めたけれども出来上がったのはこの程度のものだった、その内容に編集部としては必ずしも同意しているわけではないという表明ではなかったか。
著者はのちに発表された吉野の回想を用いて、当時の津田論文をめぐる吉野の対応を批判している(1章)。
《氏は津田の天皇論が「学者としての権威に裏付けられている」ことを、一応承認する。吉野氏はこの方面の専門家ではないが、それでも津田が正しいのではないか、少なくとも説得的ではあるまいかということを予感しているらしいのである。だからといって津田に賛成するかと言うとそうではない。逆である。説得力があると感ずれば感ずるほど、敵に利用されるのではないかと恐れているかのごとくである。
戦後史においてかなり長い間、このような論理が影響力をもっていたような気が私にはする。かなり長い間というのは、私がドイツの難民について関心を抱いたころにも―つまり六〇年安保の近くでも―ときどき耳にしたからである。
「それは真実かも知れぬ、しかし、いまそれを言うと敵を利するだけである!」。この論理によって、日本の戦後は、社会主義国家の欠陥を指摘することをタブー視してこなかったか? スターリン批判もこの国では、いつのまにか曖昧とならなかっただろうか? ハンガリー動乱も、東ドイツ、ポーランドの内乱も、東ドイツからの難民流出も、この論理の前にいくどかほかへそらされてしまわなかっただろうか?》(p.53~54)
やがて津田は変節漢、転向者と非難され、家永三郎からは「蓑田胸喜の亡霊が乗り移ったという印象」「権力のイデオローグ化した思想家」とまで評される。著者はこれに対し、津田は断じて変わらなかった、変わったのは周囲の現実であると述べている(2章)。
3章は、文革を支持し擁護した日本の一部知識人の言行を論評したもの。
この種のものは他にもあるが、あまり指摘されることがないであろう点が2つ、目についたので、書き留めておく。
一つは、文革中に投獄された日本人がいたということ。1967年12月、柿崎進さんとその次女久美子さんは、天津革命委員会にスパイとして逮捕され、紅衛兵たちの法廷で裁かれ、天津の監獄に延べ1532日間投獄され、72年に国外追放されたという。当時14人の邦人が同様に検挙されたが、この父子以外の人々は災難と諦めて口を閉ざしてきたが、柿崎さんだけは無実を訴え続けたところ、中国側もそれを認めて謝罪し、父子を招待したというニュースが、78年の『朝日新聞』で報じられたという。
父子の無実の訴えに対して、日中友好運動の関係者の対応は、全く冷たかったそうだ。父子の支援者はこう語ったという。
「異国の、非公開裁判の裏情報をうのみにして、絶望の日々を送る家族の不安、願いに耳をかそうともしない。これでも日本人なのか」
「長いものには巻かれろ、という日本人の卑屈さ、トラの威をかるキツネみたいに、中国の御用聞きをしてのさばっている中国屋たちの、軽率さ、いやらしさ。こんどの出来事は、中国人の問題である以上に、私たち日本人の心の貧しさを浮彫りにした面があった」
近年の北朝鮮による日本人拉致問題への親朝派の対応を思い起こした。
このころに比べれば、日本人も少しはマシになったと言えるだろうか。
もう一つは、「ふたたび茶番を演じないために」という一節で、次のように述べられている点。
《とくに中国に対しては、私たちはややもすれば、自分の感情を投入しすぎるきらいがある。(中略)二子山親方は、帰ってからすっかり中国びいきになったそうだ。会う人ごとに、一時は中国を讃歎してやまなかったらしいが、その言葉はいつも次の一句で終っていたという。
「中国はいいですよ。若いものがきびきびと規律正しくて、まるで日本の戦時中のようじゃった」
自民党のあるタカ派議員が中国を訪問して、やはり同じような感慨を洩らしたことが、新聞をにぎわせたことがあった。
(中略)
たしか中国訪問して、日本には自由が多すぎると発言したのは石川達三だったようだ。共通しているのは、自己への嫌悪、自己の住む自由世界(資本主義社会)への反発、自由放恣に見える若い世代への不満、贅沢と過剰への後ろめたさ、逆に言えば、純真、規律、醇乎、献身、簡素への憧憬、それらは発言者の思想方向の左右を問わず共通のものとして存在するようである。
重要なのは、それらを新しい中国のなかに見たように思うことだろう。いかにも革命に湧き立っている新生・中国のことだから、理想への献身、厳正なる規律などが支配していることはたしかであるが、それは日本のような自由主義社会においてもないわけではない。日本の社会が退廃一色でないと同様、中国の社会も純真と規律で塗りつぶされているのではない。常識をもってすれば、それらは当たり前すぎることであるが、社会主義国家においては、自由主義国家には不足乃至欠如する、それらの徳目を見たと思うのであろう。
思えば―中国に限って言えば―戦前・戦中のいわゆるシナ浪人といわれた人たちにも、その自己の心情の過剰なる投影があったように思う。今日の中国観にも彼らと、しばしば似たところがあるように思われる。
(中略)
中国の文化大革命と日本の知識人との関係は、ひろく言って外国との文化接触の問題を考える歴史的な事件となるだろう。しかし私たちが、この経験をこれからもくりかえすか、くりかえさないかは、だれも言うことはできない。私たちは、これまでも何度も、性こりもなくこの経験をくりかえしているからである。
(中略)
日本人が―いや、人類が―歴史に学ぶことができるかどうか、疑わしいところもあるが、にも拘わらず、私たちは何度でも歴史をふりかえってみようと呼びかけねばならないだろう。》(p.201~205)
以上のほかにも、興味深い記述が散見される。
《いずれにせよ、叱責されるたびに彼らは「恐懼おく處を知らずして退出」するのだが、本当に恐懼したのかどうか、面従腹背というべきか、あとはケロリとして天皇の叱責もヌカに釘、つねに無視してしまうのである。さきの原田日記の一節「これは又瞞すのかと思召されたらしく」は痛烈である。ひょっとすれば、天皇は事変のはじめから、自分がていよくダマされていることを自覚されていたかも知れないと想像したくさえなる。(中略)天皇と国民(の一部)との関係は、「宸襟を安んじたてまつる」などの美辞麗句とはまったく縁もゆかりもないどすぐろい不信の関係だったようにも考えられる。(中略)
ひょっとすれば美濃部達吉や津田左右吉の天皇観は、この不信の関係をいかにもありそうな忠君愛国で飾ろうとする偽善への怒りから発していたかも知れない。東京裁判で被告たちが、天皇を戦争責任から遠ざけようとしたとき、はじめて彼らはその生涯において「忠義」を示したのかも知れない。》(1章、p.38~39)
《戦後、日本には俄かづくりの「民主主義者」「戦争反対者」が満ちあふれた。平和と文化国家が突然、この国の合い言葉となった。こんなに沢山の民主主義者がいたのに、どうして結核の私が軍隊に引っぱられ、やがて乞食同然の外地引揚家族と、馬小屋を改造した、その名も「平和寮」という板張りのバラックに住まなければならなかったのか?
戦中派たるもの、いささか憮然たる思いであったことは書いておいてもいいであろう。》(あとがき、p.207)
著者の名は、近年まるで聞かない。私は本書ともう1冊しかこの著者の本を読んだことはないのだが、今日においても十分読み返すだけの価値はある文章だと思う。
(引用文中、旧かな、旧漢字は新かな、新漢字に修正した。また傍点は省略した)
(以下2011.2.11付記)
著者は2008.10.9に86歳で逝去されたと2009年1月に公表された。