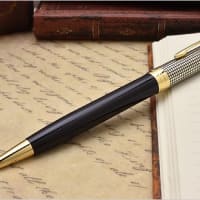新聞に面白い記事があった。
医学画一広場
認知機能低下ぱ40代から始まる
認知機能の低下は50歳前から始まっている可能性が高い、
とフランス国立衛生医学研究所疫学・公衆衛生研究セン
ターのアルチャナー・シン・マヌーー博士らが英医学
誌に発表した。
同博士らは、公務員7390人(45~70歳、男性51
98人)を10年間追跡した。
一定の間隔を置いて3回にわたって、記憶、語彙、推論、
それに言語流ちょう性などの認知機能テストを行った。
高年齢になるほど認知機能の低下は速かったが、推論
能力は男女とも45~49歳で大きく低下し始めていた。
以上。
興味深い研究である。
「推論能力は男女とも45~49歳で大きく低下し始めていた。」
ところで、推論については、
Yahoo!辞書 大辞林 (国語辞書) すいろん【推論】 (名) スル
ある事実をもとにして、他の事をおしはかること。
推理や推定を重ねて結論を導くこと。調査結果から事故原因
を― する.
となっている。
記事には、次のこともあった。
一定の間隔を置いて3回にわたって、記憶、語彙、推論、
それに言語流ちょう性などの認知機能テストを行った。
ということであるが、記憶、や語彙などの認知機能も
機能しなければ、推論力は成り立たない。
また、これらの能力以上に、ワーキングメモリーの機能
の状況も大事であると思う。
短期記憶(STM, short term memory)とは、短期間保持
される記憶である。約20秒間保持される。7±2(5つから
9つまで)の情報しか保持できない。
ということだが、このような記憶力・集中力の問題も
関わってくるのではと思う。
ところで、この一連の能力に関係するものとして、集中
力の問題があるが、この集中力が、実は体力の衰えに
起因すると、池谷裕二氏は、語ったが、とどのつまり、
筋肉量の減少にも起因するということになる。
昔、こまかいことは、忘れたのだが、鈴木健二の
男が50代になすべきこと?という本だったと思うが、この
ような能力は、40代の能力で、このような能力を使う
仕事は、50代からは、できない。という文章があった
ような記憶がある。
鈴木健二のような放送業界での一線で、大活躍した人が
言うのだから、わたしも、かなり説得力を感じたものだ
が、実は、今になって思いだしたが、個人的な経験を
振り返ってみても、40代の半ばに、自分の頭が機能し
なくなってきているのに気づいて、愕然としたことが
ある。
明らかに、仕事上の課題処理能力というのが、質的に
ダウンしているというか、とにかく頭が回転しなく
なっているのに、気づいたのだ。
車のアクセルを踏みんでも、速度が上がらない。
自分の作業場の道具棚から、工具を取り出そうと
したら、ちゃんと整理したいたはずの道具がない。
自分のデーターベースから、資料が無くなっている。
こんな感じである。数年前まで、当たり前だと
思っていたのに、頭が働かないのだ。これには、
さすがに、戸惑いと焦りを感じた。仕事ができ
なくなっているのである。
わたしは、40代後半、張りつめた仕事に疲れが
出てきた。
心が悲鳴をあげた。
新しいことは、何一つ起こらないでくれ。今日と同じ
明日が続いてくれ。
なんて、叫んでいた。
そのうち、50代に入ると、給料なんて下がっていい
から、仕事量と責任を減らしてほしい。なんて、つぶや
いたものだ。
実際、そうはならないのが、厳しいところで、
結局、そうは思いながらも、24時間営業の年中無休
なんて、嘯いて、自分も周囲も欺く生活にどっぷり嵌ま
っていくのだが。
今になって思えば、50代手前に、「今日と違う明日は
きてくれるな。新しいことは、何一つ起こってくれる
な」なんて、心の悲鳴が聞こえたは、もしかして、
「推論能力は男女とも45~49歳で大きく低下し始めて
いた。」ということが、わたしにも起こっていたのだ
ろう。
30代半ばまでは、5~6つのプロジェクトが同時進行
しても、仕事をこなせるパワーがあったが、年をとると
ともに、掛け持ちの仕事をすることが不可能になって
しまっているのに、気づいて愕然としている。
ただ救われるのは、池谷裕二氏は、直感力は、かえって
向上する言う。
もっもと、人間の脳は、年代によって、特徴があるよう
である。
数学のノーベル賞は、確か20代の業績で、評価されると
記憶にあるから、推論能力の衰えは悲しむには、至らない
ことかもしれない。
問題は、この年代に、フルに推論能力を生かすように
努めることで、良しとするしかないだろう。
そこで、ネットを探ってみることにした。
すると、出ました。
職場の脳科学
年代別、脳の「得意技」と「使命」
今回のテーマは、40代の自尊心の種の見つけ方…なの
だけど、その前に、ヒトの脳の「人生の波」について
話そうと思う。
「40代の脳」を理解しないと、プロフェッショナリティ
の作り方もわかりにくいからだ。
実は、ヒトの脳は、年齢によって、得意とする機能が違い、
果たすべき使命が違うのである。このことを知らないと、
どうにも生きにくい人生になってしまうことになる。
ヒトの脳のピークは50代半ば!
ヒトの脳のピークは、なんと50代半ばにやってくる。
連想記憶力が最大に働くようになるからだ。
記憶力には、単純記憶力と連想記憶力がある。
単純記憶力は、多くの情報を一気につかんで、長く
キープする力で、この能力が高いと、「これ見よがし
に頭が良く見える」ため、単純記憶力が最大に働く
15歳から30歳くらいまでが、人生のピークだと思って
いる方も少なくないと思う。
しかし、ヒトの脳の大団円は、50代半ばにピークを
迎える連想記憶力にある。
連想記憶力は、本質を見抜く能力だ。人の資質を見抜い
たり、トラブルを未然に防いだり、戦略に強く関わる
能力である。
いい上司を持っている人ならわかると思うが、50代半
ば以上の「出来るビジネスパーソン」の戦略力は、
それ以下の世代の人には到底かなわない。
静かに、本質だけを突いてくる。無駄な動きもなく、
最大限の読みを見せてくれるはずだ。
正しい20代、30代の生き方をすれば、誰もがこの域に
達するのである。
惚れ惚れする50代、目も当てられない50代
なぜ、静かに本質だけを突いてくるのか…。
実は、50代の脳というのは、「10のうち2しか見えない
脳」なのである。
ただし、その2が、その脳にとって大事な、本質的かつ
貴重な2なのだ。
かつて、将棋の米長名人が、「20代には、何十手も
何百手も読めた。
50代になると、さすがにそんなわけにはいかないが、
不思議と50代の方が強い」とおっしゃったというが、
それはまさに「本質的に必要なものしか見えない、
50代のミラクル脳」を端的に表現している。
さて、“本質的に必要なもの”というが、これは「その脳
にとって」なのである。
「社会にとって普遍の」なのではない。当たり前と言えば、
ごく当たり前。
脳は、社会のために機能しているのではなくて、その個体
のために機能しているのだから。
つまりね、現状維持に凝り固まっている50代の脳は、リスク
ヘッジのために「ネガティブな2しか見えない脳」になった
りもする、ってことだ。それが、その脳にとって大事な
事象だから。
あるいは、視野の狭い人生を過ごしてきた50代だと、「頭が
固いオヤジ」や、「思いこみの激しいオバサン」になったり
もする。
というわけで、本質を静かに見抜く、自動車のCMの“佐藤浩市”
部長みたいな、惚れ惚れするような50代もいるかと思えば、
勘違いもはなはだしいオヤジやオバサン、愚痴と「どうせ」
しか言わない情けない人もいる、というのが、50代という
年代である。
私自身は、この年代の初心者で、昨年末あたりから、どうも
情報を見落とすことが増えてきた。
個人的には「きっと、今は必要ないことだったのよね」と楽天
的だが、会社としてはそうもいかないので、「何でも見える
30代」のスタッフたちに“おんぶにだっこ”している。申し訳
ないなぁと心から思うけど、こればっかりは「脳の事態」なので、
どうしようもない。
会社事業における私の役割は、ときどき「それ、違うかも。
だって、楽しくないもん」と方向修正するとか(しかもいきなり)、
ネガティブな雰囲気になった時に「大丈夫、大丈夫。
たとえ失敗しても、あとでコンサルティングのネタにしちゃう
から」とか言ってかきまわすくらい。
それで許してもらっているなんて、本当にありがたいことで
ある。
50代への対処方法 〜明るく、単刀直入に伝えよう〜
若い世代に、50代への対処法をアドバイスしておこう。
「10のうち2しか見えない」50代は、勘違いを起こすと目も
当てられない。
なので、勘違いを起こさないような情報提供を心がけること
だ。
そのためには、「見てもらいたい2」を、最初にしっかりと
提案することである。
前置きなんかしていたら、危ない危ない。ことばも、かま
ない方がいい(「ことばをかむってことは、何か、悩みごと
でも?」と別の連想記憶が起動しまうことがある)。
また、暗い顔で提案すると、ネガティブな2しか見てくれない
ことにもなりかねない。
明るく前向きな顔、明快な滑舌で、伝えたいことから短刀直入
に。
なお、この場合の「伝えたいことから言え」は、デジタル脳型
対応の「結論から言え」ともまた違う。
たとえば、「嬉しいことがありました」とか、「少し混乱して
います」などと、これから伝えることから「感じてほしいこと」
のエッセンスを伝えるのである。
多くの職場で50代が実権を握っていると思う。特に、今の50代
前半は、バブル期にブイブイ言わせた「ポジティブで新しモノ
好きのくせに、けっこう頭の固い、勘違いしやすい」人たちな
ので、うまく手のひらに載せてしまえばいい。50代を味方に
つけると強いよ〜。
「見る目」を養う20代の脳 〜がむしゃらに経験を積み
上げる〜
さて、50代の話をなぜ延々としたかというと、10〜40代の脳が、
ここを目指して進化を重ねているからだ。
ヒトの脳は、15歳で、大人脳としての一応の完成をみる(12歳
までは、大人脳と構造の全く違う子ども脳。13〜15歳までは、
構造変換の不安定期にあたる)。
そこから27〜8歳までが、単純記憶力の最盛期だ。
とにかく、たくさんの情報をキャッチできるし、長くキープ
していける。
詰め込むだけ詰め込んで、脳は、ここから「生きるためのコツ」
を手にしようとしている。10代の後半と20代の脳は、「世の中
を見る目」を養っているのである。
この時期にやるべきことは、がむしゃらに経験を積み上げる
こと。
経験の種類は、あまりこだわらないでいい。
「営業であろうと、開発であろうと、今いる場所で、がむしゃ
らに踏ん張りなさい。そこで得たプロフェッショナリティは、
やがて別の場所に行っても使える」ということ。前回も話した
通りだ。
30代の脳は「10のうち10が見える脳」 〜惑うことに意味が
ある〜
20代の終盤、単純記憶力が陰りを見せると、がむしゃらさが
消えるのと同時に、まわりが見えてくる。
「最近、がむしゃらになれなくなったなぁ」「昔みたいに
恋に夢中になれないわ」と感じたら、「10のうち10が見える
脳」になった証拠である。
10の事象が、同じ重みで見える30代。選択に迷うし、いった
ん選択しても「他に、もっといい手があったかも」とまた
迷う。
恋愛シーンで自覚している方も多いはずだが、実は仕事で
も、この迷いが、30代を疲弊させている。
しかし!思う存分、迷って、惑ってください。
30代に、「10のうち10」を経験し尽くして、痛い思いも
しなければ、惚れ惚れとするような50代にはなれないの
である。
30代に逃げ癖、あきらめ癖をつけると、40代にそのつけを
払うことにもなる。
30代を生き抜くコツは、「逆境や失敗にめげないこと」で
ある。
「これくらいの逆境がなくちゃ、将来、有名実業家になっ
て自伝を出すときに迫力ないじゃないのさ」くらいの心
意気で。
本当の大失敗は上司が受け止めてくれる。それが50代の
役割だからね。
そんな上司もいない会社なら、大失敗を契機に辞めるのも
また人生だ…くらいの心づもりなら、かなり楽にならない
だろうか。
それと、恋に惑うのは、脳のせいでもある。夫を「運命の
相手は、この人じゃなかったのかも」と疑うのもね(微笑)。
というわけで、そこそこのいい男で手を打つのも、婚外
恋愛はしても家族をないがしろにしないにも、30代の生活
の知恵です、はい。
40代の脳は引き算の脳 〜ふらふらしても無駄〜
30代も終わりにさしかかると、めでたく「物忘れ」が始
まる。
昨日まで難なく口にしていた、よく知っている俳優の
名前が出てこなくなったり、久しぶりに使おうとした
四字熟語や慣用句が出てこなくなったり…
実はこれ、老化ではなく、進化なのである。
単純記憶のために使っていた脳を、連想記憶用にシフト
するために、「生きるためにさほど必要ないと思われる
単純記憶」を放出し始めたのだ。
お赤飯を炊いて祝ってほしいくらい、めでたいことで
ある(マジです)。
40代の脳は、「10のうち10見えていた」30代の脳から、
「10のうち大事な2しか見えない」50代の脳への移行期
にあたる。
少しずつ、見える範囲が狭まってくる。迷いが減り、生き
るのが楽になってくる。
一方で、「引き算の始まった脳」で、まったくの新天地を
求めても、実りが少ないのも事実である。
40代に入ると、「がむしゃらな20代、惑い苦しんだ30代」
を過ごした人は、腹が決まってくる。すると、その道の
プロとして、風格が出てくるのだ。
そんな同世代の迷いのない姿を見て、浮足立つ人がいる。
「私にだって、私にしか出来ないことが何かあるはず」
「私の人生は、何だったんだろう」と。
今までの人生に満足できず、セミナーやビジネス塾を
はしごして、ふらふらする40代は意外に多い。
はっきり言おう。40代で、ただふらふらしても無駄で
ある。
40代で未経験の領域に踏み込んでも、30代にその道で
悩み抜いた人たちと伍することは難しい。
「じゃぁ、40になったら、人生をあきらめなければなら
ないの?」とため息をついた方、もちろん、あきらめる
必要はない。
どんな40代にだって、泣いて笑った30代があったはずだ。
その立ち位置を捨てずに、新天地に挑めばいいのである。
40代は、サクセス・ストーリィを自分で描く〜今のプロ
フェッショナリティを売りに!〜
40代で、新たな人生を築こうとするならば、今の自分の
立ち位置からのサクセス・ストーリィを、自分で描けば
いい。
つまり、職種を変えるときにも、「今のプロフェッショ
ナリティ」を売りにして、アピールしていくのである。
たとえば、経理のOLだった人が、人事教育の専門家に
なりたいと思い立ったとしよう。
理由は、自己表現技法のコンサルタントがカッコよくて
憧れたから…しかし、40代なら、そんな理由は口が裂け
ても言ってはいけない。
「経理の畑で12年間、会社というものを見てきました。
数字の向こうに見えたのは、面白いことに“人”でした。
経理上、不思議な成長を見せる部門がある。そういう
部門には、必ずあるタイプのリーダーがいました」
「経理部門にいたからこそ見えた人材教育のポイントを
活かそうと思い、私は人間教育を学び直したのです」
くらいの屁理屈は言おう。
屁理屈でもいいのである。しかし、屁理屈を言おうと
すれば必ず、その人の立ち位置でしか見えないことが
見えてくる。
そして、それこそが、40代の持つべき、プロフェッショ
ナリティなのである。
あなたの立ち位置だったから見えたもの。それを、しっか
りとことばにしてください。
そのためのセミナーやビジネス塾は、大いに利用すれば
いい。
「自分が何になりたい」のかを探す旅に出たり、「今の
生き方とはまったく別の、想念の夢」を描くために時間
を浪費してはいけない。
20代のがむしゃら、30代の惑い。そこを運よく軽やかに
過ごしても、40代でそのつけを払うことになる…。
人生は、ほんとうに生きにくいものだと思う。
けど、それだけのことはある。50代の花は思ったより華や
かで、豊かだもの。これは、多くの先輩たちが言っている
ことだ(私は、まだ入り口なので、これから体験します)。
今、この文章を読んでくださっている方も、きっと、いろん
な「厳しさ」の中にいると思う。
けど、絶対に、厳しい思いをしただけの花が咲く。
脳は、そんなふうに出来ているのだもの。みんな、心から
応援しているからね!
以上。
ネットにあった話である。
さすが、プロである。
これを、40代半ばの頭が回転しなくて、焦った時に読んで
いたらあんなに、苦しまなくても良かったのだが。
しかし、その頃というのは、1996年以前の話であったから、
まだ、インターネットが一般的でなかった時代だ。
これは、難しい要望だ。
ここで、
「見る目」を養う20代の脳 〜がむしゃらに経験を積み
上げる〜
こう言っているが、この件については、昔、複雑な感想を
もったことがある。
とある本に、若いころは、残業も厭わずがむしゃらに、
日夜、仕事に熱中することで、仕事というのが、マクロ
に理解できる能力を身につける。
ある時期に、徹底的に仕事をしないと、質的に飛躍しない
という趣旨の主張を読んだ。
わたしは、その時期、勤務時間には、無頓着な仕事をして
いたので、我が意を得たりと喜んだのだが、その当時、
わたしは、マルクス主義の影響をかなり受けていたことも
あって、8時間勤務原則論と矛盾して、葛藤していたが、
組合主義が、そういう意味で、労働力の質の飛躍の足かせ
になっているのかと思うと、非常に複雑な気分になった
ことも覚えている。
もっとも、わたし的には、8時間勤務原則論より、自分の
労働力の質的向上の方が優先順位が高いと、矛盾は矛盾と
して、拘り続けてきたのだが。
1日に12時間?働くと、16時間働いたことになるなんて、
ランチェスター?かなんかの本を真に受けて、仕事人間を
やるはめになってしまった。
ところで、「趣味力」秋元 康著 生活人新書
次のようなことがあった。
読み出して、なかなか面白いことが、書いて
あって、一気に読んでしまった。
その中で、何か所か共感できるものがあった。
以下、その抜粋である。
初めてのことを始めてみないか
年をとるということは、どういうことなの
だろう。
そう思うと、加速度を増して「初めてのこと」が
なくなっていく事実に気づかされる。
年をとるにつれて、さまざまな経験を積み重ねる
ということは、初めての経験がなくなっていくと
いうことでもある。
初めてニューヨークに行った、初めて選挙に行った、
初めてフグを食べた……。
今の僕にとっては、そういった「初めて」をどれ
だけ捕まえられるかが人生の課題といっていいかも
しれない。
では、どうすれば「初めて」を捕まえられるのだ
ろうか?
ふと思ったのは、僕にはとくに趣味がないので何か
できたらいいなということだった。
現在、46歳。だんだん、人からものを教えていただく
機会が少なくなってきた。
だから、自分がまるで知らないことを、ゼロから習って
みたくなった。そして、何がいいだろうと考えたときに、
陶芸がいいと思いついたのである。
初めてのことに直面すると、誰だってドキドキする。
人間、初めてのことを始めるときは、ワクワクする。
後述するが、僕はこれまで仕事に関わらない時間は
まったくないというほどに、仕事に没頭してきた。
そんな僕にとって、趣味を侍つことも、陶芸を習う
のも初めてのこと。
とくにこの年になって、人からものを教わることが
「こんなに刺激的なことなのか!」と再発見したよう
な気がしている。
もしかしたら初めてのことを始めるというのは、包丁
を研ぐようなものなのかもしれない。ずっと同じ包丁を
使っていると、必ず同じ部分が磨耗して、切れ味が悪く
なる。
人生も同じように、単調な人生を送っていると、感性が
鈍ってくる。だから、磨耗した包丁を研ぐように、初めて
のことを始めて、感覚を研ぎ澄ませる。
すると、ルーティンワークになっていた日常が新鮮に見え
てくるのだ。
人は年をとると、仕事でも何でもそうだが、思い通りに
できることを選ぶようになるのではないだろうか。
僕くらいの年齢になると、勝算のあることしかやりたが
らないし、楽なほうへと流れていきがちになる。
たとえば、僕より上の年代の男性は、会社にパソコンが
導入されても、いきなりパソコンに向かおうとは思わ
ないのではないか。
しかし、そうやって思い通りになることしか選択しない
ようになると、感覚が麻卑して、刺激がなくなっていく。
年をとるごとに、自分が楽にできることばかり選ぶように
なると、確実に心も頭も錆びついていく。
この年になって、思い通りにならないことに出会うのは、
むしろすごく新鮮なのである。
陶芸をやっているときは、うまくできなければ先生が的確
に教えてくれる。粘土が思い通りにならなくても、教わる
ことによって、少しずつ形になっていく。「教わるという
ことは、なんて楽しいのだろう!」となんだか得した気分に
なる。
だから、日常に追われて「毎日、同じ繰り返しだな」と
感じている人がいたら 趣味を始めることをぜひおすすめ
したい。
「だんだんドキドキワクワクすることがなくなってきたな」
という人にこそ「初めてのことを始めてはいかがですか」と
言いたい。
なかには、「趣味なんかやっている時間はない」という
仕事人間もいるかもしれない。
そういう仕事中毒の人には「では、仕事の中に初めての
ことがありますか」と問いたい。仕事で成績を上げて、
実績を出していくのが楽しいにしても「どこかに初めて
のことはありますか」と聞きたい。
年をとると「初めて」がなくなる。だから、初めての
ことを始めよう。これが僕と同じ年代のすべての人たちに、
いちばん伝えたいことなのだ。
~~~~~~
初めてのことを始めなければ、運はついてこない。
初めてのことに挑まなければ、運命の神様から
ご褒美はもらえないのだ。
~~~~~
とにかく「年をとるにつれて、初めてのことがなく
なるから、初めてのことを始めよう」というのが、
今、僕がいちばんおすすめしたいことだ。
見たことないもの、聞いたことのないこと、行った
ことのないところ、やったことのないことに触れる
のは間違いなく面白いし、ワクワクする。
「初めて」はいつだって人生の刺激なのだ。だから、
初めてのことが少なくなってくる年代になったら、
意識して初めてのことを見つけたい。
大切なことは「昨日と違う今日をどうしたら作れる
か」ということだ。
日常の中に「初めて」はたくさんある。「初めて」を
見つけるのは、「初めて」を見つけようとするあなたの
積極的な意識なのだ。
~~~~~~
以上、本の中から、抜粋してみたが、
彼は、こういっている。
人は年をとると、仕事でも何でもそうだが、思い通りに
できることを選ぶようになるのではないだろうか。
僕くらいの年齢になると、勝算のあることしかやりたが
らないし、楽なほうへと流れていきがちになる。
たとえば、僕より上の年代の男性は、会社にパソコンが
導入されても、いきなりパソコンに向かおうとは思わ
ないのではないか。
しかし、そうやって思い通りになることしか選択しない
ようになると、感覚が麻卑して、刺激がなくなっていく。
年をとるごとに、自分が楽にできることばかり選ぶように
なると、確実に心も頭も錆びついていく。
以上、である。
おそらく、わたしたちの年代は十分に心当たりが、あるだ
ろう。
秋元氏は、
人は年をとると、仕事でも何でもそうだが、思い通りに
できることを選ぶようになるのではないだろうか。
こう言ったが、どういうわけだか、職場では、そのように
立ち回れる人もいるものだ。
わたしには、残念ながら、性分的に、そのような生き方に
なじめないのは、損な性格かもしれない。
しかし、
年をとるごとに、自分が楽にできることばかり選ぶように
なると、確実に心も頭も錆びついていく。
これも、事実で、いつも、何かと逃げ出すと、人間が卑屈
になるのは、悲しいことでもあるし、その卑屈さ合理化する
心理に疑問を持たない人でない限り、そのような生き方は
できないからやっかいだ。
しかし、おうおうにして、そのような合理化を人は、どこ
かで、やっていて、生きずらさをしのいでいるのかもしれ
ない。
結局、このような現実が、たいがいの人間に、
推論能力は男女とも45~49歳で大きく低下し始めていた。
という現実をより加速度的に強いるものかも知れぬが、
秋元氏、曰く。
初めてのことを始めなければ、運はついてこない。
初めてのことに挑まなければ、運命の神様から
ご褒美はもらえないのだ。
大切なことは「昨日と違う今日をどうしたら作れる
か」ということだ。
以上。
心して、推論能力の減退に少しでも抗して、生きたい
ものだ。