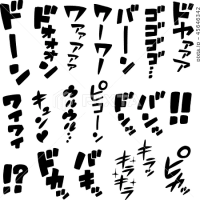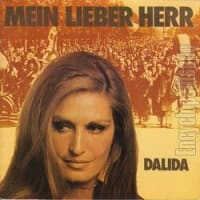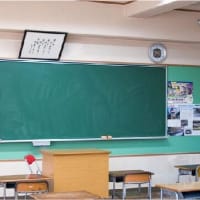師の森の樗の花の月夜かな 西嶋あさ子
西嶋先生の「師」といえば安住 敦ですね。久保田万太郎の流れを汲み、普通の人の心の動きを抒情的に詠んだ作風は、西嶋先生がしっかり受け継いでいるように・・・読みようによってはさらに女性のたおやかな感性が加わりしっとりとした作風に感じます。
句の中の「樗」は悩ましかったです。「あふち」「おおち」などと読む「栴檀」の木だと思います。ただそうすると花の時期は5月から6月ごろになりますので「月夜」という秋の季語とは少しく季節感がずれます。
西嶋先生の季語に対する考え方が分かりませんが、決して「固定観念」的なガチガチものではないのでしょう。
私の考え方ですが、もちろん有季定型を原則と考えてはいますが、現代の生活実態と余りにもかけ離れた「季節感」は自由な詞的感慨を阻害することもあり、それは見直すべきだと思っています。
例えば「障子」は冬の季語とされていますが、元々は「さえぎる物」で杉の戸、板戸、蔀などすべてが障子でした。夏に簀戸をはめ冬に和紙を張った障子に変える家はどれだけあるでしょう?こうした失われた季節感を墨守し、知っていることを滔々と語る先達の方もいますがどうなのかな?とかねがね思っています。