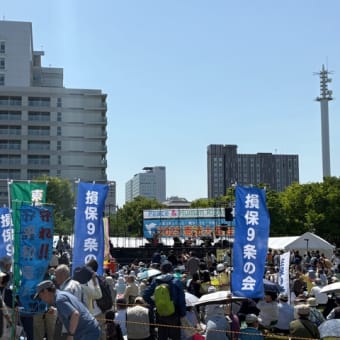昨日、能登半島地震・奥能登豪雨の被災者支援2日目。珠洲市に入り、被災地の状況を確認しつつ、街の中でお会いした方と対話しました。その方の自宅は準半壊で、見舞金と30万円以内の修繕の補助しか出ません。住んでいる地区は約150世帯で残っているのは20世帯程度と、近くの田んぼ58ヘクタール(多くは米作りができなくなった米農家から借り受け)で津波による塩害や豪雨災害により、田植えができなくなった田んぼもあるとのことでした。漁師もされていて、豪雨による土砂が風向きにより混ざり、魚が近くで漁れないそうです。

早めの昼食後に、蛸島漁港近くの仮設住宅に物資のお届けと要望などの聞き取り。12月の入居や10日前に入居した方が多い居住エリアでした。氾濫した川のすぐ近くに住んでいた方は、「川の護岸をしっかりやってもらわないと自宅をどうするかの判断はできない」と言います。またある方は、「住宅を立て直すことに決めた」ということでした。「2年後にどうなっているかわからないので、住み続けられるならそうしたい」など様々でした。
今回、お願いをして仮設住宅の中も見せていただきました。台所のコンロはIHでしたが、同時に煮炊きすると一方が火力が下がってしまい、時間がかかってしまうのと、グリルがないため魚が焼けないとのこと。魚焼きグリルトースターで焼いたら煙が出で煙感知器が反応してしまったそうです。
仮設住宅であっても被災者の生活をより良いものにしていくためには、改善が求められていると感じました。



その後に向かったのは、外浦(日本海側)で、原子力発電所予定地だった場所や、地震と豪雨による土砂崩れで大きな被害が出た大谷地区。沿岸部の崩れた岩を横に見ながら「復興道路」と言われる道路を走り、棚田で有名な白米千枚田の状況も見ました。ここは子どもが小さい時に旅行で訪れてたところです。


久手川(ふてがわ)地区の土砂災害による被害を見ながら、最後は輪島市の朝市と輪島漁港へ。光景はほとんど変わってはいません。まだまだ復興まで道半ばです。