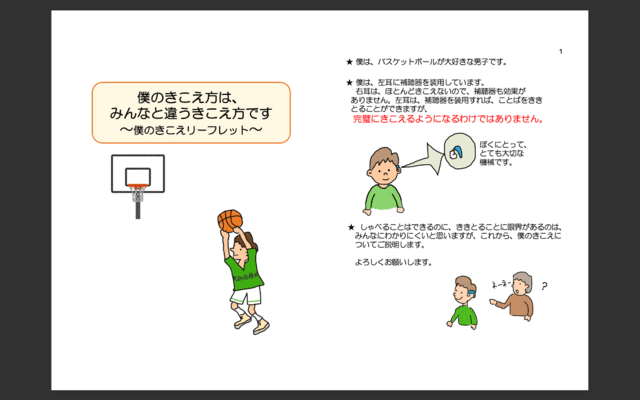ちいさん IT企業→公務員 32歳 90dB→100dB 両耳補聴器装用
ちいさんは、現在32歳、公務員で育児休業中だ。4歳と1歳のきこえるお子さんを子育て中。ろう者の旦那さんと4人家族で暮らしている。小さいお子さんがいる場合は、やはり忙しく、なかなかインタビューも難しいが、そろそろ仕事に復帰されるときいて、今しかない!とインタビューをお願いした。
聴力は、小さい頃は、平均で90dBくらいで、高音域になると徐々に下がる聴力図だった。
今は、平均して100dBを越えるくらいだそうだ。0歳代から補聴器を両耳に装用して現在にいたる。
現在は、音声と手話を両方使っている。始め、小学校は地域の学校に通ったが、中学校は、ろう学校を選択した。また、一度就職した大手IT企業をやめ、公務員に転職した。それらを含めた経緯を一度きちんと聞いてみたいなとずっと思っていた。二人目のお子さんの育児休暇明け直前にやっと伺うことができた。
【 ちいさんのストーリー 】
< 幼児期 >
療育施設には、1歳代から通った。友だちと廊下で三輪車に乗って遊んだこと、ことばやコミュニケーションの個別指導の他は、楽しく遊んだことしか覚えていない。
幼稚園も4歳から併行して通った。友達と遊んだり、物を作ったりした。一つだけ自分のものが誰かに取られて失くなることがあり、先生が子供達を並ばせて、友だちのものを取るのは、やめましょうとお話したことは、記憶に残っている、
< 小学校時代 >
小学校に入って、授業中にFMを使ったり、前から2番目に座ったりすることで、自分だけ補聴器をつけているという意識ができてきた。しかし、地元の幼稚園から同じ友だちがたくさん同じ小学校に入学したこともあり、まわりの理解が自然とあったためか(もちろん、親御さんの努力の賜物)困ることはなかった。
1年生の時は1クラスで、38名、2年生の時は、2クラスで20人と21人と言うように全体として小規模だった。宿題は割とまじめにやっていたし、勉強も理解できていた。
友だちは、仲のよい友だちが2、3人いて、よく遊んだ。休み時間に遊んだり、帰宅してからも、電話(スピーカーホン)で、自分で電話して、「今から遊びにいってもいいですか」と約束し、自転車で遊びにいっていた。
しかし、5、6年生になると、友だちと話がつづかなくなり、面白くないなと思い始めた。それで、昼休みは、図書室に行って、本を借りたり、読んだりすることが多くなっていった。友だちとも遊ぶが、図書室にいる方が落ち着いた。皆、幼稚園からの友だちなので、ゆっくり丁寧に話してくれていたが、なんとなく、同じテンポで会話ができなくなった。
6年生になり、進学先について色々と迷った。幼児期に療育施設で出会った友人の中に、小学校からろう学校に行っていた友だちがいて、その子とパソコンでメールのやりとりをしていたが、その子の話からろう学校の様子を教えてもらっていた。それでろう学校は楽しそうだなと感じるようになった。
父母も中学校に関しては、ろう学校という選択肢もあるよと言ってくれていた。特に母は、地域の中学校が聴覚障害ににあまり理解がないことを問題視していたようだ。(中学校に見学に行ったら、特別支援級に案内された。)
ろう学校中等部の見学もした。手話を使って授業を受けたいと思ったし、友だちと楽しくコミュニケーションを取りたいと思った。また、英語が始まることへの不安もあったので、ろう学校への進学を決めた。ろう学校に幼馴染の友だちがいたことが一番大きかったかもしれない。
< 中学校(ろう学校中等部)時代 >
手話は、小学校時代に母と一緒に地域の手話教室に通って、簡単な手話は知っていた。しかし、本格的には、ろう学校に入ってから学んだ。
ろう学校中等部に入学した頃、ろう学校では、それまで採用していたキュードスピーチをやめ、手話を採用したところだった。従って、生徒はまだキュードスピーチを使い慣れていたが、授業では、先生が手話を使うという状態だった。
友だちに、キュードスピーチや手話を一つ一つ教えてもらった。中3になる頃には、生徒たちは会話はほぼ手話で行っていた。
授業が手話だったのは、やはり分かりやすかった。授業内容が一般の学校に比べて、ゆっくりなのは、気になったが、「わかる」ことはよかった。手話のありがたみを感じた。
手話で友だちとたくさんコミュニケーションを取ることができた。手話で喧嘩もしたが、手話で友だちがどういう考えなのか、どう感じているかもわかったので、相手の気持ちになって考えることもできるようになったと思っている。
小学校の時は、喧嘩できるほどのコミュニケーションは取れてなかった。全体に一方通行のコミュニケーションで終わることが多かった。
その頃のろう学校は、人数も多く、同じ学年は18、19人いた。部活もバレーボール部に入り、楽しい中学校生活を送った。
高校進学にあたり、そのまま、ろう学校の高等部に内部進学するか、他のろう学校にいくか、地域の高校に行くか、迷った。地域の高校は、見学に行った際、聴覚障害があることを伝えると、あまり反応がよくなかった。入ってもいいけど、サポートはできませんなどと、不安になるような答えが返ってきた。
部活でのバレーボールの大会の時に、筑波大附属のろう学校のチームを見た時、よさそうな学校だなと思った。筑波大附属にも見学に行った。すると、怖そうな先生が多くいて、それで、却って、ワクワクした。附属受験に挑戦することにした。
受験対策として、親にお願いして、地元のマンツーマンの塾に通わせてもらった。論文は、学校の担任の先生に個別に指導してもらった。また、模擬試験を受けたりした。そして、合格することができた。
< 高校時代 >
附属高校は、家から2時間かかるので、寄宿舎に入った。鹿児島から北海道の全国から生徒がきていて、活気に溢れていた。積極的な子が多かった。
試験の結果は廊下に張り出され、自分の順位がわかるようになっていた。(今はやっていないかもしれない)それは、自分にとっては、みんなの中での自分の順位がはっきりわかり、わかることで、もっと頑張ろうと思えた。勉強の大切さを教えてもらった気がしている。
部活はバレーボールに入った。体育館が狭くて、卓球と場所を分かち合っていた。バレーのコート分のスペースがなかなか取れなかった。体育館が使えない日は、外でトレーニングをしていた。
寄宿舎生活は、初めは、ホームシックになり、週1回は、実家に却っていた。実家でまたエネルギーを蓄えて、またがんばろうという気持ちになった。多分私が、寄宿舎の中で、一番頻回に家に帰っていたと思う。
附属には、有名なろうの方が多くいて、色んなロールモデルを知ることができた。ろうの世界も知った。
学校では、対応手話を使っていた。友人の中には、日本手話を使う人もいて、私は、日本手話の読み取りはできるようになったが、自分で表現するのは、ちょっと難しい。
< 大学へ >
初めは、栄養士の資格を取りたいと思っていた。いくつかその資格が取れる学校を見学した。しかし、聴覚障害があることを伝えると、現場実習で調理器具のブザーの音がきこえないので、その時の対応が難しいなどと言われて、やや受け入れがよくない印象を受けた。後輩の子で、栄養士の資格が取れる学校に行った子もいるので、もう少しがんばればよかったのかもしれないが、あっさり諦めてしまった。
結局担任の先生と相談して、衣食住のことが幅広く学べる家政系の大学を選んだ。
< 大学生活 >
一般の大学に入学し、小学校以来のきこえる世界に入ることになった。少しずつ友達もできて、1つのグループに入れてもらって、遊んだりもした。ろうの学生は自分一人だけだったが、他の大学の手話サークルに入って、そこで手話で会話ができたので、バランスがとれていたのかもしれない。
授業は、FMマイクを使った。席はなるべく前に座って、ノートテイクもしてもらった。大学の学生がノートテイクをしてくれる仕組みがあった。しかし、段々と人手不足で十分にはしてもらえなかった。また、被服の授業の服の作成は難しかった。
運動は、聴覚障害者協会のバレーボール部に入った。その時参加したデフバレーは、結婚して子どもを産むまで続けた。
< 就職活動 >
民間企業を受けたいと思って、障害者雇用でサーナとか、クローバーなどの会社に相談した。企業のブースに行って、エントリーシートを書いた。IT企業に内定をもらった。
< IT企業への就職 >
会社は新橋にあったが、途中異動があって、埼玉から勝どきまで通った。遠くて大変だった。1年目と3年目は、実家から通ったが、2年目だけアパートに一人暮らしした。一人暮らしがなぜ2年目の1年間だけだったのかというと、ある事件があったからだ。
アパートは、2階建てで、私は2階に住んでいた。ある日、洗面所の水道を出しっぱなしにして、出勤してしまった。水の音に気づけなかった。その日仕事中に知らない電話番号から電話があったが、後でかけ直そうと思って放置していた。すると親から連絡が来て、そこで、出しっぱなしにした水が溢れて、水が床にたまり、1階の部屋まで水浸しになっていることを知らされた。
保険に入っていたので、なんとか収まったが、もう一人暮らしはいいやと思った。
会社は、IT系の会社だったので、情報保障もしっかりしていた。社員同士の会話はチャットが使えた。会議の時はGoogleのドキュメントワークを使って、同僚が会議の内容をPCに打ち込んでくれたので、それを見て理解した。会議で発言するまでには、いかなかったが、内容を知るだけでも大きかった。
朝礼の時は、UDトークを使った。打ち合わせのメンバーで丸くなって、話す人は、携帯に向かって話をしてくれた。それを自分の携帯で文字で確認した。
全体に目で見える情報が多かったので、やり易かった。ただ、通勤に時間がかかるのと、埼玉にいる人との結婚を考えていたので、「東京のOL」には、執着しないことにした。埼玉で働けるように県の公務員試験を受けた。
< 公務員 >
今は、県の公務員として、事務の仕事をして6年目になる。職場は、コロナの前は、全体にアナログで、前職と比べて苦労したが、県民のために働くというやりがいは感じている。コロナ後に育児休暇から職場に復帰したが、随分情報保障が改善されていた。コロナのおかげでzoomが導入されたし、職員同士でチャットができるようになった。
マスクをしている人との会話は難しかったりしたが、仕事は、人対応というより、事務仕事が中心なので、何とかなっている。会議はそれほど多くはない。
今は、異動で2つ目の部署にいるのだが、そこは保健所で、受付のところには地域の方がくる。その窓口対応は、私には難しいので、誰かにお願いしたりしている。仕事の内容は総務の仕事をしている。
研修は、人事課にお願いして、手話通訳を派遣してもらっているので、最低限の情報は得られている。普段は、携帯の音声文字変換アプリをよく使っている。コミュニケーションはなんとかなっているが、仕事を覚えるというところが大変だ。5月から仕事復帰なので、がんばりたい。
< 結婚、子育て >
中学校の時の同級生の一人と20歳の時に成人式などで再会したりして、ご飯に行ったり、遊びに行くようになって、付き合うようになった。彼は、きこえない人で、主に手話で会話をする。気心知れた仲間ということもあり、気を遣う必要もなく、話し易かったのもある。5年くらい付き合って、結婚して、今は5年くらい経つ。子どもは、今二人いる。
夫婦での会話は手話。子どもたちはきこえる子たちだが、家族の間では手話が通じるようにしたいと思っている。今は、ことばを覚える時期でもあるので、ことばに手話をつけて話している。
上の子は4歳で、話すことのほうが多いが、わかる手話を使っても話してくれる。私とより、父親と話す時の方が、手話を使う。私もできるだけ手話を使おうと思っているが、緊急の時は、つい、あぶないよ!とか、早く歯を磨いて!とか口が先に出てしまう。
下の子は、1歳3ヶ月なので、まだ、それほどことばが出ておらず、身振りが多い。アンパンマン、指差し、クサイクサイなどは身振りで表現している。
今夫婦で手話で話をしていると、4歳の息子が何話しているの?ときいてくる。私たちが、きこえる人たちの話がわからないように、息子も私たちの話がわからないんだと思って、きをつけないとだめだなと思っている。
父はきこえない人で、母は、口話も手話も使い、近くで呼べば、振り返るという違いを息子なりにわかってきている。後ろから呼ぶ時は、父には、トントンとたたいて知らせる。
保育園の保護者会の時は、市の手話通訳をつけてもらっている。保育園の担任の先生と話をする時は、口話で話している。先生にはマスクをはずしてもらう。ただ、今日の息子の様子はこうでしたよなどという話はあまりない。他の親を見ていると、先生と色々おしゃべりしている感じだが、私には事務的に、今日は元気にしていましたなどという簡単な報告だけで終わってしまう。そこは少し寂しく感じるところで、もっとやり方を工夫しようと思っている。
< 療育施設時代の仲間 >
幼児期に通った療育施設の友だちとは、ずっと付き合いがある、1年に、1、2回は、4、5人で集まって、色んな話をする。考え方が少しずつ違うが、会って話をすることが楽しいし、教えてもらうところもたくさんある。口話も使うし、手話も使う。これからもこの付き合いは大事にしていきたい。
<あとがき>
ちいさんは、幼児期に同じ療育施設で出会った友だちとずっと付き合っている。ちいさんの学年は、例年より人数が多かった。そして、親御さんたちがとてもよい関係を持っていて、メーリングリストを作って情報を交換したり、他の学年にも呼びかけて、保護者で毎年文集を作ったりしていた。この文集は、後輩の保護者さんたちに、自分たちの経験を知ってもらって、参考にしてもらいたいという思いからできたものだ。ちいさんたちが卒業してからも、保護者同士のでんごんばんとして今なお続いている。
小学校に入学する時には、教室の椅子の足にテニスボールを履かせるように(椅子の足が床に擦れる音は、補聴器装用耳には、うるさくて辛い)、学校に掛け合う方法を知らせあったり、テニスボールに切れ込みを入れる方法を知らせあったりしていた。
療育施設を卒業してからも、毎年集まり、子どもたちを一緒に遊ばせたり、小学校での生活の情報交換したりして、その関係を持続させていた。そのおかげで、子どもたちは、年頃になると、自分たちだけで定期的に会うようになったのだ。個性の異なる子どもたちが、それぞれ異なる道を歩んでも、関係が続いていることは、素晴らしいと思う。時々集まった時の写真を私にも送ってくれて、それは、とても嬉しい。
ちいさんは、小学校の5、6年になって、友だちとの会話についていけなくなるのを感じたのだが、その時も、ろう学校に行った友だちから、ろう学校の様子をきいて、そういう場所もあることを知ったことは、とても大きいことだと思う。
ちいさんのようになんとなく疎外感を感じて、図書館で静かに本を読んで過ごしても、傍目には、本の好きな子としか映らないし、親御さんも成績に問題がなければ、問題なしと考えることが多い。特に当時は、できれば地域の学校できこえる友だちと一緒に過ごさせたいという風潮があったので、音声言語から手話への切り替えをこの年齢でしたのは、少し驚いたものだった。私自身、今でこそ、難聴のある子どもたちの日常の困り感に留意しなければならないと思うようになっているが、当時は、学校への適応を「成績」と「友だち関係」で考えていて、友だち関係も特にトラブルがなければよしとしていたので、ちいさんが抱えていた「疎外感」を汲み取って、進路を決めたご本人と親御さんはすごいなと思っている。
ちいさんは、ろう学校で手話で友だちと楽しくコミュニケーションを取り、時には手話で喧嘩もして、改めて、小学校でのコミュニケーションは、一方通行だったと気づくことができたし、その点を解決できる道へと進路変更できたことは、ちいさんにとっては、大切な選択となったと思う。
現在、日本手話の旦那さんと対応手話と音声言語のちいさん、そしてきこえる二人のおこさんの家族で、共通手段は手話にするという方針で子育てしているということだ。ちいさんの保育園の先生とのコミュニケーションの話が少し気になったが、遠慮しないで、スマホのアプリなども活用して、がんばって、コミュニケーションを取ってほしいなと思う。
ちいさんのお母さんは、これまで県や全国の難聴児を持つ親の会で随分と尽力されてきた方で、今でも会の運営を引っ張っておられる方だ。1歳のちいさんを連れて我々の療育施設にきた時は、小学校の教員をされていた。ちいさんは、高度難聴だったので、補聴器に頼らざるを得なかった当時は、仕事はやめて、ちいさんの療育に専念することをお勧めした。
結局、その年度が終わって、担任業務が終わってから、ちいさんのお母さんは、仕事を退職し、ちいさんの療育に専念した。そしてちいさんが小学校4年生くらいの時に、非常勤講師として午前中だけ勤務し、ちいさんが中学生になった時に再度教員試験を受けて、もう一度教員として、仕事に復帰された。その時、昔と比べて、つまり、ちいさんを育てる前よりも、後のほうが、コミュニケーションが上手ではない児童に目が行くようになったと仰っていた。私は、そのことばがとてもうれしかったのをよく覚えている。やはり、お子さんのためと言えども、仕事をやめてもらったことに少し申し訳ない気持ちもあったからだ。そして、また、ちいさんの療育を通して、一人ひとりの子どもと丁寧にコミュニケーションを取ることを大事にする教師になってくださったことに感銘を受けたのだ。そして、退職前には、支援級の教師として大活躍されたことには、心底感服している。
このブログのNO.15で書いている「マッキーズ」というオンライン手話おしゃべり会にも、お母さんは、現在熱心に参加してくださっている。ちいさんの旦那さんと少しでもコミュニケーションを取りたいという思いからだ。そして、私も月一のマッキーズで学び、今回多少なりともインタビューに手話を役立てることができたと思っている。
この文章をブログにアップしてもよいかどうか、ちいさんとお母さんに事前に読んでいただいたが、ちいさんのお母さんから、療育や親の会での出会いへの感謝のメッセージが送られてきた。以下のようなメッセージだ。
「3人の子どもたちを育てるために、無我夢中でやってきました。3人の子どもたちがまっすぐに育ってくれたのは、一緒に療育を受けたお母さんたちのおかげです。療育施設でのお昼休みの時に娘(ちいさん)の姉と兄のことを話し、2人の接し方について考えることができました。また、親の会の行事に参加して、先生方や先輩のおかあさんからたくさんのことを教えてもらい、娘の接し方や進路を考える時の参考になりました。」
人生はまだまだ続く。ちいさんの仕事もうまくいってほしいし、お子さんたちも、パパともママともよくコミュニケーションをとって、幸せな家族になってほしい。太っ腹おばあちゃんの力を借りながら。
【 みんなの感想 】
動画を視聴してくださった方々の感想をご紹介します。
ちいさんの背景にこのような選択肢があったのですね。ろう学校に行かれてからも、さらに視野を広げて行動していった親御さんも本人もすごいなと思いました。
難聴児を育てる上で、インテさせたとしても、その先に色んな道があるし、色々なロールモデルがあると思うので、色々な世代の話が知りたいと思いました。
例えばろう学校に行きたかったけど、親御さんに手話を使うことを反対されたとか、仲のいい友だちとクラスが別れてしまって、もう無理だと思って、ろう学校に行く決心をしたとか、今になって色んな話をきいて、感心することが多いです。
これまで聞いた話では、最終的に7、8割の人が、最終的に行き着くところは、ろうや難聴同士のコミュニティかなと感じています。
(当事者、難聴児を子育て中)
今までの動画に出演していた方は、お会いしたことのない方達でしたが、今回初めて知り合いが出演していたので、所々知っていることもあり、普段とは違う楽しさがありました。(笑)
とはいえ、普段の会話の内容は、共通の趣味や知り合いのことが多く、昔のことは知らないことがほとんどだったので、「そうだったんだ!」となることも多々ありました。逆にここでは話してないことを私が知っていたりするのも知り合いならではの面白いところですね。(笑)
(当事者)
全体を通して、特に印象的だったのは、ちいさんの周りには、いつも素敵な友だちや先生がいて、その時々の環境や仲間に支えられてきた様子が伝わってきたことです。それは、まさにちいさんの人柄の表れだと思います。
中学進学の際には、ろう学校の様子をきいたり、より理解できる手段(手話)で学びのスキルを高めたいという思いから、中学校の段階で自己選択をされたことに感心しました。
また、お母様がろう学校の見学に連れて行く環境を整えたことも素晴らしいと思いました。先生がおっしゃっていた通り、その時代の親御さんは、地域の学校に通ってほしいと願うことが多かったと思うので、ちいさんの自己決定を尊重したお母様の姿勢に感動しました。私は、当事者ではありますが、当時の親御さんとしての心境を、1人の母親の視点からもぜひきいてみたいと思いました。
ちいさんのお話を通してしみじみ感じたのは、「環境の大切さ」です。子育て真っ最中の忙しい仲で貴重なお話をありがとうございました。
(当事者)
うちの子が小さい時に参加した親の会の合宿に高校〜大学生のちいさんが毎年来られていたと思います。小さい子に優しく声をかけていて、笑顔で優しく接してくれていたのを良く覚えています。
もう結婚して、お子さんもいる、なんて、とてもうれしく思いました。近いうちにうちにもある、大学進学〜就職の話が聞けてよかったです。ありがとうございました。
(保護者)
ちいさんは、きこえる世界ときこえない世界を柔軟に行き来していてすごいなあと思いました。小学校と中学校と高校と大学、そして社会人と、その時の自分の興味関心に合わせて環境を決め、楽しんでいるようにお見受けしました。きっとお話されたこと以外に大変なこともあっただろうなと推察しますが、充実した生活のお話から、意思の強さとしなやかさを感じました。
個人的にも、うちの難聴の娘がちょうどちひろさんと同じくらいの聴力で、普通小学校に入学したばかりなこともあり、色々考えさせられました。私を含め、普通学校とろう学校とどっちがいいのか悩む親は多いと思いますが、ちいさんのように世界を決めつけず、その時の本人の気持ちを大切にして決められるのが一番いいだろうなと思いました。今回も非常に勉強になりました。ありがとうございました。
(保護者)
普通小からろう学校中等部へ。大学時代の手話サークル。デフバレー部。このように自分の居場所を自分で作れるのは、素敵なことだと思います。
今の生活も充実しているようで、すごく幸せそうに見えます。ご主人とのコミュニケーションの部分でほっこりしました。日本手話と日本語対応手話、そして音声言語。お二人のお子さんがトリリンガルで使いこなせるようになるのだなあと勝手に想像しました。子どもの適応力ってすごいですね!
(保護者)
お母様の手助けを受けながら、社会人として母として立派にやっておられて、とても頼もしく感じました。人生の時々に、しっかり判断して進んでらしたのだと思います。仕事復帰後も大変だと思いますが、ぜひ頑張ってほしいです。
(保護者)
ちいさん、前向きで頑張りやさんで素敵な方ですね。その時その時で自分に合った選択をされていて、やらされているのではなく、自分で選んだ道だから頑張れるんだなと感じました。復帰されて大変なこともあるでしょうけど、これからも明るく頑張っていかれるんだろうなと思いました。
(保護者)
ちいさんは、育児、仕事で今忙しくて大変な時期ですね。それに加えて、難聴があることで、お子さんや保育園の先生とのコミュニケーションの苦労があるのですね。でも、色々工夫して乗り越えてゆく強さを感じました。
小学校高学年でろう学校の進学を選択するなど、その時々で自分はどうするのがいのか、自分で考えて決断してきたことが本当にすごいなと思いました。自分のことを理解し、向き合うことができていたのですね。きっとお子さんも優しい人に成長し、頼もしい存在になることでしょう。今回も貴重なお話ありがとうございました。
(支援者)
ちいさんは、中学・高校・大学・就職・子育てとその時々の大切な人生の節目で、ご両親やお友だちからの意見を参考にしながら、ご自身でよく考え、よい選択をされてきたと感じました。子育てをしながらの職場復帰は大変だと思いますが、お身体に気をつけて、ごろ湯真にお力添えをいただきながら無理せずにがんばってください。
(支援者)