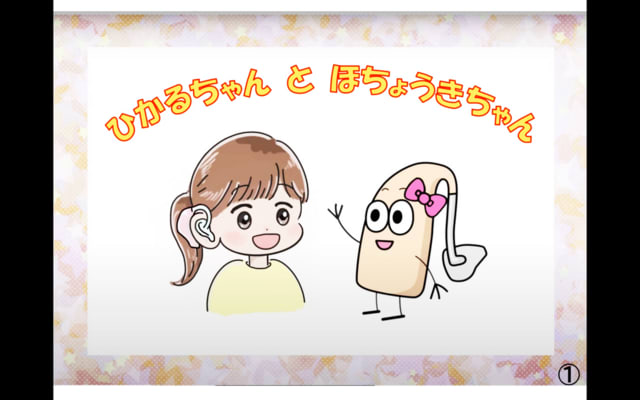ひでさん 劇団員 29歳 良聴耳80dB台 補聴器装用
ひでさんは、ご両親がろう者のご家庭に生まれた。高度難聴だった。ひでさんが1歳代の時、他県から転居してきて埼玉県の療育施設に通い始めた。そして、母方の祖父母も他県から転居されてきた。祖父母は、きこえる方で、子どもたちの「聞く、話す」を育てるために同居を決めたのだ。妹さんが生まれたが、その後ご両親は離婚され、お母さんは、祖父母の協力を得ながら、二人のお子さんを育て上げた。ひでさんは、素直なやさしい男の子だった。妹思いでもあり、友達思いでもあった。
ひでさんは、大人になってから、2回ほど私たちの療育施設にきて、保護者や療育者に経験談を話してくれた。ユーモアもあって話上手だった。実は、この記録は、その2回目の講演の記録である。
1回目の講演の時は、まだ就職前で、内容的には、自分は、苦労もあったけど友達に恵まれて結構楽しくやってきました、というような内容だったが、2回目は社会に出て色々な経験をし、デフファミリーに生まれた自分のことを見つめ直したより濃い内容の話だった。2回目の講演は、1回目ほどきれいにまとまった内容ではなく、途中で「まとめきれません!」とおどけてみせる場面もあった。しかし、1回目よりももっと自分の本当の思いを伝えようとしてくれたことがわかる内容だった。私たちは、笑ったり、涙ぐんだりして話に引き込まれたのだった。
彼は、この講演の4年後33歳の若さで癌のため亡くなった。まだ幼い息子さんを残して天国に行ってしまった。あまりにもあっけなく彼はいなくなってしまった。私は、特にこの2回目の講演に字幕をつけて期間限定でYouTubeで配信した。そして、今回、一連の他のインタビューの記録と一緒に、ここに彼の講演もご紹介することにした。今後も彼の濃い33年の人生を大切に語り継ぎたいと思う。
【 ひでさんのストーリー 〜講演より〜 】
<学校>
就職前に一度、昔お世話になったこの療育施設で講演をしたが、その講演ではぼくは、自分を出していなかったかもしれない。見栄や強がる気持ちもあったかもしれない。ぼくは、長い間きこえる人の中で勝手に負い目を感じていた。ずっと相手の顔色をうかがってきた。
療育施設を卒園した後、小、中、高とずっと地域の学校に通った。その12年間で身につけたことは、何かというと、何かおもしろい話でみんながどっと笑った時に、何がおもしろいのか分からなくても、タイミングよく一緒に笑うことだった。そして、それを深刻に考えることもなく、まーいっかいっかと流すのが自分のやり方だった。
<就職>
高校を卒業して、障害者の職業訓練校に2年間通った後、IT企業に就職した。そこに5年勤めた。初め、「電話はできますか?」と言われ、「ぼくが難聴だとわかっている人となら電話で会話できますが、ぼくがきこえる人だと思って、わーっと喋られると難しいです。」と答えた。会社はそれを了解してくれた。そして、初めのうちは、顔を見て話をしてくれたり、わかりやすく話してくれたりしていた。しかし、ぼくが普通にしゃべるので、段々みんなそういう配慮をするのを忘れるようになった。
会議も、自分は聞き取ることが難しいと上の人に伝えていたのに、特に配慮はなく、周知もしてくれなかった。会議の内容がわからず、その時間は眠くなるだけなので、別の仕事をしたいと申し出たが、却下された。それどころか、会議の書記を頼まれたりもした。書記を頼まれた時はさすがにびっくりしたが、あんまり「できないできない」というばかりではいけないと思って、引き受けたことがある。しかし、一人ずつ順番に発言しているうちはよいが、段々みんなが熱くなってきて、複数の人の発言が被るようになると、全くわからなくなり、分からないので寝てしまったのだった。記録はやはりできなかった。
あとで、書記をしないで、寝ていたことを注意されて、寝てしまったことについては謝った。しかし、「ぼくは、話せるけれども、全部は聞き取れません。まさか書記を頼まれるとは思いませんでした」と抗議した。その時は、会社の人も謝ってくれたが、何度言っても、きこえないことを理解してくれず、周知もしてくれず、段々と嫌になってきたのだった。結局会社の中での自分の存在は軽く捉えられているのだと思うようになった。
<大橋さんとの出会い、そして転職>
会社に勤めていた頃、大橋弘枝さんという聴覚障害の女優さんの舞台を見る機会があった。ダンスがとても上手で素晴らしい舞台だった。それを見てとても感銘を受けた。ろう者でも舞台に立っていいんだ!!と思った。それまで会社の中で悶々としてきた思いが一気に弾けた。そして、少しでもその舞台に関わりたいと思って、なんでもやらせて欲しいとお願いしに行った。すると、ちょうど男性のダンサーが足りないとかで、大橋さんにダンスやってみない?と言われたのだった。会社に行きながらだったが、まずダンスから練習を始めた。
ダンスの次には役者にも挑戦した。役者は楽しかった。舞台の上で医者にも弁護士にも何にでもなれるというのがとても楽しく感じた。段々と役者をやりたいという気持ちが膨らんでくる中で、会社での自分の存在意義が感じられなくなってきていたこともあり、会社を辞めることになった。
会社を辞める前に、人形劇団デフパペットシアターひとみという劇団を教えてもらった。その劇団は、地方回りが多く、全国を回っていた。そこの劇団員になることになった。
ぼくは、この劇団に入る前は、手話を使うことはあまりなかった。祖父母や母は、ぼくの「聞く話す」という力を育てたいと思っていたので、あえて手話を覚えなさいとは言わなかった。自分も覚えようとは全く思っていなかった。ろう者である母も、がんばって口話を使ってくれていた。子どもの頃から、きこえない人ときこえる人がいることはわかっていたが、母とのコミュニケーションで困ったら、文字を書くことで通じていたので、特に困ってはいなかった。
社会に出る前に、ろうの友だちに「デフファミリーなのになんであんたは喋れるの?あんたはろうなの?難聴なの?」ときかれた。ぼくが「難聴」と答えると、チェッという顔をして離れていく友だちが何人もいた。それを母に相談すると、「あなたが自分を難聴と思うなら、それでいいじゃない。離れていかない友だちを大事にすればいい」と言われた。確かに、ろうの友だちの中には、「おまえ、しゃべれるの?じゃ通訳してよ。」と頼んでくれる友だちもいた。それで、広く浅くではなく、狭く深い友だちづきあいをすることにした。
劇団には、口も動かさず、早い手話(日本手話)でコミュニケーションする50代のろうの人がいた。一方で、声と共に手話(日本語対応手話)を使う人もいて、それぞれが会話をする時には、同じ聴覚障害者なのに、通訳が必要だった。そういう色々な人と毎日付き合っているうちに、段々とぼくも手話を覚えてきて、声なしの早い手話(日本手話)もできるようになった。(ひでさんが劇団でろう者と難聴者、聴者の橋渡しとして働く姿は、NHKのハートネットTV、または、その前身の番組でも紹介されたことがある。)
( ※ 注 日本手話 → ろう者の伝統的手話、日本語対応手話 → 日本語に対応した手話 両者は、別々の文法を持つ異なる言語。)
<母とぼく>
ぼくが、家でその声なしの手話(日本手話)を使った時は、母は驚いていた。しかし、同時にとてもうれしそうな顔をしていた。その時初めて、ぼくは「あ、母は、今まではぼくのために、使いたかった手話を、あえて使わないで接してくれていたんだな」と気づいたのだった。ぼくは、母に尋ねた。「ぼくが(日本)手話を使うことで、お母さんの今までの何年もの間の苦労が無駄になると思わない?」すると母は、「それはあなたが決めることだから、何とも思わないよ。」と言ってくれた。元々仲はよかったが、手話でやりとりすることで、さらに関係が深まった。母とは手話で、祖父母とは口話で話すようになった。
今、仕事でろう学校に行くこともある。最近のろう学校は、人工内耳の子どもが増えてきて、ろう学校でも口話の子どもが増えていてびっくりしている。同時に少し「さみしいな」とも思う。母の時代は、ろう学校で手話は禁止されていたので、母たちは学校ではがんばって口話を使い、家に帰ったり、友だち同士では手話を使っていた。それが段々ろう学校でも手話を使っていいんだよというふうに変わったのに、今度は人工内耳で口話が主流になっていて、なんだか不思議な気がする。手話か口話かは、大人が決める。どっちじゃなきゃダメということはない・・・。ぼくはどっちでもいい・・・。ただ、母にはすごく感謝している。(ここで時計を見て、時間が押していることに気づき、あわててどうしても触れておきたいという祖父の話に移った。)
<祖父のこと>
母がろう者だったので、他県から祖父母が孫と一緒に暮らすために来てくれた。ぼくは初めは祖父母と一緒に暮らせることを喜んでいたが、ぼくが小学校に上がったとたん、祖父は厳しくなった。ぼくは、ぼくが何か悪いことをしたから祖父に嫌われたんだと思った。
祖父はことばの教室にも来てくれて、そこで教え方をメモして、家で訓練した。学校から帰宅すると、遊びに行かせてもらえず、家で勉強させられた。50音を一つずつ発音させられたり、いろんなことを教えられた。間違えるとげんこつが飛んできて、それがとても痛かった。小学校1年から3年までは訓練され、間違えるとたたかれるという体育の先生と生徒みたいな関係だった。
ぼくは、小、中とぼくのことをよくわかってくれる友だちのいる地域の学校に通った。そして高校は公立の高校に進んだ。高校では、知らない友だちばかりの環境になった。高校に入った時、友だちに、「おまえ、補聴器はずしたらきこえないんだろ?だけどそんなにしゃべれるなんてすごいなおまえ。」と言われた。その時初めて祖父があんなに厳しく訓練してくれたことの意味―きこえる人と対等にいられるようにーに気づいた。それで、学校から帰って、「今日学校で友だちにすごく褒められた。それはおかあさんやおじいちゃんのおかげだと思う」と話をした。すると祖父は、「本当はよくある孫とおじいちゃんの関係でいたかった。だけど、おまえは父親がいないからその代わりをするのはおれしかいないだろ?だからしつけも厳しくしたし、ことばの訓練も本当は遊ばせてやりたかったけど、社会に出た時に困らせたくなかったからやったんだ。お母さんが社会に出たときにすごく苦労したから、それもあってやったんだ」と語って、初めて涙した。その時は、ぼくも一緒に泣いた。それからは、普通のおじいちゃんと孫の関係で暮らした。祖父は、3年前に亡くなった。
ぼくは総じて環境に恵まれていたと思う。学校で特にいじめに遭ったこともないし、幼、小、中、高と色々な方々にお世話になり、ありがたいなと思っている。
< あとがき >
講演は少し時間が足りず、最後は、少々無理やりまとめて終了となった。本当は、ひでさんは、もっともっと言いたいことがあったのではないかなと思っている。もう少し突っ込んで話をきいておけばよかったと今になって思う。
ここで少し歴史的な背景を説明する。
<ひでさんのお母さんが学校生活を送った時代>
ひでさんのお母さんが育った時代は、日本の多くのろう学校で手話が禁止されていた時代だった。その理由は、ろうであれ、「日本語」を学ぶべきだという当時の「文部省」の方針だった。お母さんは、高度難聴にも関わらず、ご両親がきこえる方だったので、学校でも家でも口話を求められた。しかし、充分な補聴もされないままの口話教育には限界があり、コミュニケーションの手段にはなり得なかった。本当は、「言語習得」だけでなく、周りの人たちと「コミュニケーション」がとれる手段が絶対的に必要だったのに、そこが見落とされていた。ところがどっこい子どもたちは逞しい。ひでさんのお母さんたちは、先生の見ていないところでは、子ども同士で手話を身につけていった。上の子ども達が下の子どもたちに伝えたところもあっただろうし、デフファミリーの子どもたちは、家庭で手話を自然に学んでいたのだろう。結局お母さんたちは、口話よりも、ろう者の言語である「日本手話」を身につけた。
<ひでさんたちが育った時代>
補聴技術が進歩して、聴覚を活用することでの聴覚口話教育がそれまでにない成果を上げるようになっていた。ろう学校では、手話は禁止はされることはなかったが、使用されていたのは、口話(音声)と同時に使えるキュードスピーチ(母音や子音を表す手指サイン)とか日本語対応手話などだった。
ひでさんの時代には、補聴効果が一定以上あり、幼児期の対応をしっかり行えば、1対1の会話は実現可能になっていた。しかし、「聴覚活用」を目指して、耳を鍛錬するという観点から、手話を遠ざける傾向があった。ひでさんの家庭でも、音声での交信が日常的にできるようにきこえる祖父母との同居を選んだのだった。
一方で、まだ世の中には、情報保障という概念が浸透しておらず、聴覚口話で育った子どもたちは、きこえる子どもたちの「集団」の中で、苦労することが多かった。集団では、雑音の中で様々な音が飛び交い、後ろから横からの複数の音声など、聞き取れないことが山ほどあった。その中で、まわりの空気を読んできこえるフリを身につける子どもが多かったし、どんどん自己不全感を募らせることが多かったのである。ひでさんたちは、お母さんとは別のところで、お母さんとは異なる苦労を体験したと言ってよい。
<現在>
現在は、補聴に関しても、デジタル補聴器、人工内耳の技術も進んできており、補聴援助システムの性能も向上している。難聴の発見も早まり、人工内耳の手術年齢も早まり、両耳人工内耳の効果も成果を挙げている。もちろん課題も少なくないが、高度重度難聴の聴覚活用は以前とは革命的に変化してきているのは事実である。
また、情報保障という概念が充分と言えないまでも、以前よりは浸透してきているし、合理的配慮は、法的にも正当に要求できるものとなっている。ノートテイク、手話、音声文字変換ツールなどのサポート手段も選択肢が広がってきている。当事者自身がしっかりと自分に合った支援を求める必要があるが、今後もこの領域が進展してほしいところである。
一方で、「ろう」として生きることを主体的に選択する場合もあり、その生き方も尊重されるようになってきている。日本手話で育てる学校の数が決定的に少なく、まだ教育環境が整備されているとは言い難いが、少なくともそういう選択肢もあるべきだということは、認識されるようになってきている。多様性を尊重する時代では、当然ろうとして生きる道も保障されなければならないが日本ではまだ未整備と言わなければならない。
このように時代の推移をみると、お母さんは、きこえないのに口話を強いられるという理不尽な目に遭っている。ひでさんは、話せるようになったが、やはり聞き取りには限界があることを充分には理解されないまま集団生活を送った。私たちもひでさんの時代に療育施設でその時代の色に染って仕事をしていたなと思う。おそらくお母さんは、子ども達に「社会で困らないように」より多くの選択肢を持って欲しかったのだと思うし、私たちもそう思っていた。あの頃、私たちは、聴覚活用し、日本語を習得した子どもたちは、きこえる子どもたちの集団の中でのコミュニケーションではどのような経験をするかについての充分な想像力を持っていなかったなとつくづく思う。
「社会で困らないように」の「社会」そのものが変わっていかなければならないこと、そしてことばの発達が保障されるだけでなく、親子の、家族のコミュニケーションが豊かなものであること、集団の中で充分に情報保障されて、個々の子どもたちの尊厳が守られること等々、今後も課題はたくさんある。
ひでさんが「まーいっかいっか」の生き方をやめて、自分の尊厳に目覚めた大きなきっかけは、大橋弘枝さんというロールモデルに出会ったことだろう。きこえにくさを理解しようとしない会社に見切りをつけ、自分でも舞台に上がっていいんだ!と一歩踏み出した。空気を読んで遠慮して生きるのをやめたのだ。
しかし、劇団の活動の中で、手話か口話か、ろうか難聴かの二者択一ではなく、「どっちでもいい」または「どっちも受け入れる」ところに彼のアイデンティティは行き着いたのではないかと思う。その辺りはもう少し話をしてほしいところだった。
そして、自分に深い愛情を注いでくれた母や祖父への感謝で講演は終わったのだった。
<大橋弘枝さんのこと>
大橋弘枝さん(1971〜)は、「もう声なんかいらないと思った」(出窓社)の著者で、聴覚障害のダンサー、女優である。ひでさんより10歳以上年上だが、子ども時代は、口話を学び、やはりきこえる人たちの中で、理不尽な目に遭ってきた方である。この本を読むと、ひでさんとは異なる個性だとしても、口話という選択肢しかない苦しみや葛藤、そしてそれを理解しなかった社会を知ることができる。彼女も紆余曲折を経て、この本の最後で、ろうか難聴かの問いに「私は私!」と言い切った。きっと大切なことは、どちらかを選択することではないのだ。