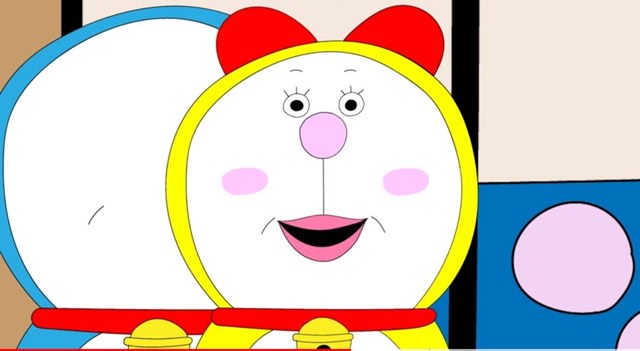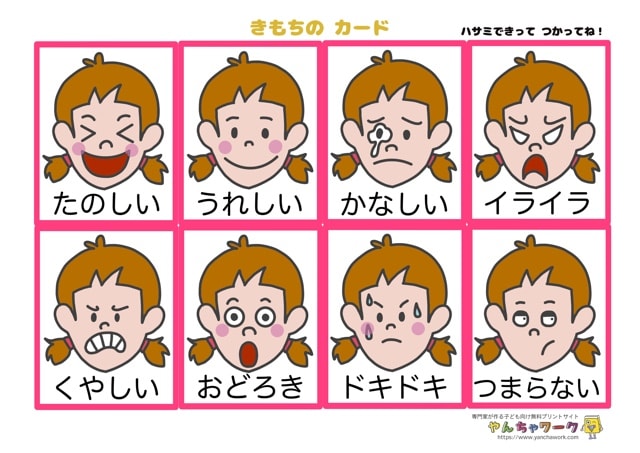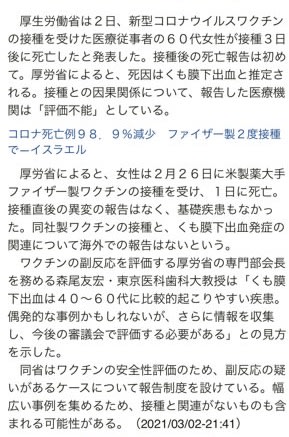すコロナが作る分断

その理由として、現在感染もしくは濃厚接種者と判明した瞬間から私権を半強制的に制限され、外出や他者接触は愚か、同居している家族にまでその影響がもろに広がる訳です。不安定な雇用条件で生計を立てている家庭からすれば私権制限による経済活動の停止は死活問題です。
労働者人口の大多数にとって重症化率の低さと、重症化する方の特徴が明確化された昨今、オミクロン株に感染して受ける身体的ダメージよりも私権制限による経済的、精神的ダメージが上回ってきているからではないでしょうか。
Twitter界隈では「2類を継続派」と「5類に変更派」での論戦が巻き起こり、熱くなり過ぎて水掛け論に陥り、終いには対立、分断、意見の一致している人達以外は遮断、という残念な状況が生じています。
この議論を前に進める為には、「2類派」「5類派」の議論が陥りやすい魔の対立ロジックが存在していて、お互いがそれに陥る事の危険性を理解する必要があると私は思います。
「魔」の対立ロジックとは

その魔の対立ロジックを端的に表現するならば、お互いが「命を盾に主張を展開してしまう」と言えるでしょう。
2類派は「重症化リスクの高い人達の命」、
5類派は「経済的心理的負担で失われる命」、
それぞれが掛け替えの無い「命」を旗印に戦ってしまうのです。
ざっくりとその議論内容を紹介してみましょう。
5類派
「もはやコロナでの年間死亡者数は8500人程で、その数は餅などを詰まらせて亡くなる方と同じ位なんだぞ!それにインフルエンザで多い年は10000人も亡くなっているではないか!3年前まで社会はそれを許容していた事実もある!だからこそコロナで亡くなる事だけを特別扱いするのはおかしいではないか!!!」
2類派
「その8500人という数字は2類という厳しい体制化での数字。規制を緩和すれば当然分母である感染者数は増え、重症化する人は比例して増幅するのが目に見えてるではないか!!そもそも、命を落とした8500人の命を軽んじるな!経済を回す為、重症化リスクの高い人の命は切って構わないとでも言うのか?」
5類派
「ハッキリと言おう。社会全体でその犠牲は許容すべきだと思う。綺麗事ばかりで世の中は回らないのだ!大体年間19000人もの人が自殺で亡くなっているんだぞ!!コロナで亡くなった数の倍だ!この規制による経済的、精神的な負担で自殺した人の命はどうでも良いのか?」
2類派
「勿論自殺で失われた命を軽んじるつもりは無いが、それは適切な補償や相談システム等社会の仕組みがきちんと設計されていない事によるエラーが原因だ!それを感染症で亡くなった方々と同列に扱うべきでは無い!そもそも三年前にインフルエンザで10000人以上亡くなっていたからそれ以下のコロナは許容すべきと言っていたが、インフルエンザに対する三年前の対応が正しかったのか?そこから議論すべきではないか?」
5類派
「もういい加減にしろ!じゃあ死者が何人なら許容できるんだよ!交通事故で亡くなる人がいるから車は乗るな、外を歩くな!とでも言うつもりか。人はいつか死ぬんだよ!そんな事を繰り返して人類は今まで歴史を紡いで来たのだ!もう君とは話にならないな!本当に馬鹿な奴だ」
2類派
「人としてありえない。命を軽んじている。身体が弱い人間は淘汰されて仕方ないと言い切る冷徹な貴方とは話す事はない!最後の一文はそっくりそのままあなたに返すよ」
5類派、2類派
「あー、なんて馬鹿な奴なんだ!」
…とまぁこんな感じです。
双方が「命を盾に主張を展開してしまう」の意味が掴めましたでしょうか?
「餅を詰まらせて亡くなる」
「コロナで亡くなる」
「インフルエンザで亡くなる」
「自殺で亡くなる」
「命」と「命」を天秤に掛けてしまい、引っ込みがつかなくなり、水かけ論になって、お互いの間に「バカの壁」が聳え立つ。
これが先に述べた「魔のロジック」なんです。
冷静にこの議論の問題点を整理してみましょう。
2類派は重症化リスクの高い人達の命を守る為に、自殺で亡くなる方の命を生贄にしても致し方ないと遠回りに言っています。
「社会の仕組みが引き起こしたエラー」というもっともらしい理屈を引き出してはいますが、「19000人の自殺」という数字は、見通しではなく、すでに失われた結果の数。取り返しなどつかぬものにそれらしい理由を後出しで添えたところでなんの意味があるのでしょう。
そもそも社会の仕組みを整備するプロセスを具体的にイメージすれば、瞬発的に整備する事など出来ないのは明白ですよね…。
5類派は売り言葉に買い言葉で、完全に「重症化リスクが高い方の命が失われる事を社会全体で許容すべき」言い切っています。つまり、弱肉強食の世間では8500人の犠牲は致し方ない。
もっと露骨に言えば生産性が高い人達の経済的心理的な負担を軽減し、自ら命を絶つという行動を取らせないない為には、必要な犠牲だと言ってしまっている訳ですね。
もはや優勢思想。
この議論に隠された「魔」とは、
「どの命を切り捨てるのか」
を正義感満載にお互いが主張している点です。
果たしてそんな正義なんかあるんでしょうか。
私は「あるカテゴリーの命を守る為にはあるカテゴリーの命は失われてやむなし」という議論のトレードオフ化から脱却する必要を強く感じます。
「どの命を切り捨てるのか」では無く、
年齢、生活環境、健康状態、性別、そういった全く異なる個々人の集合体である日本国で、
一人一人の権利をバランス良く守りながら
「どう命を守って行けるのか」
を議論するべきだと私は思います。その為には
「国による私権制限が正当か否か」
という議論と
「リスクがある命を社会としてどうやって守るのか」
という議論を同時進行させず、丁寧に分けて語らなければならないと考えます。
まず第一段階として、
①国による私権制限を可能にしている法的根拠を理解する。
②その適用がこの国に住む人々にとって最適解であるか否か、「法文」が持つ意味の客観的解釈と、「統計データ」をベースに答え合わせを行う。
この2つの工程を丁寧に踏襲する必要があります。
狙いとしては、「個々人の感情論」という不安定な前提を話し合うフェーズから脱却し
☆「私権制限を可能にしている法律と、法律に記されている言葉の意味」
☆「蓄積された数字」
という事実ベースに基づいた、客観的で不可逆的な「前提」が構築され、2類派5類派双方でこの前提を共有するところにあります。
一人一人の権利を守りながら「どう命を守るのか」という建設的で意味のある前向きな議論は、双方が共通の前提を持ってこそできると私は考えています。
その為にも次回「オミクロンがもたらした残念な分断の解説と、35歳フリーターの考えその②」で先に述べた工程を踏襲していきたいと思います。