【ネタ切れに付き、過去記事の「編集・加筆」です。】
選挙での1票の格差が問題視され、長い間裁判沙汰になっています。これは、
憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
に、違反するとされていますが、選挙権の有無や一票の格差は「差別」ではないので、明示的には禁止されていません。実際に、子供や受刑者には選挙権がないので、単に解釈の問題でしかありません。
選挙での1票の格差が問題視され、長い間裁判沙汰になっています。これは、
憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
に、違反するとされていますが、選挙権の有無や一票の格差は「差別」ではないので、明示的には禁止されていません。実際に、子供や受刑者には選挙権がないので、単に解釈の問題でしかありません。
「すべて国民は、」とされているので、田舎者が大都会に住んでも差別を受けない事を保証しているだけで、「地域の特性」そのモノを考慮してはいけないとは書いていません。誰に対しても、その地域に住めばその「一票の格差」は等しく受けます。「憲法の趣旨」は、その事を言っているだけなので、恣意的な拡大解釈をして社会を混乱させることは許されません。
寧ろ「過疎地や離島」等が国防上重要である地方と、都市部の便利さとの均衡を図るためには必要な「一票の格差」です。しかし、最高裁判決では「概ね2倍以上の格差は憲法違反の状態にある。」としています。国民審査で最高裁判事を承認しているので、国民はこの「2倍以内は合憲」の解釈を支持しているとも言えます。
一方、国民には等しく「請願権」が保障されており、また議員には等しく質問権が保障されています。
憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・
憲法第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
選挙は公約を掲げて戦う事から考えると、国民の請願数が投票結果として現れると考えられます。国民の多数の支持を得られたのが与党なので、当然ながら与党議員に対する国民の請願数も多いと考えられ、それに対応した国会質問の量も多いのが自然です。
しかし、国会での議員の質問時間は凡そ「過半数議席の与党が1に対して、少数野党には4」が割り当てられています。これは、国民の意思を反映していません。国民が与党議員に請願すると、質問時間が野党議員の1/4にされてしまい、明らかな差別待遇を受ける事になり、憲法違反に当たります。
主権のある国民に、一票の格差を2倍までしか認めないのなら、野党の質問時間も2倍以内が合理的です。実際には、過疎地の野党は都市圏の与党の2倍の「一票の格差」と4倍の「質問時間」で、合わせて8倍の「請願権・質問権」を得る事になります。
寧ろ「過疎地や離島」等が国防上重要である地方と、都市部の便利さとの均衡を図るためには必要な「一票の格差」です。しかし、最高裁判決では「概ね2倍以上の格差は憲法違反の状態にある。」としています。国民審査で最高裁判事を承認しているので、国民はこの「2倍以内は合憲」の解釈を支持しているとも言えます。
一方、国民には等しく「請願権」が保障されており、また議員には等しく質問権が保障されています。
憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・
憲法第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
選挙は公約を掲げて戦う事から考えると、国民の請願数が投票結果として現れると考えられます。国民の多数の支持を得られたのが与党なので、当然ながら与党議員に対する国民の請願数も多いと考えられ、それに対応した国会質問の量も多いのが自然です。
しかし、国会での議員の質問時間は凡そ「過半数議席の与党が1に対して、少数野党には4」が割り当てられています。これは、国民の意思を反映していません。国民が与党議員に請願すると、質問時間が野党議員の1/4にされてしまい、明らかな差別待遇を受ける事になり、憲法違反に当たります。
主権のある国民に、一票の格差を2倍までしか認めないのなら、野党の質問時間も2倍以内が合理的です。実際には、過疎地の野党は都市圏の与党の2倍の「一票の格差」と4倍の「質問時間」で、合わせて8倍の「請願権・質問権」を得る事になります。
これは、支持率7%の野党が支持率50%の与党よりも強い事を意味します。多くの場合、野党は自らの「公約」や、日本の「防衛」に対しては興味が無いようなので、2倍の質問時間ですら無駄と言えます。
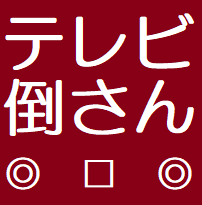
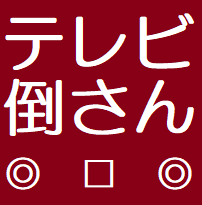










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます