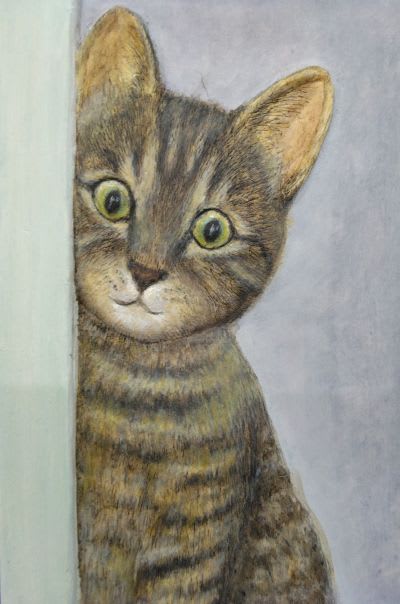例えば欧米で、不良品率が1%の工場に新しく「新管理システム:NMS」を導入し、不良品率が0.5%になった場合、「NMS導入で不良品率が半減した」と言えます。それを聞いた日本の不良品率0.1%の会社が同じNMSを導入し不良品率が0.5%と5倍増した場合でも、NMSの販売会社は「このシステムは不良品率を半減した実績があると言っただけで、誇大宣伝ではない」と言えば、法的責任は問われません。
MS.Copilot君に「”国際法では、占領下の国での法律改正は禁止されている”と聞いたことが有るのですが、その根拠法を教えてください。」と尋ねたところ、
「ハーグ陸戦規則 第43条:正統な権能を有する権力が事実上占領者の手に移ったときは、占領者は、絶対的に妨げられることがない限り、その地域の現行法令を尊重しつつ、可能な限り公共の秩序と安全を回復し確保するため、自らの権能においてあらゆる措置を取るものとする。
この条文は、占領者が占領地の現行法令を尊重する義務を負うことを定めています。つまり、占領軍が勝手に法律を改正したり、新しい法体系を押し付けることは原則として認められていない、という解釈が成り立ちます。
ただし、解釈には幅があります。
①公共の秩序や安全の維持に必要な場合には法令の変更も許容される。
②戦闘が終了した後の占領(例:日本のGHQ統治)は適用外。
③憲法のような根本法の改正は慎むべきとする立場があります。
④「新しい合意は古い合意に優先する」という原則が適用される。」
と答えてくれました。
日本人の中にも「日本国憲法は無効」から「押し付け憲法上等。GHQが押し付けてくれなかったら、更にひどい憲法が制定されていた」まで様々です。
私は「①公共の秩序や安全の維持に必要な場合には法令の変更も許容される。」の解釈が妥当と思います。つまり、占領中のGHQを含む公共の安全の維持を目的とした「占領統治法」とする解釈です。
なので、現在も「日本が被占領中」ならば、所謂「日本国憲法」は有効と結論付けます。但し、不良率は欧米並みで、「日本国憲法(特に9条)」を参考にする国も見た事が有りません。これは「敗戦国日本」以外では成立しない憲法であり、日本人の犠牲と交換に「アジア解放に成功した」と思う人にはゴミだと思います。
なので、私は「日本国憲法廃棄論」を主張します。聖徳太子の「十七条の憲法」には改正・破棄・廃棄条項が無く、変更された形跡も無いので今も有効です。一方、「日本国憲法」には困難な改正条項は有るのですが、破棄・廃棄条項は無く、実定法の慣例に従うと、手続き上はいつでも廃棄可能と云うことです。

MS.Copilot君に「”国際法では、占領下の国での法律改正は禁止されている”と聞いたことが有るのですが、その根拠法を教えてください。」と尋ねたところ、
「ハーグ陸戦規則 第43条:正統な権能を有する権力が事実上占領者の手に移ったときは、占領者は、絶対的に妨げられることがない限り、その地域の現行法令を尊重しつつ、可能な限り公共の秩序と安全を回復し確保するため、自らの権能においてあらゆる措置を取るものとする。
この条文は、占領者が占領地の現行法令を尊重する義務を負うことを定めています。つまり、占領軍が勝手に法律を改正したり、新しい法体系を押し付けることは原則として認められていない、という解釈が成り立ちます。
ただし、解釈には幅があります。
①公共の秩序や安全の維持に必要な場合には法令の変更も許容される。
②戦闘が終了した後の占領(例:日本のGHQ統治)は適用外。
③憲法のような根本法の改正は慎むべきとする立場があります。
④「新しい合意は古い合意に優先する」という原則が適用される。」
と答えてくれました。
日本人の中にも「日本国憲法は無効」から「押し付け憲法上等。GHQが押し付けてくれなかったら、更にひどい憲法が制定されていた」まで様々です。
私は「①公共の秩序や安全の維持に必要な場合には法令の変更も許容される。」の解釈が妥当と思います。つまり、占領中のGHQを含む公共の安全の維持を目的とした「占領統治法」とする解釈です。
なので、現在も「日本が被占領中」ならば、所謂「日本国憲法」は有効と結論付けます。但し、不良率は欧米並みで、「日本国憲法(特に9条)」を参考にする国も見た事が有りません。これは「敗戦国日本」以外では成立しない憲法であり、日本人の犠牲と交換に「アジア解放に成功した」と思う人にはゴミだと思います。
なので、私は「日本国憲法廃棄論」を主張します。聖徳太子の「十七条の憲法」には改正・破棄・廃棄条項が無く、変更された形跡も無いので今も有効です。一方、「日本国憲法」には困難な改正条項は有るのですが、破棄・廃棄条項は無く、実定法の慣例に従うと、手続き上はいつでも廃棄可能と云うことです。