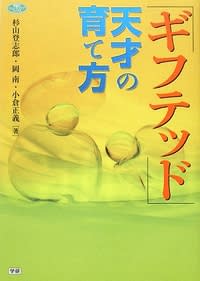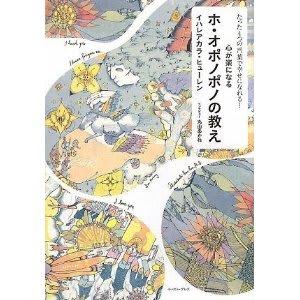10年前くらいから徐々に目に触れることも多くなってきた、アスペルガーや自閉症スペクトラ
ムという言葉。
社会で生き辛さを抱え自分がそうではないか、と調べ始めた人に書かれた本であろうか。
・春ウコンが有効な人がいる。統合失調症はインドで少ないことから、サフランを多く取ると
いいらしい。
・グレーゾーンの人はけっこういるらしい。
・多くの因子によって、発症(というか)する。例えば、高血圧の病気を
発症するのは、いろんな環境が作用して、、、。というのと同じ。遺伝病ではない。
必ず遺伝するというものではない。
・生活の仕方としては、
①出来ることを認めていくという作業をしましょう、書き出しましょう、
②地域の福祉を利用しましょう、年を取れば誰でも福祉のお世話になるのだから、 ためら
わないで障害者センターなどとつながりをつくっていきましょう。
障害者福祉法ができて、今は障害のある人をケアすることが、地方公共団体の義務にも
なっているのだから。
・言われるままに学校などでは受動型として適応してきた人が、社会に出て自分から積極的
に働きかけなければならないという場面で困難をかかえて、職場から離れてしまう例なども
ある。困難にぶちあたっても、パニックにならず、0か10かでなく、真ん中の5を模索しましょ
う、というようなことが書いてあったように思う。
・また、他の本では告知は様子を見てと書いてあるのを読んだことがあるが、この本では
本人へ知らせるのは出来るだけ早いほうがいい、対策をとっていきましょう、ということだっ
た。
(様子をみてというのは、家族が受け入れられない場合だったかもしれません。)