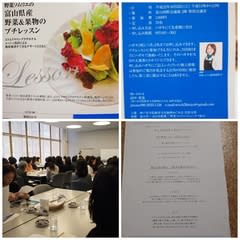「医食同源を学ぶ」第二弾。
その前に昨日の補足を・・・
塩分の摂りすぎはよくないといわれていますが
塩分は体を温める働きがあります。
塩分が少ないと活力がなくなります。
鹹は腎に作用すると言われています。
だから、「冬は鹹」なんです
風邪のひき始めに良く効く風邪薬に
「葛根湯」があります。
葛根だけにあるプエラリンというポリフェノールの一種は
血圧・体重・血中のコレステロールを下げる働きがあり
生活習慣病予防に効果があると言われています。
漢方でいわれる陳皮(ちんぴ)は
熟した温州ミカンの皮を干したものをさします。
陳皮に含まれるノビレチンの効能
1 記憶障害改善作用
2 脳コリン作動性神経の編成抑制作用
医学的で良くわかりませんが、脳内コリンの働きが
悪くなると認知症になるようです。
3 脳内でのアミロイドβの蓄積抑制作用
アミロイドβはアルツハイマー型認知症を
引き起こす物質といわれています。
赤ワインや落花生の皮に含まれる
レスベラトロールは・・・
食事の際、腹八分目で押さえることによって
長寿遺伝子が活性化されるそうです。
おなかいっぱい食べるのではなく
「腹八分目、ほどほど」が長寿の秘訣なんですね
許先生のお話を聴いていると
野菜・果物の料理は薬膳につながっている
と思いました。
明日は、薬膳粥の話です。ツボの話もあります・・・
薬都・富山ならではのお話です
ブログ村ランキングにエントリーしています。
ニコラをクリックすると、ランキングに反映されます。
素敵な野菜ソムリエさんの旬の情報が入手できます。
みなさんの応援クリックが元気の源 です。
です。 ポッチン♪
ポッチン♪ 










 今年の3月の健康づくり教室
今年の3月の健康づくり教室











 私、ティーバッグ愛用者です。
私、ティーバッグ愛用者です。










 もっと食べたい」
もっと食べたい」  11月6日、穏やかな晩秋のひととき
11月6日、穏やかな晩秋のひととき