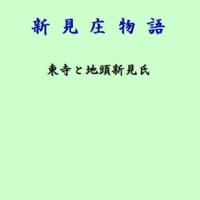上下:茎上部で十字対生状に分岐して先端に花序をつける。

下2段:上は開花して間がなく、柱頭が写っているはずであるが識別し難い。
下は花粉分泌を終えた状態だろうか、丸い柱頭がよく見える。(ひょっとすると雄性先塾)
オミナエシ (オミナエシ科 オミナエシ属 学名Patrinia scabiosaefolia 多年草 花期夏~秋) 葉は対生してつき、葉身は羽状複葉状~3出複葉状に切れ込む。茎の上部で枝が対生して分岐し、その枝先に散房花序を形成して黄色い小花を多数つける。花冠は5裂して平開、雄蕊4、雌蕊1。本種は万葉の歌にも多く詠まれているように、当時から“おみなえし”と呼ばれ愛でられていた。名の由来は、黄色い粒々の花を“女飯おみなめし”(粟飯あわめし)に見立てて“おみなめし”と呼び、それが転訛したという一説。「女郎花」の漢字が当てられたのも平安時代である。当時「女郎」は女性に対する尊称であったので、オトコエシに対し優しげなという意味でこの漢字が当てられたのではあろうか。遊女を意味する女郎は近世(江戸時代)に入って使われるようになったので、遊女の意味はあるまい。ましてや花のにおいが女郎くさいとは異説であろう。女郎くさいにおいとはどんなにおいか知らないが、化粧のにおいという意味であれば、現代車中や歩行中すれ違いざまに嗅がかされるが、概ね佳い臭いだろうと思う。これと比べオミナエシの花は鼻を擦りつけなければ臭わない。根茎を乾燥させたものは“敗醤”という生薬として利用され、これは乾燥させていると僅かに醤油の腐った臭いがするところから漢名が生まれたとある。
属名Patrinia 人名(フランスの植物学者Patrin1742-1814)に因むとあるが、人物不詳。
種小名scabiosaefolia マツムシソウ属(scabiosa)のような葉の
萩の花 尾花葛花 なでしこの花 をみなえし また藤袴 朝貌の花 万葉歌人・山上憶良(660頃-733頃)



オトコエシ (男郎花 オミナエシ科 オミナエシ属 学名Patrinia villosa 花期8月~10月) オミナエシと同様に茎の上部で対生分岐しその先に散房状の花序を形成し白色の小花を多数つける。。茎はやや太く全体に毛が多く、葉は対生、葉身は卵状~卵状披針形で、茎下部では羽状に切れ込み、茎上部で単葉が見られる。花冠は5裂、雄蕊4、雌蕊1。オミナエシが茎がやや細く、黄色の華やかな花を咲かせるのに対し、本種は茎がやや太く地味な白花を咲かせるのでオトコの名前がついたのであろう。どちらも人家の近くに育つが、草刈りをする人がいなくなったためだろうか、里山でもあまり見ることがなくなった。オミナエシは庭で育てる趣味人が多いがオトコエシの方はそれもない。
種小名villosa villus毛 villosa 長い柔毛のある