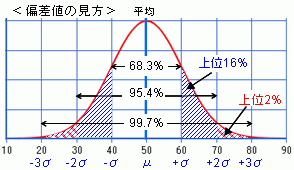
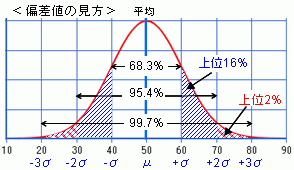
小学生の時、よく理解できなかった偏差値ですが、
要は母数や難易度の異なる試験条件においても、
点数と人数の度数分布を正規分布に当てはめることで、
点数を比較的確からしい順位へ変換することのできる、
統計的手法です。
ただし、受験者と点数の度数分布が正規分布をしていることが
前提。
サピαクラス(3クラスある校)の偏差値ですが
α3:59~63
α2:63~67
α1:67~
くらいの割り振りでしょうか。
この偏差値を前提に考えると、
α3:標準問題ミスなく確実にとれてちょっとした応用問題も解ける
α2:ちょっとした応用問題はもちろん、調子がよいときは難関校の受験問題も解ける
α1:難関校の問題もどんどん解ける
なイメージですかね。
で、このα3(偏差値60辺りをいったりきたり)とその先の間には
ちょっとした隔たりがあると思います。
ちょっと賢い、要領のいい子はα3にすぐに到達します。
要領の悪い子でも、親がしっかりとサポートしてミスを修正していけば
到達できると思います。
でも、その先に、α上位クラスには行くには、文字通りプラス”α(アルファ)”が必要になってくるのです。
そのプラス”α”とは、「○○算では解けない領域」です。
中学入試の算数にはいろんな○○算があります。
つるかめ算、旅人算、植木算、……
子供は問題を見た瞬間、どの○○算を当てはめるのかを考えます。
ませた子供は未知数をx,yとおいて連立方程式で解こうとします。
実際、大半の○○算はそれで解けてしまいます。
ですが、63オーバーの難関校の問題は○○算では解けません。
連立方程式でも解けません。(未知数が方程式の数よりも多いからです)
難関校の問題は制約と規則性に気をつけて、全てを列挙する
が標準的な解答法です。
このゲームチェインジに気づけること、慣れること、
○○算が使えないことを恐れないこと……。
それが分水嶺になります。
応用問題といいますが、応用というよりは別物だと思います。
むしろ○○算の知識が邪魔なんじゃと思うくらい……
(実際にはそんなことはないんですが)
30年前、それらの問題を見たとき自分も思いましたね。
これって、(○○算とかやってきた)今までの勉強って意味なくね?
と。
本当に頭のいい子(地頭70オーバー)はこの辺を感覚でクリアするから、
世の中、平等とはいかないものです。。。

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます