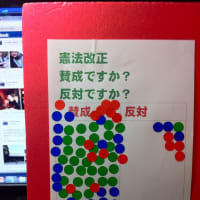「漢検」バッシングは的外れ
外国人が漢字を学ぶ機会の創出を
文科省立ち入り検査
「漢検は儲けすぎ!」
文部科学省は2月9日、財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市)に立ち入り検査を行った。過去5年間で合計約20億円の利益を上げており、公益法人にしては利益水準が大きすぎる、というのが立ち入りの趣旨。つまり「儲けることは許さない」ということだ。
「日本人の漢字能力の向上」を目的とする同協会の主な事業は漢字検定試験。旧文部省が法人許可した1992年の受検志願者数は12万人だったが、2008年には20倍超の280万人まで増加した。1~10級に分類された漢字能力は、進学や就職時の評価材料として定着。世相を表す漢字を公募し、京都・清水寺で披露する「今年の漢字」は年末の風物詩となり、普及活動にも成功している。
また、書店には漢字に関する書籍が数多く並び、「漢検」ゲームソフトが発売されるなど漢字ブームを生み出した。こうした取り組みは、創意工夫によって新たな需要を創造し、事業を成功させた例として一般企業にも参考になる。
富を否定すると
国の発展が阻害される
公益法人とは、学校法人やNPO法人のように、不特定多数の利益の実現を目的とした事業を行う団体。そう聞くと「利益」は無用のように思えるが、そうではない。利益や、それを将来のために蓄えておく内部留保は、「事業の存続・発展のためのコスト」であり、これを否定すれば、「毎月、毎年、赤字すれすれの自転車操業を続けろ」と言われているのと変わらない。それでは本来の目的である公益の実現そのものが危うくなろう。
政府は、公益法人の内部留保の水準は事業費や管理費などの30%以下が望ましいとしているが、そもそも内部留保を制限すること自体が、「自転車操業」「貧乏経営」のすすめとなっている。この基準を守らせるにしても、今回、文部科学省が漢検にすべき指導は利益の否定ではなく、その利益を新規分野へ投資し、フロンティアを開拓させることでさらなる公益を実現することだったのではないか。
現在海外で日本語を学ぶ外国人は300万人を超えると言われ、増え続けている。日本に関心をもち、日本で仕事をしたいと願う人も何千万単位でいる。漢検が、そういう人々に漢字を学ぶ機会を提供するのも一つの手だろう。
1000万人の移民受け入れを提唱する外国人政策研究所の坂中英徳所長はこう話す。
「日本企業で働きたくても、漢字の読み書きが難しくて断念する外国人も多い。安く漢字を学べる場や、『外国人漢字能力検定』などをつくって就職の際の目安にしても面白い。長い目で見れば、それは日本の利益につながる」
もちろん、公益法人の不適正な報告や資金の公私混同は正されるべきだが、富を否定するような考え方は日本全体の利益を損なうだけだ。より多く稼いだ企業や団体、個人がその富を再投資して、さらなる価値を生み出すことで社会は発展・繁栄していくことを忘れてはならない。