
交響曲第8番(ハース版)
・北ドイツ放送交響楽団
・1987年8月22日・23日 リューベック大聖堂
・CD:RD60364(RCA)
1mov.16:50
2mov.15:37
3mov.28:29
4mov.25:15
演奏 ★★★★
音質 ★★★☆
北ドイツ放送響とベートーヴェンやブラームスの全集に取り組んだヴァントが、1987年よりブルックナーの再録音を開始。
その第1弾となったのが第8番で、リューベック大聖堂で行われたシュレスヴィヒ=ホルシュタイン音楽祭でのライヴ録音である。
第1楽章は、抑制の効いた響きと先を急がないじっくりとした運びがこの演奏全体のスタイルを予感させる。
弦楽群は残響の長さを意識したのか、どこか慎ましい表情だ。随所におけるオーボエの孤独な歌はなかなか魅力的なもの。
楽想に応じてテンポを切り替えるが、ここでは必要最小限に抑えられ、あくまで自然な印象である。
金管は明快で充分に鳴るが、飽和しないようコントロールされており、力みのなさがスケールの大きさに繋がっている。
スケルツォも落ち着いたテンポで始まる。冒頭のテーマはまずはストレートなもので、過去の録音から考えると意外な気がする。
全体の運びはややたっぷりとしたもので、下手をすると締りのない演奏になりかねないスタイルだが、要所での金管の強奏がメリハリを与えている。
例のティンパニーの処理は、クレッシェンドの頂点の位置がおかしい。しかし、リピート時も同じなので奏者のミスとも思えず、これはちょっと解せない。
トリオは、表現自体は深遠で素晴らしいが会場が響きすぎる。ここはもう少しクリアな音で聴きたい。
アダージョは、まずは安心して聴ける演奏と言えるだろう。
但し、長い残響が細部の表情をぼかしてしまっている場面が多くある。
マスとしての響きの立派さは味わえるが、ヴァントらしいこだわりはやや伝わりづらく、当盤ならではといえるような印象は特に感じられない。
フィナーレは、長い残響を突き破るような金管で開始される。
この楽章でもフレーズの節目や楽想の変わり目でたっぷりとした響きを確認しながら進むが、表情に弛緩がないのは流石だ。
第3主題はデュナーミクの処理が細かく、この辺りはヴァントならではだと思う。
その後の金管の凝縮した響きによる剛毅な表現は立派なもの。
ただ、響きの長さのせいで音色や表情の変化が充分には伝わってこない場面も多く、ティンパニーがモコモコと聴こえるのには疑問も残る。
コーダはゆったりとしたテンポによる雄大なものだが、飽和を避けたのか響きはやや抑制気味な印象だ。
録音は先述の通り会場の長い残響がピントの甘さに繋がっており、音色が変質していたりもどかしさを感じさせる部分が多い。
ただ、先の85年の第3番があまりに感触の硬い音だったので、その後に聴くとホッとする面があったのも事実である。
ヴァントらしい細部のこだわりは捉えにくいが、ケルン時代やN響との演奏と比べて抑制された渋さの中から深みが生まれ始めていることを感じることが出来る。
演奏の★4つはやや甘いかもしれないが、両端楽章にはそれなりに納得したのでこの評価とした。

交響曲第9番(原典版)
・北ドイツ放送交響楽団
・1988年6月24日~26日 リューベック大聖堂
・CD:RD60365(RCA)
1mov.26:02
2mov.10:24
3mov.26:08
演奏 ★★★★
音質 ★★★★
第8番の翌年に同じリューベック大聖堂で行われた公演で、今度は第9番である。
第1楽章は、最初の木管やホルンが奥まった場所から聞こえてくる。
やや不明瞭ではあるが、ミステリアスな雰囲気は悪くない。
その後の主題提示では最強音でも無理をさせ過ぎず、残響の長さを考慮して注意深くコントロールされている。
テーマを歌うヴァイオリンに響きが付きすぎてピントがぼやけがちなのは否めないが、思ったほど混濁はなく清澄な印象を有している。
低弦の響きもよく伸びるが、良くも悪くも重厚さに繋がっているというべきだろうか。
全体にヴァントならではの鋭さがいくらか和らいでいるとはいえ、再現部での厳しい響きは流石に素晴らしい。
弦楽器のテーマやモチーフにホルンが重なってくるあたりでは緻密なニュアンスが作られているはずだが、響きの中に埋没気味で表情がややアバウトになるのは惜しい。
しかしコーダでは金管が牙をむき、充分な凄味を湛えながら終結。
スケルツォはまずピチカートが意外に明瞭に聴こえるのが良い。
全体としてはアクセントはそれほど鋭くなく重量感もほどほどで、マスとしての響きはむしろマイルドな印象だ。
しかしホルンの抉りなどは積極的で、物足りなさを感じさせない。
トリオも表情はやや地味だが丁寧な印象を残すのが良い。
アダージョは全曲中で最も優れているかもしれない。
曲想のせいか会場の響きもそれほど気にならず音楽に集中できる。
意志的なテンポの動きがうまく決まっており、そしてここでもホルンの抉りが意味深い。
終盤ではさらに視界が広がり、清らかなフルートと美しい金管の響きで幕を閉じる。
第8番と同じく抑制の効いた演奏だが、表現自体の説得力はこちらの方がやや勝っており、特にアダージョは魅力的な演奏だと思う。
録音の傾向は8番と似ていて解像度は高くないが混濁感は抑えられており、作品自体の違いにもよるのか直接的な迫力の点でやや上回っている。
しかし、全体としては細部の明瞭さよりも響きの奥深さから生まれる深遠さが特徴と言える盤だと思う。


















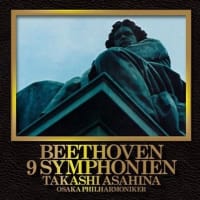




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます