

交響曲第7番(ハース版)
・大阪フィルハーモニー交響楽団
・2001年5月10日 フェスティバルホール(大阪)
・SACD:OVCL-00315(EXTON)
・CD:OVCL-00068(EXTON)
1mov.21:18
2mov.20:40
3mov.8:35
4mov.12:29
演奏 ★★★★☆
音質 ★★★★★(SACD) ★★★★☆(CD)
2001年にはザ・シンフォニーホールにおける第5・8・9番のシリーズのほかに、フェスティバルホールでの定期演奏会でもブルックナーをとりあげた。それがこの第7番で、朝比奈が大フィルの定期演奏会に登場した最後の公演である。(他には11月に第3番も予定されていたが、惜しくも実現しなかった。)
まずは第1楽章。
ヴァイオリンのトレモロの中から始まるチェロのテーマは悠々と歌う。しかし入れ込みすぎることはなく、どこか心の静けさを感じさせるものだ。
テーマがヴァイオリンに移ると線がくっきりと浮かび上がり、さらにトランペットが強靭な響きで加わる。
第2主題は木管の素直な表情で始まり、ヴァイオリンが艶のある音色で続く。
随所における金管の強奏は硬めのサウンドで明晰に響くが、ときには豪快だ。
第3主題はやや速めのテンポでためらいなくどんどん前へ進む。
展開部以降は、シンプルな外見の中でそれぞれの楽想を入念に描き分けている。チェロのテーマのたっぷりとした抒情的な表情、それに呼応するヴァイオリンの神秘的な弱音の対照性は絵画的とも言える印象深いものだ。
コーダではトランペットの容赦ない強奏が大フィルらしいが、過剰になることはなく真っ直ぐに頂点へ至る。
アダージョも格調の高さが一貫する。
序盤の重厚な弦楽合奏の祈りは流石だが、ここでも没入する感じではなく、自らを客観視するような趣がある。ヴァイオリンの硬質で透明度の高い響きは、過去の大フィルから一歩抜け出したものかもしれない。
第2主題も歌いすぎることなく淡々としている。しかし句読点のつけ方が巧みで、ニュアンスがストレートに伝わってくる。高音域においてほのかに苦味が混じるのは大フィルならではのような気がする。低弦の合いの手はここでは寡黙な表情を貫いている。
中盤からは胸を張った姿勢で歩みをいくらか速めるが、第1主題が回帰してくる箇所では、より翳の濃い響きとなるのが印象的だ。精神的な意味での頂点をここに持ってきているのかもしれない。
いよいよ到達するクライマックスでは金管の喨々とした響きが立派だが、トランペット以外が渋めであるのはこの当時の大フィルの演奏に共通する特徴だ。
終結における清潔な透明感は孤独な情景にも繋がり、そこには独特の緊張感も滲む。
スケルツォは躍動感に満ちた快演だ。
トランペットは緻密とは言えないが、意欲的な姿勢に好感が持てる。
テンポは速めで、弦も管も上滑りするかしないかのギリギリの中で必死に喰らいついている。
そしてフォルティッシモの剛毅で荒々しいサウンドは大フィルならではの味だ。
トリオでは一切の埃臭さを振り払うような清新なイメージが一貫する。
フィナーレも各場面を的確に描ききった秀演だ。
視点が明確で、全ての楽句が確信に満ちた表情で鳴りわたる。
金管の積極的な吹奏が輪郭を大きく描き、弦楽器もくっきりとしたサウンドで応える。
後半に入ってからはテンポの伸縮も加わり、より多彩に語りかける。
コーダは落ち着いた運びとなり、輝かしいトランペットを軸として高らかに歌い上げて終結となる。
全体としては硬質でクリアなサウンドで一貫した演奏と言えると思う。
フレージングやデュナーミクが細部まで徹底されており、曖昧さがどこにもない。
とりたてて目立つような新しい表現が見られるわけではないのだが、前半楽章ではいつになく冷静な空気感が底流しているように感じた。
録音もややデッドなフェスティバルホールのハンディをうまくカバーしていると思う。この演奏は私も客席で聴いたのだが、率直に言って録音で聴いた印象の方が客席での記憶を上回るように感じている。
客席では音の溶け合いに不足を感じて、もうひとつ酔うことが出来なかったのだ。
CDでも充分に優秀なサウンドだが、SACDでは響きの伸びが向上し、演奏自体の美質がより実感出来るように思えた。


















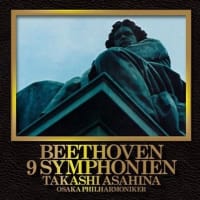




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます