遅くなりましたが丑三つ時更新できましたの追加クエストもどき〜(ハードル低いなおい)。月とか花だとかですと幻想的な話にはなるんだろうな〜とは思っていましたが、思っていたより幻想的というよりは観念的な話になってしまいまして自分でも意外。イザヤール様が案外楽天的というのはあくまで津久井のイメージですが、メンタルの強さや適応力の高さや不可思議事態もあっさり受け入れるいい加減さから察するに、実際にそうなんではないかというような気がします。
ダーマ地方の高台の湖水の畔には、サイクロプスと小さな男の子が仲良く暮らしている。そこを訪れた帰りにミミは、岸辺のひとつに野菊の花が群生している場所を見つけた。可憐な花にすっかり嬉しくなった彼女はしばらくうっとりとその景色と香りを楽しみ、それからいくらか手折って小さな花束を作り、帰ろうとした。
ルーラを唱えようとした彼女は、ふと、視界の端に、ここでは通常無い筈のものを捉えて、唱えるのを止めた。たくさんある湖のうちの一つの畔に、小さな祠が立っている。前からあれば絶対気が付く筈のものだ。しばらく来ない間に誰かが建てたのか、それとも何かのワナで幻覚なのか、とにかく確認しなくてはならないと考えて、ミミは祠の前まで行ってみた。
すぐ傍まで近寄ってみると、急拵えの建物らしく、木造で簡単に作られている。だがそれでいて、明らかに聖なる力が感じられるという不思議な建物だった。軒先には、聖なる力があると言われている草の数々が束ねられ飾られており、その中にはミミの持っているのと同じ、野菊の花もあった。
少しためらいながらもミミが律義にノックをすると、中から威厳のある女性の声で、「お入り」と返事があった。
用心しながらミミが扉を開けると、中には白絹が直接地面に敷かれていて、その上に法衣に身を包んだ老婆がきちんと背筋を伸ばして座っていた。彼女は、ミミが手にしている野菊の花束を見て言った。
「ようやく来たね、今年の巫女さんや。待っていたよ」
「巫女?何のことですか?」
全く覚えがなかったので、ミミはきょとんとした。すると老婆は、驚いたように言った。
「おや違うのかい?でもおかしいねえ、この祠は、心の清らかな者にしか見ることも入ることもできないし、第一あんた、ちゃんと巫女の印の花を持っているじゃないか」
「巫女の印の花?この野菊のことですか?あまりに綺麗だから、少し頂いてしまったけれど、そんな大事な花だなんて知りませんでした・・・」
申し訳なさそうにミミが言うと、老婆は面白そうに笑った。
「おやまあ、本当に違うのかい?この花もね、心の汚れた者には摘むことさえできないんだよ。あんたはどうやら、若いのによほど善行を積んでいるらしいねえ。偉いよ」
「そ・・・そうなんですか?」
元天使だったゆえに、人間よりずっとずっと長く生きて「善行」を積んでいるのも当然と言えば当然なので、少々ミミは面映ゆい気分になった。だがそんなミミの当惑をよそに、老婆は開いた戸から見える傾いた日差しに眉をしかめて、ぶつぶつと言った。
「じゃあ本当の巫女はどうしたんだろうねえ。このままじゃ日が暮れて間に合わなくなってしまうよ。困ったもんだ」
「あの、ここまで来るのはたいへんだし、もしかしたら途中で何かあったのかも・・・。私、探してきましょうか?」
ミミが申し出ると、老婆は渋面をやめて嬉しそうに微笑んだ。
「やっぱりあんたはいい子だねえ。思った通りだ。ふふふ、実はね、本当の巫女なんて予め決まってなんかいないんだよ。毎年必ず、心の清らかな娘が導かれて、印の花を持ってこの祠にやってくることになっているのさ。必ずこの場所とは決まっていない、その年の地上で月の一番近くにある場所に、この祠は現れるんだ。つまり、今年の巫女はあんたってこと」
「巫女・・・私が?」
思いがけなさすぎて、ミミは濃い紫の瞳を見開いて再びきょとんとした。
「そうだよ。それにあんた、どうやら踊り子さんらしいから、ますますちょうどいいじゃないか。古代の巫女さんは、踊りながら神託を伺うっていうしね」
「でも・・・何をすればいいんですか?」
思いがけない展開に戸惑いながらミミは尋ねた。もしかして踊るの?とも思った。
「そんなに心配しなくても大丈夫だよ。野菊の花冠をかぶってこの祠の中に座って、鏡を持って一晩中月光が鏡に当たり続けるようにしてくれればいいのさ」
「一晩中、ですか。じゃあ、必ず戻ってきますから、一度帰ってもいいですか?黙って外泊したら、みんな心配しちゃう」
「残念だけど、それは無理だね。もうすぐ日は落ちる。太陽が落ちた瞬間から、月光を鏡に当てなければ意味は無い。あんたがどんなに早く戻って来られると言っても、日没までには間に合わない。たとえ天の箱舟を使おうともね」
何故そんなことまでと、思わずミミが身構えると、老婆はにっこりと笑った。警戒心を思わず解きほぐしてしまうほど、優しくあたたかい笑顔だった。
「精霊がね、教えてくれるのさ。あんたがどんな人で、何をしてきたか、ってね。大丈夫、あんたの恋人は、おそらくここへあんたを探しに来るだろう。彼も正しい心の持ち主ならば、ここに来ることができて、私が説明してやれるというわけさ。それならいいだろう?」
ミミはためらったが、本当にもうすぐ日没になってしまう。帰ってしまえばどんなに急いでも、目的はわからないが「月光を日没直後から鏡に当てる」儀式はできないだろう。老婆の言葉とイザヤールが探しに来てくれることを信じることにした。ミミはクエスト「月を溜める鏡」を引き受けた!
老婆はミミを白絹の上に座らせると、袋の中から丸い鏡を取り出した。ラーの鏡に似ているが、はめ込まれた宝石と刻まれている文字が異なっているが、古代文字をいくらか知っているミミでも読むことはできなかった。
「この鏡に月光を当てると、鏡は今宵の特別な月光を蓄える。聖なる花の力と一緒にね」老婆はそう言って、ミミに鏡を手渡した。
「月光を蓄える・・・。でも、何故そんなことを?」
「強いて言えば、未来の為、ってところだね。この鏡に蓄えられた聖なる月光の力が、いつか役に立つ日が必ず来る。近い未来か遠い未来かわからないけどね」
そう言ってから老婆は、日がすっかり沈みかけているのを見て、ミミに告げた。
「おっと、私のお喋りはここまで!では頼んだよ。大丈夫、鏡が導いてくれるからね」
老婆はミミに花冠をかぶせて、祠から出た。
祠の入口は開け放たれているので、半分ほどの月齢の月光でも、充分鏡に降り注いだ。鏡が導くという言葉の意味が、ミミにも間もなくわかった。鏡が自ら動くわけではないのだが、月の傾きに従って、鏡を持つミミの手が、自然に月を追うように向きを調整するのだ。操られているという感じは無く、自然にそうしたくなるのだった。
花冠の清浄な香りが、静かな心をいっそう穏やかにする。単調どころかほとんど動くこともないが、退屈だとも特に思わず、ミミは鏡に映る月を見つめた。鏡は今の角度では、ミミのかぶる花冠もいくらか映し出していた。月光を受けて花冠は仄かに白く輝き、その輝きもまた鏡の中に満たされていくように見えた。そのやわらかな輝きを見て、ミミは思った。
(こうしていると、鏡の中に、月そのものを満たしているみたい・・・)
時も世界も、神ですら不変ではなく移ろい行くことを、ミミは自らの目で見てきて知っていた。今の平和とて、永遠のものではないだろう。次に世界の異変が起きたとき、人としての儚い寿命となった自分たちは、もう生きてこの世には居ないかもしれない。けれど。自分たちの血筋であろうとそうでなかろうと、自分たちの意志を継ぐ者は必ず現れて、大好きなこの世界を、守ってくれることだろう。この鏡も、もしかしたらその役に立つかもしれない・・・。そう思うと、ミミはわくわく感と安堵感の入り交じった、不思議な安らぎを覚えた。
やがて、誰かが会話をしている声が少し離れたところから聞こえてきた。おそらくミミを探しに来たイザヤールと、彼に事の次第を説明している老婆のものだろう。それから間もなく、祠の傍らに、誰かが静かに腰を下ろす気配がした。祠の簡素な壁越しに、ミミの隣に座るような形になっていた。
「ミミ」壁越しに、声が聞こえた。やはりイザヤールの声だった。「事情はわかった。月の光を遮るといけないから、あとしばらくはおまえの顔を見るのは我慢するとしよう」
それからしばらく彼は黙ったが、ミミには彼の物思いに耽っているであろう顔が、見えているようにわかった。
「・・・かつて、ある世界に、光の玉というものがあったそうだ」
かなり長いこと経ってから、ふいにイザヤールが呟いた。
「竜の女王が伝説の勇者に託し、その力のおかげで勇者は大魔王の闇の衣を消し去り、世界を救うことができた、でも後に竜王がそれを奪ったことで、世界が闇に包まれた・・・確かそう伝説には書かれていたっけ・・・」
「そうだ。・・・あれも、もしかしたら・・・闇の世界がいつか来ることを知っていた遠い昔の誰かが、用意していたものかもしれない、ふとそんなことを思った」
「竜の女王じゃなくて?誰かって、神様?」
「そうかもしれないし、違うかもしれない」
「別の世界にも、かつての私たちみたいな天使たちがいて、その人たちが用意してたのかも?」
「そうかもな。ただし、もしも我々と同じような能力だったとしたら、未来を予見して作ったというよりは、何かに導かれてそうしたのだろうな。・・・今宵のおまえみたいに、な」
「・・・今日私がここに来たのは、偶然じゃなくて必然だったってこと・・・?だったら、なんだかちょっと、怖いな・・・」
「怖い?何故だ?」
「だって、どんな小さな出来事でも、何か一つでも欠けたら、私はここにこうしていて、月の光を集めるなんてことは、なかったもの・・・。私が地上に落ちたことも、イザヤール様に庇ってもらって命を救われたことも、人間になったことも、またサンディたちに会えて箱舟に乗れるようになったことも、ここに今日来ようと思ったことも、花を摘もうと思ったことも・・・この中のどれが欠けても、私は今ここに居ない筈なの。そんな出来事が予め全部決まっているとしたら、膨大すぎて、頭がぐらぐらしそう・・・」
「確かにな。だが、おまえと冒険をしていて、神ですらその全ての筋書きを知っているわけではないらしいとわかってきた今では、私はこう思うぞ。そのような筋書きがあるとしても、それは結果有りきのものであって、過程はさほど重視されてないらしい、とな。おまえがここに来なければ、他の誰かが必ず現れて、この務めを果たしただろう。未来は、絶望に陥りさえしなければ悪いようにはならない、大いなる意志の筋書きが有るとしたらそうに違いないと、私は信じている」
「イザヤール様って、案外楽天的」
「嫌か?」
「ううん、そういうところも大好き」
「そうか、よかった。・・・お、月がそろそろ沈むな」
イザヤールの言う通り、月はそろそろ見えなくなりつつあった。間もなくすっかり沈むと同時に、老婆がミミの前に再び姿を現した。ミミは老婆に鏡を渡し、鏡を見て老婆は満足そうに頷いた。
「ご苦労さま。ずっと座りっぱなしで疲れたろう。帰ってゆっくりお休み。ささやかだけどこれはお礼だよ」
老婆はミミに銀の腕輪をくれた。月齢の満月から新月までを彫刻した、美しい腕輪だった。
「あんたたちに、月と星と太陽、全ての恵みがありますように」
その言葉と共に老婆の姿は何処ともなく去り、祠も無くなっていた。そして、壁越しではなくイザヤールが隣に座っていた。
「ようやく、おまえの顔を見ることができたな」
そう呟いて微笑み、彼はミミの頬を指先で優しくなでる。野菊の花冠と、いつの間にか膝に載っていた夕刻作った花束が、爽やかなな芳香で二人を包んだ。〈了〉
ダーマ地方の高台の湖水の畔には、サイクロプスと小さな男の子が仲良く暮らしている。そこを訪れた帰りにミミは、岸辺のひとつに野菊の花が群生している場所を見つけた。可憐な花にすっかり嬉しくなった彼女はしばらくうっとりとその景色と香りを楽しみ、それからいくらか手折って小さな花束を作り、帰ろうとした。
ルーラを唱えようとした彼女は、ふと、視界の端に、ここでは通常無い筈のものを捉えて、唱えるのを止めた。たくさんある湖のうちの一つの畔に、小さな祠が立っている。前からあれば絶対気が付く筈のものだ。しばらく来ない間に誰かが建てたのか、それとも何かのワナで幻覚なのか、とにかく確認しなくてはならないと考えて、ミミは祠の前まで行ってみた。
すぐ傍まで近寄ってみると、急拵えの建物らしく、木造で簡単に作られている。だがそれでいて、明らかに聖なる力が感じられるという不思議な建物だった。軒先には、聖なる力があると言われている草の数々が束ねられ飾られており、その中にはミミの持っているのと同じ、野菊の花もあった。
少しためらいながらもミミが律義にノックをすると、中から威厳のある女性の声で、「お入り」と返事があった。
用心しながらミミが扉を開けると、中には白絹が直接地面に敷かれていて、その上に法衣に身を包んだ老婆がきちんと背筋を伸ばして座っていた。彼女は、ミミが手にしている野菊の花束を見て言った。
「ようやく来たね、今年の巫女さんや。待っていたよ」
「巫女?何のことですか?」
全く覚えがなかったので、ミミはきょとんとした。すると老婆は、驚いたように言った。
「おや違うのかい?でもおかしいねえ、この祠は、心の清らかな者にしか見ることも入ることもできないし、第一あんた、ちゃんと巫女の印の花を持っているじゃないか」
「巫女の印の花?この野菊のことですか?あまりに綺麗だから、少し頂いてしまったけれど、そんな大事な花だなんて知りませんでした・・・」
申し訳なさそうにミミが言うと、老婆は面白そうに笑った。
「おやまあ、本当に違うのかい?この花もね、心の汚れた者には摘むことさえできないんだよ。あんたはどうやら、若いのによほど善行を積んでいるらしいねえ。偉いよ」
「そ・・・そうなんですか?」
元天使だったゆえに、人間よりずっとずっと長く生きて「善行」を積んでいるのも当然と言えば当然なので、少々ミミは面映ゆい気分になった。だがそんなミミの当惑をよそに、老婆は開いた戸から見える傾いた日差しに眉をしかめて、ぶつぶつと言った。
「じゃあ本当の巫女はどうしたんだろうねえ。このままじゃ日が暮れて間に合わなくなってしまうよ。困ったもんだ」
「あの、ここまで来るのはたいへんだし、もしかしたら途中で何かあったのかも・・・。私、探してきましょうか?」
ミミが申し出ると、老婆は渋面をやめて嬉しそうに微笑んだ。
「やっぱりあんたはいい子だねえ。思った通りだ。ふふふ、実はね、本当の巫女なんて予め決まってなんかいないんだよ。毎年必ず、心の清らかな娘が導かれて、印の花を持ってこの祠にやってくることになっているのさ。必ずこの場所とは決まっていない、その年の地上で月の一番近くにある場所に、この祠は現れるんだ。つまり、今年の巫女はあんたってこと」
「巫女・・・私が?」
思いがけなさすぎて、ミミは濃い紫の瞳を見開いて再びきょとんとした。
「そうだよ。それにあんた、どうやら踊り子さんらしいから、ますますちょうどいいじゃないか。古代の巫女さんは、踊りながら神託を伺うっていうしね」
「でも・・・何をすればいいんですか?」
思いがけない展開に戸惑いながらミミは尋ねた。もしかして踊るの?とも思った。
「そんなに心配しなくても大丈夫だよ。野菊の花冠をかぶってこの祠の中に座って、鏡を持って一晩中月光が鏡に当たり続けるようにしてくれればいいのさ」
「一晩中、ですか。じゃあ、必ず戻ってきますから、一度帰ってもいいですか?黙って外泊したら、みんな心配しちゃう」
「残念だけど、それは無理だね。もうすぐ日は落ちる。太陽が落ちた瞬間から、月光を鏡に当てなければ意味は無い。あんたがどんなに早く戻って来られると言っても、日没までには間に合わない。たとえ天の箱舟を使おうともね」
何故そんなことまでと、思わずミミが身構えると、老婆はにっこりと笑った。警戒心を思わず解きほぐしてしまうほど、優しくあたたかい笑顔だった。
「精霊がね、教えてくれるのさ。あんたがどんな人で、何をしてきたか、ってね。大丈夫、あんたの恋人は、おそらくここへあんたを探しに来るだろう。彼も正しい心の持ち主ならば、ここに来ることができて、私が説明してやれるというわけさ。それならいいだろう?」
ミミはためらったが、本当にもうすぐ日没になってしまう。帰ってしまえばどんなに急いでも、目的はわからないが「月光を日没直後から鏡に当てる」儀式はできないだろう。老婆の言葉とイザヤールが探しに来てくれることを信じることにした。ミミはクエスト「月を溜める鏡」を引き受けた!
老婆はミミを白絹の上に座らせると、袋の中から丸い鏡を取り出した。ラーの鏡に似ているが、はめ込まれた宝石と刻まれている文字が異なっているが、古代文字をいくらか知っているミミでも読むことはできなかった。
「この鏡に月光を当てると、鏡は今宵の特別な月光を蓄える。聖なる花の力と一緒にね」老婆はそう言って、ミミに鏡を手渡した。
「月光を蓄える・・・。でも、何故そんなことを?」
「強いて言えば、未来の為、ってところだね。この鏡に蓄えられた聖なる月光の力が、いつか役に立つ日が必ず来る。近い未来か遠い未来かわからないけどね」
そう言ってから老婆は、日がすっかり沈みかけているのを見て、ミミに告げた。
「おっと、私のお喋りはここまで!では頼んだよ。大丈夫、鏡が導いてくれるからね」
老婆はミミに花冠をかぶせて、祠から出た。
祠の入口は開け放たれているので、半分ほどの月齢の月光でも、充分鏡に降り注いだ。鏡が導くという言葉の意味が、ミミにも間もなくわかった。鏡が自ら動くわけではないのだが、月の傾きに従って、鏡を持つミミの手が、自然に月を追うように向きを調整するのだ。操られているという感じは無く、自然にそうしたくなるのだった。
花冠の清浄な香りが、静かな心をいっそう穏やかにする。単調どころかほとんど動くこともないが、退屈だとも特に思わず、ミミは鏡に映る月を見つめた。鏡は今の角度では、ミミのかぶる花冠もいくらか映し出していた。月光を受けて花冠は仄かに白く輝き、その輝きもまた鏡の中に満たされていくように見えた。そのやわらかな輝きを見て、ミミは思った。
(こうしていると、鏡の中に、月そのものを満たしているみたい・・・)
時も世界も、神ですら不変ではなく移ろい行くことを、ミミは自らの目で見てきて知っていた。今の平和とて、永遠のものではないだろう。次に世界の異変が起きたとき、人としての儚い寿命となった自分たちは、もう生きてこの世には居ないかもしれない。けれど。自分たちの血筋であろうとそうでなかろうと、自分たちの意志を継ぐ者は必ず現れて、大好きなこの世界を、守ってくれることだろう。この鏡も、もしかしたらその役に立つかもしれない・・・。そう思うと、ミミはわくわく感と安堵感の入り交じった、不思議な安らぎを覚えた。
やがて、誰かが会話をしている声が少し離れたところから聞こえてきた。おそらくミミを探しに来たイザヤールと、彼に事の次第を説明している老婆のものだろう。それから間もなく、祠の傍らに、誰かが静かに腰を下ろす気配がした。祠の簡素な壁越しに、ミミの隣に座るような形になっていた。
「ミミ」壁越しに、声が聞こえた。やはりイザヤールの声だった。「事情はわかった。月の光を遮るといけないから、あとしばらくはおまえの顔を見るのは我慢するとしよう」
それからしばらく彼は黙ったが、ミミには彼の物思いに耽っているであろう顔が、見えているようにわかった。
「・・・かつて、ある世界に、光の玉というものがあったそうだ」
かなり長いこと経ってから、ふいにイザヤールが呟いた。
「竜の女王が伝説の勇者に託し、その力のおかげで勇者は大魔王の闇の衣を消し去り、世界を救うことができた、でも後に竜王がそれを奪ったことで、世界が闇に包まれた・・・確かそう伝説には書かれていたっけ・・・」
「そうだ。・・・あれも、もしかしたら・・・闇の世界がいつか来ることを知っていた遠い昔の誰かが、用意していたものかもしれない、ふとそんなことを思った」
「竜の女王じゃなくて?誰かって、神様?」
「そうかもしれないし、違うかもしれない」
「別の世界にも、かつての私たちみたいな天使たちがいて、その人たちが用意してたのかも?」
「そうかもな。ただし、もしも我々と同じような能力だったとしたら、未来を予見して作ったというよりは、何かに導かれてそうしたのだろうな。・・・今宵のおまえみたいに、な」
「・・・今日私がここに来たのは、偶然じゃなくて必然だったってこと・・・?だったら、なんだかちょっと、怖いな・・・」
「怖い?何故だ?」
「だって、どんな小さな出来事でも、何か一つでも欠けたら、私はここにこうしていて、月の光を集めるなんてことは、なかったもの・・・。私が地上に落ちたことも、イザヤール様に庇ってもらって命を救われたことも、人間になったことも、またサンディたちに会えて箱舟に乗れるようになったことも、ここに今日来ようと思ったことも、花を摘もうと思ったことも・・・この中のどれが欠けても、私は今ここに居ない筈なの。そんな出来事が予め全部決まっているとしたら、膨大すぎて、頭がぐらぐらしそう・・・」
「確かにな。だが、おまえと冒険をしていて、神ですらその全ての筋書きを知っているわけではないらしいとわかってきた今では、私はこう思うぞ。そのような筋書きがあるとしても、それは結果有りきのものであって、過程はさほど重視されてないらしい、とな。おまえがここに来なければ、他の誰かが必ず現れて、この務めを果たしただろう。未来は、絶望に陥りさえしなければ悪いようにはならない、大いなる意志の筋書きが有るとしたらそうに違いないと、私は信じている」
「イザヤール様って、案外楽天的」
「嫌か?」
「ううん、そういうところも大好き」
「そうか、よかった。・・・お、月がそろそろ沈むな」
イザヤールの言う通り、月はそろそろ見えなくなりつつあった。間もなくすっかり沈むと同時に、老婆がミミの前に再び姿を現した。ミミは老婆に鏡を渡し、鏡を見て老婆は満足そうに頷いた。
「ご苦労さま。ずっと座りっぱなしで疲れたろう。帰ってゆっくりお休み。ささやかだけどこれはお礼だよ」
老婆はミミに銀の腕輪をくれた。月齢の満月から新月までを彫刻した、美しい腕輪だった。
「あんたたちに、月と星と太陽、全ての恵みがありますように」
その言葉と共に老婆の姿は何処ともなく去り、祠も無くなっていた。そして、壁越しではなくイザヤールが隣に座っていた。
「ようやく、おまえの顔を見ることができたな」
そう呟いて微笑み、彼はミミの頬を指先で優しくなでる。野菊の花冠と、いつの間にか膝に載っていた夕刻作った花束が、爽やかなな芳香で二人を包んだ。〈了〉










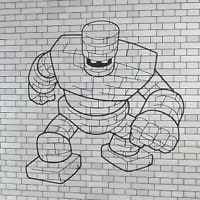















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます