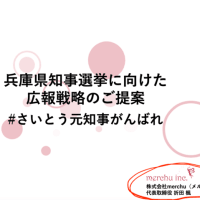前回は地区リーダーになった辺りのことまで書きましたが、ちょっと戻ってB長時代の話です。
B長の任命を受け、ぬるい活動をしつつ、功徳をどんどん認定され、会合参加も少しずつ増やしつつあったその頃。
まだその時は会合に行ってもお客様状態で、居心地は悪くなかったし、こんなんだったら会合出てもいいかなと思うようになっていました。
そんなある日のこと、部長が改まって家にやって来ました。
「遊説、やってみない?」
遊説というのは選挙のウグイス嬢のことで、当時は女子部のなるべくなりたてぐらいの子が声をかけられていました。
「でも、遊説って大変なんじゃないですか?怖くないですか?」私がそう聞くと部長は、
「大丈夫。そんなに怖くないし、楽しいこともあると思うし、思い出に残ると思うよ」
そんなにたいしたことじゃない、ということを部長は繰り返しましたので、それならば、とやってみることにしました。
その選挙の規模や地域によっても違うと思いますが、私の場合、一ヶ月ぐらい前から「練習」というのが始まりました。
練習に行く交通費などはすべて自腹です。
もちろん、練習にいっても、お金は一切もらえません。
ただ、選挙期間中の遊説で車に乗った時だけは、いくらか出たと思いますが、金額は忘れました。
はっきりいってしまえば、ボランティアです。
そんなボランティアのために、一ヶ月間ほぼ毎日の練習があり、遊説の車に乗るときは会社を休まねばなりませんでした(二日有給とりました)。
私の会社は休みに厳しい会社でしたので、短期間に二日も有給を、しかも直前に言ったので、当然社長には渋い顔をされました。
「広宣流布のために取った休みなんだから、絶対に後で何かの功徳になって返ってくる」などと言われましたが、
ただ単に信用を失っただけで終わったような気がします。
さて、遊説の練習です。
仕事が終わると毎日、創価学会の会館に通いました(公●党の遊説の練習なのに会館を使うのは政教一致にならないの?)。
土曜も日曜も、すべて練習で埋め尽くされます。
集められたのは、私と同じように活動家になったばかりで、同じ20代前半の女子部員たちばかりでした。
(今は女子部が少なくて婦人部の方がされることが多いようです。お疲れ様です……)
まだ創価の常識がよく分かっていなく、それをスパルタ形式で教え込まれていきます。
まず、練習の教官ともいうべき女子部のお姉さんが何かを喋ると、返事をしなければなりません。
しかも、大声で「ハイッ!!!!!!!」ぐらいの返事です。
ものすごく違和感がありましたが、声が小さいと、一人だけあてられ、教官役のお姉さんが納得するまで「ハイッ!!!!!」と言い続けなければなりません。
一人だけやり直すのは嫌ですから、当然もう最初から「ハイッ!!!!!!!」と返事をするようになります。
あと教官のお姉さんの話は、すべてメモを取らなくてはなりません。
それを知らずにぼやーっと聞いていると「そこっ!メモを取らなくていいんですか!?」と怒鳴られます。
実は私は遊説の練習が始まってすぐに高熱を出して二日ほど練習を休んでしまったんですが、
その際にも家に電話があり「練習に来れないのは仕方ないですが、腕立て、腹筋、背筋それぞれ30回やっておくように」と母に言づてたそうです。
当時は携帯電話はまだ普及してませんでしたので、それを聞いた母はさすがに驚いたみたいでした。
「熱40度近くあるって言ったんだけどね……」
そんなの関係ねえって感じだったみたいです。
ともあれ、そういうスパルタ練習が一ヶ月間ほぼ毎日、仕事で疲れた体にむち打って……どうなるか分かりますよね?
一ヶ月経てば、立派な創価学会の活動家ができあがるわけです。
遊説の練習は声を出すということもあり、体力をつけるということもあり、腹筋、背筋、腕立てなどの準備運動から始まります。
これも厳しいです。腕立ても(なぜ遊説に腕立てが?)ちゃんと腕が曲がってないと怒られます。
本気の腕立て、腹筋、背筋をしなければなりません。
その後、発声練習をして、具体的に遊説の時にマイクを握って喋ることを覚えていきます。
候補の名前などははっきりと、明るく、何度も何度も言い直しをさせられます。
「そんなんじゃ伝わらない!」「魂が籠もってない!」などなど言われ、出来が悪い人は別の場所に集められ、何度もやり直しをさせられます。
いろんなパターンに対応できるように、マニュアルが配られ、たとえばマンションの窓から手を振っている人を見つければ、
「高いところからのご声援、本当にありがとうございます!!0000(候補者のフルネーム)、力一杯頑張って参ります!!」
などとマイクを通して絶叫するわけです。
遊説の車に乗ると、マイクを持つ一人の他は、手を振っている人を見つけます。
その人が手を振っているのか、旗を振っているのか、お子さんと一緒なのかなどなど、詳しく伝えます。
それに応じて、マイクを持っている人が臨機応変にアナウンスの言葉をかえ、絶叫するわけです。
そんな感じで、どんな場面にも対応できるよう厳しく特訓された遊説隊員は、たぶんプロも顔負けだと思います。
プロの人はそれでお金がもらえるかもしれませんが、私たちは失敗したら教官や組織の人たちから怒られるという恐怖があります。
人を動かす力は、お金もそれなりにあるかもしれませんが、恐怖のほうが強いように思います(なんて安上がりな私たち……涙)。
また、こうした厳しい練習の後はなぜだか「池田先生」の書物やスピーチなどの学習があります。
これも一ヶ月の練習の際に毎回組み込まれます。
創価学会のために従順に動く駒を育成するとともに、「池田先生」という存在が何よりも大切なものであると、このとき同時にすり込まれていくのです。
これが一ヶ月ほぼ毎日のように続いていきます。するとどうなるか。
最初は「池田さん?それなに?」程度だった仲間たちが、遊説の練習が終盤になる頃には
「池田先生」を語りながら涙を流すようになっていました。もちろん、私もです。
涙を流さなければならないと最初は思い、周りの雰囲気に合わせて泣いていたのが、
気がつけば自然と涙が零れるようになっていたのです。
遊説隊員にはお題目のノルマもありました(一日一時間だったかな?)。
これはまた次の記事で詳しく紹介しますが、当然、何人の人に頼んだかという「F」のノルマもあります。
ともあれ、こうして私たちは効率よく洗脳されていき、選挙で戦える活動家として出荷されるのです。

B長の任命を受け、ぬるい活動をしつつ、功徳をどんどん認定され、会合参加も少しずつ増やしつつあったその頃。
まだその時は会合に行ってもお客様状態で、居心地は悪くなかったし、こんなんだったら会合出てもいいかなと思うようになっていました。
そんなある日のこと、部長が改まって家にやって来ました。
「遊説、やってみない?」
遊説というのは選挙のウグイス嬢のことで、当時は女子部のなるべくなりたてぐらいの子が声をかけられていました。
「でも、遊説って大変なんじゃないですか?怖くないですか?」私がそう聞くと部長は、
「大丈夫。そんなに怖くないし、楽しいこともあると思うし、思い出に残ると思うよ」
そんなにたいしたことじゃない、ということを部長は繰り返しましたので、それならば、とやってみることにしました。
その選挙の規模や地域によっても違うと思いますが、私の場合、一ヶ月ぐらい前から「練習」というのが始まりました。
練習に行く交通費などはすべて自腹です。
もちろん、練習にいっても、お金は一切もらえません。
ただ、選挙期間中の遊説で車に乗った時だけは、いくらか出たと思いますが、金額は忘れました。
はっきりいってしまえば、ボランティアです。
そんなボランティアのために、一ヶ月間ほぼ毎日の練習があり、遊説の車に乗るときは会社を休まねばなりませんでした(二日有給とりました)。
私の会社は休みに厳しい会社でしたので、短期間に二日も有給を、しかも直前に言ったので、当然社長には渋い顔をされました。
「広宣流布のために取った休みなんだから、絶対に後で何かの功徳になって返ってくる」などと言われましたが、
ただ単に信用を失っただけで終わったような気がします。
さて、遊説の練習です。
仕事が終わると毎日、創価学会の会館に通いました(公●党の遊説の練習なのに会館を使うのは政教一致にならないの?)。
土曜も日曜も、すべて練習で埋め尽くされます。
集められたのは、私と同じように活動家になったばかりで、同じ20代前半の女子部員たちばかりでした。
(今は女子部が少なくて婦人部の方がされることが多いようです。お疲れ様です……)
まだ創価の常識がよく分かっていなく、それをスパルタ形式で教え込まれていきます。
まず、練習の教官ともいうべき女子部のお姉さんが何かを喋ると、返事をしなければなりません。
しかも、大声で「ハイッ!!!!!!!」ぐらいの返事です。
ものすごく違和感がありましたが、声が小さいと、一人だけあてられ、教官役のお姉さんが納得するまで「ハイッ!!!!!」と言い続けなければなりません。
一人だけやり直すのは嫌ですから、当然もう最初から「ハイッ!!!!!!!」と返事をするようになります。
あと教官のお姉さんの話は、すべてメモを取らなくてはなりません。
それを知らずにぼやーっと聞いていると「そこっ!メモを取らなくていいんですか!?」と怒鳴られます。
実は私は遊説の練習が始まってすぐに高熱を出して二日ほど練習を休んでしまったんですが、
その際にも家に電話があり「練習に来れないのは仕方ないですが、腕立て、腹筋、背筋それぞれ30回やっておくように」と母に言づてたそうです。
当時は携帯電話はまだ普及してませんでしたので、それを聞いた母はさすがに驚いたみたいでした。
「熱40度近くあるって言ったんだけどね……」
そんなの関係ねえって感じだったみたいです。
ともあれ、そういうスパルタ練習が一ヶ月間ほぼ毎日、仕事で疲れた体にむち打って……どうなるか分かりますよね?
一ヶ月経てば、立派な創価学会の活動家ができあがるわけです。
遊説の練習は声を出すということもあり、体力をつけるということもあり、腹筋、背筋、腕立てなどの準備運動から始まります。
これも厳しいです。腕立ても(なぜ遊説に腕立てが?)ちゃんと腕が曲がってないと怒られます。
本気の腕立て、腹筋、背筋をしなければなりません。
その後、発声練習をして、具体的に遊説の時にマイクを握って喋ることを覚えていきます。
候補の名前などははっきりと、明るく、何度も何度も言い直しをさせられます。
「そんなんじゃ伝わらない!」「魂が籠もってない!」などなど言われ、出来が悪い人は別の場所に集められ、何度もやり直しをさせられます。
いろんなパターンに対応できるように、マニュアルが配られ、たとえばマンションの窓から手を振っている人を見つければ、
「高いところからのご声援、本当にありがとうございます!!0000(候補者のフルネーム)、力一杯頑張って参ります!!」
などとマイクを通して絶叫するわけです。
遊説の車に乗ると、マイクを持つ一人の他は、手を振っている人を見つけます。
その人が手を振っているのか、旗を振っているのか、お子さんと一緒なのかなどなど、詳しく伝えます。
それに応じて、マイクを持っている人が臨機応変にアナウンスの言葉をかえ、絶叫するわけです。
そんな感じで、どんな場面にも対応できるよう厳しく特訓された遊説隊員は、たぶんプロも顔負けだと思います。
プロの人はそれでお金がもらえるかもしれませんが、私たちは失敗したら教官や組織の人たちから怒られるという恐怖があります。
人を動かす力は、お金もそれなりにあるかもしれませんが、恐怖のほうが強いように思います(なんて安上がりな私たち……涙)。
また、こうした厳しい練習の後はなぜだか「池田先生」の書物やスピーチなどの学習があります。
これも一ヶ月の練習の際に毎回組み込まれます。
創価学会のために従順に動く駒を育成するとともに、「池田先生」という存在が何よりも大切なものであると、このとき同時にすり込まれていくのです。
これが一ヶ月ほぼ毎日のように続いていきます。するとどうなるか。
最初は「池田さん?それなに?」程度だった仲間たちが、遊説の練習が終盤になる頃には
「池田先生」を語りながら涙を流すようになっていました。もちろん、私もです。
涙を流さなければならないと最初は思い、周りの雰囲気に合わせて泣いていたのが、
気がつけば自然と涙が零れるようになっていたのです。
遊説隊員にはお題目のノルマもありました(一日一時間だったかな?)。
これはまた次の記事で詳しく紹介しますが、当然、何人の人に頼んだかという「F」のノルマもあります。
ともあれ、こうして私たちは効率よく洗脳されていき、選挙で戦える活動家として出荷されるのです。