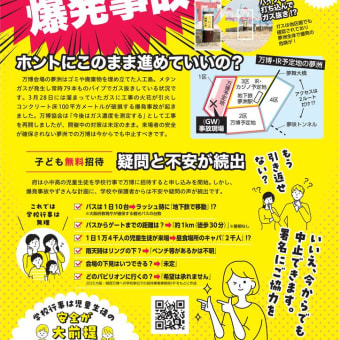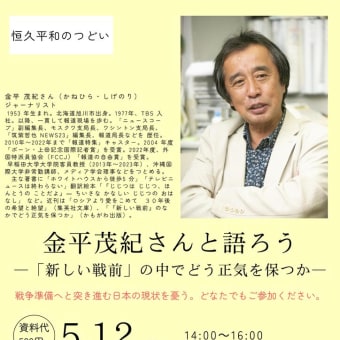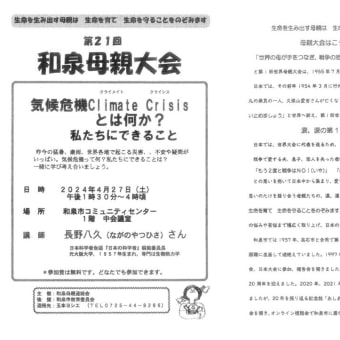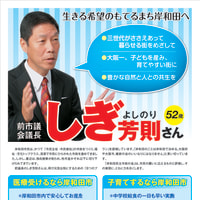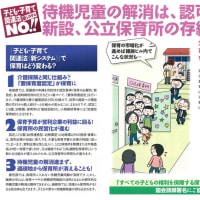台風17号の接近が伝えられる中、「憲法を生かし、安心して住み続けられる地域、日本を」めざして全国から自治体労働者、地方議員、研究者、市民などが研究・交流をおこなう「第11回地方自治研究全国集会」が29日(土)~30日(日)に埼玉市大宮で開催され、初日の全体会に1600名、2日目の分科会をあわせてのべ3000人が参加しました。和泉市職労からも4名が参加しました。
初日の全体会のオープニングは、地元秩父市の本町子ども太鼓教室のみなさんによる秩父屋台囃子の太鼓演奏でした。秩父屋台囃子は、日本三大曳山祭りの一つである秩父夜祭りで笠鉾と屋台が曳行される際に演奏されるものだそうで、特に楽譜と言ったものがなく、地区それぞれの囃子があり、大人から子どもへ伝承で受け継がれているもので、国の重要無形文化財にも指定されているそうです。
当日は、運動会と重なって参加できない子どもたちもいるとのことでしたが、その子どもたちの思いも受けて立派な演奏でした。
つづいての記念講演は、「すべての人に、暮らしを守るセーフティネットを」と題して、国立社会保障・人口問題研究所の阿部 彩さんが行いました。
阿部さんは、豊富なデータによるグラフにもとづいて諸外国と比較して日本の貧困の実態をわかりやすく明らかにしました。
日本の貧困率は2009年に15.7%と高率水準で、このことが注目されたのはリーマンショック以降からだが、それ以前の1985年にはすでに12%を超えており、その後、一貫して上昇し続けていたことを指摘。それは、勤労世帯の状況の悪化だけでなく、高齢化と核家族化やひとり親世帯の増加などの世帯構造の変化など社会的背景があることを明らかにしました。
日本の貧困の特徴
ワーキングプア率では、OECD参加中で高い方から5番目、ひとり親世帯ではダントツ一番である。一方、公的扶助については、生活保護受給率が1.6%と他国より特徴的に低い。さらに、所得再分配にかかる政策介入前後の状況をみると、再分配後の子どもの貧困率が改善されず、逆に高くなったのは日本だけであることをデータで示しました。
貧困連鎖と格差極悪論
貧困率が高いということはなぜ問題なのか。例えば、子どもの貧困が学力、健康などに及ぼす影響を見てみると、明らかに関連性が見られる。この影響は大人になっても続き、成功の可能性確率が低くなり、徐々に社会的階層ができ、貧困の連鎖が生まれてくる。
貧困・格差によって、人々は、少し上の人がねたましく、逆に少し下の人には攻撃的になっていく。現在行われている生活保護受給者や公務員バッシングにつながっている、という指摘は、橋下・維新の会のもとで市民分断が持ち込まれている大阪で特に実感される。
社会的排除対策政策を
貧困の現象は、自己肯定感の喪失を生み、家族などの個人的つながりから社会のさまざまな側面のつながりまで、自らを取り巻く環境ぁら排除される。従来は、貧困は不可抗力な悪とされていたが、こういった「社会的排除」を社会の問題としてとらえ、社会のありようを変える政策(社会的包摂)が必要である。対症療法的な対応ではなく、「川上」対策=貧困を生まないようにする政策が必要である、とのまとめでした。
最後に、阿部氏は日本で今一番足りないのは連帯感であり、今こそすべての人が連帯して声をあげなければならない時期に来ていると、強調しました。「多くの人々を巻き込み、社会を変える取り組みをはじめましょう」と参加者を激励しました。