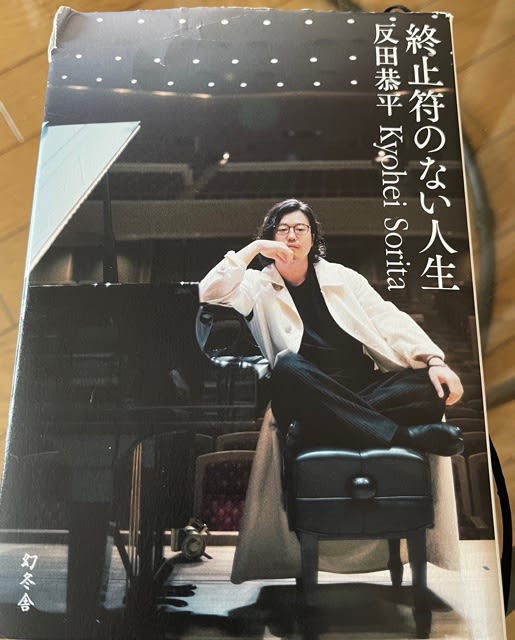
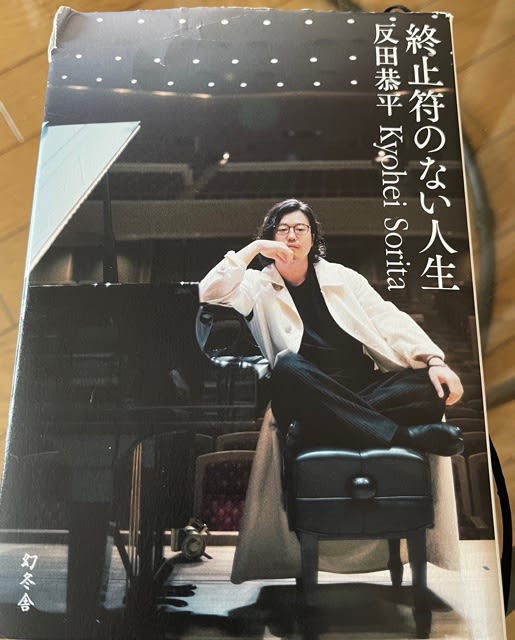
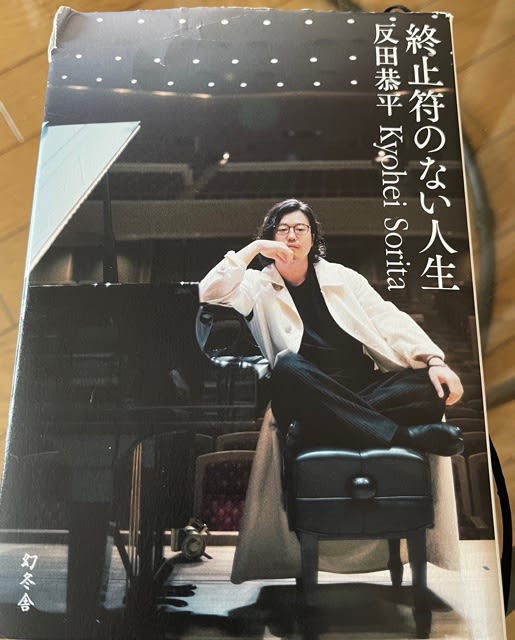


 |
新装版 ドビュッシーと歩くパリ[CD付き] |
| クリエーター情報なし | |
|
アルテスパブリッシング ・・・・・・ ドビュッシー演奏家の中井正子さんの著書。 高校生の時からパリに留学されている中井さんのドビュッシーを中心にした視点からのパリガイド。 素敵な写真とCD(中井さん演奏)とともに、読み進められます。 ドビュッシーをこれから、勉強しよう!という方に、とてもおすすめだと思います! パリの美術館情報もあり、絵画と照らし合せることができます。 上昇志向だったというドビュッシー ドビュッシーの人生の流れに合わせて、よく引っ越しをしていたよう・・・。 写真付きで紹介されています。 おススメのカフェなどの紹介もあり、とても読みやすい内容でした。
フランスのソルフェージュ教育と日本のソルフェージュ教育は違うと・・・ 音大時代、ソルフェージュの授業で、パリ音楽院で使っている、テキストを使っていましたが 、かなり難しかった記憶が蘇りました。
|
 |
「音大卒」は武器になる |
|
クリエーター情報なし |
|
|
ヤマハミュージックメディア ・・・・・・・ 武蔵野音楽大学 就職課の大内さんの著書。 ひたすら好きな音楽に真剣に目いっぱい打ち込んだ過程で得られた力は、音大卒にとって武器である。 また、音大と一般大学の大きな違いは、先生とのマンツーマンレッスンがあること。 その厳しいレッスンの中で、自然と身についた「叱られる力」「めげない力」は、社会で必要な実力となる。 目上の先生とのマンツーマンレッスンで培った、コミュニケーション能力は、社会でに出て、最大の武器となる。
|
チェロを生きる 堤 剛 新潮社
・・・・・・・・・・・
チェロって良い音色ですよね~!
チェロは、人間の声の様な楽器と言われますね!
特に男性の話し言葉と同じ音域なので、とても音色に温かみがあると思います。
ですので、とても好きな楽器の1つです。
この本は、堤さんの自伝の様な作品です。
まずは、音楽との出逢い、桐朋学園・斉藤秀雄のレッスン、シュタルケル先生との出逢い、教え、留学時代の事、演奏旅行の事、現代曲の事、最後にチェロ協会の活動等が書かれています。
斉藤秀雄のレッスンでは、いかにこの時代が良い時代だったかが感じられます。
現在は、CDや音源があふれているので、すぐに有名な音楽家の演奏を聞く事ができます。
この時代は、まだまだ西洋音楽を聞くという習慣が少なかったので、1枚のレコードから聞こえてくる演奏は、なんとも憧れのようでした。想像力を掻き立てていたようです。
また斉藤秀雄は、海外からの演奏家が来日した場合、必ずご自宅に呼び、生徒達に目の前で聞かせる様にしていたようです。
鬼教師と呼ばれていた斉藤秀雄、小沢征爾等、有名な弟子を育てた先生の情熱は、すごいものだったようです。
シュタルケル先生。ゾルタン・コダーイの無伴奏チェロ・ソナタを初めて弾いたのは、シュタルケル先生だったそうです。
この先生からの「プロフェッショナルとは」とういう教え。
アメリカに留学して、もう1度基礎からやり直した事、並大抵の努力ではなかったと思われますが、さらっと書かれています。
楽譜を読むプロセス、音楽だけでなく、全ての事を勉強した上で、自分なりの演奏が出来るようになる!それは、チェロだけでなく、全ての楽器に共通することですが・・・・。
堤さんの哲学もまた知る事が出来ました。
♪ゾルタン・コダーイの『無伴奏チェロソナタ』。とても好きな曲で、大学時代、図書館でよく聞いてました
↓シュタルケル先生の演奏です! 『無伴奏チェロソナタ』 1楽章
http://www.youtube.com/watch?v=4MEUIGjfHNw&feature=related
↓第2楽章
http://www.youtube.com/watch?v=2qm7_cI2b30&feature=related
↓第3楽章
http://www.youtube.com/watch?v=ZvOEwGlwgJo&feature=related
幼児のちから~モンテッソーリ教育の現場から~
松浦公紀著 発売元 静岡新聞社
・・・・・・・・・・・・・
先日の日記に、リトミック研究センターのカリキュラムは、モンテッソーリ教育との融合である!と書きました。
また、かなり前になりますが、「エチカの法則」だったと思いますが、中国では、子供の口の中から細胞をとり、遺伝子検査を行い、その子が、どういう道に進むべきか!を、その検査結果から親が導いていく!と言っていました。
スポーツが得意な遺伝子を持っている子は、スポーツを習わせ、文化的な事が得意そうな子は「モンテッソーリ」のお教室に通わせるそうです!
凄い事するな!とも思いましたが、現在、アメリカやアジアでは、この教育法が盛んに行われているそうです!!
実際、モンテッソーリのお教室では、どのような事をしているのか、とても興味があるので、この本を読みました!!
これは、著者が開いているお教室「松浦学園(子供の家)」での活動が書かれています!
イタリア人女性 マリア・モンテッソーリ(1870年~1952年)が、モンテッソーリ教育施設「子供の家」をローマに開設しました。
精神科医でもあるモンテッソーリが教育に携わった時に、まず「観察」という方法により、幼児期の子供について色々な発見をしました。
子供には自分で自分を成長させていく「自己開発力」とか「自己教育力」というものが存在する。
「子供の家」では、身体を動かしたり、手を使ったりする活動がたくさんあるそうです。
ハサミを持って、紙を切る。針を持って縫う。リボンを結ぶ。歩く。座る。折る。貼る。洗う。拭く等。日常生活の練習という分野
「知性」の働き。その中の出発点は"比べる"という活動です。比べることで"同じ"や"仲間わけ"・"順序"などを体験して理解していきます。
同じ色を見つける! 大きい物から順番に並べる等。感覚教育と言う分野

「リトミックってなあに~リズムの良い子を育てよう~」
岩崎光弘著 ドレミ楽譜出版社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リトミック研究センター会長「岩崎光弘先生」が書かれた本です。
「リトミック」はスイスの作曲家・音楽教育家エミール・ジャック・ダルクローズによって考え出された音楽教育。
・・・音楽教育は、人間の心と体の発達段階を考慮して行うべきだとダルクローズは提唱した。
音楽を聞く、歌う、演奏する、作るといった音楽教育で学ぶ全ての事を、体を動かす経験を通じて感じ取っていくのがリトミック教育法である。
それは、リズムという素材を生かし、音楽に反応して動く事により、感じる心、想像力を養う。
心で感じた物を、体を使って自分なりに表現することで、心と体の強調・調和を作りだそうとする。
人間が人間らしく生きるために必要な、自己表現できる力を引き出すリトミックは、また音楽教育だけでなく人間教育でもある。・・・
また、リトミックの歴史は、ダルクローズによって1902年ジュネーブ音楽学校でリトミックのための特別クラスが開かれて以来、ヨーロッパ全土に広がったそうです。
その後、ダルクローズ研究所において開かれた会議では、教育者、生理学者、心理学者等、様々な人によってリトミックについての研究発表がなされました。
日本では、明治時代から大正にかけてヨーロッパから入ってきました。
ヨーロッパに、日本からリトミックを学びに行った最初の人は「黒柳徹子」の先生である「小林宗作」でした。
リトミックの導入は、演劇や舞踏の分野だったそうです。
山田耕筰もドイツ留学中にダルクローズのアトリエに訪れて、大きな刺激を受けた様です。
現在、リトミック研究センターでは、他の教育法との融合がなされています!
「モンテッソリーの教育法」・・マリア・モンテッソリー(1870年~1952年)イタリアの教育家。
モンテッソリーは、子供には自ら成長する力があるという事を前提に子供達の心と体の自発的発達を助長する自由な教育法を推進しました。
ダルクローズは音楽を通して、モンテッソリーは子供の生活を通して「教育のメソード」を作り上げました。
リトミック研究センターのカリキュラムの中には、この「モンテッソリーの教育法」も採り入れられています。
というような事が岩崎先生により、細かく書かれています!
「2才からのピアノ・レッスン」 ~小さい子の上手な教え方~
遠藤蓉子著 サーベル社
・・・・・・・・・・・・・・・・・
「1才からのピアノ・レッスン」の続編。
タイトルは2才からと書かれていますが、著者は2才にとらわれず、「小さい子の教え方」として出版したそうです!
1才から2才は「言葉と身体の為のプログラム」。
2才から3才は「リズムと音感のためのプログラム」。
3才から4才は「音譜と鍵盤導入の為のプログラム」。
この本は2才~3才の「リズムと音感の為のプログラム」の事を中心に書かれています!
著者が出版している様々なテキストを使用したレッスン方法が紹介されています。
小さい子のレッスンは、本当に難しくて壁にぶつかる事がよくありますが、指導者は少しの忍耐と情熱があれば、どんな事も乗り越えられるそうです!
とても励まされる1冊です.
最後に、年齢別・体験レッスンの仕方も紹介されています!
著者の出版しているテキストの中の、ソルフェージュのテキストは、とても気になります!
すぐに実践できそうです!!