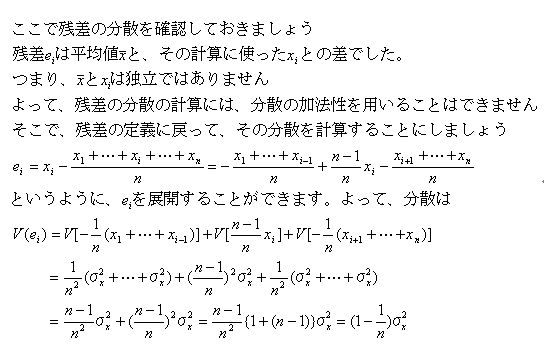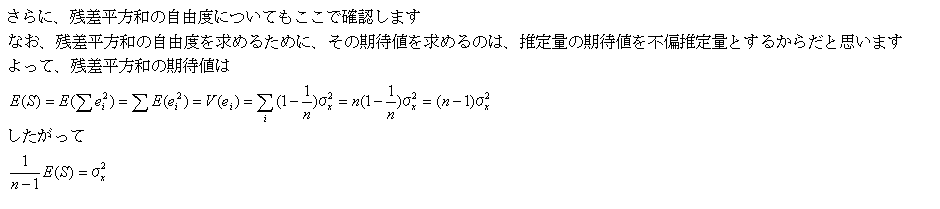この章では、2変数のモニタリングを学びます。まず、散布図と相関係数との関係を学び、その上で、相関関係と因果関係を学びます
[4.1]散布図と相関係数
(1)散布図
2つの変数の関係は、散布図によって視覚的に確かめられます。散布図を描くとき、横軸(x軸)と縦軸(y軸)に、どの変数を割り当てるかが、最初の問題になります。回帰分析との関連を視野に入れれば、次の基準で軸を選ぶ習慣をつけるのがよいでしょう
○2変数に原因と結果の関係があるときは、x軸に原因となる変数をおきます
○2変数に原因と結果の関係がないときには、予測したい変数をy軸におきます
さらに、散布図を眺めるとき、以下の観点に注意することが重要です
a ) 直線関係か、曲線関係か
b ) 外れ値はないか
c ) 異質な観測値が混ざっていないか(散布図に2系列のデータが認められるか?)
あらかじめ、a) ~ c )に注意する必要がある理由は、これらのデータ傾向が、相関係数の計算結果に大きな影響を与えるからです。相関係数とは、散布図で認めれらるようなデータ傾向を、直線関係で要約する手段です。よって、この前提(直線関係)を満たすデータでなければ、たとえ一定の関係が散布図で認められたとしても、相関係数は低くなります。そして、実は、相関係数をもちいて、変数間の関係をうまく捉えられないデータが、まさにa) ~ c )なのです。よって、a) ~ c )を、あらかじめ確認することで、与えられたデータの関係を、相関係数で表現できるかどうかを、大まかに判断しておくことができるようになります。
(2)相関係数
相関係数とは、相関関係の強さをあらわす指標です。ただし、ここで考える相関関係は、直線関係で表されるものです。よって、曲線関係の相関関係があったとしても、相関係数でうまく表すことはできません。相関係数rは、以下の式で表されます

[4.2]相関係数・相関関係・因果関係
相関係数有意ではないから、2つの変数間に関係がないと判断してはいけません。相関係数は、直線関係の強さを測る指標です。したがって、曲線関係を相関係数で知ることはできません。
また、異質な集団の集まりであるとき、全体としては無相関であっても、層ごとに散布図を描くと相関を発見できることがあります
相関関係と因果関係の関係をまとめたのが、下の図です。下の図を見ると、因果関係があるときは、必ず相関関係がありますが、相関関係があるからといって、因果関係があるとは限らないことが、よく分かります。

ただし、注意すべきことは、関係があるから、すぐに因果関係(原因と結果)があると判断してはならない、ということです。第3の変数が両変数に影響を与えているために、見かけの相関がある場合がある可能性があります。このような相関を、擬似相関といいます
そこで、擬似相関には、下の二つのケースがあります。このような擬似相関関係が見られるとき、x→yというように因果関係を決定してはいけません。

[4.1]散布図と相関係数
(1)散布図
2つの変数の関係は、散布図によって視覚的に確かめられます。散布図を描くとき、横軸(x軸)と縦軸(y軸)に、どの変数を割り当てるかが、最初の問題になります。回帰分析との関連を視野に入れれば、次の基準で軸を選ぶ習慣をつけるのがよいでしょう
○2変数に原因と結果の関係があるときは、x軸に原因となる変数をおきます
○2変数に原因と結果の関係がないときには、予測したい変数をy軸におきます
さらに、散布図を眺めるとき、以下の観点に注意することが重要です
a ) 直線関係か、曲線関係か
b ) 外れ値はないか
c ) 異質な観測値が混ざっていないか(散布図に2系列のデータが認められるか?)
あらかじめ、a) ~ c )に注意する必要がある理由は、これらのデータ傾向が、相関係数の計算結果に大きな影響を与えるからです。相関係数とは、散布図で認めれらるようなデータ傾向を、直線関係で要約する手段です。よって、この前提(直線関係)を満たすデータでなければ、たとえ一定の関係が散布図で認められたとしても、相関係数は低くなります。そして、実は、相関係数をもちいて、変数間の関係をうまく捉えられないデータが、まさにa) ~ c )なのです。よって、a) ~ c )を、あらかじめ確認することで、与えられたデータの関係を、相関係数で表現できるかどうかを、大まかに判断しておくことができるようになります。
(2)相関係数
相関係数とは、相関関係の強さをあらわす指標です。ただし、ここで考える相関関係は、直線関係で表されるものです。よって、曲線関係の相関関係があったとしても、相関係数でうまく表すことはできません。相関係数rは、以下の式で表されます

[4.2]相関係数・相関関係・因果関係
相関係数有意ではないから、2つの変数間に関係がないと判断してはいけません。相関係数は、直線関係の強さを測る指標です。したがって、曲線関係を相関係数で知ることはできません。
また、異質な集団の集まりであるとき、全体としては無相関であっても、層ごとに散布図を描くと相関を発見できることがあります
相関関係と因果関係の関係をまとめたのが、下の図です。下の図を見ると、因果関係があるときは、必ず相関関係がありますが、相関関係があるからといって、因果関係があるとは限らないことが、よく分かります。

ただし、注意すべきことは、関係があるから、すぐに因果関係(原因と結果)があると判断してはならない、ということです。第3の変数が両変数に影響を与えているために、見かけの相関がある場合がある可能性があります。このような相関を、擬似相関といいます
そこで、擬似相関には、下の二つのケースがあります。このような擬似相関関係が見られるとき、x→yというように因果関係を決定してはいけません。



















 が大きくなるときに、外れ値と判断します。
が大きくなるときに、外れ値と判断します。