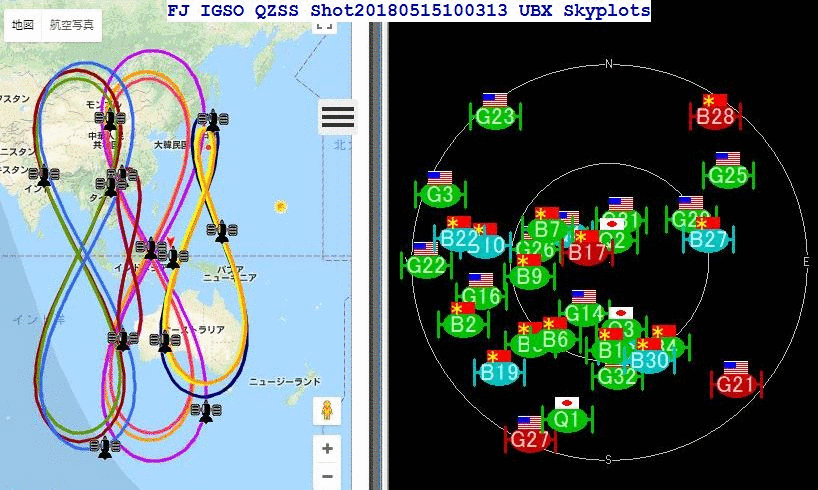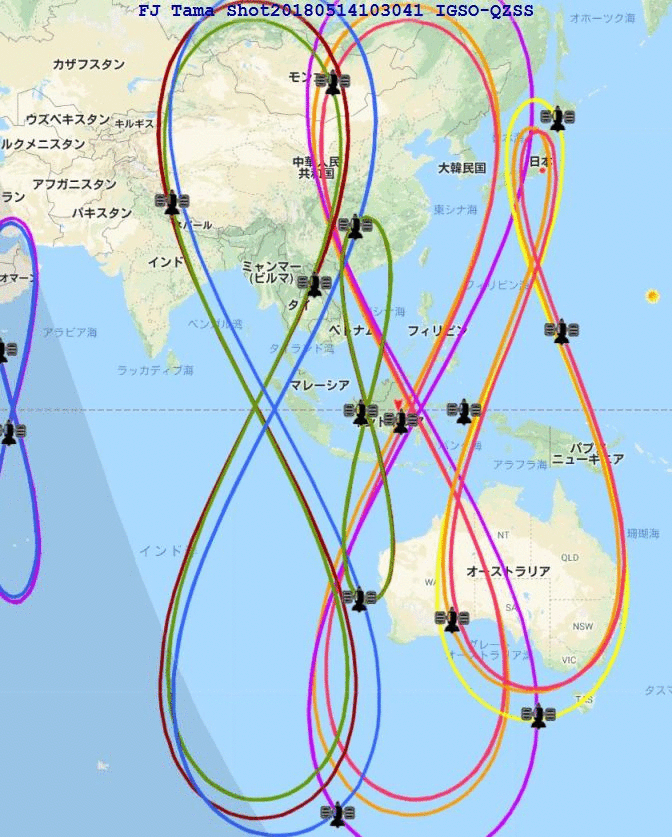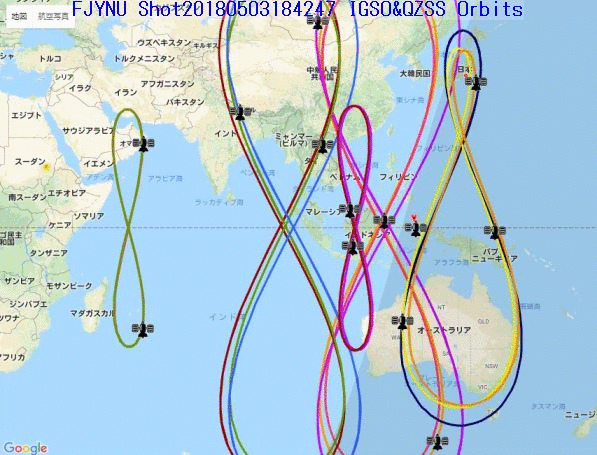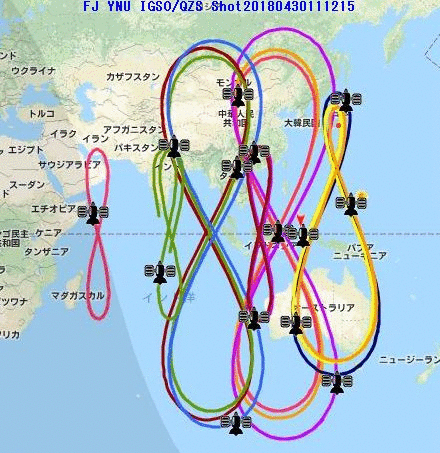2018 05/04:アンカー移動が無く,N2YOサーバの負担軽減のための強制縮小の画像化も無しでの、東アジアの全IGSO&QZSS衛星軌道の24時間アニメを記録します。
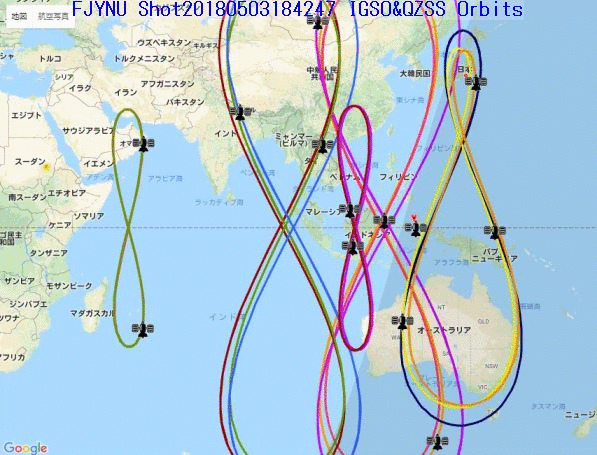
N2YOサイトを利用されている方は、これが貴重であることがお分かりだと思います。また11時台JSTでのQZS-
4の太陽合は相変わらず続いています。一体いつまでこの合は続くのでしょうか。
2018/04/02-2018/04/04の期間中のTLEまたは3LEは以下の通りです。
●2018/04/02-2018/04/04のTLE:
1 42965U 17062A 18122.03961250 -.00000342 00000-0 00000+0 0 9991
2 42965 40.5842 21.9833 0747881 270.6269 80.8480 1.00272205 2069
1 42965U 17062A 18122.03961351 -.00000342 +00000-0 +00000-0 0 9994
2 42965 040.5842 021.9834 0747852 270.6249 080.8504 01.00272234002065
1 42965U 17062A 18123.03687725 -.00000338 +00000-0 +00000-0 0 9990
2 42965 040.5847 021.9701 0747829 270.6405 080.8343 01.00271988002078
1 42965U 17062A 18123.03687811 -.00000338 +00000-0 +00000-0 0 9996
2 42965 040.5847 021.9703 0747798 270.6381 080.8370 01.00272014002079
●2018/04/02-2018/04/04の3LE:
0 QZS-4
1 42965U 17062A 18122.03961250 -.00000342 00000-0 00000+0 0 9991
2 42965 40.5842 21.9833 0747881 270.6269 80.8480 1.00272205 2069
0 QZS-4
1 42965U 17062A 18122.03961351 -.00000342 +00000-0 +00000-0 0 9994
2 42965 040.5842 021.9834 0747852 270.6249 080.8504 01.00272234002065
0 QZS-4
1 42965U 17062A 18123.03687725 -.00000338 +00000-0 +00000-0 0 9990
2 42965 040.5847 021.9701 0747829 270.6405 080.8343 01.00271988002078
0 QZS-4
1 42965U 17062A 18123.03687811 -.00000338 +00000-0 +00000-0 0 9996
2 42965 040.5847 021.9703 0747798 270.6381 080.8370 01.00272014002079
多くの日本の若い方々が、衛星軌道について学習しようと挑戦する基本データとなることを期待します。
https://smallsats.org/tag/tle/ によれば:
OctaveないしMATLABにてTLEから瞬時の衛星軌道要素を導くコードは以下の通りです。
mu = 398600; % Earth’s gravitational parameter [km^3/s^2]
R_earth = 6378; % Earth radius [km]
J2 = 0.0010836;
we = 360*(1 + 1/365.25)/(3600*24); % Earth's rotation [deg/s]
fname = 'Raduga.txt'; % TLE file name
% Open the TLE file and read TLE elements
fid = fopen(fname, 'rb');
while ~feof(fid)
% Reading TLE File
L1 = fscanf(fid,'%23c%*s',1);
L2 = fscanf(fid,'%d%6d%*c%5d%*3c%*2f%f%f%5d%*c%*d%5d%*c%*d%d%5d',[1,9]);
L3 = fscanf(fid,'%d%6d%f%f%f%f%f%f%f%f',[1,9]);
epoch = L2(1,4)*24*3600; % Epoch Date and Julian Date Fraction
Db = L2(1,5); % Ballistic Coefficient
i = L3(1,3); % Inclination [deg]
RAAN = L3(1,4); % Right Ascension of the Ascending Node [deg]
e = L3(1,5)/1e7; % Eccentricity
omega = L3(1,6); % Argument of periapsis [deg]
M = L3(1,7); % Mean anomaly [deg]
n = L3(1,8); % Mean motion [Revs/day]
% Orbital parametres
a = (mu/(n*2*pi/(24*3600))^2)^(1/3); % Semi-major axis [km]
T = 2*pi*sqrt(a^3/mu)/60; % Period in [min]
rp = a*(1-e);
h = (mu*rp*(1 + e))^0.5; % Angular momentum
E = keplerEq(M,e,eps);
theta = acos((cos(E) -e)/(1 - e*cos(E)))*180/pi; % [deg] True anomaly
取り急ぎ、以上です。