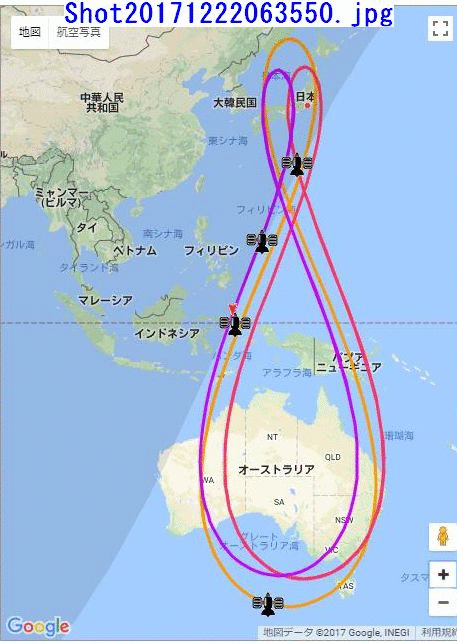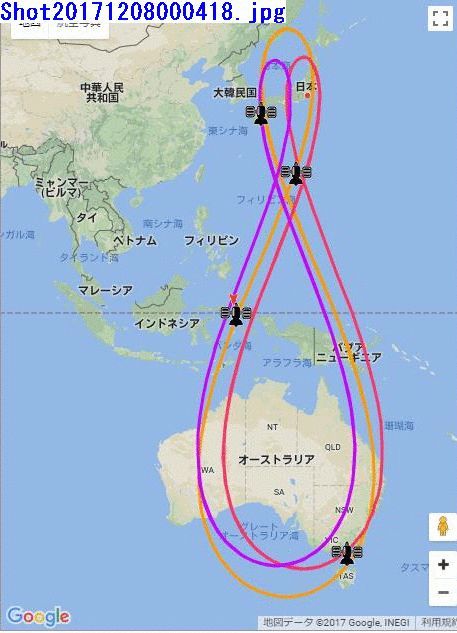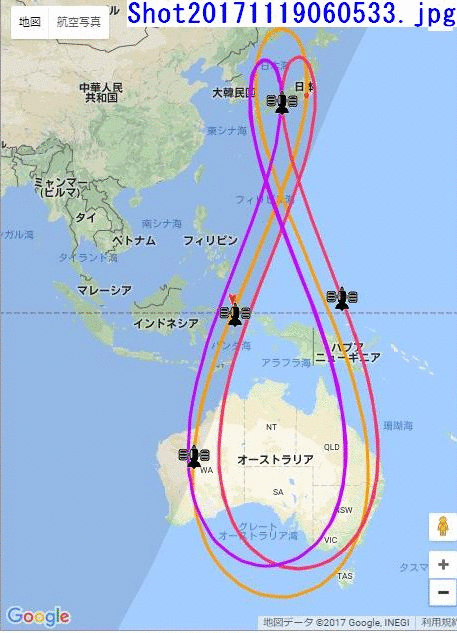サンタが南北半球の間をジグザグに飛んでいました。
なんでもアニメGIFにして記録しておくと面白いものです。
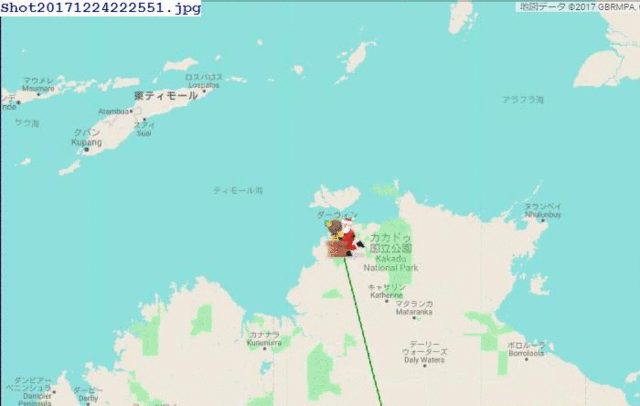
最初の出発のフィジーは日付変更線をまたぐ国、つまり一番早くXmasイブの夜が始まる国なので、出発点に選ばれたようです。最初の方は記録できなくて残念でした。
まだサンタは移動しています。大西洋を渡って、南北アメリカ間をジグザクに飛んでいます。
どこが最終点になるのでしょうか。
新東京五輪前の国内聖火リレーにおいて、もっと長期にかつ緻密にこうしたリレー走者の聖火位置情報を高精度にネットでの実時間公開をしながら、リレーできるようにすることにも参考になるかもしれません。
このサンタの例でのゲームや映像・アニメと位置情報の併用の仕方などは、老いも若きも子どもたちまでの新五輪の国民の関心を高め、持続させるために、大いに参考になるでしょう。
当然走者や聖火のセキュリティ確保や、ニセ走者情報への対策も完璧にこなすシステムにしなければいけません。それはまさにIoT自体の最大の課題です。
じっくりご覧になりたい方のための超スロー版はこちらをどうぞ。

全部の地点をくまなくでは回ったわけではないようですね。理由は不明ですが。
これだけ走り回ったトナカイの疲れきった様子は以下のムービーにて確認できます。
https://santatracker.google.com/intl/ja/tired.html
同じくサンタがみちびき衛星に遭遇するムービーもありましたよ、本当に。衛星をひっくり返して遊んでいました。大丈夫ですか、みちびき衛星さんは。あれはJ199?だったようです。
Xmasの日の座興でした。
------------------20時JST前追加:
最終点はハワイでした。ハワイでGool!となって、そしてGoogleサンタの故郷はアラスカでしたね。サモアやトンガなど西経180度に近い南太平洋島嶼国まで行ってくれると期待してましたが、ちょっと残念でした。故郷アラスカに戻って、最終盤アニメはループしています。

なんでもアニメGIFにして記録しておくと面白いものです。
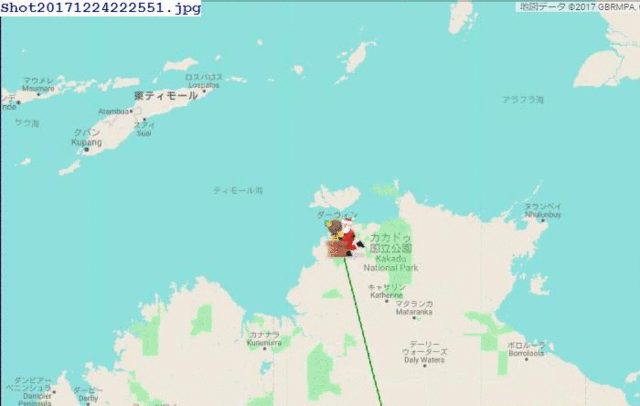
最初の出発のフィジーは日付変更線をまたぐ国、つまり一番早くXmasイブの夜が始まる国なので、出発点に選ばれたようです。最初の方は記録できなくて残念でした。
まだサンタは移動しています。大西洋を渡って、南北アメリカ間をジグザクに飛んでいます。
どこが最終点になるのでしょうか。
新東京五輪前の国内聖火リレーにおいて、もっと長期にかつ緻密にこうしたリレー走者の聖火位置情報を高精度にネットでの実時間公開をしながら、リレーできるようにすることにも参考になるかもしれません。
このサンタの例でのゲームや映像・アニメと位置情報の併用の仕方などは、老いも若きも子どもたちまでの新五輪の国民の関心を高め、持続させるために、大いに参考になるでしょう。
当然走者や聖火のセキュリティ確保や、ニセ走者情報への対策も完璧にこなすシステムにしなければいけません。それはまさにIoT自体の最大の課題です。
じっくりご覧になりたい方のための超スロー版はこちらをどうぞ。

全部の地点をくまなくでは回ったわけではないようですね。理由は不明ですが。
これだけ走り回ったトナカイの疲れきった様子は以下のムービーにて確認できます。
https://santatracker.google.com/intl/ja/tired.html
同じくサンタがみちびき衛星に遭遇するムービーもありましたよ、本当に。衛星をひっくり返して遊んでいました。大丈夫ですか、みちびき衛星さんは。あれはJ199?だったようです。
Xmasの日の座興でした。
------------------20時JST前追加:
最終点はハワイでした。ハワイでGool!となって、そしてGoogleサンタの故郷はアラスカでしたね。サモアやトンガなど西経180度に近い南太平洋島嶼国まで行ってくれると期待してましたが、ちょっと残念でした。故郷アラスカに戻って、最終盤アニメはループしています。