香は、仏教と共にわが国に伝来しました。
日本書紀には、595年に大きな沈香木が淡路島に漂着したと記されています。
また、奈良時代中頃に渡来された鑑真和上によって、様々な香料の配合が教えられました。
10世紀になると高度な唐様文化を営む貴族社会に転機が訪れました。
わが国の風土に即した懐かしさや柔らかさこそが心に響くという実感が深まります。
古今集が編まれ遣唐使を廃止し熊野詣が始まりました。
和洋化がいよいよ開花する中で、貴重な香料の配合にも独自の工夫が施され、貴族達にとって欠かすことの出来ない生活の香りとして「薫物」が愛用されることとなりました。
源氏物語や枕草子などの王朝文学には、「追い風」 「誰ヶ袖」 「伏籠」など、香りを意味する美しい表現が伝えられています。
大陸では宋・元・明と多様に文化が発展し、わが国では鎌倉から室町へ武家の時代が推移しました。
天竜寺船など積極的な交易による様々な文物は、都に集る活力ある人々の耳目を魅了し、禅宗の影響と相まって新しい価値観の具現が次々と行われました。
婆娑羅と呼ばれる気風が三代将軍足利義満による北山文化として開花し、香においては、沈香木を直接に焚香することが流行します。
15世紀には応仁の乱が起こり、都は灰燼と化し人々は精神的に限界まで追い詰められました。
激動の社会環境の中、緑豊かな東山の閑静な地に義政による山荘が営まれ、同胞衆による文化のサロンが形成されました。
連歌の宗祇、茶の湯の珠光、立花の池ノ坊、古今伝授の三条西実降、佐庭の阿弥、そして聞香の志野宗信などが義政を囲んだと伝えられます。
北山文化では観阿弥と世阿弥が義満と出会い能楽を大成しました。
東山文化に源を発する多くの文化的潮流の一つとして香も知られ、実隆と宗信が聞香の始祖として名を残してます。
徳川家康による江戸開幕で太平の世を迎え、琉球貿易から発展した南蛮交易が大きく展開されました。
アジアの各地に日本人町が形成されたのはこの時代です。多様な文物と共に香木もたくさん舶載され、立花や茶の湯と共に聞香も堂上公家社会の興味を集めました。
寛永の文芸復興に大きく寄与した香は、高度な王朝教養文化と融合し、今日、香道と呼ばれる芸道文化を奥深い世界へと熟成させたのでした。
江戸時代を通じて、大名社会における女人の教養文化として認知され、豪商などを通じて徐々に町衆などにも知られるものとはなりましたが、鎖国の続く中ほとんど実際に手にすることは叶わず、「伽羅」 「栴檀」など貴重な香を意味する言葉が形容詞としてもてあそばれる様にもなりました。
江戸時代初期には、細く線状に作る線香の製造技術が伝来し、時を同じくして施行された檀家制度と相まって線香は広く生活の具として利用されるようになりましたが、香料の希少性が高まり、廉価なものとして普及してしまいました。
明治維新以降の西欧化の中、古典的な香の文化をいとおしむ人々は細々とその美しさを伝承してきました。
今改めて、わが国の文化が再評価される中、香の伝統も現代的な工夫と共に新たな愛好家を得ています。
[松榮堂社長・畑 正高氏]
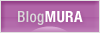
応援クリックお願いします!!













