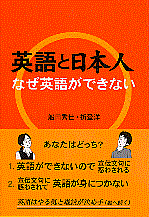"Taxpayer's Money" に次いで、公共放送とは名ばかり、肥大化し、法外な受信料を徴収するNHKについて書くと、前回言いましたが、これらの日本の社会的問題同様、このブロッグの表題になっている、もう一つの問題を今回優先することにしました。「英友社」の話は、また先延ばしにしますが、この話は、「英友社」の話以上に先延ばしになっている「英友社ランゲージスクール」の開校が日の目を見た時の記念に取っておこうかなとも思っています。
これまで、日本人の英語に対する認識についての書、『英語と日本人 なぜ英語ができない』 (英友社、2007年)を、名城大学教授、船田先生との共著によって出版することができたと、たびたび紹介してきました。また私は私なりに、当ブロッグで、この国の英語教育についていろいろ書き、また批判してきました。しかし、相変わらず堂々巡りに終わっています。
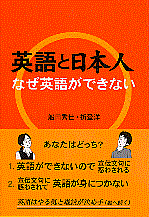
ここ20年間のデフレと経済の低迷(『 「10年一昔」、「20年二昔」 以上でした』〈2013年12月20日〉参照)で、日本の世界での影響力の低下を憂うことから、今や国中で、改革だ!変革だ!という言葉がマスコミ挙げて飛び交っていますが、英語教育は微動だにしません。私がイタリアから帰国して日本の英語教育の惨状を目にしたのは、実に40年以上も前のことです。受験用英文法中心、大学の英文学教授による学術論文のような難しい教材や英米文学の著書の抜粋が、中・高校生に与えられていました。
この状況を何とかしなければと、私は、「英友社」から英語学習参考書として、松本亨氏の著書の他に、以下の書籍を出版しました。この中で、最も市場に受け入れられたのは、3.の『アメリカ口語英語〈発音とヒヤリングの演習〉』(正編)でした。
- 『私が採点する日本の英語(English: A National Disaster)』(1974年、Donald Harrington著)
- 『なぜ英語が聞きとれない、話せない』(1979年、Gregory Stricherz著)
- 『アメリカ口語英語〈発音とヒヤリングの演習〉・正編 (Real American Pronunciation)』(1980年、Gregory Stricherz著)
近年、使える英語の教育ということで、かなり改善されてきたものの、机上の空論の域を出ず、小学生英語と検定英語(英検、TOEIC)を偏重することでお茶を濁しています。その実態は大型書店に行って英語関連の書棚を見れば一目瞭然です。また、それを助長する一般企業の動き(「英語が社内公用英語になるという怖~い話」〈2010年8月26日〉参照)が、「グローバル人材の育成」などという錯覚にすり替えられ、英語という外国語が、外国を知らない日本人の思考を汚染しています。
帰国後、教材の不備とは別に、日本人の英語下手は何が起因しているのかずっと自問自答してきました。その答えを引き出すために、かつて、東京で英語教師をしていたストリカーズ氏に相談、彼の私見を著したのが、上記の 『なぜ英語が聞きとれない、話せない』 でした。今、振り返ってみると、本書の最終章に、氏が述べた一節が当を得ていることに改めて思いを致しています。それは、日本人自体に主因があると、氏は洞察していたのです(「口下手で社交下手な日本人が英語を話すとき」〈2010年10月11日〉参照)。
その後も、日本人の英語に対する「不可思議な意識」について、頭がくらくらするぐらい自問自答を繰り返してきた結果、日本人の「コミュニケーション能力の欠落」にあることに、最近やっと気が付きました。日本人が英語のみならず外国語(外国人との交流)を苦手とするのは、長年培ってきた(?)閉鎖社会、村社会の産物である、日本の文化に欠ける、生の人間と人間との交流方法、つまり、コミュニケーション(日本語に訳せない)の術(すべ)を知らないのです。これまで、「意思疎通」 という表現が日本社会に於ける 「人と人同士の言葉による交流」 を代弁している、と思っていたら、辞書を引いて見て驚きました。
「意思疎通」とは、「意思の疎通を図る」、つまり相手に自らの意思を伝えることを言い、「自身と相手の考えとの交流または互いに伝え合う」 意味ではないことを、恥ずかしながら初めて認識したのです。
「意思の疎通」と「コミュニケーション」は同義語ではない
これまで述べたように、近年やっと、技術的なことより、コミュニケーション能力の育成が英語の習得に必要であるということが認識されてきましたが、「コミュニケーション(communication)=名詞」というカタカナ語と同義語の日本語は有りません。「コミュニケーション」 は、「伝達」 「連絡」 のように和訳されていますが、実は「考え、感情を伝える作業」が本来の英語の意味なのです。また、英語の「コミュニケート(communicate)=動詞」の意味は「(先方と)情報を交換する」(to exchange information, news, ideas, etc. with somebody=Oxford 現代英英辞典) が、第一の意味ですが、この言葉に相当する日本語も有りません。日本語で「コミュニケーション」に最も近い言葉は「意思の疎通」ですが、この意味は、上記の「自分の意思を先方に理解させる」「自分の意思が支障なく相手に通じる」で、「先方と情報を交換する」というのとは、全く違います。ですから、カタカナ語で代替しても本来の意味を伝えきっていません。
日本人が英語をはじめ欧米語の習得が苦手なのは、語順の違いという文法や日本語に無い発音の問題などがありますが、それよりも、下に述べる日本の特異な言語文化が影響しています。その典型的な例に、最近、日本の大手製薬会社の社長が会長に退いて、外国人(イギリス人)を社長に迎えたのですが、某経済誌のインタビューに、「彼(社長)は、コミュニケーションを(社員に対し)非常に重視する人ですが、私は、日本人の以心伝心に甘えていたところがある」のように述べていました。つまり、「意思の疎通」「以心伝心」「腹芸」などは、日本的な人間関係を表す言葉で、英語で表わす人間関係と同等ではありません。
注:上記の説明でお分かりでしょうが、一般に使われている「コミュニケーション能力」よりも「コミュニケートする能力」と、動詞用法を使う方が正しいでしょう。皮肉なことに、TOEIC (Test of English for International Communication) は、和訳すると「国際間での意思疎通(交流)のための英語(能力)試験」ということでしょうが、ここでのコミュニケーションは、私には「交流」としか訳せません。国際交流するために英語の試験をするというのは、何か変ではありませんか?TOEIC とは、「日本で、日本人が、日本人のために(どこかで聞いたことがあるような…)考案した英語の試験」としか私には考えれないのですが、いかがでしょう。言い換えれば、日本人用の英語試験、つまり、日本人だけに通用する英語の試験、さらに言えば、金儲けのための試験です。TOEFL (Test of English as a Foreign Language) は、英語圏(主にアメリカとカナダ)の大学・大学院に入学して学業を修めるだけの英語力があるかどうか認定する試験です。難易度は、当然、前者よりもこちらの方がずっと難しいようです。世界180カ国での日本人の平均点は、下から数えた方が早いという結果になっています。TOEIC については、日を改めて話したいと思います。
なぜ日本には「情報を交換する」という言葉が存在しないのか?
- 日本は四方を海に囲まれた島国で、他国・他民族から侵略されず、その必要がなかった。
- ヨーロッパ大陸のような異文化・異民族・異宗教との紛争・抗争を経験していないので必然性がなかった。
- 日本人同士の紛争・抗争は身内の出来事で、異文化・異民族・異宗教同士のそれとは違うのでその必要がなかった。
つまり、島国ゆえに身内同士が分かり合えることで事足りたのです。
「情報を交換する」ということは、情報をやり取りすることで、情報を発信する側と受ける側があり、転じて受ける側が発信する側になり、一方通行にならないことですが、残念ながら、日本では言葉でのやり取りよりも、上に述べた事情から「以心伝心」または「意思の疎通」で物事を処理する伝統文化が発達しました。この文化の最大の弱点は、言葉で互いに交信する能力が極端に劣る事です。さらに重大な問題は、日本人がその事実を自覚していないことです。
英語難民を量産し続ける日本の英語教育
英語検定試験に汚染された日本の英語を、私は「張りぼて英語」と呼んでいます。なぜならば、中身がない英語だからです。英検の等級やTOEICの得点を競うだけで、受験者が実際に、不特定多数の外国人に対し、英語で意見や意思の交換をする能力は試されていないからです。
今年の3月17日に、以下のような調査結果が文部科学省によって公表されました。
国公立の高校3年生約7万人を対象に英語の実力を調査した結果、その実力は中学卒並みであると判明。また英語が嫌いな生徒は全体の60%近くに上る。
日本の英語教育は、毎年、私の言うところの「張りぼて英語」と「英語難民」を量産している上、副産物に大量の「英語嫌い」を生じさせています。このみじめな状況から「英語難民」を救出するために、「英友社」は、40年間奮闘してきましたが、書籍の出版で目的を達成させるには限界があり、やっと「英友社ランゲージスクール」で、結果を出せると確信するまでに至りました。
無策な英語教育の垂れ流しは「国家的損失」
日本人が言葉で発信・交信する能力の低い事が、日本に詐欺まがいの英語産業を蔓延させています。「聞き流すだけで英語が上達」などの宣伝文句は、ちょっと理性を働かせば、あり得ない事ですが、儲かるのでしょう、毎日のようにマスメディアをにぎわせています。その一方で、NOVA のような英語学校の破たんがありました。日本の英語産業は、まるで振り込み詐欺のような社会現象を生んでいます。
このような事態は、日本の 「国家的損失」であると、私は見ています。文部科学省は、上に述べた、日本の文化的背景の深層や実態を把握しようとしないために、先に述べた 「英語難民」 と 「英語嫌い」 を量産しています。
日本は「能」や「浄瑠璃」のように抑圧した言語表現を伝統文化とするのに対し、「オペラ」や「ミュージカル」のように最大限の、時には誇張した言語表現を売り物にするのが欧米の文化です。英語検定試験が英語上達の道のように国を挙げて推奨するのは、「英語亡国」への道です。
上記 1. の 『私が採点する日本の英語(English: A National Disaster)』 は、「Japan Times社」出版の「Student Times」紙に連載された、ハリントン氏の日本の英語教育を批判したコラム記事を、同社の許可を得て1974年に再編出版したものですが、この本の英語の表題 "English: A National Disaster" (英語:国家の大惨事)は、40年前も今も、膨大な時間と金を、一外国語の英語の習得に費やしているのは、まさしく「国家的大惨事」であることを文部科学省も英語教育界も肝に銘ずべきです。しかし残念ながら、それを望むことはまず無理でしょう。英語ができれば、グローバルな人材になれるなど、おかしな考えが広まっている国ですから。
寡黙対冗舌(饒舌)
寡黙を美徳とし冗舌を良しとしない文化は、日本に長い間にわたって根付いた文化です。民族性ともなっているこの文化的特性は、今も変わらず受け継がれています。戦後、アメリカの影響で学校教育などにいくらか変化が見られるものの、前述したように、発信する側(教師)と受信する側(生徒)との関係は、伝統的な状況が続いているのではないでしょうか。つまり 「意思疎通」 です。
「ものづくり」の文化は、日本を世界第2位の経済大国にし、この事実は、大いに讃えられてよいことですが、これは日本人の「勤勉さ」と「真面目さ」によるものです。しかし、職人気質とも言える寡黙の美徳そのものが「コミュニケートする能力」を妨げていることも事実です。残念ながら「寡黙の文化」と「コミュニケートする文化」は両立しません。
バイカルチュラルの推奨
上記 『英語と日本人 なぜ英語ができない』の「第1部」、「第2章」の 6.「バイリンガルよりバイカルチュラル」(77頁)で、日本人にとって、英語並びに外国語の習得にその必要性を詳述してあります。ここでは長くなるので、割愛しますが、日本という閉鎖社会の人間関係、例えば、サラリーマン社会における言葉の交流は、日本特有であると言っても過言ではありません(「英語を話すときは英語の生活感覚で」〈2008年07月25日〉参照) 。
このたび 「英友社ランゲージスクール」を立ち上げるに当たり、その指導内容の心臓部となる方針に心を砕きました。その根幹を形成するものは、バイカルチュラルの指導です。バイカルチュラルは、英語で biculturalと書き、2文化の、2文化併存の、といった意味があります。
私自身がバイカルチュラルな人間なので、卑近な言葉で言うと「アメリカかぶれ」なので、バイカルチュラルとはどういうことか、実体験者として 「英友社ランゲージスクール」 を開校すれば、効果的な指導ができるのではないかと自負しています。今年中に実現できれば、と奮闘しています。
長くなりましたが、私としては、上記した書籍で言い足りなかったことを、皆さんにどうしても伝えたかったのです。
次回は、モンスター化したNHKです。