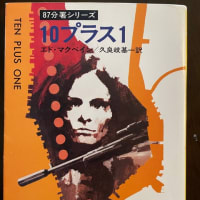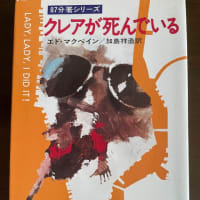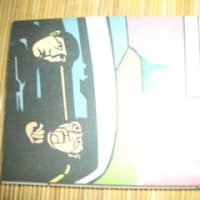本ブログのカテゴリのうち、『思考機械』(その84定吉七番は永遠に)で、記したものの追加です。
批判ばかりでは、どこぞの国の政党みたいで、あまりにも情けなく、探偵小説好事家と自称しているのならと、わたくしのそれについて挙げさせていただきます。
国産探偵小説については、以前同様に近い趣向のものをとりあげていますので、今回は翻訳探偵小説に絞ってみました。
それでは、まずは、これ。
J・P・マンシェット『狼が来た、城へ逃げろ』
何度か書いたかもしれませんが、わたくしは自分の性格がそうだからかもしれませんが、ねちねちしたフランスの探偵小説が大嫌いで毛嫌いしていたのですが、これを読んでびっくり。フランス産探偵小説を見直しました。(でも、今になって思うと、結局好きだったのは、マンシェット作品だけだったのですが。)
ネットで調べてみたら、改訳改題で翻訳が出ているようですね。
二番めは、これです。
ジェフリー・ハウスホールド『影の監視者』
1960年作らしいけれども、その十年後の1970年の訳書ですから、対象作品の候補には当てはまりますよね。
代表作と謂われる『追われる男』ばかりに注目が集まっているようですが、これも、傑作のひとつです。
最後は、これ。
ルシール・フレッチャー『スタンフォードへ80ドル』
じつは、カトリーヌ・アルレー『目には目を』を推すつもりだったのですが、1960年作の1961年翻訳で、対象期間から外れていました。
『スタンフォードへ80ドル』は、見過ごされがちな、いかにもしゃれた都会風のサスペンスで、日本でも映像化したそうですね。小ぶりな作品ですが、お薦めです。
最後に、おおもとの企画では、三作品の選出となっていたようですが、わたくしは企画に参加していません(呼ばれてもいません)ので、あえて四番めに、とっておきの、
ルイ・C・トーマの、・・・
と、思ったのですが、残念ながら、書名が出てきません。
たぶん『死のミストラル』ではなかったかと思うのですが、案外『悪魔のようなあなた』かもしれませんし、ひょっとすると『カトリーヌはどこへ』かも。
しかしながら、最終てきには、わたくしは、岡村孝一氏の翻訳書が一等の好みだったようです。
批判ばかりでは、どこぞの国の政党みたいで、あまりにも情けなく、探偵小説好事家と自称しているのならと、わたくしのそれについて挙げさせていただきます。
国産探偵小説については、以前同様に近い趣向のものをとりあげていますので、今回は翻訳探偵小説に絞ってみました。
それでは、まずは、これ。
J・P・マンシェット『狼が来た、城へ逃げろ』
何度か書いたかもしれませんが、わたくしは自分の性格がそうだからかもしれませんが、ねちねちしたフランスの探偵小説が大嫌いで毛嫌いしていたのですが、これを読んでびっくり。フランス産探偵小説を見直しました。(でも、今になって思うと、結局好きだったのは、マンシェット作品だけだったのですが。)
ネットで調べてみたら、改訳改題で翻訳が出ているようですね。
二番めは、これです。
ジェフリー・ハウスホールド『影の監視者』
1960年作らしいけれども、その十年後の1970年の訳書ですから、対象作品の候補には当てはまりますよね。
代表作と謂われる『追われる男』ばかりに注目が集まっているようですが、これも、傑作のひとつです。
最後は、これ。
ルシール・フレッチャー『スタンフォードへ80ドル』
じつは、カトリーヌ・アルレー『目には目を』を推すつもりだったのですが、1960年作の1961年翻訳で、対象期間から外れていました。
『スタンフォードへ80ドル』は、見過ごされがちな、いかにもしゃれた都会風のサスペンスで、日本でも映像化したそうですね。小ぶりな作品ですが、お薦めです。
最後に、おおもとの企画では、三作品の選出となっていたようですが、わたくしは企画に参加していません(呼ばれてもいません)ので、あえて四番めに、とっておきの、
ルイ・C・トーマの、・・・
と、思ったのですが、残念ながら、書名が出てきません。
たぶん『死のミストラル』ではなかったかと思うのですが、案外『悪魔のようなあなた』かもしれませんし、ひょっとすると『カトリーヌはどこへ』かも。
しかしながら、最終てきには、わたくしは、岡村孝一氏の翻訳書が一等の好みだったようです。