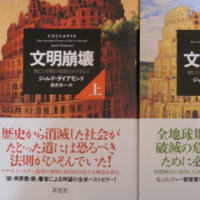今回は、重松清『その日のまえに』(文藝春秋)です。
まだ文庫化はされてなかったかな(2006年11月現在)。読みたいけど文庫落ちしてないしなぁと思ってると、図書館でハケーンヽ(゜∀゜)ノ
このごろ重松作品、はまってるなぁ・・・。
それと、読みたい本が丁度図書館に返却されてて、実に有難い限りです(笑)
--------あらすじ--------
僕たちは「その日」に向かって生きてきた
男女が出会い、夫婦になり、家族をつくって、幸せな一生なのか。消えゆく命の前で、妻を静かに見送る父と子。感動の重松ワールド (出版社 / 著者からの内容紹介)
--------------------
ストレートに「死」をテーマにした、連作短編集です。でも、だからと言って
ベタなお涙頂戴小説と思わないで欲しい。
何たらかんたらと物語があって、結果的に死んじゃったね。悲しいね。という小説ではないです。そんなオチじゃないの。
はじめっから「死」そのものがテーマなんです。真っ正面から「死」と向き合った小説です。
【1. ひこうき雲】
アルツハイマーが進行した祖母を見舞うために、郊外の介護施設へ向かって電車に揺られながら、小学生の子どもがいる「僕」が語る思い出。
小学生の頃、クラスの同級生「ガンリュウ」というあだ名の女の子が入院したときの話。強くて、口が悪くて、無愛想な「ガンリュウ」。ちっとも病気をしそうなタイプじゃない。彼女を見舞い、クラス全員で書いた色紙を渡したときも、「ガンリュウ」はやはり「ガンリュウ」だった。でも、読んでいた文庫本に目を落とした瞬間、「ガンリュウ」の目から涙がこぼれ落ちた。
私、実は人を見舞った経験がほとんどないんですよ。いつも見舞われる側。小さい頃から何度も入院してました。
小さいときは、いわゆる「こども病院」に入院してて、ああいう病院って結構面会時間の制限が厳しいんですよ。子どもしか入院してないから、あんまり親がべったり面会に来ると、面会に来られない子どもが可哀想ということもあったのかな。
それで、午後3時か4時くらいに面会時間が終わる頃の病棟の雰囲気。どこかから必ず小さい子の泣き声が聞こえて、みんなの顔がふっと暗くなって、親が帰っていく姿を窓から見たりしてね。でも入院に慣れてる子は悟ったように何でもない顔をしてたりして。
あの頃仲良くなった子、もしかしたら亡くなってる子もいるのかもしれないな・・・と、読みながら思っちゃったりしました。
だから、私は「ガンリュウ」目線で読んでたなぁ。
見舞われるのって結構大変なんですよ(笑) 準備も要るし。何でもないよって顔を作って、不安な顔を隠して、嬉しそうな笑顔を用意しなきゃいけない。だから私は、親以外の見舞いは、嬉しいけど少し苦手だったなぁ。今もだけど。
病院でもやはり無愛想だった「ガンリュウ」は、頑張って用意したもので、流した涙は、用意した顔の割れ目から覗いた「ガンリュウ」の本当の顔なのかなという気がしています。
【2. 朝日のあたる家】
高校の教師をしている「ぷくさん」。彼女は旦那を突然亡くしている。他の物語では死について話し合ったり考える時間があったが、ぷくさんと旦那さんはその時間もなかった。
そんなぷくさんに、元教え子の問題が舞い込む。
【3. 潮騒】
末期癌で余命3ヶ月の宣告を受けた俊治。鉄道の路線図で、小学生の頃過ごした懐かしい地名を発見し、何となくやってきた。そして、ガキ大将だった石川と再会し、小学生の頃に海で溺死した、同級生の友達オカちゃんの話をする。
【4. ヒア・カムズ・ザ・サン】
トシと母ちゃんは、母子家庭歴15年。最近母はストリートでグレゴリオ聖歌を歌う風変わりなストリートミュージシャン、カオルくんにお熱だ。
その母が癌になった。でも、母はトシに直接伝えずにある賭けをする。一つ目はトシがカオルくんに会いに来るか、二つ目はトシが家にある「家庭の医学」を読むか。この母がなかなか面白くて、すごく切ない。
「完璧に隠しとおすほどの強さもなくて、ちらっと思わせぶりなことを言ったりする、そんな母ちゃんの弱さとか、情けなさとか、甘ったれたところが、なんか笑えて、だめじゃん母ちゃん、と肘で小突いてやりたくて、母ちゃんのこと、俺、かわいいと思う。」 (P157,158)
この言葉、ものすごく好きです。読みながら「泣き笑い」みたいになってしまいました。
私、この「ヒア・カムズ・ザ・サン」は、この小説で一番好きだし、一番泣いた。お茶目で、ちょっとダメダメな母ちゃんとトシの掛け合いが、すごい面白いのに、すごいあたたかくて、哀しくて、良かったです。
この後の「その日」シリーズで登場する和美さんは、時間をかけてゆっくり死と向き合い、「その日」(死ぬ日)のためにやれることをやっておこうという話だから、すごく冷静で強いです。それに対して、この母ちゃんは、弱くて、強がって、心配性で、すごく「普通」で、かえって親近感がわいて魅力的でした。
【5. その日のまえに】
5,6,7は、3つでひとつの物語です。
和美と僕が新婚時代に生活をした町を歩く。
最後の思い出作りであると同時に、「その日」を迎える決意を固める旅でもあった。
【6. その日】
和美の「その日」の家族の話。
僕と和美は「その日」を迎えるに当たって、色々な準備や約束をしてきた。和美は子どもたちには自分の病気のことは話さないで、と決めた。でも僕はその約束を破る。
病院から「朝から詰めていてください」という連絡を受け、僕は中学生の健哉・小学生の大輔を連れて、病院へ向かう。
【7. その日のあとで】
和美が死んだ後の話。
和美を喪ったあとの、僕・健哉・大輔の三者三様の思いの表し方が良いです。和美宛のダイレクトメールなど母を思い出すものを嫌う健哉、みんなとママの話をしたくてしょうがない大輔、そして和美の面影が小さくなっていくことを自覚しながら、日常生活を送っている僕。
「その日」から3ヶ月目のある日、和美が良くしてもらっていた看護婦から、僕に電話が入る。和美からの手紙を預かっている、とのことだった。その手紙には、たった一言。
「忘れてもいいよ」 (P268)
この言葉を素直に受け取れるかは分からない。
私はまだ大切な人を亡くした経験はないから、そのときもしこう言われても何と答えるか分からない。「忘れたりしないよ!!!」って反論するかもしれない。
でも、大切な人の死を乗り越えるって、こういうことかもしれないなと思った。常にそばにいて思い出す状態っていうのは、まだ乗り越えていないということなのかな。本当に死を乗り越えたっていうのは、日常忘れているけど、ちゃんと心の奥では存在しているっていう状態なのかもしれませんね。
「『その日』を見つめて、最後の日々を過ごす人は、実は幸せなのかもしれない、って。自分の生きてきた意味や、死んでいく意味について、ちゃんと考えることができますよね。あとにのこされるひとのほうも、そうじゃないですか?」 (P279)
うん。こういうふうにきちんと考えて、話し合って死ねるのは幸せなのかもしれないな、と私も思いました。
最後の「その日」シリーズでは、それ以前の物語の登場人物がちょいちょい脇役で登場します。
例えば、「ヒア・カムズ・ザ・サン」の母ちゃんとトシくんとか、「潮騒」の石川とか。それぞれの物語で語られた後日談のような感じで登場するのですが、いや~重松清さん、本当に上手いなぁと思ってしまいました。普通に「短編集」だと思っていたら、最後みんな登場してくるので驚きました。
この小説の魅力をうまく伝えられたかは分かりませんが、本当にオススメです!是非読んでみてください!絶対損はないと思います。
まだ文庫化はされてなかったかな(2006年11月現在)。読みたいけど文庫落ちしてないしなぁと思ってると、図書館でハケーンヽ(゜∀゜)ノ
このごろ重松作品、はまってるなぁ・・・。
それと、読みたい本が丁度図書館に返却されてて、実に有難い限りです(笑)
 | その日のまえに 重松 清 文藝春秋 2005-08-05 by G-Tools |
--------あらすじ--------
僕たちは「その日」に向かって生きてきた
男女が出会い、夫婦になり、家族をつくって、幸せな一生なのか。消えゆく命の前で、妻を静かに見送る父と子。感動の重松ワールド (出版社 / 著者からの内容紹介)
--------------------
ストレートに「死」をテーマにした、連作短編集です。でも、だからと言って
ベタなお涙頂戴小説と思わないで欲しい。
何たらかんたらと物語があって、結果的に死んじゃったね。悲しいね。という小説ではないです。そんなオチじゃないの。
はじめっから「死」そのものがテーマなんです。真っ正面から「死」と向き合った小説です。
【1. ひこうき雲】
アルツハイマーが進行した祖母を見舞うために、郊外の介護施設へ向かって電車に揺られながら、小学生の子どもがいる「僕」が語る思い出。
小学生の頃、クラスの同級生「ガンリュウ」というあだ名の女の子が入院したときの話。強くて、口が悪くて、無愛想な「ガンリュウ」。ちっとも病気をしそうなタイプじゃない。彼女を見舞い、クラス全員で書いた色紙を渡したときも、「ガンリュウ」はやはり「ガンリュウ」だった。でも、読んでいた文庫本に目を落とした瞬間、「ガンリュウ」の目から涙がこぼれ落ちた。
私、実は人を見舞った経験がほとんどないんですよ。いつも見舞われる側。小さい頃から何度も入院してました。
小さいときは、いわゆる「こども病院」に入院してて、ああいう病院って結構面会時間の制限が厳しいんですよ。子どもしか入院してないから、あんまり親がべったり面会に来ると、面会に来られない子どもが可哀想ということもあったのかな。
それで、午後3時か4時くらいに面会時間が終わる頃の病棟の雰囲気。どこかから必ず小さい子の泣き声が聞こえて、みんなの顔がふっと暗くなって、親が帰っていく姿を窓から見たりしてね。でも入院に慣れてる子は悟ったように何でもない顔をしてたりして。
あの頃仲良くなった子、もしかしたら亡くなってる子もいるのかもしれないな・・・と、読みながら思っちゃったりしました。
だから、私は「ガンリュウ」目線で読んでたなぁ。
見舞われるのって結構大変なんですよ(笑) 準備も要るし。何でもないよって顔を作って、不安な顔を隠して、嬉しそうな笑顔を用意しなきゃいけない。だから私は、親以外の見舞いは、嬉しいけど少し苦手だったなぁ。今もだけど。
病院でもやはり無愛想だった「ガンリュウ」は、頑張って用意したもので、流した涙は、用意した顔の割れ目から覗いた「ガンリュウ」の本当の顔なのかなという気がしています。
【2. 朝日のあたる家】
高校の教師をしている「ぷくさん」。彼女は旦那を突然亡くしている。他の物語では死について話し合ったり考える時間があったが、ぷくさんと旦那さんはその時間もなかった。
そんなぷくさんに、元教え子の問題が舞い込む。
【3. 潮騒】
末期癌で余命3ヶ月の宣告を受けた俊治。鉄道の路線図で、小学生の頃過ごした懐かしい地名を発見し、何となくやってきた。そして、ガキ大将だった石川と再会し、小学生の頃に海で溺死した、同級生の友達オカちゃんの話をする。
【4. ヒア・カムズ・ザ・サン】
トシと母ちゃんは、母子家庭歴15年。最近母はストリートでグレゴリオ聖歌を歌う風変わりなストリートミュージシャン、カオルくんにお熱だ。
その母が癌になった。でも、母はトシに直接伝えずにある賭けをする。一つ目はトシがカオルくんに会いに来るか、二つ目はトシが家にある「家庭の医学」を読むか。この母がなかなか面白くて、すごく切ない。
「完璧に隠しとおすほどの強さもなくて、ちらっと思わせぶりなことを言ったりする、そんな母ちゃんの弱さとか、情けなさとか、甘ったれたところが、なんか笑えて、だめじゃん母ちゃん、と肘で小突いてやりたくて、母ちゃんのこと、俺、かわいいと思う。」 (P157,158)
この言葉、ものすごく好きです。読みながら「泣き笑い」みたいになってしまいました。
私、この「ヒア・カムズ・ザ・サン」は、この小説で一番好きだし、一番泣いた。お茶目で、ちょっとダメダメな母ちゃんとトシの掛け合いが、すごい面白いのに、すごいあたたかくて、哀しくて、良かったです。
この後の「その日」シリーズで登場する和美さんは、時間をかけてゆっくり死と向き合い、「その日」(死ぬ日)のためにやれることをやっておこうという話だから、すごく冷静で強いです。それに対して、この母ちゃんは、弱くて、強がって、心配性で、すごく「普通」で、かえって親近感がわいて魅力的でした。
【5. その日のまえに】
5,6,7は、3つでひとつの物語です。
和美と僕が新婚時代に生活をした町を歩く。
最後の思い出作りであると同時に、「その日」を迎える決意を固める旅でもあった。
【6. その日】
和美の「その日」の家族の話。
僕と和美は「その日」を迎えるに当たって、色々な準備や約束をしてきた。和美は子どもたちには自分の病気のことは話さないで、と決めた。でも僕はその約束を破る。
病院から「朝から詰めていてください」という連絡を受け、僕は中学生の健哉・小学生の大輔を連れて、病院へ向かう。
【7. その日のあとで】
和美が死んだ後の話。
和美を喪ったあとの、僕・健哉・大輔の三者三様の思いの表し方が良いです。和美宛のダイレクトメールなど母を思い出すものを嫌う健哉、みんなとママの話をしたくてしょうがない大輔、そして和美の面影が小さくなっていくことを自覚しながら、日常生活を送っている僕。
「その日」から3ヶ月目のある日、和美が良くしてもらっていた看護婦から、僕に電話が入る。和美からの手紙を預かっている、とのことだった。その手紙には、たった一言。
「忘れてもいいよ」 (P268)
この言葉を素直に受け取れるかは分からない。
私はまだ大切な人を亡くした経験はないから、そのときもしこう言われても何と答えるか分からない。「忘れたりしないよ!!!」って反論するかもしれない。
でも、大切な人の死を乗り越えるって、こういうことかもしれないなと思った。常にそばにいて思い出す状態っていうのは、まだ乗り越えていないということなのかな。本当に死を乗り越えたっていうのは、日常忘れているけど、ちゃんと心の奥では存在しているっていう状態なのかもしれませんね。
「『その日』を見つめて、最後の日々を過ごす人は、実は幸せなのかもしれない、って。自分の生きてきた意味や、死んでいく意味について、ちゃんと考えることができますよね。あとにのこされるひとのほうも、そうじゃないですか?」 (P279)
うん。こういうふうにきちんと考えて、話し合って死ねるのは幸せなのかもしれないな、と私も思いました。
最後の「その日」シリーズでは、それ以前の物語の登場人物がちょいちょい脇役で登場します。
例えば、「ヒア・カムズ・ザ・サン」の母ちゃんとトシくんとか、「潮騒」の石川とか。それぞれの物語で語られた後日談のような感じで登場するのですが、いや~重松清さん、本当に上手いなぁと思ってしまいました。普通に「短編集」だと思っていたら、最後みんな登場してくるので驚きました。
この小説の魅力をうまく伝えられたかは分かりませんが、本当にオススメです!是非読んでみてください!絶対損はないと思います。