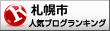小栗判官
小栗判官
「小栗判官(おぐりはんがん)」という物語をご存知でしょうか。
(私は知りませんでした。汗)
妻・照手姫の一門に殺された小栗が閻魔大王の計らいで蘇り、
姫と再会し、一門に復讐するという話で、説教節の代表作であり、
浄瑠璃や歌舞伎などにもなったりしました。
「小栗判官」の伝承はかなりの相違が見られるものの、各地に残っており、
街道の名前や川などの名の由来となっています。
 伝承のある地
伝承のある地
日本各地に伝承されているということなので、ちょっと調べてみました。
- 相模原市(神奈川県) 榎神社、照手姫遺跡の碑など
- 大垣市(岐阜県) 照手姫の水汲み井戸
- 田辺市(和歌山県) 小栗判官蘇生の地、湯の峰温泉、力石、車塚、蒔かずの稲
- 米原市(滋賀県) 白清水(しろしょうず)
- 筑西市(茨城県) 小栗判官まつり
などなど。
 横浜市金沢区の場合
横浜市金沢区の場合
ここ横浜市金沢区(神奈川県)にも小栗判官の妻、照手姫の伝説が残されています。 興味のある方は廣瀬隆夫氏のブログ「侍従川の話」内にある、
興味のある方は廣瀬隆夫氏のブログ「侍従川の話」内にある、
「照手姫ものがたり」をご覧ください。
伝説が残っているのは
(1)侍従川
照手姫の乳母の名からつけられた川。
照手姫はここで追手につかまり、川に投げ込まれたが、観音様の力により、奇跡的に助かる。
(2)姫小島水門
姫の美しさに嫉妬した漁師の妻が姫を松にしばり付け、松の青葉でいぶし殺そうとした。
観音様の力により風が吹き、助かる。
(3)千光寺
侍従川に投げ込まれた照手姫を救ったのが、こちらのご本尊・十一面千手観音様と言われている。
となっています。
 姫小島水門
姫小島水門
色々調べてみたところで、今回は「姫小島水門」に行ってみました。


「ダイエー金沢八景店」のすぐそばにあります。

姫小島の姫は照手姫のことだったのですね。

姫小島の水門です。

姫小島水門は永島家6代目段右衛門が金沢入江新田開発のために造ったものと言われています。
新田開発は干潟を埋め立てて行ったため、満ち潮の時に海水の流入をどのように防ぐかという問題が発生しました。
この水門は門扉が海側にのみ開閉するため、潮が満ちれば水門が閉じ、
干潮の時には開いて川の水が流れ出るようになっていました。
江戸時代では中央が左右に開く観音式の水門が主流であったため、
大きい上に、下側が開く姫小島水門は大変貴重とのことです。
照手姫のお話と江戸時代の土木建築として貴重な遺構である水門の両方を
後世に伝えていくために整備された「姫小島水門」はちょっと目立たないのですが、
こちらに設置された水門の説明板は素晴らしく、一読する価値のあるものとなっています。
ダイエーにお買い物ついで、あるいは図書館からの帰りにでもぜひ、立ち寄ってみてください。
 参考文献
参考文献
『横浜金沢魅力帳』(横浜市金沢区地域振興課 発行)