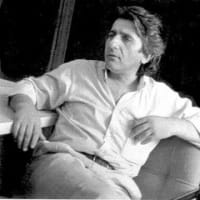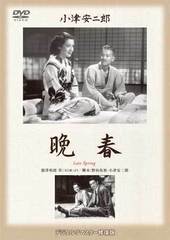
■『晩春』 (1949年/松竹) 小津安二郎 監督
●ミシン-(1)
銀座へ出た紀子(原節子)は、偶然、父(笠智衆)の友人・小野寺(三島雅夫)と再会します。その際、交わされる会話には《ミシン》という言葉が出てきます。キーワードです。
21=銀座の舗道
小野寺 「おお、やってるんだね絵の個展、行ってみようか」
紀 子 「あたし、ミシンの針かいたいんだけど……」
小野寺 「どこだい、行こう行こう」
(※写真:1)
この場面から小料理屋「多喜川」までの省略の仕方に関しては、吉田喜重さんの著書『小津安二郎の反映画』(岩波書店)に分かり易く解説があります。小津さん流の諧謔です。一読の価値はあります。 それはそうと…。ここで注目したいのは《ミシン》という言葉です。後にも先にも《ミシン》という言葉は、ここでの台詞のみですが、この後、画面上では《ミシン》が頻繁に登場して来ます。
(※写真:2)
叔母のまさ(杉村春子)は、なぜズボンの直しを自分ではせず、姪の紀子に頼んだのでしょう…? 時代から言っても、世代から言っても、叔母のまさが針仕事の出来ない女性とは考え難い事です。素直に考えれば、紀子の方が叔母よりも縫物が上手という事なのでしょう。仮にそう考えて、未だ独身で子供のいない紀子の方が、叔母よりも縫物が上手というのはどういう事なのか…。そこで、ちょいちょい画面に登場する《ミシン》の存在です。今でこそ紀子が使っているであろう《ミシン》も、そもそもは母の持ち物であった可能性があります。母は縫物が上手で、紀子はその母から縫物を習ったのではあるまいか…。
小料理屋「多喜川」では、再婚した小野寺に対し、その娘の美佐子(桂木洋子)を気遣う紀子の台詞があります。
25=小料理屋「多喜川」
紀 子 「奥様お貰いになったんですってね?」
小野寺 「ああ貰ったよ」
紀 子 「美佐子さんがお可哀そうだわ」
小野寺 「どうして」
紀 子 「だって……やっぱり変じゃないかしら」
小野寺 「そうでもなさそうだよ、うまくいってるらしいよ」
紀 子 「そうかしら―でも何だかいやねえ」
小野寺 「何が? 今度の奥さんかい?」
紀 子 「ううん、小父さまがよ」
小野寺 「どうして」
紀 子 「何だか―不潔よ」
小野寺 「不潔?」
紀 子 「きたならしいわ」
(※写真:3)
龍安寺の石庭では、周吉と小野寺が、共に妻を亡くした者同士である事が暗に示めされていました。当然、紀子と小野寺の娘・美佐子も、共に母を亡くした境遇です。ですから紀子が美佐子へ同情を寄せる想いと、この後、父・周吉の再婚話によって芽生える父への憎悪は、同一視できるように思います。つまり、紀子が父に対して抱いたものは「不潔」「きたならしい」という印象であった…。父や小野寺を性的な存在として想像した結果、そのような印象を抱いたのでしょう。その心の裏には母への想いがあったからではあるまいか…。父の再婚話は母への裏切りである、という想いです。「美佐子さんがお可哀そうだわ」という紀子の台詞からも察せられます。
(※写真:4)
終盤、京都旅行の際に小野寺一家が登場し、美佐子と継母(坪内美子)の関係は良好である事が示されます。それを受けて、その晩、紀子は心境の変化を告白します。有名な壺のカットがある場面です。父への理解と、愛する母や服部(宇佐美淳)への想いが交錯する紀子の胸の内が、見事に表現されていました。以前にも触れた能舞台『杜若』での謡「…やがて杜若の精は、草木を含めて全てを仏に導く法を授かり、悟りの境地を得たとして、夜明けと共に姿を消すのであった…」と、宿の障子に映る月光の草木(業平竹?)との連鎖です。
(※写真:5)
(※写真:6)
(※写真:7)
(※写真:8)
(※写真:9)
紀子に心境の変化を齎した、清水寺での美佐子の明るい様子からは、《亡き母》に対する温度差が感じられます。想像される事としては、母を亡くした時の二人の年齢です。若い美佐子の場合は、幼い頃に母を喪ったものと考えられ、その為に母の記憶が薄く、紀子の場合は大きく成長してから母を喪い、母の記憶が鮮明な為に父の再婚話が許せずにいたのではあるまいか…。例えば、縫物をする優しい母の記憶……可愛い服をたくさん作ってくれた……。その技量を娘の紀子が母から受け継ぎ、その象徴が《ミシン》です。この作品に一切登場しない《亡き母》の気配を、小津さんなりに精一杯表現していたように思います……つづく。


●ミシン-(1)
銀座へ出た紀子(原節子)は、偶然、父(笠智衆)の友人・小野寺(三島雅夫)と再会します。その際、交わされる会話には《ミシン》という言葉が出てきます。キーワードです。
21=銀座の舗道
小野寺 「おお、やってるんだね絵の個展、行ってみようか」
紀 子 「あたし、ミシンの針かいたいんだけど……」
小野寺 「どこだい、行こう行こう」
(※写真:1)

この場面から小料理屋「多喜川」までの省略の仕方に関しては、吉田喜重さんの著書『小津安二郎の反映画』(岩波書店)に分かり易く解説があります。小津さん流の諧謔です。一読の価値はあります。 それはそうと…。ここで注目したいのは《ミシン》という言葉です。後にも先にも《ミシン》という言葉は、ここでの台詞のみですが、この後、画面上では《ミシン》が頻繁に登場して来ます。
(※写真:2)

叔母のまさ(杉村春子)は、なぜズボンの直しを自分ではせず、姪の紀子に頼んだのでしょう…? 時代から言っても、世代から言っても、叔母のまさが針仕事の出来ない女性とは考え難い事です。素直に考えれば、紀子の方が叔母よりも縫物が上手という事なのでしょう。仮にそう考えて、未だ独身で子供のいない紀子の方が、叔母よりも縫物が上手というのはどういう事なのか…。そこで、ちょいちょい画面に登場する《ミシン》の存在です。今でこそ紀子が使っているであろう《ミシン》も、そもそもは母の持ち物であった可能性があります。母は縫物が上手で、紀子はその母から縫物を習ったのではあるまいか…。
小料理屋「多喜川」では、再婚した小野寺に対し、その娘の美佐子(桂木洋子)を気遣う紀子の台詞があります。
25=小料理屋「多喜川」
紀 子 「奥様お貰いになったんですってね?」
小野寺 「ああ貰ったよ」
紀 子 「美佐子さんがお可哀そうだわ」
小野寺 「どうして」
紀 子 「だって……やっぱり変じゃないかしら」
小野寺 「そうでもなさそうだよ、うまくいってるらしいよ」
紀 子 「そうかしら―でも何だかいやねえ」
小野寺 「何が? 今度の奥さんかい?」
紀 子 「ううん、小父さまがよ」
小野寺 「どうして」
紀 子 「何だか―不潔よ」
小野寺 「不潔?」
紀 子 「きたならしいわ」
(※写真:3)

龍安寺の石庭では、周吉と小野寺が、共に妻を亡くした者同士である事が暗に示めされていました。当然、紀子と小野寺の娘・美佐子も、共に母を亡くした境遇です。ですから紀子が美佐子へ同情を寄せる想いと、この後、父・周吉の再婚話によって芽生える父への憎悪は、同一視できるように思います。つまり、紀子が父に対して抱いたものは「不潔」「きたならしい」という印象であった…。父や小野寺を性的な存在として想像した結果、そのような印象を抱いたのでしょう。その心の裏には母への想いがあったからではあるまいか…。父の再婚話は母への裏切りである、という想いです。「美佐子さんがお可哀そうだわ」という紀子の台詞からも察せられます。
(※写真:4)

終盤、京都旅行の際に小野寺一家が登場し、美佐子と継母(坪内美子)の関係は良好である事が示されます。それを受けて、その晩、紀子は心境の変化を告白します。有名な壺のカットがある場面です。父への理解と、愛する母や服部(宇佐美淳)への想いが交錯する紀子の胸の内が、見事に表現されていました。以前にも触れた能舞台『杜若』での謡「…やがて杜若の精は、草木を含めて全てを仏に導く法を授かり、悟りの境地を得たとして、夜明けと共に姿を消すのであった…」と、宿の障子に映る月光の草木(業平竹?)との連鎖です。
(※写真:5)

(※写真:6)

(※写真:7)

(※写真:8)

(※写真:9)

紀子に心境の変化を齎した、清水寺での美佐子の明るい様子からは、《亡き母》に対する温度差が感じられます。想像される事としては、母を亡くした時の二人の年齢です。若い美佐子の場合は、幼い頃に母を喪ったものと考えられ、その為に母の記憶が薄く、紀子の場合は大きく成長してから母を喪い、母の記憶が鮮明な為に父の再婚話が許せずにいたのではあるまいか…。例えば、縫物をする優しい母の記憶……可愛い服をたくさん作ってくれた……。その技量を娘の紀子が母から受け継ぎ、その象徴が《ミシン》です。この作品に一切登場しない《亡き母》の気配を、小津さんなりに精一杯表現していたように思います……つづく。