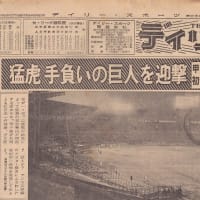僕が阪神タイガースの入団3年目の昭和29年、「野球界」という雑誌の記者から取材依頼がありました。筑紫五郎さんという記者です。取材の内容は、僕が阪神に入団するまでの生い立ちでした。筑紫五郎さんが僕のもとにインタビューに訪れ、その取材内容が、「青春劇場―渡辺省三」というタイトルで「野球界」に掲載されました。


妹の死
「敏子ッ、敏子ッ」
父と二人でいくら呼んでも、3つになったばかりの妹は、もう目を開こうとしなかった。「亡くなりましたか。お可哀そうに」。隣に座っていたオバさんが、目をそっとふいた。しかし、他の人達はやせて大きくなった目をギョロギョロこちらへ向けて、「今日も又誰か死んだ」と口の中でつぶやくだけだった。ここは人間の世界ではない。連日のように襲ってくるソ連軍の掠奪に震えおののき、飢えと寒さに死と直面している地獄絵図だ。
昭和21年2月、朝鮮平壌市の町外れにある醸造会社の倉庫に、終戦と同時に家を失い、働ける男をソ連の強制徴用に、いずこともなく拉致されたあとの婦女子ばかりの邦人200名が集団雑居していた。一日の糧は、一椀の高粱がゆで、栄養失調で死ぬものが、多い時には1週間に10名もいた。生きている人達も、みな老人のようにやせこけて、眼だけがうつろに大きくなって、この世の人とは思わぬほどであった。子供一人の死は、池に小石を投げた波紋ほども、ここにいる人達の心を動かさない。渡辺省三は、この非境の中に最愛の妹を失った。
省三が14才の誕生日をあと10日に控えた時のことである。辛く悲しい生活はまだまだ続くが、ここでこれまでの彼の生い立ちを振り返ってみよう。
省三は、昭和8年2月、指物を職とする父義信氏と母なみ子さんの間に、愛媛県西条市で生まれた。7才の時、お父さんが軍属として徴用され、一家は朝鮮に渡り平壌市外の航空支廠官舎に移り住んだ。ここで船橋小学校に入り、平壌工業学校に進んだが、工業に入った13才の年の7月に、お母さんが8つと5つと2つの妹を残して世を去るという不幸に遭い、その上、8月になって運命の終戦を迎えたのだった。進駐してきたソ連軍は、日本人の働ける男の全部を強制徴用したが、子供ばかりの家族に心配した日本人会の代表者が、お父さんの名を名簿に書かなかったので、お父さんは徴用を免れた。不幸中の幸いであった。
9月に入って、官舎から強制立退きを命ぜられた。「すぐに内地へ送還する。2時間以内に退去すべし」という突然の命令なので、布団を持たず身のまわりのものだけリュックに入れて家を出た。この時、一度家を出た省三は、再びとって返し、堀を乗り越えて家に入り、まだ何か持っていくものはないかと物色した。結局は醤油の一升瓶を持ち出したというが、当時の想い出の中で、このことだけが唯一の笑いであるという。
すぐに内地へ還れるというのは、ぬか喜びだった。200名程度の邦人婦女子は、ある時は風呂屋に起居し、ある時はあてどなく宿を求め、そして新しい年を迎えても、一向に返還の気配は見られなかった。お父さんは、唯一人の男性だったので、この集団の代表者となって外部の仕事に忙しかった。したがって省三は、幼い三人の妹の面倒を見たり、働いて食糧を得なければならない。「何か仕事をさせてください」省三は、朝早起きると、高粱がゆを炊き、三人の妹に食べさせると、町へ飛び出し、そしてソ連兵の官舎に行って、仕事を貰いに回って歩いた。「お前はまだ子供ではないか」手振りで言われて断られると、腕を曲げたり伸ばして見せて、「子供でも力はある」ということを示す。実際14才と言っても、5尺を超えている省三は、腕力には自信があった。薪割り、ガラスふき、庭掃除、頼まれれば何でもやった。ボロボロの服を着て、髪は伸び、ただでさえ色が黒いのに、垢がたまっているから、浮浪児同然の姿であった。仕事に対する賃金は、時には金をくれるところもあったが、たいていは食い残しの黒パンであった。1椀の高粱がゆの腹には、それでさえ貴重だった。新聞紙に包んだ黒パンは、妹たちにとっては、生命の糧だったのである。倉庫の中で死んでゆくものの殆どが、体力のない老人と子供だったから省三は妹達のために、毎日黒パンを得るために街へ出た。
山へ登って見下ろす平壌の町は、平和な何事もない町に見えた。小学校時代の楽しい想い出のある、あの川、あの森、そして自分の住んでいた官舎も見える。全てがそのままである。しかし、可愛い妹は、もういない。異境に生まれ故郷を知らずに、今自分の後ろの土の中に眠っているのだ。むしろに包んだ妹の亡きがらを山へ運び、父と子は、穴を掘って埋めた。新しく掘り返された土の上には、猫かなんかの墓のような形ばかりの墓標がたっている。その墓標を背に、父と子が見下ろす街の、なんと静かなことだろう。省三は、妹の死も、倉庫内の生地獄もウソのような気がしてならなかった。
「一日でも内地を見せたかったね。お父さん」
「省ちゃんの黒パンも無駄になったな」
「けれど、きっといつか内地へ帰れるね」
「どうだかな。でも生きているうちに帰れるよ」。
平和に見える街、それを見下ろす丘の悲しい父と子の会話であった。しかし、待望の内地返還の日は、案外早くやってきた。それから2カ月たった4月、丘の上の墓に、心づくしのタンポポの花を供えて、渡辺家一家は、4月中旬、暗い思い出ばかりを胸に祖国に帰りついたのである。
「ノコギリと金ヅチたのむよ」
「はい」
「ペンチとハリ金」
「はい」
帰国してから西条中学を出ると、倉敷レーヨンに入社した。16才なので、一人前の仕事が出来ず、又労働基準法に触れるので、与えられた仕事が、道具番だった。しかし、仕事は子供の仕事でも、野球部員としては一人前の働きをやってのけていた。帰国後、高等小学校に入ってはじめて握ったスポンジ・ボールだったが、それまで埋もれていた嚢中の錐は、すぐに鋭鋒を現わした。ピッチャーをつとめ、西条中学に入っても、主戦投手、主力打者として重きをなした。しかし、倉敷レーヨンで軟式をやっていることが、省三にはあきたりなくなってきた。そして26年10月、甲子園球場で行われたタイガースのテストを受けたのである。近い将来、阪神タイガースのエースと目されている渡辺省三の歩んできた道は、常人のそれとは全く違った苦難の連続であった。しかし、彼は言っている。「御飯炊きでも、便所掃除でも何でもやりましたが、そういう苦しい体験も、今では人生に対する自信というものを植え付けてくれた尊い体験だと思っています。阪神へ入団してからは、幸い人より恵まれた道を進んで、ようやく幸福らしいものを得ました。
◆◆◆
僕は、昭和20年7月25日に、平壌でおふくろを亡くしました。終戦の2週間前でした。僕の親父は、軍属として徴用され、僕は7歳の時に一家で、北朝鮮に渡ったんです。平壌市内の大同江のそばの官舎で、親父とおふくろ、僕と2人の妹と5人で生活しました。そこで、大同江近くの船橋小学校に入学しました。

船橋小学校4年生の時に、妹、敏子が生まれました。平壌の冬は、とても寒く、大同江の河の水が凍るんです。そこで、スケートをして友人と遊んだことは、懐かしい思い出です。平壌工業高校に入った13歳の年の6月、沖縄占領の報を受けて、親父が突然、「このまま、平壌に居ては危険だ。軍部は日本軍が有利な報道ばかりするが、実際は、そのうちに沖縄に上陸され、本土もいつ、上陸されるかわからない状態が迫っているように思う。だから、おまえたちは日本に帰っている方が安全だ」と言いだしたのです。
当時は、日本に不利な話などをすると、憲兵隊につかまる可能性があり、内心で思っていることを、絶対に他言できない時代でした。「3月にアメリカに硫黄島を占領されて以来、日本では連日空襲が続いているらしい。もし、不幸にして戦争に負ければ、朝鮮人の暴動が起きるかもしれない。本土が安全というわけではないが、例え日本が負けたとしても、誰彼構わず、女、子供まで皆殺しにされたりしないだろう」と、突然、日本への帰り支度をさせる理由を、親父が13歳の僕に納得がいくように説明してくれました。
いざ、日本に帰ると言っても、釜山から下関間の船は、沖縄を占領した米軍機が、この航路の船を襲撃するということで、運航休止になっていました。唯一、「清津」という港から、敦賀まで行く日本海横断の船便を頼るしか日本へ帰るルートはありませんでした。6月下旬、僕たちは、汽車にゆられたり、テクテク歩いて、途中、高原で野宿したり、丸2日かけて「清津」の港を目指しました。へとへとになりながら、やっと「清津」に着いたところ、敦賀に空襲があったとのことで、敦賀行きの船が運航休止になったんです。「どうやら、駅がやられただけで、数日後には船が出るらしい」とか「もう、日本に帰れる船はない」とか、港でいろいろな噂が飛び交っていました。僕たち一家は、1週間、清津に滞在し、船の運航開始を待ちましたが、運航のめどは立ちませんでした。仕方なく、又来た道を戻って平壌に帰るしかありませんでした。
当時、おふくろは、7か月の身重の体だったんですが、平壌に帰り着いたあくる日に早産してしまいました。当時のおふくろは、栄養状態も悪く、そのうえ、清津までの長旅、日本に帰れると思っていたのに船が出ず帰れなかったことの気落ちなどのせいからか、産後の肥立ちもよくありませんでした。おふくろの容態があまりに悪いので、親父に近所の内科の先生を呼んでくるよう、朝早くに言われ、僕は急いで先生を呼びに行きました。先生がおふくろの容態を診て、「これはいかん。回復する見込みは少ないが、注射を打ってみよう」と言って、一本の注射を打ってくれたんです。おふくろは、注射のあと、すぐに静かになり、2、3度大きく呼吸をしたかと思うと、その後、吸った息を吐き出すことはありませんでした。僕は、これがおふくろの最期の瞬間だと気づくのに、しばらく時間がかかりました。昭和20年7月25日午前8時ごろのことです。おふくろは、親父、僕、8歳、5歳、2歳の妹たち、そして、生れたばかりの弟を残して死んだんです。そして、その日から5日後、生まれたばかりの弟も亡くなりました。
おふくろが亡くなって、約20日後の8月15日に終戦を迎えました。その後の状況は、「野球界」に掲載されている内容の通りです。おふくろ亡きあと、当時2歳だった敏子は、僕に甘え、僕が背中におぶって、あちこち、逃げまどいました。妹たちを食べさせるために、盗みをしたこともありました。廻りで死んだ行く人がたくさんいる中、生き伸びてほしいと思うばかりだったんです。それだけに、昭和21年2月16日、敏子が、栄養失調で僕の腕の中で息を引き取った時は、つらく悲しかったです。(文責:渡辺直子)
参考文献:「野球界」(昭和29年発行)
「牛若丸の履歴書」(吉田義男著)
デイリースポーツー小山正明氏が語る「猛虎豪傑列伝」渡辺省三編 芯も体もバクチも強かった
「渡辺義信 我が人生の回顧録」
「母さんのコロッケ」(喜多川泰)


妹の死
「敏子ッ、敏子ッ」
父と二人でいくら呼んでも、3つになったばかりの妹は、もう目を開こうとしなかった。「亡くなりましたか。お可哀そうに」。隣に座っていたオバさんが、目をそっとふいた。しかし、他の人達はやせて大きくなった目をギョロギョロこちらへ向けて、「今日も又誰か死んだ」と口の中でつぶやくだけだった。ここは人間の世界ではない。連日のように襲ってくるソ連軍の掠奪に震えおののき、飢えと寒さに死と直面している地獄絵図だ。
昭和21年2月、朝鮮平壌市の町外れにある醸造会社の倉庫に、終戦と同時に家を失い、働ける男をソ連の強制徴用に、いずこともなく拉致されたあとの婦女子ばかりの邦人200名が集団雑居していた。一日の糧は、一椀の高粱がゆで、栄養失調で死ぬものが、多い時には1週間に10名もいた。生きている人達も、みな老人のようにやせこけて、眼だけがうつろに大きくなって、この世の人とは思わぬほどであった。子供一人の死は、池に小石を投げた波紋ほども、ここにいる人達の心を動かさない。渡辺省三は、この非境の中に最愛の妹を失った。
省三が14才の誕生日をあと10日に控えた時のことである。辛く悲しい生活はまだまだ続くが、ここでこれまでの彼の生い立ちを振り返ってみよう。
省三は、昭和8年2月、指物を職とする父義信氏と母なみ子さんの間に、愛媛県西条市で生まれた。7才の時、お父さんが軍属として徴用され、一家は朝鮮に渡り平壌市外の航空支廠官舎に移り住んだ。ここで船橋小学校に入り、平壌工業学校に進んだが、工業に入った13才の年の7月に、お母さんが8つと5つと2つの妹を残して世を去るという不幸に遭い、その上、8月になって運命の終戦を迎えたのだった。進駐してきたソ連軍は、日本人の働ける男の全部を強制徴用したが、子供ばかりの家族に心配した日本人会の代表者が、お父さんの名を名簿に書かなかったので、お父さんは徴用を免れた。不幸中の幸いであった。
9月に入って、官舎から強制立退きを命ぜられた。「すぐに内地へ送還する。2時間以内に退去すべし」という突然の命令なので、布団を持たず身のまわりのものだけリュックに入れて家を出た。この時、一度家を出た省三は、再びとって返し、堀を乗り越えて家に入り、まだ何か持っていくものはないかと物色した。結局は醤油の一升瓶を持ち出したというが、当時の想い出の中で、このことだけが唯一の笑いであるという。
すぐに内地へ還れるというのは、ぬか喜びだった。200名程度の邦人婦女子は、ある時は風呂屋に起居し、ある時はあてどなく宿を求め、そして新しい年を迎えても、一向に返還の気配は見られなかった。お父さんは、唯一人の男性だったので、この集団の代表者となって外部の仕事に忙しかった。したがって省三は、幼い三人の妹の面倒を見たり、働いて食糧を得なければならない。「何か仕事をさせてください」省三は、朝早起きると、高粱がゆを炊き、三人の妹に食べさせると、町へ飛び出し、そしてソ連兵の官舎に行って、仕事を貰いに回って歩いた。「お前はまだ子供ではないか」手振りで言われて断られると、腕を曲げたり伸ばして見せて、「子供でも力はある」ということを示す。実際14才と言っても、5尺を超えている省三は、腕力には自信があった。薪割り、ガラスふき、庭掃除、頼まれれば何でもやった。ボロボロの服を着て、髪は伸び、ただでさえ色が黒いのに、垢がたまっているから、浮浪児同然の姿であった。仕事に対する賃金は、時には金をくれるところもあったが、たいていは食い残しの黒パンであった。1椀の高粱がゆの腹には、それでさえ貴重だった。新聞紙に包んだ黒パンは、妹たちにとっては、生命の糧だったのである。倉庫の中で死んでゆくものの殆どが、体力のない老人と子供だったから省三は妹達のために、毎日黒パンを得るために街へ出た。
山へ登って見下ろす平壌の町は、平和な何事もない町に見えた。小学校時代の楽しい想い出のある、あの川、あの森、そして自分の住んでいた官舎も見える。全てがそのままである。しかし、可愛い妹は、もういない。異境に生まれ故郷を知らずに、今自分の後ろの土の中に眠っているのだ。むしろに包んだ妹の亡きがらを山へ運び、父と子は、穴を掘って埋めた。新しく掘り返された土の上には、猫かなんかの墓のような形ばかりの墓標がたっている。その墓標を背に、父と子が見下ろす街の、なんと静かなことだろう。省三は、妹の死も、倉庫内の生地獄もウソのような気がしてならなかった。
「一日でも内地を見せたかったね。お父さん」
「省ちゃんの黒パンも無駄になったな」
「けれど、きっといつか内地へ帰れるね」
「どうだかな。でも生きているうちに帰れるよ」。
平和に見える街、それを見下ろす丘の悲しい父と子の会話であった。しかし、待望の内地返還の日は、案外早くやってきた。それから2カ月たった4月、丘の上の墓に、心づくしのタンポポの花を供えて、渡辺家一家は、4月中旬、暗い思い出ばかりを胸に祖国に帰りついたのである。
「ノコギリと金ヅチたのむよ」
「はい」
「ペンチとハリ金」
「はい」
帰国してから西条中学を出ると、倉敷レーヨンに入社した。16才なので、一人前の仕事が出来ず、又労働基準法に触れるので、与えられた仕事が、道具番だった。しかし、仕事は子供の仕事でも、野球部員としては一人前の働きをやってのけていた。帰国後、高等小学校に入ってはじめて握ったスポンジ・ボールだったが、それまで埋もれていた嚢中の錐は、すぐに鋭鋒を現わした。ピッチャーをつとめ、西条中学に入っても、主戦投手、主力打者として重きをなした。しかし、倉敷レーヨンで軟式をやっていることが、省三にはあきたりなくなってきた。そして26年10月、甲子園球場で行われたタイガースのテストを受けたのである。近い将来、阪神タイガースのエースと目されている渡辺省三の歩んできた道は、常人のそれとは全く違った苦難の連続であった。しかし、彼は言っている。「御飯炊きでも、便所掃除でも何でもやりましたが、そういう苦しい体験も、今では人生に対する自信というものを植え付けてくれた尊い体験だと思っています。阪神へ入団してからは、幸い人より恵まれた道を進んで、ようやく幸福らしいものを得ました。
◆◆◆
僕は、昭和20年7月25日に、平壌でおふくろを亡くしました。終戦の2週間前でした。僕の親父は、軍属として徴用され、僕は7歳の時に一家で、北朝鮮に渡ったんです。平壌市内の大同江のそばの官舎で、親父とおふくろ、僕と2人の妹と5人で生活しました。そこで、大同江近くの船橋小学校に入学しました。

船橋小学校4年生の時に、妹、敏子が生まれました。平壌の冬は、とても寒く、大同江の河の水が凍るんです。そこで、スケートをして友人と遊んだことは、懐かしい思い出です。平壌工業高校に入った13歳の年の6月、沖縄占領の報を受けて、親父が突然、「このまま、平壌に居ては危険だ。軍部は日本軍が有利な報道ばかりするが、実際は、そのうちに沖縄に上陸され、本土もいつ、上陸されるかわからない状態が迫っているように思う。だから、おまえたちは日本に帰っている方が安全だ」と言いだしたのです。
当時は、日本に不利な話などをすると、憲兵隊につかまる可能性があり、内心で思っていることを、絶対に他言できない時代でした。「3月にアメリカに硫黄島を占領されて以来、日本では連日空襲が続いているらしい。もし、不幸にして戦争に負ければ、朝鮮人の暴動が起きるかもしれない。本土が安全というわけではないが、例え日本が負けたとしても、誰彼構わず、女、子供まで皆殺しにされたりしないだろう」と、突然、日本への帰り支度をさせる理由を、親父が13歳の僕に納得がいくように説明してくれました。
いざ、日本に帰ると言っても、釜山から下関間の船は、沖縄を占領した米軍機が、この航路の船を襲撃するということで、運航休止になっていました。唯一、「清津」という港から、敦賀まで行く日本海横断の船便を頼るしか日本へ帰るルートはありませんでした。6月下旬、僕たちは、汽車にゆられたり、テクテク歩いて、途中、高原で野宿したり、丸2日かけて「清津」の港を目指しました。へとへとになりながら、やっと「清津」に着いたところ、敦賀に空襲があったとのことで、敦賀行きの船が運航休止になったんです。「どうやら、駅がやられただけで、数日後には船が出るらしい」とか「もう、日本に帰れる船はない」とか、港でいろいろな噂が飛び交っていました。僕たち一家は、1週間、清津に滞在し、船の運航開始を待ちましたが、運航のめどは立ちませんでした。仕方なく、又来た道を戻って平壌に帰るしかありませんでした。
当時、おふくろは、7か月の身重の体だったんですが、平壌に帰り着いたあくる日に早産してしまいました。当時のおふくろは、栄養状態も悪く、そのうえ、清津までの長旅、日本に帰れると思っていたのに船が出ず帰れなかったことの気落ちなどのせいからか、産後の肥立ちもよくありませんでした。おふくろの容態があまりに悪いので、親父に近所の内科の先生を呼んでくるよう、朝早くに言われ、僕は急いで先生を呼びに行きました。先生がおふくろの容態を診て、「これはいかん。回復する見込みは少ないが、注射を打ってみよう」と言って、一本の注射を打ってくれたんです。おふくろは、注射のあと、すぐに静かになり、2、3度大きく呼吸をしたかと思うと、その後、吸った息を吐き出すことはありませんでした。僕は、これがおふくろの最期の瞬間だと気づくのに、しばらく時間がかかりました。昭和20年7月25日午前8時ごろのことです。おふくろは、親父、僕、8歳、5歳、2歳の妹たち、そして、生れたばかりの弟を残して死んだんです。そして、その日から5日後、生まれたばかりの弟も亡くなりました。
おふくろが亡くなって、約20日後の8月15日に終戦を迎えました。その後の状況は、「野球界」に掲載されている内容の通りです。おふくろ亡きあと、当時2歳だった敏子は、僕に甘え、僕が背中におぶって、あちこち、逃げまどいました。妹たちを食べさせるために、盗みをしたこともありました。廻りで死んだ行く人がたくさんいる中、生き伸びてほしいと思うばかりだったんです。それだけに、昭和21年2月16日、敏子が、栄養失調で僕の腕の中で息を引き取った時は、つらく悲しかったです。(文責:渡辺直子)
参考文献:「野球界」(昭和29年発行)
「牛若丸の履歴書」(吉田義男著)
デイリースポーツー小山正明氏が語る「猛虎豪傑列伝」渡辺省三編 芯も体もバクチも強かった
「渡辺義信 我が人生の回顧録」
「母さんのコロッケ」(喜多川泰)