※ 本トピックの意図としては,2つの来店拒否の違いを比較することにあります。来店拒否が直ちに法律問題になるという趣旨ではありません。
※ さらに,私と意見の異なる弁護士の先生に対して敵意をもったトピックでもありません。むしろ,意見が分かれるその境目はどこなのかを知りたいなという純粋な興味から挙げたトピックです。
※ あくまでも戯言としてお読みいただければと。
先日,「ご自由に」のネギを大量にラーメンに入れたところ出禁になった,というネタをもとに,弁護士ドットコムに記事を書いたところ,賛成,反対さまざまな意見が寄せられました。
その記事は下記のとおりです。
「ご自由にお取りください」ラーメン屋でネギを大量に食べたら「出禁」こんなのアリ?
ラーメンのおいしさを引き立たせる「ネギ」。麺やスープと比べると「脇役」だが、たくさん食べたい人も多いだろう。しかし、ネットの掲示板では、あるラーメン屋で「ご自由にお取りください」と書かれていたネギを大量に食べたら、出入り禁止をくらったという書き込みがあった。
投稿主は、週に1回程度、このラーメン屋を訪れ、おかわりしながら、どんぶり2杯分くらいのネギを食べていたら、店員から「こっちも商売でやってるんで・・・うちのご利用は控えてもらえますか?」と言われてしまったそうだ。
投稿主は「自由に食っていいんじゃないですか?ちゃんと食ってますよ?」と反論したそうだが、自由に取っていいと書かれているネギを大量に食べたことを理由に、入店を断ることはできるのだろうか。中村憲昭弁護士に聞いた。
●ラーメン屋と客の合意も「契約」
「法律的には、客のほうが正しいと思います。ラーメン屋と客の合意も契約です。『ネギを自由に取って良い』という店の勧誘に対して、客がラーメンを注文した時点で契約が成立します。いったん契約が成立すれば、当事者はその合意に従わねばなりません。
店の義務は商品を提供することで、客の義務はその商品に対価を支払うことです。今回の場合、店はラーメンに加えて、客の好きなだけネギを提供するという提案をし、客はその提案を受け入れてラーメンを注文していることになります。店には、店内で客が好きなだけ食べられるようにネギを提供する義務があります」
ネギ好きにとってはうれしい答えだ。しかし、ネットの書き込みにも「常識外の注文をする方がおかしい」と批判の声もあった。
「たしかに、店に客を選ぶ権利はあるので、理屈としては、次回以降の利用を断ることはできます。
ただ、その場合、『ご自由にお取りください』の張り紙は剥がすべきでしょう。できない約束を掲げて客を勧誘するのはアンフェアですし,大食いに対する『理由なき差別」です」
●サービスで客の信用を失わないように
張り紙の「ご自由にお取りください」も契約の内容となるわけか。
「私も学生時代『替え玉し放題』のラーメン屋に通い続けていたら、あるときから、店の方針が『替え玉2回まで』に変更されました。
これは納得できましたが、高級寿司の食べ放題に仲間と行った際、2巡目から明らかにネタの質を下げられたのには、納得できませんでした。
そして、二度と行きませんでした(笑)。『高級寿司』の看板に偽りありです。店は客商売です。サービスで逆に客を失わないよう、上手にサービスを提供するよう心掛けたいものです」
中村弁護士はこう語っていた。
(弁護士ドットコムニュース)(引用終わり)
ラーメンのおいしさを引き立たせる「ネギ」。麺やスープと比べると「脇役」だが、たくさん食べたい人も多いだろう。しかし、ネットの掲示板では、あるラーメン屋で「ご自由にお取りください」と書かれていたネギを大量に食べたら、出入り禁止をくらったという書き込みがあった。
投稿主は、週に1回程度、このラーメン屋を訪れ、おかわりしながら、どんぶり2杯分くらいのネギを食べていたら、店員から「こっちも商売でやってるんで・・・うちのご利用は控えてもらえますか?」と言われてしまったそうだ。
投稿主は「自由に食っていいんじゃないですか?ちゃんと食ってますよ?」と反論したそうだが、自由に取っていいと書かれているネギを大量に食べたことを理由に、入店を断ることはできるのだろうか。中村憲昭弁護士に聞いた。
●ラーメン屋と客の合意も「契約」
「法律的には、客のほうが正しいと思います。ラーメン屋と客の合意も契約です。『ネギを自由に取って良い』という店の勧誘に対して、客がラーメンを注文した時点で契約が成立します。いったん契約が成立すれば、当事者はその合意に従わねばなりません。
店の義務は商品を提供することで、客の義務はその商品に対価を支払うことです。今回の場合、店はラーメンに加えて、客の好きなだけネギを提供するという提案をし、客はその提案を受け入れてラーメンを注文していることになります。店には、店内で客が好きなだけ食べられるようにネギを提供する義務があります」
ネギ好きにとってはうれしい答えだ。しかし、ネットの書き込みにも「常識外の注文をする方がおかしい」と批判の声もあった。
「たしかに、店に客を選ぶ権利はあるので、理屈としては、次回以降の利用を断ることはできます。
ただ、その場合、『ご自由にお取りください』の張り紙は剥がすべきでしょう。できない約束を掲げて客を勧誘するのはアンフェアですし,大食いに対する『理由なき差別」です」
●サービスで客の信用を失わないように
張り紙の「ご自由にお取りください」も契約の内容となるわけか。
「私も学生時代『替え玉し放題』のラーメン屋に通い続けていたら、あるときから、店の方針が『替え玉2回まで』に変更されました。
これは納得できましたが、高級寿司の食べ放題に仲間と行った際、2巡目から明らかにネタの質を下げられたのには、納得できませんでした。
そして、二度と行きませんでした(笑)。『高級寿司』の看板に偽りありです。店は客商売です。サービスで逆に客を失わないよう、上手にサービスを提供するよう心掛けたいものです」
中村弁護士はこう語っていた。
(弁護士ドットコムニュース)(引用終わり)
これに対して,複数の弁護士の先生から,ツイッターやブログで反論が寄せられました(論争したいわけではないので,敢えてリンクはしません)。
その理由としては,
1 ラーメンの供給契約は,店主が注文を受諾した時に成立する
2 施設管理権は経営者にある。どんな理由であれ,民間施設であれば国家によりその出入りを制限されない。
3 ラーメンの供給の問題と,店の出入りの問題とは別
4 法的問題と道義的問題は区別されるべき
というもののようです。
正直,わかったようなわからないような,というのが率直な気持ちです。
もちろん,人と人との紛争のすべてが法的問題にはならないのはその通りですし,その観点でいえば,「ラーメン屋の入店拒否くらいで目くじら立てんなよ」「そんな店に行かなければいいじゃん」という意見には全面的に賛同します。
ただ,出入り禁止が「どんな場合でも」自由かというと,そう言い切れないような気がするのです。
私自身,店が態度を変えるのは全く構わないと思います。
例えば,ネギ食べ放題を拒否したかったら,「1人につき2杯まででお願いします」でもいいし,「節度をもってお取り下さい」でもいいですから,何らかの留保を付ければいいわけです。
そのような対応を取ることは,店にとって簡単です。
また,施設管理権を理由に入店拒否をすることがどんな場合でも可能,ということにはとても違和感があります。
なぜなら,差別を正当化するための方便が,まさにそのような方法でなされる可能性があるからです。
などともやもやしている時に,こんなニュースが流れました。
ミシュランで星をもらった名店が,外国人に対して入店を拒否したのではないか,というニュースです。
差別? 予約拒否された外国人が憤るミシュラン寿司店の対応 (2015年4月26日日刊ゲンダイ)
ショッキングな話である。2015年の「ミシュランガイド東京」で2つ星を獲得した銀座の「鮨 水谷」が、予約をしようとした外国人に差別的な対応をしたという。実際に店側とやりとりし、「がっかりした」と話すのは、在日30年の中国人ジャーナリスト・莫邦富氏だ。
今月8日、莫氏の秘書(日本人女性)が「水谷」に電話をし、5月12日に4人で訪れたいと伝えたところ、「空いています」との返事だった。ところが、連絡先や氏名を伝えると、「えっ、海外の方ですか?」と聞かれ、日本在住であることを伝えても、「日本人は同行しますか」「調整が必要です」の一点張り。莫氏本人が電話を代わり、4人とも中国人で、しかし自分は来日30年でジャーナリストとして仕事をしていること、今回の食事が莫氏側の招待であること、招待客の1人は日本に留学経験があり、日本の政官界とも仕事をしている社長であることなど、本来なら伝える必要のない個人情報まで明らかにしても、「調整が必要です」とハッキリしない態度だったという。
「水谷」はカウンター10席で、夜のおまかせコースが2万円からという超高級店。常連客によると「金持ちの白人がしょっちゅう来て、大声でしゃべっている」という。外国人を受け入れている店なのに、莫氏へのヒドい対応は何なのか? 莫氏の電話を受けた店の担当者に取材すると、こんな言い分だった。
「店の雰囲気づくりのため、海外の客と日本人客の比率を半々にしています。海外の客については予約をしたのに来ないなど、トラブルが多発したので、ホテルのコンシェルジュ、もしくはカード会社を通じた予約だけに限定しています」
ただ、莫氏は海外からの旅行客ではなく、日本に永住している。
「旅行客かそうでないかは、電話だけでは判別できません。海外の客には、一律でこういう対応をしています」
■外国人観光客増加を目指す日本の課題
莫氏は、石川県や山梨県などのインバウンド(訪日外国人)誘致のアドバイザーの仕事もしている。
政府は東京五輪の2020年までにインバウンド2500万人(14年は1300万人)を目指しているが、莫氏はそんな日本の高級店の不可解な対応に、こう憤る。
「外国人客の困った事態があったのかもしれませんから、『水谷』さんの立場は理解します。ただ、私は日本に永住していますし、そもそも外国人と日本人を分断する意識は差別としか言いようがありません。『水谷』さんだけの問題ではなく、日本のインバウンド全体のイメージをよくするために、意識改革が必要なのではないでしょうか」
水谷は、ケネディ米大使から予約電話があっても、「ホテルのコンシェルジュかカード会社を通して」と拒否するのだろうか? (引用終わり)
ショッキングな話である。2015年の「ミシュランガイド東京」で2つ星を獲得した銀座の「鮨 水谷」が、予約をしようとした外国人に差別的な対応をしたという。実際に店側とやりとりし、「がっかりした」と話すのは、在日30年の中国人ジャーナリスト・莫邦富氏だ。
今月8日、莫氏の秘書(日本人女性)が「水谷」に電話をし、5月12日に4人で訪れたいと伝えたところ、「空いています」との返事だった。ところが、連絡先や氏名を伝えると、「えっ、海外の方ですか?」と聞かれ、日本在住であることを伝えても、「日本人は同行しますか」「調整が必要です」の一点張り。莫氏本人が電話を代わり、4人とも中国人で、しかし自分は来日30年でジャーナリストとして仕事をしていること、今回の食事が莫氏側の招待であること、招待客の1人は日本に留学経験があり、日本の政官界とも仕事をしている社長であることなど、本来なら伝える必要のない個人情報まで明らかにしても、「調整が必要です」とハッキリしない態度だったという。
「水谷」はカウンター10席で、夜のおまかせコースが2万円からという超高級店。常連客によると「金持ちの白人がしょっちゅう来て、大声でしゃべっている」という。外国人を受け入れている店なのに、莫氏へのヒドい対応は何なのか? 莫氏の電話を受けた店の担当者に取材すると、こんな言い分だった。
「店の雰囲気づくりのため、海外の客と日本人客の比率を半々にしています。海外の客については予約をしたのに来ないなど、トラブルが多発したので、ホテルのコンシェルジュ、もしくはカード会社を通じた予約だけに限定しています」
ただ、莫氏は海外からの旅行客ではなく、日本に永住している。
「旅行客かそうでないかは、電話だけでは判別できません。海外の客には、一律でこういう対応をしています」
■外国人観光客増加を目指す日本の課題
莫氏は、石川県や山梨県などのインバウンド(訪日外国人)誘致のアドバイザーの仕事もしている。
政府は東京五輪の2020年までにインバウンド2500万人(14年は1300万人)を目指しているが、莫氏はそんな日本の高級店の不可解な対応に、こう憤る。
「外国人客の困った事態があったのかもしれませんから、『水谷』さんの立場は理解します。ただ、私は日本に永住していますし、そもそも外国人と日本人を分断する意識は差別としか言いようがありません。『水谷』さんだけの問題ではなく、日本のインバウンド全体のイメージをよくするために、意識改革が必要なのではないでしょうか」
水谷は、ケネディ米大使から予約電話があっても、「ホテルのコンシェルジュかカード会社を通して」と拒否するのだろうか? (引用終わり)
このお寿司屋さんも,店の管理権を有しています。
もちろん,店の混雑やネタ切れなど合理的な理由があれば,予約を受け付けないのも致し方ないと思います。
ただ,これについても,単に施設管理権を理由に,全く自由に入店を断るという理屈になるのでしょうか。
確かに,「人種差別の問題と,店の経営的な観点から採算の取れない客を拒否することとは事案が異なる」という意見はあるでしょう。
でもそうだとしたら,なぜ両者で結論が異なるのかを明確に説明しなければなりません。
少なくとも,民間施設なら施設管理権を理由に来店を無制限に拒否出来るという立場からは,人種差別的な目的による入店拒否でもなんら法的な問題は生じないことになります。
ただ,この点については,小樽市の温泉施設の入浴拒否事件などをはじめとして,違法であるという判断が裁判所から出されていることは事実です(ちなみに,小樽市の事件は公衆浴場ではなく民間の経営する温浴施設です)。
この点について,私と意見を異にする先生がどのように判断されるのか,純粋に興味があります。
私のトピックは,法律上の問題点を述べながらも,結論として「法律論としては客が正しい」と冒頭に書いています。
反対意見を述べている先生は,おそらくこの点をもって「法律論と道義的責任論を混同している」と述べられているのでしょう。
そしてその指摘は間違ってはいません。
なぜなら,敢えてそのように書いたからです。
法律家としては,単に合法か違法かを示すだけでは足りないと思っています。
この事案でも,どちらが正しいかを示すにあたっても「店が正しい。しかし~」とは書きたくなかったという事情はあります。
メッセージとして,店に対して対応を考えようよ,ということを伝えたかった,というのが真情です。
ただ,半面「原則として~」とか「~の可能性が高い」といった曖昧な表現も避けたいと考えていました。
そのため,法律論,つまりどの時点で合意が成立するのかを述べつつ,慎重に「店が正しい」というニュアンスを避けたわけです。
それを約500字という制限の中で書いたのがあのトピックです(何だか言い訳じみてきました)。
まあ,今考えれば「難しいけど,心情的には客が正しい」くらいにしておけば良かったんでしょうかね。そうなるとますます法律家の助言としてふさわしくない,と言われそうですが。
何だか,棋士が観賞戦で敗因を分析しているような内容になってしまいました。
バカネタとして,皆様の娯楽に少しでも貢献できれば幸いです(笑)

※ これは最近行った某店の掲示。
これなら節度をもって食べなきゃという気持ちになります(笑)
(4月28日追記)
FBでも意見をいただきました。
やはり(私の個人的感情を抜きにして)法律的にいえば,違法とまでは言えない,ということになりますね。
基本的には契約自由の原則が妥当するとして,本件来店拒否が例外的に違法とまで言えるか,ということになります。
差異的取扱いが許されるかどうかは,民間企業であっても完全に自由ではありません。
が,直ちに憲法が適用されるわけではなく,民法90条の公序良俗違反と言えるかどうか,という点から判断されます。
私としては,単に「次回来店を拒めるか」ではなく「『ご自由に』という貼り紙をしながら,そのとおりに行動した客を拒むのが相当か」という問題意識でした。
ただ,道義的責任はともかくとして,そもそも「ねぎを自由に食べる権利」などというものは権利性が乏しいと言われればそれまでです(別の店を選べばいい)。
店の経営上の理由という差異的取扱いの目的は一応合理的ではあるし,それに対する手段として来店拒否を講じることも関連性はありといえそうです。
そうなると「道義的責任はともかく,法的には店が正しい」というのが,「法的には」正しいことになりますね。
かつ,人種差別を理由とする来店拒否についても説明出来ます(判断基準が厳格になります)。
普通に考えれば憲法の教科書レベルの合憲性判断のお話でした。










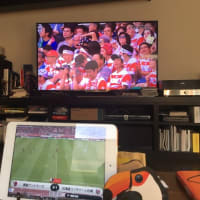







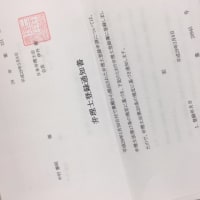

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます