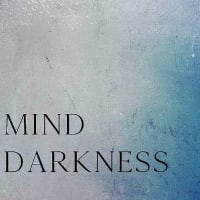現在最多のCoreを載せている一般機種はMac Proの8Coreです.............
MacFanかMacPeopleで以前おいらが考えていた事と同じ内容のことが提案されていました。
複数のOSを起動させて使用するServer的な使用方法です。
一応おいらの記事のリンクを下に貼っておきます。
BootCampがもたらす影響
雑誌の記事では複数のWindowsOSを起動させる事が提案されていましたが、時期MacOSでは複数のMacOSの仕様を設定できて選択画面で選択した仕様に即変更が出来るという機能が搭載されています。
もしかしたらMacOSを複数起動させて使えるようになるかもしれませんね~。
あくまで憶測でしかないのですが、もしそうなるのであればMac Proではレクチャーする際に同じMacを使用して教えることが出来ます。
もしそうなれば、便利ですよね~。
Windowsを複数起動できるのにMacintoshが一つしか起動できないのはおかしいと思うわけです。
まあこんなおいらのBlogなんかを覗いていないでしょうから書きますが、出し惜しみして欲しくないんですよね~。
使えるのであればとことんで使える仕様にして欲しいものです。
もしこのような機能が追加されるのであれば、特に重宝するのはMac Proを使用する人でしょう。
拡張性に富み、タフな構造を誇っているわけですし、CPUもしくはMPUを搭載しているのですから、2人で使用するのであれば単純に2分割したらいいわけです。
またもし3人以上になるのであれば4分割まではQuadCoreの場合はハード的に分割できるでしょう。
しかし上記の条件としてメモリのスロットを全て埋めておく必要があります。
デュアルメモリ効果を使用できるようにしておくことは常識となりつつありますからね~。
まあ、おいらのMacintoshは古い機種ですのでデュアルメモリの恩恵はあまりあずかることが出来ないんですけどね。
Computerの進歩というのはすごい勢いで進んで居るんだな~とよく感じます。
上記の雑誌で気になったベンチマークテストでは8CoreをFullに使用出来るApplicationはごく少数で8Coreを持てあましているという事実が書かれていました。
そしてベンチマークに使うアプリケーションによっては4Coreの方が高速に処理できるモノが多かったようです。
これは処理の割り振りが最適化されておらず、CPUの性能を効率的に使えていないからだともとも書かれていました。
よっておいらが提案するポイントは下記の事です。
・メモリの割り振り同様のCPUの割り振り
・ApplicationからのCPUの割り振りも良いかもしれない(Photoshopのメモリの割り振りと同様)
Macintoshを起動する際に複数のソフトを同時に起動することは当たり前でしょう。
おいらの場合はiTunesとMail、safariなど音楽やインターネットを起動させた上に画像処理ソフトを起動させていることが多いんですな。
Photoshopはかなりの物理メモリ空間を割り当てていますので他のソフトを使用するのには問題があります。
よってPhotoshopを起動させる場合はiTunesぐらいしか同時起動させないようにしています。
というか画像処理ソフトはすべてかなりの物理メモリを占有するので極力他のアプリケーションを起動しないようにする必要が求められています。
あまりコンピュータのことを考えずに複数のアプリケーションを同時起動させていたときにOSが不安定になりApplicationがフリーズすることがたまにありました。
今から考えると無理な使い方をしていたことが良くわかりますが、当時は「またフリーズしたよ...」と良く嘆いていたモノでした。
あの頃から比べるとかなりの知識を頭に入れましたので無茶していたんだな~とか思いますな(笑)
このことはおいらのMacが如何にLowSpecなのかが解る現象ですな。
まあいいんです。
これはこれで楽しめていますからね。
ところでPhotoshopに関して書きますね。
Photoshopは環境設定でメモリの占有率を決めることが出来ます。
Applicationで決めることが出来るのにMacOSの環境設定で割り当てることが出来ないのはおかしいですよね。
まあG5とかMac Proなら出来るのかもしれませんが、知っている方は笑ってください。(笑)
Photoshopではメモリの占有率のみ設定できますが、もう一歩踏み込んでCPUの占有率も設定できる方法を作ってもらえないモノでしょうかね。
これってけっこう重要だと思うんですよ。
同時起動させるApplicationに相互に影響しない安定した起動というのは安心感があるはずです。
それを可能にするのが2つ以上CPUを載せているMacでしょう。
演算処理の割り当てというのはCPUの数が多ければ多いほど難しくなります。
これはBench Mark TestでほとんどのApplicationのCPUの稼働率を見れば一目瞭然です。
よって効率的に稼働できるCPU数をApplicationを作成するメーカが出してユーザに教えて、ユーザは目安として提示されたCPU数を割り当てるということです。
まあ、どんどん複数のCPUを使用することに最適化されて行くことでしょうから、CPUの数の変動というのは起こりますし、OSのアップデートで最適化も追加されていくことでしょうからあくまで目安にしかならないですけどね。
更に気になる点としてIntel特有のモノもありますよね。
これから出てくるCPUのことも考えます。
・ハイパースレッディング対応も出る可能性
これは捨てきれないでしょう。
特に雑誌で特集されていたBench Mark Testを考慮するとほとんどのCPUで半分も稼働していないCPUが目立っていました。
このことを考慮するとハイパースレッディングというのは威力を発揮する分野だと言えます。
ハイパースレッディング機構が作られた理由はCPUの稼働率の無駄を無くすためです。
そして稼働していないところを使って1つのCPUを2つと認識させて稼働していない部分を効率的に稼働させるために作られたんですな。
もし8Core Xeonでハイパースレッディング機構を搭載させると仮想的に16Coreと認識されます。
まあ実際に16CoreのCPUを搭載させることはIntelのロードマップを見ていると直ぐでしょうけどね。
CPUを効率的に稼働させる為には沢山のCPUを搭載させてもこのハイパースレッディング機構というのは重宝することでしょう。
ここで断っておかなければならないこととしてこのハイパースレッディング機構というのは最初から全てのCPUを効率的に使用出来るのであれば意味がないということも書いておかなければなりません。
ハイパースレッディング機構はCPUの稼働率が低いときに余った稼働率の部分を使用するからです。
最適化されたApplicationを使用し稼働率が全てのCPUでMAXに近い場合に息を潜めるようになっているんですな。
しかし現在のCPUの最適化はまだまだなされていないApplicationがほとんどです。
よって今の状態でこそ重要な機構だと言えます。
なんだか憶測の話で申し訳ないんですが、こんな記事を書くのであればあの本を買っておけば良かったとさえ考えてしまいます。
MacFanかMacPeopleで以前おいらが考えていた事と同じ内容のことが提案されていました。
複数のOSを起動させて使用するServer的な使用方法です。
一応おいらの記事のリンクを下に貼っておきます。
BootCampがもたらす影響
雑誌の記事では複数のWindowsOSを起動させる事が提案されていましたが、時期MacOSでは複数のMacOSの仕様を設定できて選択画面で選択した仕様に即変更が出来るという機能が搭載されています。
もしかしたらMacOSを複数起動させて使えるようになるかもしれませんね~。
あくまで憶測でしかないのですが、もしそうなるのであればMac Proではレクチャーする際に同じMacを使用して教えることが出来ます。
もしそうなれば、便利ですよね~。
Windowsを複数起動できるのにMacintoshが一つしか起動できないのはおかしいと思うわけです。
まあこんなおいらのBlogなんかを覗いていないでしょうから書きますが、出し惜しみして欲しくないんですよね~。
使えるのであればとことんで使える仕様にして欲しいものです。
もしこのような機能が追加されるのであれば、特に重宝するのはMac Proを使用する人でしょう。
拡張性に富み、タフな構造を誇っているわけですし、CPUもしくはMPUを搭載しているのですから、2人で使用するのであれば単純に2分割したらいいわけです。
またもし3人以上になるのであれば4分割まではQuadCoreの場合はハード的に分割できるでしょう。
しかし上記の条件としてメモリのスロットを全て埋めておく必要があります。
デュアルメモリ効果を使用できるようにしておくことは常識となりつつありますからね~。
まあ、おいらのMacintoshは古い機種ですのでデュアルメモリの恩恵はあまりあずかることが出来ないんですけどね。
Computerの進歩というのはすごい勢いで進んで居るんだな~とよく感じます。
上記の雑誌で気になったベンチマークテストでは8CoreをFullに使用出来るApplicationはごく少数で8Coreを持てあましているという事実が書かれていました。
そしてベンチマークに使うアプリケーションによっては4Coreの方が高速に処理できるモノが多かったようです。
これは処理の割り振りが最適化されておらず、CPUの性能を効率的に使えていないからだともとも書かれていました。
よっておいらが提案するポイントは下記の事です。
・メモリの割り振り同様のCPUの割り振り
・ApplicationからのCPUの割り振りも良いかもしれない(Photoshopのメモリの割り振りと同様)
Macintoshを起動する際に複数のソフトを同時に起動することは当たり前でしょう。
おいらの場合はiTunesとMail、safariなど音楽やインターネットを起動させた上に画像処理ソフトを起動させていることが多いんですな。
Photoshopはかなりの物理メモリ空間を割り当てていますので他のソフトを使用するのには問題があります。
よってPhotoshopを起動させる場合はiTunesぐらいしか同時起動させないようにしています。
というか画像処理ソフトはすべてかなりの物理メモリを占有するので極力他のアプリケーションを起動しないようにする必要が求められています。
あまりコンピュータのことを考えずに複数のアプリケーションを同時起動させていたときにOSが不安定になりApplicationがフリーズすることがたまにありました。
今から考えると無理な使い方をしていたことが良くわかりますが、当時は「またフリーズしたよ...」と良く嘆いていたモノでした。
あの頃から比べるとかなりの知識を頭に入れましたので無茶していたんだな~とか思いますな(笑)
このことはおいらのMacが如何にLowSpecなのかが解る現象ですな。
まあいいんです。
これはこれで楽しめていますからね。
ところでPhotoshopに関して書きますね。
Photoshopは環境設定でメモリの占有率を決めることが出来ます。
Applicationで決めることが出来るのにMacOSの環境設定で割り当てることが出来ないのはおかしいですよね。
まあG5とかMac Proなら出来るのかもしれませんが、知っている方は笑ってください。(笑)
Photoshopではメモリの占有率のみ設定できますが、もう一歩踏み込んでCPUの占有率も設定できる方法を作ってもらえないモノでしょうかね。
これってけっこう重要だと思うんですよ。
同時起動させるApplicationに相互に影響しない安定した起動というのは安心感があるはずです。
それを可能にするのが2つ以上CPUを載せているMacでしょう。
演算処理の割り当てというのはCPUの数が多ければ多いほど難しくなります。
これはBench Mark TestでほとんどのApplicationのCPUの稼働率を見れば一目瞭然です。
よって効率的に稼働できるCPU数をApplicationを作成するメーカが出してユーザに教えて、ユーザは目安として提示されたCPU数を割り当てるということです。
まあ、どんどん複数のCPUを使用することに最適化されて行くことでしょうから、CPUの数の変動というのは起こりますし、OSのアップデートで最適化も追加されていくことでしょうからあくまで目安にしかならないですけどね。
更に気になる点としてIntel特有のモノもありますよね。
これから出てくるCPUのことも考えます。
・ハイパースレッディング対応も出る可能性
これは捨てきれないでしょう。
特に雑誌で特集されていたBench Mark Testを考慮するとほとんどのCPUで半分も稼働していないCPUが目立っていました。
このことを考慮するとハイパースレッディングというのは威力を発揮する分野だと言えます。
ハイパースレッディング機構が作られた理由はCPUの稼働率の無駄を無くすためです。
そして稼働していないところを使って1つのCPUを2つと認識させて稼働していない部分を効率的に稼働させるために作られたんですな。
もし8Core Xeonでハイパースレッディング機構を搭載させると仮想的に16Coreと認識されます。
まあ実際に16CoreのCPUを搭載させることはIntelのロードマップを見ていると直ぐでしょうけどね。
CPUを効率的に稼働させる為には沢山のCPUを搭載させてもこのハイパースレッディング機構というのは重宝することでしょう。
ここで断っておかなければならないこととしてこのハイパースレッディング機構というのは最初から全てのCPUを効率的に使用出来るのであれば意味がないということも書いておかなければなりません。
ハイパースレッディング機構はCPUの稼働率が低いときに余った稼働率の部分を使用するからです。
最適化されたApplicationを使用し稼働率が全てのCPUでMAXに近い場合に息を潜めるようになっているんですな。
しかし現在のCPUの最適化はまだまだなされていないApplicationがほとんどです。
よって今の状態でこそ重要な機構だと言えます。
なんだか憶測の話で申し訳ないんですが、こんな記事を書くのであればあの本を買っておけば良かったとさえ考えてしまいます。