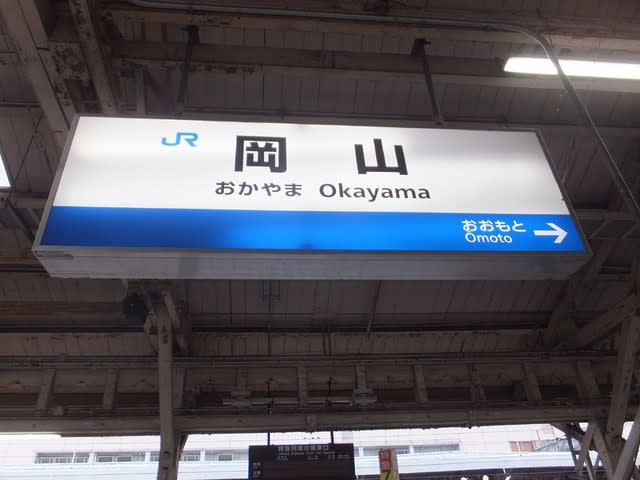8月19・20日に船橋市で「マリンフェスタ」というイベントがあり、新旧2代の南極観測船が並びました。
せっかくなので歴代の南極観測船についてまとめてみました。
南極へ物資、人員の輸送を行う船が南極観測船。日本にはこれまでに4隻の南極観測船が造られ、南極調査に活躍し、引退後も多くの人に親しまれています。
初代「宗谷」1956~1962

東京お台場の船の科学館
1957、1958年は国際地球観測年とされ、日本は南極観測に参加することを決めました。そこで北半球の日本から赤道を越え南極まで向かう船が必要になり、当時は船を新造する予算がなく既存の船を改造することになりそれに抜擢されたのが宗谷でした。
かなり変わった経歴の持ち主だったりします。
宗谷はもともとソ連向けの貨物船として1938年に長崎で生まれたのですが、第二次世界大戦前という情勢の下、国内で「地領丸」として活躍することになりました。
その後戦争がはじまり、海軍の特務艦「宗谷」となりました。魚雷が命中するも不発に終わるエピソードは有名で強運の持ち主と言われています。
終戦後は引揚船「宗谷丸」として大連や樺太へ赴き、その後は海上保安庁の灯台補給船「宗谷」として1955年まで全国を回りました。
そして1956年11月~の第1次南極観測へ初代観測船として参加。1957年1月24日、オングル島に接岸し昭和基地を開設しました。
あのタロとジロが乗ったのも宗谷。1962年の第6次観測まで南極観測船として南極への輸送に従事しました。
その後は海上保安庁船として海難救助など15年間務めを果たし、1979年から船の科学館で公開されるようになりました。
2代「ふじ」1965~1983

水族館も近い、名古屋港ガーデンふ頭
1965年に初めての本格的砕氷艦として竣工しました。全長83mの「宗谷」から100mに大型化。「ふじ」からは南極観測船は海上保安庁から防衛庁によって運用されることになりました。そのため「ふじ」以降は観測船のほか砕氷艦とも呼ばれます。
1921年の「大泊」以来の砕氷艦建造となり設計には多くの力がそそがれました。チャージングでは頻繁に前後進を切り替えるため、電力でスクリューを回すディーゼル電気推進を採用しています。
第7次から第24次観測で使用され1984年に引退。翌1985年から現在の場所で展示されています。

「ふじ」のスクリュー
3代「(初代)しらせ」1983~2008

船橋港で余生を過ごす。「マリンフェスタ」にて。
全長134mと竣工当時、自衛隊の最大の艦船として誕生。名前の由来は日本初の南極探検隊隊長の白瀬矗(しらせのぶ)。当時、山の名前を付けることがルールだったため人名はつけられなかったのですが、「白瀬氷河」を理由に「山または氷河」とルールを変えることでこのをつけることができたそうな。
引退後は「宗谷」や「ふじ」のように残そうという声があったものの過去最大の観測船は維持に費用がかかりすぎるため、保存を断念し解体が一旦は決定しました。
しかし予算がないから価値があるものを処分するなんてお金でしか物が測れないのか、日本の恥だと考えた民間気象情報会社「ウェザーニューズ」の当時社長が購入を決意。交渉の末、成立。「SHIRASE」として第二の人生を送ることになりました。

横須賀基地にて現役当時の様子
4代「2代・しらせ」2009~

横須賀基地一般公開にて。上の「初代しらせ」とほぼ同じアングル。
全長138mと一回り大きくなりました。「初代しらせ」引退後、2008年の50次観測隊ではオーストラリアの民間砕氷船「オーロラ・オーストラリス」をチャーターしました。その後に登場したのが2代目の「しらせ」です。
現役の船と同じ名前の船をつけることは原則できないのですが、白瀬矗の出身地であるにかほ市などからの多くの声をうけ「しらせ」となりました。統合電気推進という推進力と艦内電力の両方を同じ発電機によってまかなう方式が採用されています。
同じアングルから撮影した2枚の写真を見比べると艦首の形状が丸くなったのが分かります。また新たに取り付けられた散水用の穴が見えます。約20年間の研究の成果なのでしょうか。
というわけで歴代の南極観測船についてまとめてみました。幸運にもすべての船が現存しており、今日も海に浮かんでいるというのは嬉しいことです。
氷の世界で目立つオレンジ色の船は、これからも新たな世界を切り開いていくことでしょう。

UW-御安航を祈る-を掲げる初代しらせ(左)と艦首に日の丸をはためかせる2代しらせ(右)。「マリンフェスタ」にて再会を果たしました。
せっかくなので歴代の南極観測船についてまとめてみました。
南極へ物資、人員の輸送を行う船が南極観測船。日本にはこれまでに4隻の南極観測船が造られ、南極調査に活躍し、引退後も多くの人に親しまれています。
初代「宗谷」1956~1962

東京お台場の船の科学館
1957、1958年は国際地球観測年とされ、日本は南極観測に参加することを決めました。そこで北半球の日本から赤道を越え南極まで向かう船が必要になり、当時は船を新造する予算がなく既存の船を改造することになりそれに抜擢されたのが宗谷でした。
かなり変わった経歴の持ち主だったりします。
宗谷はもともとソ連向けの貨物船として1938年に長崎で生まれたのですが、第二次世界大戦前という情勢の下、国内で「地領丸」として活躍することになりました。
その後戦争がはじまり、海軍の特務艦「宗谷」となりました。魚雷が命中するも不発に終わるエピソードは有名で強運の持ち主と言われています。
終戦後は引揚船「宗谷丸」として大連や樺太へ赴き、その後は海上保安庁の灯台補給船「宗谷」として1955年まで全国を回りました。
そして1956年11月~の第1次南極観測へ初代観測船として参加。1957年1月24日、オングル島に接岸し昭和基地を開設しました。
あのタロとジロが乗ったのも宗谷。1962年の第6次観測まで南極観測船として南極への輸送に従事しました。
その後は海上保安庁船として海難救助など15年間務めを果たし、1979年から船の科学館で公開されるようになりました。
2代「ふじ」1965~1983

水族館も近い、名古屋港ガーデンふ頭
1965年に初めての本格的砕氷艦として竣工しました。全長83mの「宗谷」から100mに大型化。「ふじ」からは南極観測船は海上保安庁から防衛庁によって運用されることになりました。そのため「ふじ」以降は観測船のほか砕氷艦とも呼ばれます。
1921年の「大泊」以来の砕氷艦建造となり設計には多くの力がそそがれました。チャージングでは頻繁に前後進を切り替えるため、電力でスクリューを回すディーゼル電気推進を採用しています。
第7次から第24次観測で使用され1984年に引退。翌1985年から現在の場所で展示されています。

「ふじ」のスクリュー
3代「(初代)しらせ」1983~2008

船橋港で余生を過ごす。「マリンフェスタ」にて。
全長134mと竣工当時、自衛隊の最大の艦船として誕生。名前の由来は日本初の南極探検隊隊長の白瀬矗(しらせのぶ)。当時、山の名前を付けることがルールだったため人名はつけられなかったのですが、「白瀬氷河」を理由に「山または氷河」とルールを変えることでこのをつけることができたそうな。
引退後は「宗谷」や「ふじ」のように残そうという声があったものの過去最大の観測船は維持に費用がかかりすぎるため、保存を断念し解体が一旦は決定しました。
しかし予算がないから価値があるものを処分するなんてお金でしか物が測れないのか、日本の恥だと考えた民間気象情報会社「ウェザーニューズ」の当時社長が購入を決意。交渉の末、成立。「SHIRASE」として第二の人生を送ることになりました。

横須賀基地にて現役当時の様子
4代「2代・しらせ」2009~

横須賀基地一般公開にて。上の「初代しらせ」とほぼ同じアングル。
全長138mと一回り大きくなりました。「初代しらせ」引退後、2008年の50次観測隊ではオーストラリアの民間砕氷船「オーロラ・オーストラリス」をチャーターしました。その後に登場したのが2代目の「しらせ」です。
現役の船と同じ名前の船をつけることは原則できないのですが、白瀬矗の出身地であるにかほ市などからの多くの声をうけ「しらせ」となりました。統合電気推進という推進力と艦内電力の両方を同じ発電機によってまかなう方式が採用されています。
同じアングルから撮影した2枚の写真を見比べると艦首の形状が丸くなったのが分かります。また新たに取り付けられた散水用の穴が見えます。約20年間の研究の成果なのでしょうか。
というわけで歴代の南極観測船についてまとめてみました。幸運にもすべての船が現存しており、今日も海に浮かんでいるというのは嬉しいことです。
氷の世界で目立つオレンジ色の船は、これからも新たな世界を切り開いていくことでしょう。

UW-御安航を祈る-を掲げる初代しらせ(左)と艦首に日の丸をはためかせる2代しらせ(右)。「マリンフェスタ」にて再会を果たしました。