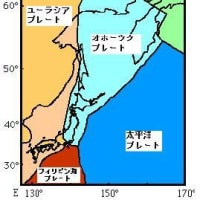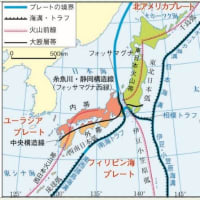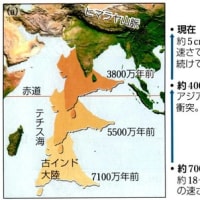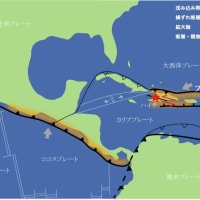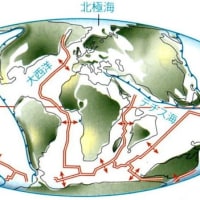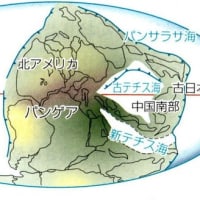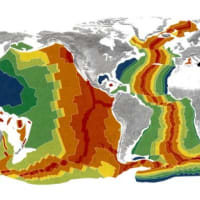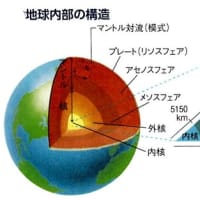インドの米の配給制度
米の配給制度を持続させるためには、米の政府保有米が十分であること、農家が十分な生産を続けることが必要である。インド政府は1975年から、米の安定確保と配給制度の基本として、政府が農家から政府が買う米の価格を定めている。農家は、価格の安定した米作に熱意を持つ。一方、都市の消費者には米を安く売っている。その結果として、政府に米会計の赤字が累積する。
なお、小麦についても同様であり、農家から高く買い、消費者には安く売っている。
インド政府による米(小麦)の買い入れ価格(ルピー/10kg)
1975年 74(105)
1980年 95(130)
1985年 137(157)
1990年 185(215)
1995年 340(360)
2000年 490(580)
2005年 560(640)
※ 政府買入価格の設定されているのは、米・小麦以外に、綿花・砂糖、ジュート、豆類、など、主食以外の作物にも及ぶ。この国家統制的農民保護政策は、インド的な社会主義政策そのものである。
インドの社会保障
インド政府の米・小麦の高価格買い入れ政策が農民保護政策が、インドの財政の大きな負担になっている。しかし、このことが農民・地主の生活保障にもなり、インドの政治・経済の安定に大きく寄与していることも事実である。農産物の輸入自由化拡大が、農民の生活苦を招いた日本の農業政策と比較すると、インドの食料の国家管理つまりインド的食糧管理政策の方が進んでいる。
インドの米価10kgの一般市場価格は、全国平均で20ルピーである。日本円で50円相当だから、10kg500円である。インドの米価は日本のほぼ10分の1である。
最貧困層(AAY)には、政府(インド政府と州政府)の補助があり、米の配給価格は10kgあたり10ルピーであり、市場価格の半値である。
インド政府の貧困家庭への安価な米の配給は、政府の生活保護政策に相当する。日本のような現金支給ではなく、米の現物支給で、貧困家庭を救っている。
インドの農産物の価格保障は、社会福祉政策の恩恵を受けられないインド農民への社会保障政策とみなすことができる。米・小麦の政府買入価格の引き上げは、確実に農民の生活を豊かにする。地主制度の束縛の中で生活する小作農民あるいは土地無し農民にしても、政府による価格引き上げの恩恵を多少は受けている。
日本では疾病、高齢、失業、貧困などの問題を、国民全体の社会保障問題とみなして、該当者に金銭的支払いが実行されている。健康保険、年金、失業保険、生活保護などの名目で、最低限度の生活が保障される。社会保障費用の膨張は、日本の財政赤字を増大させて、日本の経済力を低下させた。
インドには、日本のような国民皆保険・皆年金の制度はない。しかし、インド政府は、貧困層の集中する農村から農産物を高価格で買い上げることにより、農村への社会保障を実現している。また、最貧困層には米を市場価格の半値で配給し、現物支給による生活保護を実施している。
ボパール化学工場爆発事故(1984)
インドの農業近代化(緑の革命)を進める名目で、アメリカの農薬製造企業ユニオン=カーバイド社が、デカン高原北部のボパールに、農薬工場を1969年に建設した。1984年12月2日~3日に工場から、殺虫剤カルバリルの中間生成物質イソシアンメチル40トンが流出した。無色・無臭の劇薬イソシアンメチルを吸い込んだインド人2000人が死亡、1万人以上が内臓・神経系に何らかの障害を受けた。
この事故の原因について、ユニオン=カーバイド社側はインド人従業員が故意に操作ミスとしたこととした。一方、インド側調査による事故原因は、工場建設の段階から安全装置に欠陥は・・・

BOP(Bottom of Pyramid)ビジネス
貧しい者、貧しい集団、貧しい国を相手にする商売・・・

米の配給制度を持続させるためには、米の政府保有米が十分であること、農家が十分な生産を続けることが必要である。インド政府は1975年から、米の安定確保と配給制度の基本として、政府が農家から政府が買う米の価格を定めている。農家は、価格の安定した米作に熱意を持つ。一方、都市の消費者には米を安く売っている。その結果として、政府に米会計の赤字が累積する。
なお、小麦についても同様であり、農家から高く買い、消費者には安く売っている。
インド政府による米(小麦)の買い入れ価格(ルピー/10kg)
1975年 74(105)
1980年 95(130)
1985年 137(157)
1990年 185(215)
1995年 340(360)
2000年 490(580)
2005年 560(640)
※ 政府買入価格の設定されているのは、米・小麦以外に、綿花・砂糖、ジュート、豆類、など、主食以外の作物にも及ぶ。この国家統制的農民保護政策は、インド的な社会主義政策そのものである。
インドの社会保障
インド政府の米・小麦の高価格買い入れ政策が農民保護政策が、インドの財政の大きな負担になっている。しかし、このことが農民・地主の生活保障にもなり、インドの政治・経済の安定に大きく寄与していることも事実である。農産物の輸入自由化拡大が、農民の生活苦を招いた日本の農業政策と比較すると、インドの食料の国家管理つまりインド的食糧管理政策の方が進んでいる。
インドの米価10kgの一般市場価格は、全国平均で20ルピーである。日本円で50円相当だから、10kg500円である。インドの米価は日本のほぼ10分の1である。
最貧困層(AAY)には、政府(インド政府と州政府)の補助があり、米の配給価格は10kgあたり10ルピーであり、市場価格の半値である。
インド政府の貧困家庭への安価な米の配給は、政府の生活保護政策に相当する。日本のような現金支給ではなく、米の現物支給で、貧困家庭を救っている。
インドの農産物の価格保障は、社会福祉政策の恩恵を受けられないインド農民への社会保障政策とみなすことができる。米・小麦の政府買入価格の引き上げは、確実に農民の生活を豊かにする。地主制度の束縛の中で生活する小作農民あるいは土地無し農民にしても、政府による価格引き上げの恩恵を多少は受けている。
日本では疾病、高齢、失業、貧困などの問題を、国民全体の社会保障問題とみなして、該当者に金銭的支払いが実行されている。健康保険、年金、失業保険、生活保護などの名目で、最低限度の生活が保障される。社会保障費用の膨張は、日本の財政赤字を増大させて、日本の経済力を低下させた。
インドには、日本のような国民皆保険・皆年金の制度はない。しかし、インド政府は、貧困層の集中する農村から農産物を高価格で買い上げることにより、農村への社会保障を実現している。また、最貧困層には米を市場価格の半値で配給し、現物支給による生活保護を実施している。
ボパール化学工場爆発事故(1984)
インドの農業近代化(緑の革命)を進める名目で、アメリカの農薬製造企業ユニオン=カーバイド社が、デカン高原北部のボパールに、農薬工場を1969年に建設した。1984年12月2日~3日に工場から、殺虫剤カルバリルの中間生成物質イソシアンメチル40トンが流出した。無色・無臭の劇薬イソシアンメチルを吸い込んだインド人2000人が死亡、1万人以上が内臓・神経系に何らかの障害を受けた。
この事故の原因について、ユニオン=カーバイド社側はインド人従業員が故意に操作ミスとしたこととした。一方、インド側調査による事故原因は、工場建設の段階から安全装置に欠陥は・・・

BOP(Bottom of Pyramid)ビジネス
貧しい者、貧しい集団、貧しい国を相手にする商売・・・