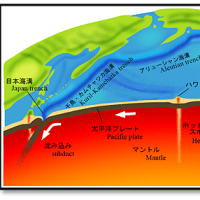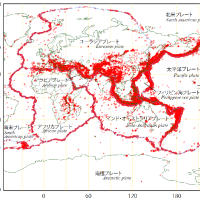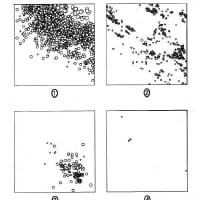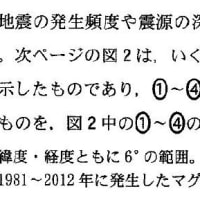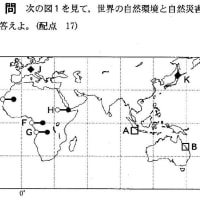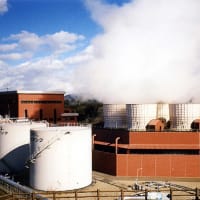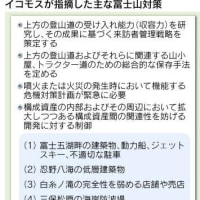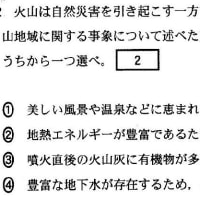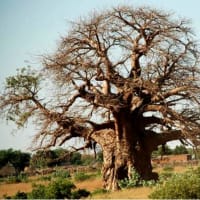ニシンの漁獲量激減
北海道日本海岸のニシン漁は幕末期から始まった。一時はニシンで海岸が埋め尽くされ、本州からの出稼ぎ労働者ヤン衆が漁場に集まった。ニシン漁で巨利を得た者は、海岸の漁場を見下ろす高台に豪華なニシン御殿を建てた。しかし、1955年から漁獲量は激減した。はじめ、不漁は周期的現象と説明されたが、以後は漁獲量の回復はなく、国内におけるニシンの大漁は夢となった。
ニシンの漁獲量が減少し、現在の漁獲量は年間5千トンであり、10万トンはアラスカ・カナダ。ノルウェーなどから輸入する。他の魚類では資源保護のための漁獲規制があるが、ニシン漁には規制がない。日本のニシン漁獲量の減少は、次の理由が複合したものと考えられる。
(1) 海水温度の上昇
一時的な海流異変とみられていたが、海流の進路も海水温も異変のままであり、正常な状態はなくなった。ロシアのシベリア開発、地球温暖化の影響と考えられる。
(2) 日本海岸のニシン繁殖地での乱獲
2月~4月に、繁殖のために沿岸に押し寄せるニシンの群れを一網打尽に捕獲した。食用としてはさばききれず、肥料用・飼料用としても出荷するほどであったが、大漁貧乏で破産する網元も少なくなかった。
(3) 海岸線の道路建設や森林伐採
沿岸がコンクリートで補強されたり、森林がなくなり海岸の海草が枯渇して、ニシンの生育環境が極度に悪化した。
まぐろの需要増加と漁獲量減少
まぐろの年間漁獲量第1位はインドネシア30万トン第2位は日本20万トンである。しかし、日本は需要の増加と漁獲量減少のため、年間消費量の51%を輸入に頼っている。
まぐろの漁獲量が減少した理由は、次の(1)~(5)の複合である。
(1)排他的経済水域(EEZ)
1990年以降、日本のまぐろ遠洋漁業の漁場海域を、沿岸各国が200海里排他的経済水域に設定して、日本漁船を締め出したり、高額の入漁料を徴収したりした。日本のまぐろ漁船は200海里外の漁獲量の少ない海域に移るか、操業前に入漁料を支払うようになった。なお、入漁料は年々高くなり、1990年には200万円程度であったが、現在はその10倍である。
(2) 経費の上昇
1973年の第1次石油危機以後、まぐろ延縄の値上がり、レーダー・魚群探知機・大型急速冷凍庫などの高価な装備、大型化高速化による船体建造費の上昇、燃料用重油の高騰などが続いている。遠洋漁業は資本力のある船主に集約され、国全体の漁獲量は減少した。
(3) 高齢化
漁業就業者は約18万人、過去10年間で3割減少した。遠洋まぐろ漁業の船員6,000人のうち、60歳以上が42%、50代以上では83%になる。若い船員が少ない。
(4) 資源の減少
乱獲が原因とされる。乱獲は遠洋まぐろ漁船が大型の高価なまぐろを大量捕獲するためだが、近年は沖合漁船がまぐろ幼魚を大量捕獲して、養殖業者に販売することも資源減少の大きな原因とされている。
(5) 海外の小型まぐろ漁船の増加
日本のまぐろ漁業は漁船の大型化でコストダウンを図ってきた。しかし、台湾・韓国などは排他的経済水域規で規制を受けない39トン小型漁船を使い、まぐろ資源の豊富な国に船籍を移して、低コストでまぐろを捕獲して日本に輸出する。このような輸入まぐろが日本市場に増加し、日本の遠洋まぐろ漁業の経営を脅かしている。しかし、このような小型漁船には、日本の水産会社の技術・資金により、つまり実質的に日本企業に属して、まぐろを獲る漁船も少なくない。
日本のまぐろ遠洋漁業はコストが高く、1970年代にの遠洋漁業全盛期に戻ることは難しい。現在できることとして、国際的にまぐろ資源の管理を進め、短期間に大漁を目指すオリンピック型漁業から経済的合理性のとれたの資源管理型漁業への転換がある。しかし、小型漁船を利用したり、他国船籍のまぐろ運搬船を利用したりするアウトサイダーの問題がある。
遠洋まぐろ漁船の船員の高齢化対策として、外国人船員の雇用が進められている。ほとんどがインドネシア人であり、6,000人が遠洋まぐろ漁船に乗り組んでいる。遠洋まぐろ漁業船員の半数はインドネシア人船員である。賃金は日本人船員の3割程度である。
まぐろの養殖が増加している。価格の暴落したはまち・たいなどの養殖から、まぐろの養殖への転換である。まぐろの養魚を購入して生け簀で飼育するものである。養魚を捕獲することと、大量のえさを与えるので、資源管理よりはむしろ資源浪費型の養殖である。
近畿大学の研究成果として、まぐろの卵から成魚まで完全養殖することが可能になった。飼料も開発された。近大まぐろのブランドで市場に出回っている。また、近大から養魚の提供を受けている養殖業者も増えている。しかし、近大まぐろもまぐろ資源の保護にはなるが、日本の年間まぐろ消費量20万トンに対して200~300トン程度の供給量である。
TAC
漁獲可能量(total allowable catch)は漁業資源保護のために政府が決定し、漁業協同組合などに漁獲量の制限を守らせるものである。個別の漁船に漁獲量を指定する方法と、各漁協の総枠として漁獲制限を設定する方法とがある。個別の漁船に漁獲量を指定する方が厳格ではあるが、船主の利害が絡んで実行しにくい。そのため、各漁協の総枠を設定して、漁協に調整をゆだねる方法がとられている。多くは漁協などが漁期を設定し、TACの上限に達した時に漁獲を打ち切る方法が採られている。対象は7魚種である。
現在、実行可能の資源保護としては最善である。しかし、漁期を守らない漁船がいたり(密漁)、外国漁船が日本の漁期以後に操業をするケース(違反操業)が多いといわれている。
漁業資源保護の先進国ノルウェーでは個別の漁船に漁獲量を指定するが、違法な漁業については資源保護の大枠が守られていればよいとして、過度な違法操業でない限りは放置している。
日本では密漁・違反操業の実態は不明であり、指導も取り締まりもできない状況であり、結果としてノルウェーと同じ姿勢である。
TACを厳密にしたり該当魚種を増やすと、密漁・違反操業が増加する。TACの資源保護の根本理念が揺らいでしまう恐れがある。漁業資源の保護は、容易ではない。
また、TACの規制数値が高すぎれば、現実の乱獲を追認することになり、資源保護には逆行することになる。日本の7種のTACのうち、さんまに関しては漁獲規制すをする数値だが、他の魚種ではTACの数値が高く、有効な規制になっていない。TACはさんま以外では、乱獲を追認しているのが現状である。