『世界はひとつの教室』(サルマン・カーン)を読みました。
第3部「現実の世界へ」の中に「教育は年齢を超えて」という節があります。
外国語の学習は子どもの方が向いていて、大人はあまり向いていないということがよく言われます。
実際に日本語を教えていて、高校を出たての学生と40に近い学生とでは覚える速度が違います。
しかし、本書では子どもと大人では学び方を変えれば、それぞれに学習ができると説いています。

p.177
したがって、学習は子ども時代のほうがやりやすいとか、やりにくいとか、そういう決めつけはなかなかできません。言えるのは、成人期には学習へのアプローチが変わるということ。このアプローチと、それに最も適した指導法を表す言葉があります。教育法(アンドラゴジー)です。これはもっとよく知られた教授法(ペタゴジー)とは対照的な言葉です。ペタゴジーは教える側の先生に重きを置きます。何をいつ学ぶか、どのようにテストするかを決めるのは先生です。他方、アンドラゴジーは学習者自身に重きを置き、責任を負わせます。大人は別に学ばなくてもかまいません。学ぶことをみずから選択するのです。この積極的な選択と、その背後にある意欲のせいで集中力が高まり、学習が容易になります。

教育法と教授法の違いは考えたことがありませんでした。
あったとしても、対にして考えたことがありませんでした。
教授法ばかり気にしていました。
学習者には何事も意欲が大切で、これがなければ始まりませんが、その意欲が出てきた時にインターネットを使用しての学習は効果があると思いました。
まず、学習者に意欲を持たせること。
この難問に取り組まなければなりません。
進度ばかり気にして、その部分を疎かにしてしまっていたと反省しました。










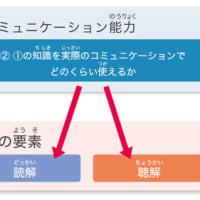
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます