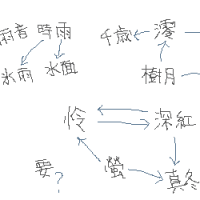もうだいぶ前に最終巻が発売した『魔人探偵脳噛ネウロ』ですが今更感想などを書いてみようと思います。相当好きなマンガなので感想全部を書こうとすると最後まで気力がもたないだろうから、なるべくさらっと。のつもりが今回も長いです。先に謝っときます。
1~23巻という長いストーリーを読み進めるうちに何度も思ったのは「一体いつから計算していたのか」ということ。ラスボスの存在やそれに繋がる人物、主人公に大きな影響を与える人物、最終戦のカギとなる人物とエピソード、勝敗を左右する人物。それら全てがこの長大な話の序盤ですでに登場している。
22巻である人物が言う台詞が、5巻ですでにその片鱗を見せ、3巻でネウロが言った台詞を最終巻で弥子がもう一度なぞる。全てが序盤から伏線で繋がっていると言っても過言ではない。寄り道がなく迷いもなく、始まった瞬間から終わりを目指して一直線に進んでいるような、無駄のない展開だった。
長期連載だと話の方向性が変わったり(ほのぼのからバトルものになるとか)、後から取ってつけたような設定があったり、どうしてもそうなりがちだが『ネウロ』にはそういうものが一切なかった。連載は人気によっては打ち切りになったり、逆に引き伸ばされたり、作者の希望通りにはならないこともたくさんある。いつ終わるか分からない中でこれだけ多くの伏線を張り、その全てを回収し、一つのテーマを変えずに貫く。それが出来た『ネウロ』は奇跡的な作品だと思った。
しかし最終巻のあとがきを読むと、それが決して『奇跡』ではないことが判る。話の半ばで打ち切られる可能性もある連載という形の中で、作者は「(責任を持って始め、責任を持って終わらせる)」ことを最重要課題としていた。そしていつ来るか分からない終わりに備えて複数のストーリープランを用意していた。あちこちのレビューサイトで最終話が「きれいな終わり方」と評されていたのは、奇跡ではなく作者の努力による当然の結果だった。
『ネウロ』の特徴や長所は数多くあるが、私が感心したことの一つは「最初から最後まで一つのテーマを貫いている」という点。読み終えて「このマンガのテーマは?」と聞かれたら誰もがすぐ『進化』と答えられるだろう。多くのエピソードとキャラを描きながらそれらを全て一つのテーマに集約させるのは相当難しいんじゃないだろうか。ほんとに読んでいて作者のストーリーの構成力に感心する。というか戦慄する!
ストーリーも当然好きなんだけど、それと同様に『ネウロ』の魅力を占めているのがネウロと弥子の関係。『謎』を喰う為に弥子を脅して傀儡にし、弥子は仕方なく奴隷扱いを受けている。というはずだったのに、話が進むにつれて『そうだけどそれだけじゃない』関係になってきている。様々な人や犯人と接し、自分にできることを精一杯しようと成長していく弥子。食糧である『謎』を生み出そうと足掻く人間の『進化』を好ましく思う魔人。種族のまるで違う二人がお互いに影響し合い、変化していく過程がとても丁寧に描かれている。
あと以前にも書いたけど、突っ込む気力も失せるほどのバラエティを極めたDVの数々が『ネウロ』の醍醐味。文章にするとすごすぎるので書かないけど、なんかもうDVっていうよりスキンシップくらいの気軽さ(笑)。しかしギャグテイストにしているもののネウロは毎回容赦なくドSを貫いている。対して弥子は精神的にはタフだし胃袋は四次元だけど、体格は標準よりほっそりして小柄。それが毎回鎖とかロープとか手錠とかのオプションが付いてていくらギャグでもどうなのそれ!?と床を転げまわりたくなるんだけど。DVなのにドキドキするんだけど。
ネウロの容赦の無さと弥子のドライさが二人の間にある『性別』という差を完全に消しているにも関わらず、読者は二人がお互いにどう思っているのか気になってしかたがなくなるだろう。二人の間には終盤に進むにつれ信頼や絆が生まれるけど、二人の意識に『性別』が入ることは最初から最後まで絶対に無い。そこら辺の作者の抑制はハンパじゃない。普通ちょっとくらい恋愛っぽいものを入れたくなると思うんだ。そして読者もそういうのちょっとは期待すると思うんだ(笑)。
しかしそれを抑制したからこそ、二人の間にある言葉で表せない何かを、「そこにあるのは何だ」と読者に思わせることができたのではないか。
最終話手前での二人のやり取りと行動が、悲しくはないのに切なくてしょうがない。
もう一つ二人に関して叫びたい事が。22巻のあるシーンで「膝かよ!!!!!」と叫んだファンは少なくないだろう。うああああすごい衝撃というか破壊力というか作者が爆弾落としてきた!とのた打ち回りたくなったよ…。
やっぱり感想長い!ねちこい!でも一気に書いてしまおう。今までは一応客観っぽく書いてきたけど、ここからはバリバリ主観で叫ぶのでご了承を。
主人公コンビ以外で一番好きなキャラは笛吹。最初は探偵である弥子に警察として嫌味ばかり言うポジションだったのに、どんどん有能さを発揮して最終戦では人間側代表として最重要人物に。もうかっこいいったらない!!22巻でかっこよさ爆発。嫌味でツンデレでメルヘン趣味なところが可笑しいんだけど、この人の潔癖さと強すぎる責任感が好き。どんな凶悪犯罪でも、たとえ相手がラスボスでも許さない。普通なら諦めと妥協が入るところなのに、絶対折れない。もー一番好きー!!笹塚も好きだったんだけど、弥子達を支える吾代も好きなんだけど、笛吹が上回りました。9巻あたりからノンストップ。
そして個性がすごすぎる犯罪者達の中で、やはり群を抜いた存在はサイ。登場もすごいインパクト。犯罪動機も人間の枠から軽くはみ出している。7巻でのネウロとの戦闘はすごく興奮した!高層ビルのクレーンの上で、地面と平行に立つ二人が繰り広げるバトル。常に余裕だったサイが、ネウロの弱体化を知って孤独と不安に焦る。このシーンが好き。サイとは迫力あるバトルが多いなあ。
HALの事件もすごい印象的。11巻での(HAL消去中のあのシーン)、普段ドライな作者が泣かせにかかるとすごいな!
弥子の進化を『日付が変わる』と表現し、実際のものと関連させたりするセンスもすごいと思う。各話の扉絵にもそのセンスが窺える。
もう一人犯人達の中で印象に残ったのが葛西。渋い!悪い!中年なのに何そのかっこよさ!美学を貫いた生き様!(シックスでさえ結局彼を思い通りにはできなかったんじゃないだろうか。駒としては動かせても、血族として生身を捨てさせることはできなかった。望みどおりシックスより長生きしてみせた葛西は、犯罪者ながら見事だった。でも次のラスボスにはなってくれないんだろうな。そんな柄じゃないとか言って。)
ちょっとびっくりしたのが石垣。最初から徹底してダメ刑事に描かれていて、もちろん急に良くなりもしなかったんだけど、(決して喪失感を引き摺らずに、等々力よりもよっぽどしっかり仕事に向き合っていた。笹塚に頼りきりだったが故に、かえって笹塚の言葉を実行できたんだろうか。見直したよ…(泣))
あとはもう色々と。テラも面白かったな。ネウロは基本ボケなのに、それがツッコミにまわらざるを得ないほどのボケだった。ジェニュインのまつげすごい。吾代いい人!アカネちゃん(成仏してしまうエピソードあるかなと思ってたんだけど、とりあえずなくてホッとした。)
駄目だ、書いてるとキリが無い。このへんでそろそろ終わります。
最後に。最終話で作者の優しさをすごく感じた。長く壮大なスケールの話の最後に、自分のありふれた日常へと目を向けさせてくれる終わり方だった。このマンガを読めた幸運と作者に感謝!
1~23巻という長いストーリーを読み進めるうちに何度も思ったのは「一体いつから計算していたのか」ということ。ラスボスの存在やそれに繋がる人物、主人公に大きな影響を与える人物、最終戦のカギとなる人物とエピソード、勝敗を左右する人物。それら全てがこの長大な話の序盤ですでに登場している。
22巻である人物が言う台詞が、5巻ですでにその片鱗を見せ、3巻でネウロが言った台詞を最終巻で弥子がもう一度なぞる。全てが序盤から伏線で繋がっていると言っても過言ではない。寄り道がなく迷いもなく、始まった瞬間から終わりを目指して一直線に進んでいるような、無駄のない展開だった。
長期連載だと話の方向性が変わったり(ほのぼのからバトルものになるとか)、後から取ってつけたような設定があったり、どうしてもそうなりがちだが『ネウロ』にはそういうものが一切なかった。連載は人気によっては打ち切りになったり、逆に引き伸ばされたり、作者の希望通りにはならないこともたくさんある。いつ終わるか分からない中でこれだけ多くの伏線を張り、その全てを回収し、一つのテーマを変えずに貫く。それが出来た『ネウロ』は奇跡的な作品だと思った。
しかし最終巻のあとがきを読むと、それが決して『奇跡』ではないことが判る。話の半ばで打ち切られる可能性もある連載という形の中で、作者は「(責任を持って始め、責任を持って終わらせる)」ことを最重要課題としていた。そしていつ来るか分からない終わりに備えて複数のストーリープランを用意していた。あちこちのレビューサイトで最終話が「きれいな終わり方」と評されていたのは、奇跡ではなく作者の努力による当然の結果だった。
『ネウロ』の特徴や長所は数多くあるが、私が感心したことの一つは「最初から最後まで一つのテーマを貫いている」という点。読み終えて「このマンガのテーマは?」と聞かれたら誰もがすぐ『進化』と答えられるだろう。多くのエピソードとキャラを描きながらそれらを全て一つのテーマに集約させるのは相当難しいんじゃないだろうか。ほんとに読んでいて作者のストーリーの構成力に感心する。というか戦慄する!
ストーリーも当然好きなんだけど、それと同様に『ネウロ』の魅力を占めているのがネウロと弥子の関係。『謎』を喰う為に弥子を脅して傀儡にし、弥子は仕方なく奴隷扱いを受けている。というはずだったのに、話が進むにつれて『そうだけどそれだけじゃない』関係になってきている。様々な人や犯人と接し、自分にできることを精一杯しようと成長していく弥子。食糧である『謎』を生み出そうと足掻く人間の『進化』を好ましく思う魔人。種族のまるで違う二人がお互いに影響し合い、変化していく過程がとても丁寧に描かれている。
あと以前にも書いたけど、突っ込む気力も失せるほどのバラエティを極めたDVの数々が『ネウロ』の醍醐味。文章にするとすごすぎるので書かないけど、なんかもうDVっていうよりスキンシップくらいの気軽さ(笑)。しかしギャグテイストにしているもののネウロは毎回容赦なくドSを貫いている。対して弥子は精神的にはタフだし胃袋は四次元だけど、体格は標準よりほっそりして小柄。それが毎回鎖とかロープとか手錠とかのオプションが付いてていくらギャグでもどうなのそれ!?と床を転げまわりたくなるんだけど。DVなのにドキドキするんだけど。
ネウロの容赦の無さと弥子のドライさが二人の間にある『性別』という差を完全に消しているにも関わらず、読者は二人がお互いにどう思っているのか気になってしかたがなくなるだろう。二人の間には終盤に進むにつれ信頼や絆が生まれるけど、二人の意識に『性別』が入ることは最初から最後まで絶対に無い。そこら辺の作者の抑制はハンパじゃない。普通ちょっとくらい恋愛っぽいものを入れたくなると思うんだ。そして読者もそういうのちょっとは期待すると思うんだ(笑)。
しかしそれを抑制したからこそ、二人の間にある言葉で表せない何かを、「そこにあるのは何だ」と読者に思わせることができたのではないか。
最終話手前での二人のやり取りと行動が、悲しくはないのに切なくてしょうがない。
もう一つ二人に関して叫びたい事が。22巻のあるシーンで「膝かよ!!!!!」と叫んだファンは少なくないだろう。うああああすごい衝撃というか破壊力というか作者が爆弾落としてきた!とのた打ち回りたくなったよ…。
やっぱり感想長い!ねちこい!でも一気に書いてしまおう。今までは一応客観っぽく書いてきたけど、ここからはバリバリ主観で叫ぶのでご了承を。
主人公コンビ以外で一番好きなキャラは笛吹。最初は探偵である弥子に警察として嫌味ばかり言うポジションだったのに、どんどん有能さを発揮して最終戦では人間側代表として最重要人物に。もうかっこいいったらない!!22巻でかっこよさ爆発。嫌味でツンデレでメルヘン趣味なところが可笑しいんだけど、この人の潔癖さと強すぎる責任感が好き。どんな凶悪犯罪でも、たとえ相手がラスボスでも許さない。普通なら諦めと妥協が入るところなのに、絶対折れない。もー一番好きー!!笹塚も好きだったんだけど、弥子達を支える吾代も好きなんだけど、笛吹が上回りました。9巻あたりからノンストップ。
そして個性がすごすぎる犯罪者達の中で、やはり群を抜いた存在はサイ。登場もすごいインパクト。犯罪動機も人間の枠から軽くはみ出している。7巻でのネウロとの戦闘はすごく興奮した!高層ビルのクレーンの上で、地面と平行に立つ二人が繰り広げるバトル。常に余裕だったサイが、ネウロの弱体化を知って孤独と不安に焦る。このシーンが好き。サイとは迫力あるバトルが多いなあ。
HALの事件もすごい印象的。11巻での(HAL消去中のあのシーン)、普段ドライな作者が泣かせにかかるとすごいな!
弥子の進化を『日付が変わる』と表現し、実際のものと関連させたりするセンスもすごいと思う。各話の扉絵にもそのセンスが窺える。
もう一人犯人達の中で印象に残ったのが葛西。渋い!悪い!中年なのに何そのかっこよさ!美学を貫いた生き様!(シックスでさえ結局彼を思い通りにはできなかったんじゃないだろうか。駒としては動かせても、血族として生身を捨てさせることはできなかった。望みどおりシックスより長生きしてみせた葛西は、犯罪者ながら見事だった。でも次のラスボスにはなってくれないんだろうな。そんな柄じゃないとか言って。)
ちょっとびっくりしたのが石垣。最初から徹底してダメ刑事に描かれていて、もちろん急に良くなりもしなかったんだけど、(決して喪失感を引き摺らずに、等々力よりもよっぽどしっかり仕事に向き合っていた。笹塚に頼りきりだったが故に、かえって笹塚の言葉を実行できたんだろうか。見直したよ…(泣))
あとはもう色々と。テラも面白かったな。ネウロは基本ボケなのに、それがツッコミにまわらざるを得ないほどのボケだった。ジェニュインのまつげすごい。吾代いい人!アカネちゃん(成仏してしまうエピソードあるかなと思ってたんだけど、とりあえずなくてホッとした。)
駄目だ、書いてるとキリが無い。このへんでそろそろ終わります。
最後に。最終話で作者の優しさをすごく感じた。長く壮大なスケールの話の最後に、自分のありふれた日常へと目を向けさせてくれる終わり方だった。このマンガを読めた幸運と作者に感謝!